新着情報
外国人雇用で必要な書類とは?採用前〜入社後までの完全チェックリスト
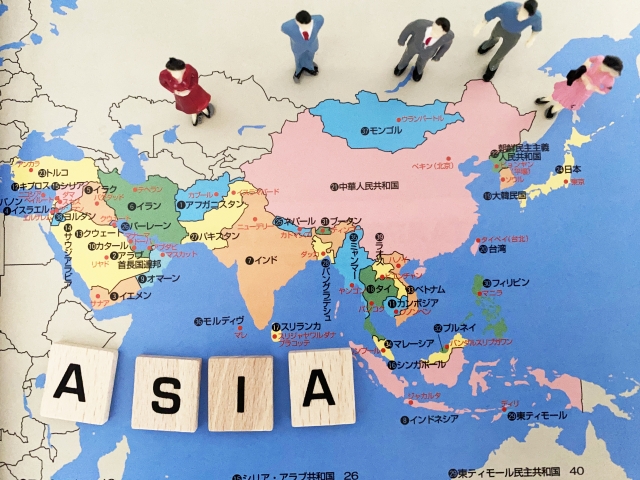
「外国人を雇いたいが、どんな書類が必要なのかわからない…」
東京、大阪、福岡、名古屋など全国の中小企業の現場では、こうした悩みが急増しています。「就労ビザの確認はどうすれば?」「在留カードって何を見るの?」「契約書は日本語だけで大丈夫?」といった不安の声も多く寄せられています。
このような混乱が生じる背景には、外国人雇用に関する制度が複雑で、書類の種類やタイミングを企業が正確に把握していないことがあります。特に、在留資格に関わる書類はミスがあると不法就労につながる重大なリスクとなります。
本記事では、外国人を採用する際に必要な書類を「採用前」「採用時」「採用後」に分けて網羅的に解説します。また、特定技能制度や登録支援機関との連携によって発生する追加書類についても詳しく説明します。この記事を読めば、外国人雇用の「手続きの迷い」がゼロになります。
外国人雇用で必須の書類一覧:ステップ別に整理
外国人を雇用する際の書類は、フェーズによって異なります。まずは全体像を把握しましょう。
1. 採用前に確認すべき書類
- 在留カード:在留資格・在留期間・就労可否を確認
- パスポート:本人確認、滞在歴の確認
- 履歴書・職務経歴書(日本語/母語)
- 日本語能力証明(JLPTなど):職種によってはN4〜N2が必要
2. 採用決定時に準備する書類
- 雇用契約書(二言語):日本語+ベトナム語・中国語など母国語で作成
- 労働条件通知書:労働基準法に基づく条件明示
- 誓約書・身元保証書
- 扶養控除等申告書(税務署提出)
3. 雇用開始後に提出・保管すべき書類
- 雇用保険被保険者資格取得届:ハローワーク提出
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
- 外国人雇用状況届出書:ハローワークへ14日以内に提出(変更時も必要)
- 在留資格更新・変更の補助資料:企業から提出する職務説明書・在職証明書など
在留資格別:追加で必要になる書類とは?
特定技能1号の場合
- 登録支援計画書
- 受入れ機関と登録支援機関の契約書
- 生活支援記録・職場訪問報告書(定期)
- 日本語教育支援資料
技能実習の場合
- 技能実習計画書(認定が必要)
- 監理団体との委託契約書
- 住居情報、生活支援体制の書類
書類作成時の注意点と実務上のアドバイス
- 二言語対応が基本:労働契約書やマニュアルは母国語併記で作成を。登録支援機関の協力が効果的。
- 在留カードのコピーを常時保管:在留資格の更新忘れを防ぐため、期限管理台帳と併用。
- 変更・更新時の社内管理体制を整備:就労ビザの期限が近づいたら、社労士や行政書士に相談を。
- 雇用状況届出は必須:入社・退職・在留資格変更があるたびにハローワークへ届出を。罰則もあり。
Q&A:外国人雇用に関する書類対応の疑問を解決
Q. 雇用契約書は日本語だけでいい?
A. いいえ。外国人が内容を理解できるよう、可能な限り母国語(ベトナム語・中国語など)との併記が望ましいです。
Q. 在留カードの有効期限が切れていたらどうなる?
A. その時点での就労は「不法就労」となります。企業も罰則を受けるリスクがあるため、管理台帳の整備が必須です。
Q. 登録支援機関に依頼すると何をしてくれる?
A. 外国人労働者の生活支援、書類整備、職場訪問など幅広く支援。特定技能の運用においては連携が不可欠です。
Q. 書類不備があった場合のリスクは?
A. 労務トラブルや入管からの是正指導、不法就労助長罪など重いペナルティが科される可能性も。社労士の監修が安心です。
まとめ:書類の正確な整備が外国人雇用の第一歩
外国人雇用においては、就労ビザ(在留資格)の確認から始まり、採用前・採用時・採用後にわたって多くの書類が必要です。これらを漏れなく、正しく整備することが、不法就労の防止、雇用関係のトラブル回避、そして外国人本人の安心につながります。
大阪、東京、名古屋、福岡など外国人労働者が多いエリアでは、登録支援機関や社労士との連携が成功のカギです。特定技能制度や技能実習制度を正しく運用するためにも、必要書類の理解と実践を徹底しましょう。
今すぐ、採用予定の外国人の「在留カードの確認」から始めてください。そこから、未来の戦力が育ちます。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人




