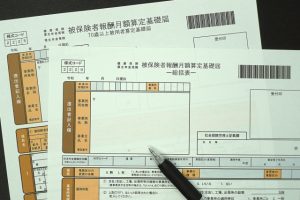新着情報
【休職中の健康保険はどうなる?】企業が知っておくべき保険料・手続き・就業規則のポイント
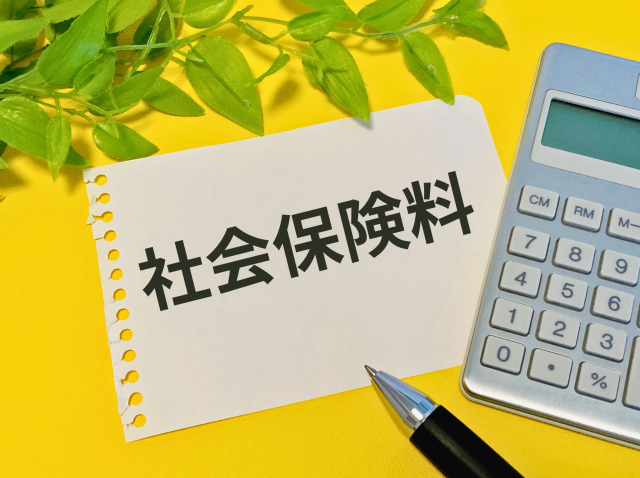
「社員が休職中でも健康保険はそのままなの?」
「保険料は誰が負担するの?会社?本人?」
「休職中の手続きを就業規則に書いてなかったけど大丈夫…?」
東京・大阪・福岡・名古屋などの中小企業、特に従業員100名以上の企業では、メンタル不調や病気・ケガによる休職が日常的に発生します。
そんな中で企業担当者が戸惑うのが、「休職中の健康保険」の取り扱いです。
保険の継続、保険料の支払い、手続き、就業規則への記載などを誤ると、従業員とのトラブルや保険資格の不整合が発生する恐れがあります。
本記事では、大阪の社会保険労務士事務所が、休職中の健康保険の基本と企業対応、就業規則・給与計算・助成金・アウトソースの連携方法まで、実務視点で解説します。
1. 休職中の健康保険、どうなる?制度の基本とポイント
◆ 健康保険は「休職=資格喪失」ではない
社員が病気・ケガ・メンタル不調などで休職しても、原則として健康保険資格は継続されます。
退職しない限り、会社の被保険者として保険証も有効です。
◆ ただし保険料は「賃金の有無」で取り扱いが異なる
- 給与支払いあり:健康保険料は給与から控除
- 給与なし:本人から会社へ直接納付(「納付書発行」や「口座振替」で対応)
◆ 社会保険料の会社負担は継続
賃金支払いの有無に関係なく、会社は会社負担分の保険料を引き続き納める義務があります。
◆ 傷病手当金の支給対象になる場合も
要件を満たせば、健康保険組合や協会けんぽから傷病手当金が支給されます(最大1年6か月)。
⇒ 対象:業務外のケガ・病気で就労不能、連続3日以上の欠勤など。
◆ B社(名古屋・商社)の事例
精神的理由で長期休職した社員に対し、保険料未回収が発生。
顧問社労士と連携し、事前説明と書面取り交わしを強化。就業規則に「休職中の保険料負担」を明文化して再発防止。
2. 休職中の健康保険対応で企業が取るべきアクション8選
- 就業規則に「休職中の保険料負担・支払い方法」を明記
労使トラブル防止のため、事前にルール化。大阪の製造業で整備済。 - 給与がゼロになる場合、保険料の本人納付の流れを説明
会社宛に振込・引き落としなど方法を文書で案内。福岡の介護業で実践。 - 休職中の従業員に「傷病手当金」の説明と申請支援
東京の医療法人で、社労士が申請サポートに入ることで離職防止に成功。 - 健康保険料納付の遅延や未納を未然に防ぐ体制を構築
毎月のリマインド・口座引落の導入など。名古屋のIT企業で導入。 - アウトソースで社会保険手続きと納付を一括管理
対象者リスト・納付スケジュールの自動管理。大阪の飲食業で工数削減。 - 復職予定日の前に保険料状況を精査・精算
過不足金が発生しないよう、復帰面談時に確認。福岡の保険代理店で活用。 - 助成金と連動(職場復帰支援・両立支援助成金など)
傷病手当と連携し、制度整備+金銭補助が可能。社労士に申請依頼。 - やってはいけない:休職したら保険を即外す
資格喪失に該当しないのに脱退処理すると違法・未保険扱いに。
3. よくある質問(Q&A)
Q. 休職中も健康保険証は使えますか?
A. はい。退職しない限り、保険資格は継続されるため使用可能です。
Q. 給与ゼロでも保険料は支払わなければいけない?
A. はい。本人が会社へ納付する形で継続します。
Q. 傷病手当金は会社からもらえますか?
A. いいえ。健康保険(協会けんぽ・健保組合)から支給されます。
Q. 休職中の手続きは誰が行う?
A. 基本的には企業の総務部門または顧問社労士が手続きを行います。
まとめ:休職中の健康保険は“制度理解と事前対応”がカギ
休職中の健康保険の扱いは、企業の労務リスクと従業員の安心を左右する重要なテーマです。
本記事では、健康保険の継続条件、保険料負担、傷病手当金、就業規則への記載、給与ソフトとの連携、助成金・アウトソースの活用まで実務視点で詳しく解説しました。
大阪・東京・福岡・名古屋などの企業でも、社労士と連携して休職制度と保険制度の整合を見直す動きが進んでいます。
従業員と企業の双方が安心できるルール整備を進め、法令順守と職場の信頼関係を築きましょう。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人