新着情報
【知らなきゃ損!】「休日の定義」とは?企業が就業規則に明記すべき重要ポイント
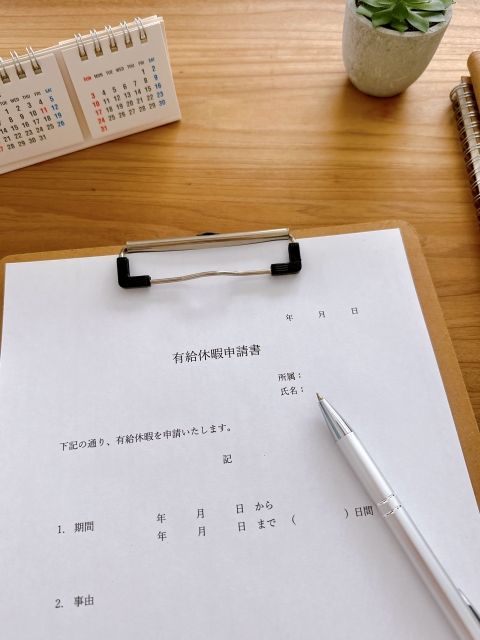
「“休日”と“休暇”って何が違うの?」
「祝日は休みじゃないのに“休日手当”は払うべき?」
「就業規則に休日の定義がなくてトラブルになった」
東京・大阪・福岡・名古屋などの中小企業、特に従業員100名以上の企業では、「休日の定義」が曖昧なまま給与計算や勤務管理を行っているケースが少なくありません。
しかし、労働基準法では「休日」に関する最低基準が定められており、企業として明確な定義と就業規則での記載がないと、法令違反や労使トラブルに発展するリスクがあります。
本記事では、大阪を拠点に多くの中小企業をサポートする社会保険労務士が、休日の正しい定義、就業規則への反映方法、給与計算・助成金・手続き・アウトソースとの関係まで実務視点で詳しく解説します。
1. 「休日」とは?労働基準法に基づく定義と実務上の区分
◆ 労働基準法上の「休日」の定義
労働基準法第35条では、企業は少なくとも週に1回、または4週に4回の休日を与えなければならないと定めています。
この休日は「法定休日」と呼ばれ、これに対する労働には休日割増(35%以上)の賃金が必要です。
◆ 「休日」と「休暇」の違い
- 休日:勤務義務が最初から発生しない日(例:日曜・土曜)
- 休暇:勤務義務がある日に、それを免除されること(例:有給休暇、慶弔休暇など)
◆ 法定休日と法定外休日の違い
- 法定休日:労基法により週1回以上設ける義務あり。労働=割増賃金支払義務あり
- 法定外休日:企業が任意で設ける休日(例:土曜日が休みなど)。割増義務はないが規定により異なる
◆ よくあるトラブル例
・土曜日に出勤させたところ、「休日出勤手当がないのは違法では?」と指摘された(→実は“法定外休日”だった)
・シフト制で休日の定義が曖昧で、社員ごとにトラブルが発生
・就業規則に「休日」の定義がなく、助成金申請時に書類不備で却下
◆ A社(名古屋・小売業)の事例
A社では週休2日制で、日曜日を「法定休日」として運用。
ある従業員が祝日(法定外休日)に勤務し、35%の割増を請求。
顧問社労士が介入し、「休日区分」と「割増の適用基準」を明文化した就業規則を作成し、誤解を解消。
2. 企業が明確にすべき実務アクション8選
- 就業規則に「休日の定義」を明記
法定休日・法定外休日を区別し、トラブルを未然に防止。大阪の製造業で導入済。 - シフト制の場合は個人ごとの休日管理表を作成
福岡の飲食業で、法定休日の管理表により労働時間の管理が明確化。 - 給与計算ソフトに休日区分を反映
出勤日が法定休日かどうか自動認識させ、割増支払いミスを防止。東京のIT企業でミスゼロ。 - 就業規則に「祝日」「会社休日」の扱いを定義
名古屋の物流会社では、祝日が出勤日のため、誤解防止に効果大。 - 休日に出勤する場合の割増率と支給タイミングを明記
支払日・計算基準を文書で共有。従業員の納得度向上。 - 休日の概念を社員研修で共有
特にシフト制や週休2日制の企業では重要。福岡の介護業でトラブル激減。 - 顧問社労士と休日設計を見直す
労基法違反リスクのチェックと、制度見直しで助成金対応も可能。 - やってはいけない:定義を曖昧にしたまま給与処理
割増支給の漏れがあった場合、遡って是正命令や追加支払いが発生する可能性あり。
3. よくある質問(Q&A)
Q. 法定休日はどの曜日にすべき?
A. 特に決まりはありませんが、日曜日など毎週固定されていると管理しやすく、就業規則にも明記しやすくなります。
Q. 法定外休日に働いたら、割増賃金は必要?
A. 法定労働時間(週40時間)を超えた分は割増対象ですが、休日手当としての支払い義務はありません(任意規定)。
Q. シフト勤務者の法定休日はどう決める?
A. 1週間ごとに勤務計画を作成し、その中で「週1日」の休日を必ず確保する必要があります。
Q. 就業規則に休日の定義がない場合どうなる?
A. 実態に応じて判断され、従業員とのトラブルや監督署の是正勧告につながる可能性があります。明記をおすすめします。
まとめ:「休日の定義」は労務トラブルを防ぐ第一歩
「休日の定義」は、単なるカレンダー上の話ではなく、企業の労務管理・給与計算・助成金対応・就業規則整備に直結する重要な要素です。
本記事では、休日の法的定義・種類別の違い・給与との関係・就業規則やアウトソース活用までを網羅的に解説しました。
東京・大阪・名古屋・福岡など都市部の中小企業では、就業規則の休日規定を見直し、制度の透明化を進める動きが広がっています。
社労士と連携し、「定義の明確化」から始めることが、企業の信頼と従業員満足を守る第一歩となるでしょう。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人




