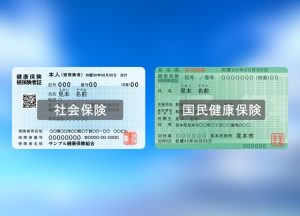新着情報
休業手当・休業補償の正しい理解と使い分けとは?

休業中の従業員の賃金補償は、人事担当者にとって重要な課題です。
企業の責任による休業か、労働災害による休業かで、対応が大きく異なります。
また、労災保険との連携も複雑です。
適切な手続きと制度の理解なくしては、従業員の権利と企業の責任を両立させることは困難です。
そこで今回は、休業手当と休業補償の違い、計算方法、法的根拠、そして労災保険との関係性を解説します。
休業手当の正しい理解
1:休業手当とは何か
休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、従業員に支払われる手当です。
使用者の責に帰すべき事由とは、企業側の都合で従業員が働けない状態になった場合を指します。
例えば、経営不振による一時的な休業、工場の機械故障による操業停止、資材不足などがあげられます。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払うことが義務付けられています。
2:休業手当の計算方法
休業手当の計算は、基本的には平均賃金の60%を基準とします。
しかし、法律では60%以上と定められているため、企業によっては、70%や80%といった割合で支払う場合もあります。
平均賃金の算出方法は、一般的に直近3ヶ月間の賃金総額をその間の暦日数で割ることで算出します。
ただし、企業の就業規則や労働協約で異なる計算方法が定められている場合もあります。
3:休業手当の法的根拠
休業手当の法的根拠は、労働基準法第26条です。
同条項は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定しています。
この条項は、企業側の責任による休業に対して、従業員の生活を保障するための最低限の措置を定めています。
休業補償の正しい理解と使い分け
1:休業補償とは何か
休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病によって働くことができなくなった場合に、企業が支払う災害補償です。
これは、賃金とは異なる性質のものです。
労働基準法第76条では、労働者が業務災害により療養のために労働できない場合、平均賃金の60%の休業補償を行うことが義務付けられています。
2:休業補償の計算方法
休業補償の計算も、平均賃金の60%を基準とします。
平均賃金の算出方法は休業手当と同様です。
ただし、休業中に一部労働した場合には、その分の賃金を平均賃金から差し引いた金額に60%を乗じて計算します。
3:休業補償の法的根拠
休業補償の法的根拠は、労働基準法第76条です。
この条項は、「労働者が療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない」と規定しています。
4:労災保険との関係性
労災保険の休業補償給付は、業務災害による休業に対して、休業4日目以降に給付基礎日額の60%が支給されます。
休業1~3日目は待期期間とされ、労災保険からの給付はありません。
この待期期間中の補償は、企業が労働基準法に基づき平均賃金の60%を休業補償として支払う必要があります。
労災保険給付は、企業の休業補償義務を軽減する役割を果たしますが、給付額は平均賃金の60%であるため、給付基礎日額と平均賃金に差額がない限り、企業は待機期間分の休業補償を支払う必要があります。
また、通勤災害の場合は、労働基準法上の休業補償の対象外となるため、会社には待期期間中の補償義務がありません。
まとめ
今回は、休業手当と休業補償の違い、計算方法、法的根拠、そして労災保険との関係性を解説しました。
休業手当は使用者の責に帰すべき事由、休業補償は業務災害による休業を対象としており、それぞれ平均賃金の60%(以上)を基準に計算されます。
労災保険は業務災害(通勤災害を含む)による休業に対して4日目以降の補償を行い、企業の負担を軽減します。
これらの制度を正しく理解し、適切に運用することで、従業員の権利保護と企業のコンプライアンス遵守を実現できます。
法令の改正や解釈の変化にも注意し、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人