新着情報
産休で会社がやるべき対応とは?制度と手続きの全知識をプロが解説
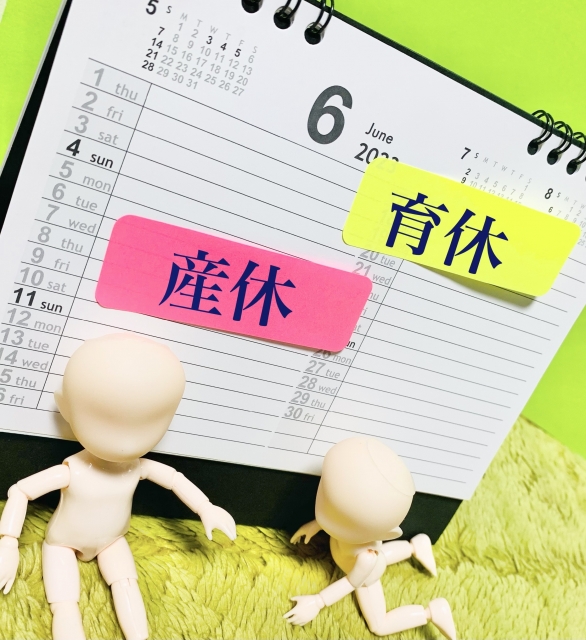
「産休の申請が出たけど、何から手を付ければいいのか分からない…」
「手続きや給与計算のミスでトラブルにならないか不安」
「就業規則に書かれているけど、実際の運用が追いついていない」
こうした悩みは、特に従業員数100名以上の中小企業で頻出しています。
東京・大阪・福岡・名古屋など都市部では女性従業員の割合が増え、産休・育休の申請件数も年々上昇中。
とはいえ、産休に関する制度は複雑で、企業としての対応も多岐にわたります。
産休の取得申請があった際、どのようなスケジュールで、どんな手続きが必要なのか、誰が対応するのかが曖昧なままでは、従業員からの信頼も損なわれ、労務トラブルにも発展しかねません。
本記事では、大阪を拠点とする社会保険労務士事務所の顧問事例をもとに、産休に関する基本知識、就業規則や給与計算への影響、そして企業が対応すべき実務の流れを、手続き・助成金・アウトソースの視点も含めて詳しく解説します。
1. 産休における会社の役割と制度理解のポイント
「産休」とは、労働基準法第65条で定められた産前産後休業の通称で、次のような期間が対象となります。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から開始
- 産後休業:出産日の翌日から8週間は原則就業不可
この期間中、企業は就業させてはいけない義務があり、同時に適切な手続きを行わなければ後々の給与計算ミスや助成金不支給につながるリスクがあります。
◆ 歴史と制度の背景
日本の産休制度は1947年に制定された労働基準法から続いています。
時代と共に女性の社会進出が進む中、現在は男性の育児参加を促す育休制度とも連動し、企業対応も複雑化しています。
◆ よくある誤解
- 「産休中も会社が給与を支払う必要がある」→×:健康保険から出産手当金が支給されます
- 「休業開始・復帰は本人の希望で自由に決められる」→△:法定期間と医師の証明が必要
◆ Aさんのケース(東京・医療法人勤務)
Aさんは妊娠8ヶ月で産休を申請。会社側が就業規則の確認を怠り、手続きが遅れて出産手当金の支給が2ヶ月遅れる事態に。
その後、顧問社労士の助言で制度を見直し、産休取得マニュアルを整備。翌年はスムーズに対応できる体制へ改善しました。
◆ 実は意外と知られてないポイント
「産休中の社会保険料免除」について、本人と会社負担の両方が対象になる制度(育児休業等期間中の保険料免除)があります。
正確な手続きで、企業負担の軽減につながるため、就業規則や給与計算と連動して確認が必要です。
2. 会社がとるべき具体的アクション8選
-
就業規則に産休・育休の詳細を明記
労使間の誤解を防ぎ、制度の公平性を保ちます。大阪の飲食チェーンでは、規則見直し後の申請トラブルがゼロに。 -
産休手続きチェックリストを整備
名古屋の中堅製造業では、チェックリスト導入後、対応時間を平均30%削減。 -
給与計算ソフトに産休モードを設定
給与支給停止や社会保険料の自動調整に対応。東京のIT企業では人的ミスゼロを実現。 -
顧問社労士と連携した制度運用
手続きミスや助成金不支給リスクを回避。福岡の医療法人では、監査対応も万全に。 -
社内周知用パンフレットやQ&A作成
従業員が安心して申請できるよう配慮。東京の物流会社で好評。 -
助成金の活用確認
育児休業給付金に加え、「両立支援等助成金」などが該当する場合も。制度活用で企業負担軽減。 -
復帰支援の仕組み構築
面談制度や短時間勤務制度の整備で職場復帰を円滑に。大阪の保育業界では離職率が半減。 -
アウトソースで手続きを代行
社会保険の届出や給与調整などはアウトソースも有効。特に複数人が同時期取得する場合に効果的。
3. よくある質問(Q&A)
Q. 産休中も給与は支払う必要がありますか?
A. 法定では給与支払い義務はありません。多くの場合、健康保険から出産手当金が支給されます。
Q. 社会保険料はどうなりますか?
A. 産休・育休中は届け出を行えば、企業・本人ともに社会保険料が免除されます。
Q. 産休はいつから申請できますか?
A. 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から取得可能。医師の証明書が必要です。
Q. 就業規則に書かれていない場合でも対応すべき?
A. はい。産休は法定義務であるため、就業規則に記載がなくても対応が必要です。
まとめ:制度対応で信頼される企業へ
産休制度は、単なる福利厚生ではなく「企業の信頼性と労務管理の成熟度」が問われる重要項目です。
本記事では、産休に関する制度の基本、給与計算や手続きのポイント、助成金活用やアウトソースの活用例を紹介しました。
特に従業員数が多くなるほど、ルールの曖昧さや対応漏れが大きな問題となります。
今後の安定運用に向けて、まずは就業規則と手続き体制の整備から始めましょう。
顧問社労士やアウトソースを活用することで、企業リスクを最小化しながら、従業員との信頼関係を築けるはずです。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人




