新着情報
法人化すると社会保険はどうなる?知らないと損する5つのポイント
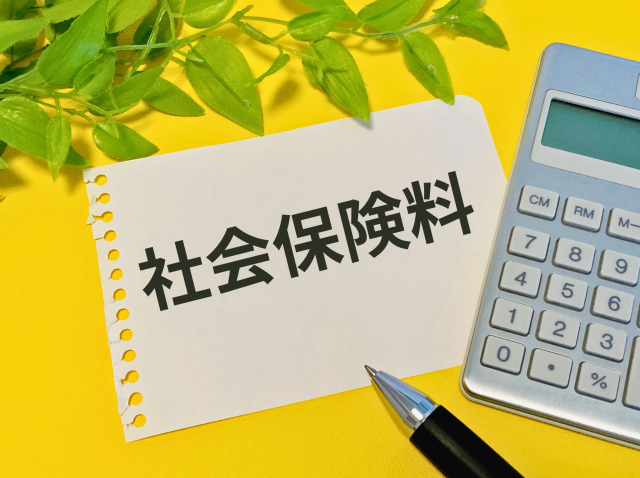
「個人事業主から法人化したけど、社会保険ってどうすればいい?」「社長1人でも加入が必要?」「手続きが面倒で放置している…」——そんなお悩み、ありませんか?法人化を検討・実施した中小企業の経営者や総務担当者が最も戸惑うのが、社会保険の取り扱いです。
導入:法人化後によくある3つの悩み
- ・「社長1人の会社でも、厚生年金や健康保険に入らないといけないの?」
- ・「役員報酬をどう決めれば保険料が最適になるのか分からない」
- ・「社会保険の手続き、どこから始めればいいのか分からない」
これらの悩みの背景には、法人化=社会保険加入義務が発生するという法制度上のルールがあります。知らないまま放置すると、後から遡って保険料を請求されたり、助成金申請が却下されたりする恐れも。
この記事では、大阪・東京・福岡・名古屋の主要都市で法人化支援を行っている社労士の視点から、法人化後の社会保険の仕組みと実務的な対応について詳しく解説します。
法人化=社会保険の加入義務が発生する理由
法人は「強制適用事業所」になる
法人化すると、従業員の有無に関係なく厚生年金保険・健康保険の強制適用事業所となり、代表取締役1人であっても加入が必要になります。これが個人事業と大きく異なる点です。
社会保険の構成と負担割合
法人が加入すべき社会保険は主に以下の4つです:
- ・健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)
- ・厚生年金保険
- ・雇用保険(従業員を雇った場合)
- ・労災保険(従業員を雇った場合)
保険料は「会社」と「役員・従業員」とで折半する仕組みです。特に厚生年金は負担額が大きく、役員報酬の金額次第で保険料も大きく変動します。
なぜ加入しないとリスクが高いのか?
- ・未加入が発覚すると最大2年分の保険料を遡って請求される
- ・助成金申請の要件を満たせず、支給対象外に
- ・退職時の年金や健康保険証の不備が従業員トラブルに
ケーススタディ:A社(大阪市・製造業)の例
法人化後も社会保険未加入のまま1年が経過。従業員5名の採用後に年金事務所の調査が入り、過去14ヶ月分の保険料を遡って支払い。経営に大きなダメージを与えた。
よくある誤解
- ・「役員報酬ゼロなら社会保険は不要」→ × 雇用関係があれば加入義務あり
- ・「赤字だから入らなくていい」→ × 法人の経営状況にかかわらず加入義務
- ・「アルバイトしかいないから不要」→ × 条件を満たせばパートでも適用対象
法人化後にすべき8つの社会保険対応アクション
- ① 社会保険の新規適用届を提出
法人設立後5日以内に年金事務所へ提出が必要。社会保険適用事業所として正式登録されます。 - ② 健康保険・厚生年金保険の加入
代表者含む役員・従業員を対象に資格取得届を提出。法人登記簿や就任承諾書などの添付書類が必要です。 - ③ 労災保険の加入(従業員雇用時)
労働基準監督署にて労災保険の成立届を提出。建設業や製造業では必須です。 - ④ 雇用保険の加入(週20時間以上勤務者)
ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出。パートタイム社員も条件次第で対象に。 - ⑤ 役員報酬額の適正設定
社会保険料は報酬額に連動するため、過剰設定は企業・本人双方に負担がかかります。節税と保障のバランスを考慮。 - ⑥ 給与計算に社会保険料控除を組み込む
毎月の給与明細に保険料を反映させる必要があります。ソフト導入や社労士の支援で対応可能。 - ⑦ 助成金の申請準備
社会保険の加入は多くの助成金の要件。福岡・名古屋などでは地域独自の支援制度もあり、加入済であることが前提です。 - ⑧ アウトソースによるミス防止
社会保険の手続きや給与計算をアウトソースすれば、ミスを防ぎ、手間を削減できます。大阪・東京などでの導入事例も多数。 - 【注意】手続きを怠ると、遡及負担が大きくなる
「あとでいいか」と放置すると、突然の調査で数十万円以上の追徴が発生することも。必ず設立直後から対応を。
よくある質問とその回答
Q. 役員1人だけでも社会保険に加入しないといけない?
A. はい。法人であれば代表者1人であっても、原則として社会保険に加入が必要です。
Q. 赤字でも保険料を払わなければならない?
A. はい。法人である限り、経営状態にかかわらず保険料の納付義務があります。
Q. 社会保険の負担が大きすぎる場合、どうすればいい?
A. 役員報酬額の見直しや、家族役員の報酬設計などで調整可能です。社労士に相談するのが最善です。
Q. 社労士に依頼すると何をしてくれる?
A. 社会保険の新規加入、給与計算、保険料の試算、助成金申請など、法人化に関する手続きを一括でサポート可能です。
まとめ:法人化後の社会保険は、最初が肝心
法人化と同時に社会保険の加入義務が発生するのは、法律上の決まりです。知らずに放置すると後々大きな負担やリスクを背負うことになります。
特に大阪・東京・名古屋・福岡といった都市部では、社会保険への適用状況を厳しくチェックされる傾向もあります。顧問社労士の支援やアウトソースを活用し、早めに対応を整えましょう。
社会保険の適正な運用は、会社の信頼性向上にもつながります。今こそ制度を正しく理解し、確実に対応していくことが求められます。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人




