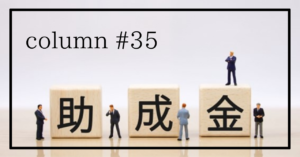新着情報
【大阪難波の社労士】リスキリング向けの助成金と補助金!実施する際のコツも解説
2023.08.22
スタッフブログ
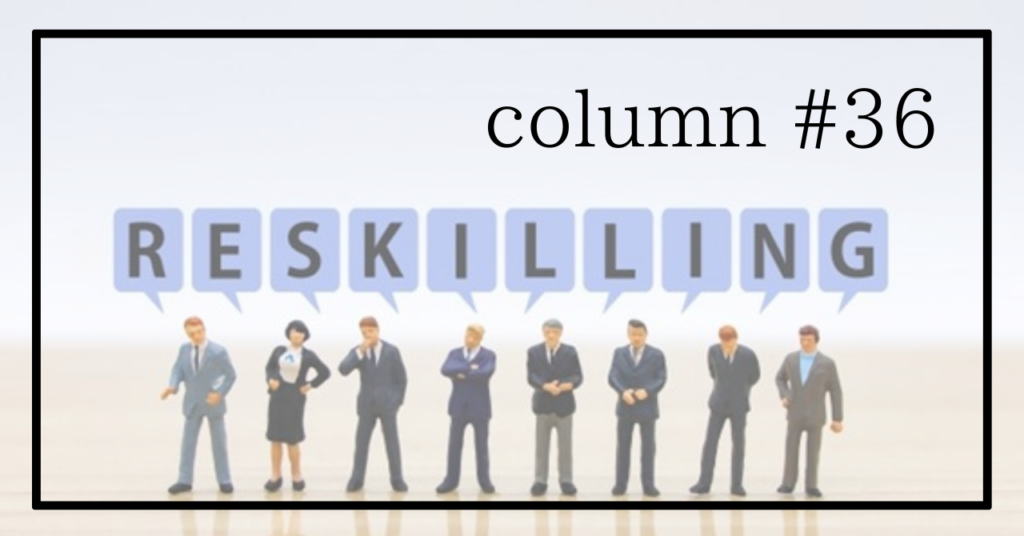
リスキリングとは新しい知識やスキルを学ぶこと
リスキリングとは英語のreskillingのことで、日本語では「新しい知識やスキルを学ぶこと」を表しています。今後新たに発生する業務に対応するために、また転職して新しい職業に就くために、必要な知識やスキルを学ぶ作業といえるでしょう。 現在日本国内でリスキリングが話題になっている理由として、主に以下のものが考えられます。- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
- 新型コロナウイルス感染症による働き方の変化
- リスキリングに関する宣言
企業がリスキリングを取り入れるメリット
企業でリスキリングを取り入れると、どのようなメリットがあるのでしょうか?主なものは次の3つです。新しい事業が生まれやすくなる
リスキリングによって、従業員が時代に合わせた最新の知識・スキルを得られます。新しいアイディアによって新しい事業が生まれやすくなり、事業拡大や売上アップなどにつながるでしょう。 また学ぶ作業を通じて自発的に行動できる人材が増え、仕事に対する従業員の満足度が向上します。効率的に業務を進められる
デジタルスキルを身につけた従業員によって、業務フローの改善や業務の自動化・スピードアップ、情報管理の一元化などが期待できます。 結果、今までよりも効率的に業務を進められ、ライフワークバランスの実現や残業代の削減といったメリットにつながるでしょう。採用コストを抑えられる
DXは専門性が高いため、DXに関する知識とスキルがある人材は採用自体が難しいのが実際です。採用するためには、高いコストが求められます。 しかし、リスキリングを通じてすでに働いている従業員に知識やスキルを身につけてもらうと、DX推進に関するコストを大幅に抑えられるでしょう。 さらに既存の従業員はすでに企業の文化や社風を知っているため、雇用管理しやすいメリットもあります。リスキリングで活用できる助成金と補助金
 プログラムの内容や導入方法などにもよりますが、企業でリスキリングを取り入れるためには一定のコストがかかります。リスキリング向けの助成金や補助金があるため、条件に合致すれば活用するのがおすすめです。
たとえば、次のようなものがあります。
プログラムの内容や導入方法などにもよりますが、企業でリスキリングを取り入れるためには一定のコストがかかります。リスキリング向けの助成金や補助金があるため、条件に合致すれば活用するのがおすすめです。
たとえば、次のようなものがあります。
- 人材開発支援助成金(厚生労働省)
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(経済産業省)
- 教育訓練給付制度(厚生労働省)
失敗しない!企業でリスキリングを実施する際のコツ
何も考えずにリスキリングを始めると、失敗する可能性が高まります。これから企業でリスキリングを実施するときは、以下で紹介するコツを知っておくとよいでしょう。従業員へリスキリングの意義を説明する
まずはリスキリングの意義を従業員へ説明しましょう。意義や目的を理解しないまま従業員に勧めても、意欲的には取り組んでもらえません。 従業員自身がメリットや重要性を理解できると、リスキリングの効果が格段にアップします。企業ごとの課題に合ったコンテンツを選ぶ
企業ごとの課題に合ったコンテンツを選ぶと、より高い効果が期待できます。 学ぶコンテンツの内容がどれだけ優れていても、企業の課題に見合った内容でなければ意味がありません。従業員の学ぶモチベーションも低下します。学習しやすい環境を整備する
働きながら無理なく学べるよう、業務の一環として就業時間内に勉強できる時間を設けるのがおすすめです。さらに外部講座や試験を受ける場合は、受講料や受験料の全額、または一部を企業が負担すると従業員の出費を抑えられます。 また一緒に学ぶ仲間がいると、離脱せずにリスキリングを継続できます。企業内で勉強会やサークルなどを設けるとよいでしょう。実践できる場を設ける
学んだ知識やスキルを実践できるチャンスがあると、定着に役立ちます。そのため、できるだけ身につけた内容に応じた実践の場を設けましょう。 すぐに実践できる業務がない場合は、将来的に想定している事業をトライアルとしてチャレンジしてもらったり、新規事業の調査・検証に携わってもらったりするのも効果的です。まとめ
リスキリングを取り入れることでDXが進み、将来に渡った企業成長が望めるようになります。リスキリング向けの助成金や補助金があるため、上手に活用するとよいでしょう。 社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。リスキリングに適した人材開発支援助成金を始め、各種助成金の申請を代行しています。 リスキリングに関する助成金でお困りの企業・担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。 【リスキリングに関連する当社のサービス】 助成金申請代行大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人