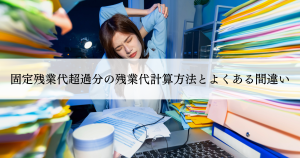新着情報
通勤手当と税金の関係解説!計算方法や非課税限度額を知ろう

会社から支給される通勤手当は、毎月の給与明細の手取り額に影響を与えます。
しかし、その計算方法や税金との関係性は複雑で分かりにくいものです。
この解説では、通勤手当と税金に関する疑問を解消し、正確な税金負担額を把握するための情報を提供します。
通勤手当は課税対象
課税対象となる通勤手当とは
通勤手当は、原則として給与の一部とみなされ、所得税や住民税の課税対象となります。
ただし、一定の条件を満たす場合は非課税扱いとなる場合もあります。
例えば、会社が定めた通勤経路や交通手段以外の利用や私的な利用が含まれる場合、超過分や私的利用分に相当する金額が課税対象となる可能性があります。
また、会社が定めた規定を超える金額や、実費精算ではなく一律支給される金額なども該当します。
さらに、これらの規定は会社によって異なるため、就業規則などを確認することが重要です。
非課税となる通勤手当の範囲
一方で、非課税となる通勤手当は、会社が定めた規定に基づき、実際に支出した通勤費用を上限として支給されるものです。
この場合、通勤経路や交通手段は会社が定めた範囲内である必要があり、私的な利用は認められません。
また、支給される金額が会社が定めた非課税限度額を超えないことが条件です。
そして、この非課税限度額は通勤距離や交通手段によって異なります。
そのため、自身の通勤状況に合わせた限度額を把握することが重要といえます。
通勤手当の非課税限度額
非課税限度額は、国税庁が定める「通勤費用の額の算定に関する基準」に基づいて計算されます。
この基準では、通勤距離や利用する交通手段に応じて、非課税と認められる通勤費用の金額が定められています。
例えば、電車通勤の場合、距離に応じて上限額が設定され、それ以上の金額は課税対象となります。
また、自家用車通勤の場合も、ガソリン代や駐車場代など、一定の条件を満たした場合に限り非課税限度額が適用されます。
さらに、この限度額は毎年改定される可能性があるため、最新の情報を税務署や国税庁のウェブサイトで確認することが大切なのです。
通勤手当にかかる税金の計算方法は?
所得税の計算方法
通勤手当にかかる所得税は、課税対象となる通勤手当の金額を給与所得に加算して計算されます。
具体的な計算方法は、給与所得から各種控除額を差し引いた課税所得に対して所得税率を適用します。
そして、所得税率は課税所得の金額によって段階的に変化します。
そのため、所得が多くなるほど税率も高くなる仕組みです。
住民税の計算方法
住民税の計算方法は、所得税と同様に、課税対象となる通勤手当の金額を給与所得に加算して計算されます。
しかし、住民税は前年の所得を基に計算されるため、その年の所得状況ではなく、前年の所得状況によって税額が決定されます。
そのため、前年の所得が高かった場合、その年の所得が少なくても住民税が高くなる可能性があるのです。
非課税通勤手当と課税通勤手当の計算例
例えば、月額5万円の通勤手当のうち、3万円が非課税、2万円が課税対象だとします。
この場合、2万円が給与所得に加算され、所得税と住民税の計算対象となります。
具体的な税額は、個々の所得状況や控除によって異なります。
また、この2万円を基に所得税と住民税の税額が計算されます。
さらに、正確な計算には、税務署や税理士に相談することが有効といえます。
通勤手当の税金の取扱い
給与天引き
多くの場合、通勤手当の税金は給与から天引きされます。
これは、会社が従業員の税金を源泉徴収する仕組みによるものです。
そして、天引きされた税金は会社から税務署に納付されます。
そのため、従業員は自身で税金を納付する手間が省けるのです。
年末調整
会社員の場合、年末に年末調整が行われます。
年末調整では、年間の給与所得や控除などを精算し、過払い分または不足分の税金を精算します。
また、通勤手当についても年末調整の対象となります。
そのため、年末調整で税金の精算が済むケースが多いです。
確定申告
確定申告は、会社員であっても、副業などで他の所得がある場合や年末調整で精算しきれない場合などに必要となる場合があります。
確定申告を行う際には、通勤手当に関する情報を正確に申告する必要があります。
例えば、医療費控除など他の控除を受ける場合、確定申告が必要となるケースもあります。
通勤手当の税金に関する情報は複雑で分かりにくい部分も多いですが、正確に理解することで自身の税金負担を適切に把握することができます。
必要に応じて税務署や税理士に相談し、疑問点を解消しましょう。
まとめ
通勤手当は、給与と同様に課税対象となる部分と非課税となる部分があります。
非課税限度額の範囲内であれば税金はかかりませんが、それを超える金額や私的利用分は所得税・住民税の対象になります。
所得税や住民税の計算には課税対象の通勤手当が給与に加算され、年末調整や場合によっては確定申告で精算されます。
自身の通勤状況や会社の規定、最新の税率を確認することで、手取り額や税負担を正確に把握できるのです。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人