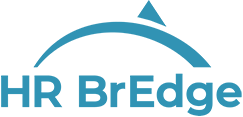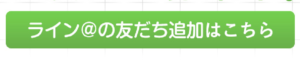新着情報
変形労働時間制」導入で失敗しない5つの秘訣と正しい残業計算
働き方改革が進む中、業務の繁閑に合わせて柔軟に労働時間を設定できる「変形労働時間制」への注目が高まっています。適切に導入すれば、無駄な残業代を削減しつつ従業員のワークライフバランスを向上させることが可能です。しかし、導入には厳格な法的要件があり、手続きの不備や誤った運用は、未払い残業代のリスクや労使トラブルに直結しかねません。

本記事では、変形労働時間制の導入を検討している企業の担当者に向けて、制度の基本から導入手続き、複雑になりがちな残業計算のルール、そして運用上の注意点までを網羅的に解説します。失敗しないための秘訣を押さえ、適正な労務管理を実現しましょう。
変形労働時間制とは?基本と導入メリットを理解する
変形労働時間制とは、一定期間(1ヶ月や1年など)を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えない範囲であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
通常、1日8時間、週40時間を超えると割増賃金(残業代)が発生しますが、この制度を活用することで、業務量に応じた柔軟な勤務設定が可能になります。主なメリットは以下の通りです。
- 残業コストの適正化: 繁忙期に所定労働時間を長く設定し、閑散期に短く設定することで、トータルの残業時間を抑制できます。
- 柔軟な働き方の実現: 従業員の希望や業務都合に合わせて、メリハリのあるシフトを組むことができます。
- 業務効率の向上: 業務量が少ない時期に早上がりや休日を増やすことで、生産性の向上が期待できます。
導入準備の第一歩:労使協定と就業規則の正しい手続き
変形労働時間制を導入するためには、法律で定められた厳格な手続きを経る必要があります。口頭での合意や、単なる慣習としての運用は認められません。必ず以下のステップを踏んでください。
- 対象労働者の範囲を決定: 全従業員に適用するか、特定の部署や職種のみに適用するかを明確にします。
- 労使協定の締結: 労働者の過半数を代表する者(または労働組合)と、書面による協定を結びます。特に「1年単位」の場合は必須です。
- 就業規則の変更と届出: 就業規則に、変形期間の起算日、各日の労働時間、対象期間などを具体的に記載し、所轄の労働基準監督署へ届け出ます。
- 社内への周知徹底: 制度の内容を従業員に十分に説明し、勤務カレンダーなどを誰でも確認できる状態にしておきます。
手続きに不備があると、制度自体が無効とみなされ、遡って多額の残業代を請求されるリスクがあるため注意が必要です。
変形労働時間制の種類別ガイド:1ヶ月・1年単位の具体的な運用
企業の業態や繁閑のサイクルによって、適した変形労働時間制の種類は異なります。ここでは代表的な2つの制度について解説します。
1ヶ月単位の変形労働時間制
毎月ごとのシフト勤務が多い業種(飲食、小売、医療介護など)に適しています。1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日や週に法定時間を超えて働かせることができます。
- 導入要件: 就業規則または労使協定のどちらかで定めることが可能です(ただし、常時10人以上の事業場は就業規則の届出が必須)。
- シフト作成の期限: 対象期間が始まる前に、各日・各週の勤務時間を確定させ、従業員に通知する必要があります。
1年単位の変形労働時間制
季節による繁閑の差が激しい業種(建設、観光、製造業の一部など)に適しています。1ヶ月を超え1年以内の期間で労働時間を調整します。
- 導入要件: 労使協定の締結と届出が必須です。
- 労働時間の上限: 1日10時間、週52時間という上限規制があり、対象期間の労働日数は原則280日が限度となります。
- カレンダーの作成: 原則として対象期間中のすべての労働日と労働時間を事前に定めなければなりません。
シフト制における残業計算の基本ルールと複雑事例の解決策
変形労働時間制における残業(時間外労働)の計算は、通常の「1日8時間超」だけでは判断できないため複雑です。以下の「3段階チェック」を順に行う必要があります。
- 第1段階(日): 就業規則等で「8時間を超える時間」を定めた日はその時間を超えた分、それ以外の日は8時間を超えた分が残業となります。
- 第2段階(週): 週の労働時間が「40時間を超える時間」を定めた週はその時間を超えた分、それ以外の週は40時間を超えた分が残業となります(※第1段階でカウントした時間を除く)。
- 第3段階(期間全体): 対象期間の総労働時間が「法定労働時間の総枠」を超えた分が残業となります(※第1、第2段階でカウントした時間を除く)。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制で、ある日に9時間のシフトを組んだ場合、その日は9時間を超えて初めて残業となります。しかし、シフト変更などで結果的に週の法定時間を超えた場合は、その超過分も割増賃金の対象となるため、勤怠管理システムの設定には細心の注意が必要です。
導入後の落とし穴:法的リスクを避けるための運用チェックポイント
制度を導入した後も、誤った運用を続けていると法的リスクを抱えることになります。特に注意すべきポイントを挙げます。
シフト変更の制限
変形労働時間制は「事前に勤務時間を特定すること」が要件です。そのため、会社都合で頻繁にシフトを変更したり、当日に時間を延長・短縮したりすることは原則として認められません。業務の都合で変更する可能性がある場合は、そのルールを就業規則に厳格に定めておく必要がありますが、乱用は制度の否認につながります。
中途入社・退職者の賃金精算
1年単位の変形労働時間制など長期の制度運用中に、期間の途中で入社または退職した従業員については、賃金精算が必要です。実際に働いた期間を平均して週40時間を超えている場合、その超過分については割増賃金を支払わなければなりません。
よくある導入失敗事例から学ぶ!避けたいトラブルとその対策
他社の失敗事例を知ることで、自社のトラブルを未然に防ぐことができます。よくある失敗パターンを紹介します。
- 事例1:周知不足による無効化
就業規則を変更したものの、従業員への周知を行わず、実態としてシフト表も共有されていなかったケース。この場合、制度自体が無効と判断され、過去2年分の未払い残業代を請求される可能性があります。 - 事例2:実態との乖離
労使協定では「1年単位」を届出しているにもかかわらず、現場ではその都度シフトを決めており、事前の年間カレンダーが存在しないケース。これは変形労働時間制の要件を満たしておらず、通常の労働時間制として扱われます。 - 事例3:管理職の理解不足
現場の管理職が制度を理解しておらず、「変形労働だから残業代は出ない」と誤解し、所定労働時間を超えた労働に対しても割増賃金を申請させなかったケース。これは明らかな労働基準法違反となります。
変形労働時間制を確実に成功させるための最終確認リスト
最後に、変形労働時間制を適正に運用するためのチェックリストを提示します。これらを満たしているか定期的に確認してください。
- 労使協定は締結し、有効期限内であるか?
- 就業規則に対象者、期間、起算日、各日の労働時間が明記されているか?
- 1年単位の場合、年間カレンダーを作成し、全従業員に周知しているか?
- 残業計算は「日・週・期間」の3段階で行われているか?
- 中途採用者や退職者の賃金精算ルールは整備されているか?
- 管理職に対して、制度の仕組みと勤怠管理の研修を行っているか?
- 実際の勤務実態が、届出した協定の内容と乖離していないか?
関連する詳しい情報はこちらのブログ一覧もご参照ください。
まとめ
変形労働時間制は、正しく導入・運用すれば企業と従業員の双方にメリットをもたらす制度です。しかし、その手続きは複雑で、日々の運用にも高い管理能力が求められます。労使協定の締結、就業規則の整備、そして正確な残業計算の3点を徹底し、法的リスクのない健全な職場環境を作りましょう。不明点がある場合は、自己判断せず専門的な情報を参照することをお勧めします。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人