新着情報
【2025年改正】雇用保険の給付制限短縮と適用拡大のポイント
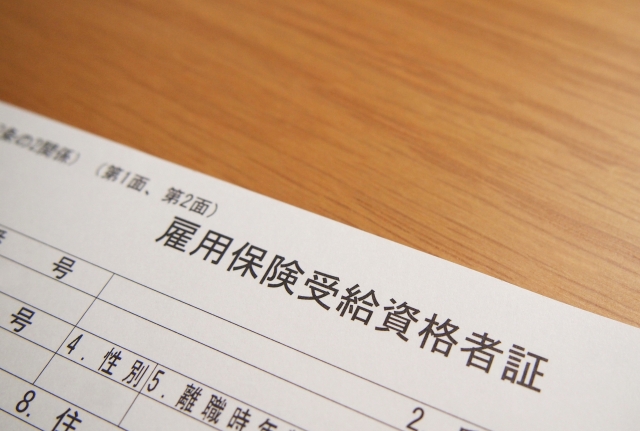
雇用保険制度の変更で手続きや負担が増えるのでは?と不安な総務担当者様へ
「また法改正で手続きが複雑になるのでは…」「給付制限短縮で退職者が増えてしまうかもしれない」そんな不安を抱えていませんか?
2025年の雇用保険法改正では、失業手当の給付制限期間の短縮や教育訓練給付の拡充が実施され、さらに2028年には週10時間以上働く労働者も雇用保険の対象となります。100名規模の企業では、パートタイマーやアルバイトを多数雇用しているケースが多く、適用範囲拡大による保険料負担増加や手続き業務の複雑化が予想されます。
一方で、この改正は企業にとってもメリットがあります。従業員のスキルアップ支援や人材流動性の向上により、組織の活性化と競争力強化につながる可能性があるのです。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、100名規模企業の経営者・総務担当者が知るべき2025年雇用保険改正の影響と対応策を詳しく解説します。制度変更を機会として活用し、従業員満足度向上と経営効率化を同時に実現する方法をお伝えします。
2025年雇用保険改正の全体像と100名規模企業への具体的影響
2025年に成立する雇用保険法の改正により、失業手当の給付制限期間の短縮や教育訓練給付の拡充が行われます。この改正は単なる制度変更ではなく、労働市場の流動性向上と人材育成の促進を目的とした戦略的な政策転換といえます。
給付制限期間短縮の企業への影響
自己都合退職者の失業手当給付制限期間が2か月から1か月に短縮されることで、退職への心理的ハードルが下がる可能性があります。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年~) | 企業への影響 |
| 給付制限期間 | 2か月 | 1か月 | 退職リスク増加の可能性 |
| 対象者 | 自己都合退職者 | 自己都合退職者 | 人材流動性向上 |
経営者の視点では、優秀な人材の流出リスクが高まる一方で、組織の新陳代謝が促進される側面もあります。総務担当者にとっては、退職手続きの頻度が増加する可能性があり、効率的な手続き体制の構築が重要になります。
教育訓練給付制度の拡充がもたらす機会
教育訓練給付の支給額が拡充され、一般教育訓練で受講料の50%(上限40万円)、専門実践教育訓練で70%(上限56万円)が支給されます。また、教育訓練を受講することで給付制限を待たずに失業手当の受給が可能になります。
これは企業にとって、従業員のスキルアップ支援に国の制度を活用できる絶好の機会です。ITスキル習得講座、語学研修、介護・福祉関連資格取得コースなど、業務に直結する教育プログラムを従業員に紹介することで、離職防止と生産性向上を同時に実現できます。
2028年適用範囲拡大への準備の重要性
2028年10月からは雇用保険の加入基準が週20時間以上から週10時間以上に拡大されます。100名規模の企業では、パートタイマーやアルバイトの雇用保険加入者が大幅に増加し、保険料負担と手続き業務が倍増する可能性があります。
早期の準備により、この変更をコスト増加要因ではなく、短時間労働者の定着率向上と採用競争力強化の機会として活用することが可能になります。
雇用保険改正を活用した戦略的人事施策と成功事例
雇用保険制度の変更を単なるコスト要因として捉えるのではなく、戦略的な人材マネジメントの機会として活用する企業が成果を上げています。以下、実際の取り組み事例と具体的な実施方法をご紹介します。
教育訓練給付を活用した人材育成プログラム成功事例
IT企業J社(従業員108名)の革新的取り組み:
2025年の制度改正を見越して、従業員向けの教育訓練支援制度を先行導入しました。会社が受講料の30%を負担し、教育訓練給付と合わせて従業員の実質負担をゼロにする仕組みを構築したところ、年間の受講者が前年比300%増加しました。
特に注目すべきは、離職率が25%から15%に改善し、従業員満足度調査でも「成長機会の提供」で高い評価を獲得したことです。総務担当者からは「制度を活用した従業員が社内で成果を発揮し、他の従業員のモチベーション向上にもつながった」との報告がありました。
製造業K社(従業員95名)の事例:
技術職の人材不足に悩んでいたK社では、既存従業員のスキルアップと新規採用を並行して進める戦略を採用しました。顧問社労士のサポートのもと、従業員に対して資格取得支援プログラムを提案し、教育訓練給付制度の活用方法を詳しく説明しました。
結果、6か月で10名が新たな技術資格を取得し、社内の技術力向上と同時に、従業員の満足度も大幅に改善しました。
段階的準備による2028年適用拡大への対応策
ステップ1:現状把握と影響分析(2025年中)
- 現在の週10~20時間労働者の正確な人数把握
- 2028年適用拡大による保険料負担増加の試算
- 手続き業務増加に伴う総務部門の工数予測
- システム改修や外部委託の必要性検討
ステップ2:制度設計と体制整備(2026年~2027年)
- 短時間労働者向けの福利厚生制度見直し
- 雇用契約書や就業規則の改定準備
- 給与計算システムの改修または変更
- アウトソース活用の検討と業者選定
ステップ3:運用開始と安定化(2028年)
- 対象労働者への制度説明と手続き実施
- 運用状況のモニタリングと改善
- 従業員満足度への影響測定
失敗を避けるための注意点
サービス業L社(従業員120名)の教訓:
「制度が変わるから対応しよう」という受け身の姿勢で準備を始めた結果、追加の手続き業務に追われるだけで、経営メリットを享受できませんでした。特に、短時間労働者への説明が不十分だったため、制度変更への不安から離職者が増加してしまいました。
この事例から学べるのは、制度変更を機会として捉え、従業員への丁寧な説明と魅力的な制度設計が重要ということです。単なる法的対応ではなく、人材戦略の一環として位置づけることが成功の鍵となります。
助成金とDXの活用による効率化
雇用保険制度の変更に合わせて、人材確保等支援助成金や業務改善助成金を活用し、システム導入や制度設計に係る費用の一部をカバーする企業も増えています。特に、給与計算システムの改修や手続きのDX化により、長期的なコスト削減効果も期待できます。
実務担当者が知りたい制度変更Q&A
Q1:給付制限短縮により退職者が増加した場合、企業はどのような対策を取るべき?
A: まず退職理由の詳細な分析が重要です。給与・待遇の問題なのか、職場環境の問題なのかを特定し、根本的な改善策を講じることが必要です。経営者としては、競合他社との待遇比較や従業員満足度調査を定期的に実施し、予防的な対策を打つことをお勧めします。総務担当者は、退職手続きの効率化とともに、引き継ぎ体制の標準化も併せて整備してください。
Q2:教育訓練給付制度を活用した従業員支援で、会社側の負担や手続きはどの程度?
A: 企業の直接的な手続き負担は多くありませんが、従業員への情報提供と相談対応が主な業務となります。効果的な活用のためには、対象となる教育プログラムのリスト化や、受講前の相談体制構築が重要です。顧問社労士と連携すれば、制度の詳細説明や申請サポートも可能で、総務担当者の負担を大幅に軽減できます。
Q3:2028年の適用拡大で、週10時間勤務のアルバイト全員を雇用保険に加入させる必要がある?
A: はい、週10時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあるすべての労働者が対象となります。ただし、学生など一部の適用除外者もいるため、個別の判断が必要です。早期の準備により、保険料負担増加を従業員の定着率向上や採用競争力強化に転換することが可能です。アウトソースの活用により、手続き業務の負担も大幅に軽減できます。
雇用保険改正を成長機会として活用し競争力を高める
2025年の雇用保険改正と2028年の適用範囲拡大は、短期的にはコストや手続き負担の増加要因となりますが、戦略的に活用すれば人材の質向上と組織力強化の絶好の機会となります。特に100名規模の企業では、大企業ほど体制が整っていない分、機動的な対応により競合他社との差別化を図ることが可能です。
重要なのは、制度変更を受け身で対応するのではなく、従業員の成長支援と組織の競争力向上につなげる積極的な姿勢です。教育訓練給付制度の活用による人材育成、短時間労働者の処遇改善による定着率向上、効率的な手続き体制の構築による総務部門の生産性向上など、多面的なメリットを享受できます。
制度変更への準備でご不安を感じていらっしゃるなら、今すぐ専門家にご相談ください。全国対応のHR BrEdge社会保険労務士法人では、2007年創業・給与計算月1万人の豊富な実績をもとに、制度変更を機会として活用する戦略的なサポートを提供いたします。LINE・Slack・Chatworkでの迅速な相談対応により、安心して制度変更に備えることができます。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人




