新着情報
給与と役員報酬、どちらがお得?そのメリット・デメリットを比較
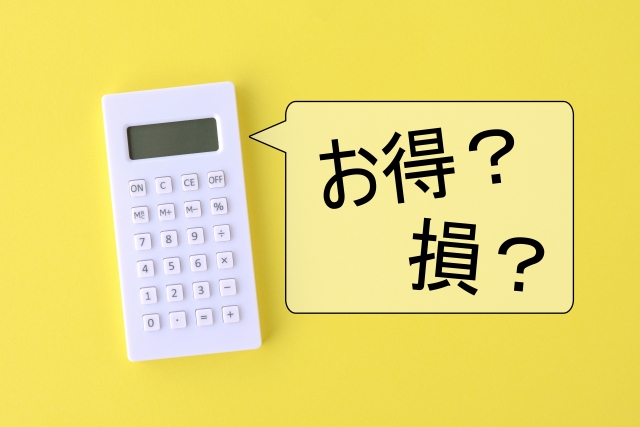
「役員報酬を高く設定しすぎて税務署から否認された」という話を聞いたことはありませんか?
「経営者として適正な報酬を受け取りたいが、税務リスクが心配…」
「給与と役員報酬の使い分けがよくわからない…」
「役員報酬の決定方法や手続きが複雑すぎる…」
100人規模の企業では、経営者や役員の報酬設定が会社の税負担と個人の手取り収入に大きな影響を与えます。しかし、給与と役員報酬の違いや最適な設定方法を正確に理解せずに運用している企業も多く、税務調査で問題を指摘されるケースや、不適切な設定により税負担が増加している事例が後を絶ちません。
特に総務担当者にとって、役員報酬の決定手続き、給与計算との区別、社会保険の適用、そして税務上の適正性確保は、専門的な知識を要する複雑な業務となっています。さらに、不適切な役員報酬設定は会社法違反や税務否認のリスクも伴うため、慎重な対応が求められます。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、給与と役員報酬の適切な使い分け、税務リスクを回避する報酬設定方法、そして経営効率を最大化する実践的なアプローチを詳しく解説いたします。
給与と役員報酬の選択が企業経営に与える決定的影響
給与と役員報酬の選択は、単なる「報酬の支払い方法」ではなく、企業の税負担、キャッシュフロー、そして経営者のリスク管理に直結する重要な経営判断です。適切な選択により、年間数百万円の税負担軽減効果を得ることも可能です。
経営者が理解すべき給与と役員報酬の根本的違い
給与は従業員が労働の対価として受け取る報酬で、労働基準法の適用を受けます。一方、役員報酬は会社の役員に支払われるもので、労働基準法の対象外となり、会社法や税法の規制を受けます。
この違いが生む具体的な影響:
法的位置づけの違い:
- 給与:労働契約に基づく対価、最低賃金や残業代の適用あり
- 役員報酬:委任契約に基づく対価、労働法規の適用なし
- 決定手続き:給与は就業規則で規定、役員報酬は株主総会等で決議
- 変更の自由度:給与は相対的に柔軟、役員報酬は期中変更に制限
税務上の扱いの違い:
- 会社側:給与も役員報酬も損金算入可能(適正額に限る)
- 個人側:どちらも給与所得として所得税の対象
- 社会保険:両方とも厚生年金・健康保険の対象
- 適正性判断:役員報酬は税務署による厳格なチェック対象
役員報酬設定による税務メリットとリスク
適切な役員報酬設定により得られる具体的な税務メリット:
ケーススタディ(年間利益2,000万円の企業):
- 役員報酬なしの場合:法人税約600万円
- 適正な役員報酬1,200万円の場合:法人税約240万円
- 税負担軽減効果:約360万円(ただし個人の所得税は増加)
一方で、不適切な設定によるリスク:
- 過大役員報酬の否認:超過分は損金不算入
- 定期同額給与の要件違反:期中変更による損金不算入
- 税務調査での重点チェック項目
- 追徴税額に加えて重加算税(35%)の可能性
総務担当者が直面する役員報酬管理の複雑性
役員報酬の管理は、給与計算以上に複雑で専門的な知識が求められます:
- 決定手続きの管理:株主総会議事録の作成と適正な決議手続き
- 定期同額給与の維持:期中変更時の税務リスクチェック
- 適正額の判断:同業他社との比較や業績との相関性検証
- 社会保険の手続き:役員の資格取得・喪失手続きの特殊性
- 給与計算との区分:システム上での適切な処理と帳簿管理
給与と役員報酬の戦略的活用で税負担を最適化した成功事例
適切な給与と役員報酬の組み合わせにより、税負担の最適化と経営効率の向上を実現した企業の事例から、実践的な設定方法を学んでみましょう。
成功事例1:製造業DDD社の段階的報酬最適化
金属加工業のDDD社(従業員数115名)では、3年間の段階的な役員報酬見直しにより、年間500万円の税負担軽減を実現しています。
DDD社の戦略的アプローチ:
- 現状分析と目標設定
既存の給与体系と税負担を詳細に分析し、最適化の目標を設定 - 段階的な役員報酬引き上げ
税務リスクを回避しながら3年間で適正水準まで段階的に調整 - 従業員給与とのバランス調整
役員報酬の変更に合わせて従業員給与体系も見直し - 専門家による継続監査
顧問税理士・社労士による定期的な適正性チェック
結果として、法人税の削減と個人所得の最適化を両立させています。
成功事例2:IT企業EEE社のアウトソース活用
システム開発会社のEEE社(従業員数95名)では、役員報酬の設定と管理を専門家にアウトソースすることで、効率的な運用を実現しています。
アウトソース活用範囲:
- 適正な役員報酬水準の調査と提案
- 株主総会決議の手続きサポート
- 定期同額給与の要件確認と維持管理
- 税務調査対応と根拠資料の整備
専門家のサポートにより、税務リスクを回避しながら最適な報酬設定を継続しています。
失敗事例:サービス業FFF社の役員報酬設定ミス
清掃サービス業のFFF社(従業員数100名)では、不適切な役員報酬設定により税務調査で否認を受けてしまいました。
失敗の原因:
- 同業他社との比較検討を怠り、業績に見合わない高額設定
- 期中での役員報酬変更により定期同額給与の要件に違反
- 株主総会での適正な決議手続きを省略
- 根拠資料の整備不足で説明責任を果たせず
この結果、3年間で総額1,200万円の追徴課税を受け、専門家との連携体制を構築することになりました。
DX化による報酬管理の効率化事例
建設業のGGG社(従業員数105名)では、人事管理システムと会計システムの連携により、給与と役員報酬の統合管理を実現しています。
システム導入効果:
- 給与と役員報酬の自動区分計算
- 適正額チェック機能による税務リスク軽減
- 決議手続きのワークフロー管理
- 税務調査対応資料の自動生成
給与・役員報酬でよくある疑問にお答えします
Q1:役員報酬の適正額はどのように判断すればよいですか?
A:会社の規模、業績、同業他社の水準、職務内容などを総合的に勘案して判断する必要があります。
税務署は、①その法人の売上高・利益率等の規模、②同業同規模の他社の役員報酬水準、③その役員の職務内容・責任、④その法人の業績・経営状況などを基準に適正性を判断します。一般的には、従業員の最高給与の2~5倍程度が目安とされていますが、根拠となる資料の整備が重要です。同業他社のデータや職務分析書などを準備することをお勧めします。
Q2:期中で役員報酬を変更することは可能ですか?
A:原則として期中変更は税務上の損金算入が認められませんが、一定の要件下では可能です。
定期同額給与の原則により、期中での役員報酬変更は損金不算入となります。ただし、①業績悪化改定事由(著しい業績悪化等)、②臨時改定事由(職制上の地位の変更等)に該当する場合は変更可能です。変更には取締役会決議等の適正な手続きが必要で、税務署に対する説明責任も生じます。慎重な判断と専門家への相談が重要です。
Q3:役員が従業員を兼務している場合の給与計算はどうなりますか?
A:役員報酬部分と従業員給与部分を明確に区分し、それぞれ適正に計算する必要があります。
兼務役員の場合、役員としての職務に対する報酬は役員報酬として、従業員としての職務に対する報酬は給与として取り扱います。重要なのは職務内容を明確に区分し、それぞれに対応する報酬額を合理的に設定することです。労働時間や職務の割合に応じた按分計算が一般的ですが、税務調査では詳細な説明が求められるため、根拠資料の整備が不可欠です。
給与と役員報酬の戦略的活用で企業価値を最大化する
給与と役員報酬の適切な設定と管理は、企業の税負担最適化と持続的成長を支える重要な経営戦略です。法的要件を満たしながら、経営者の適正な処遇と会社の財務効率を両立させることで、企業価値の向上を実現することができます。
重要なのは、税務リスクを回避しながら最適な報酬設計を行い、継続的な見直しを実施することです。また、従業員の給与とのバランスを考慮し、組織全体のモチベーション向上につながる公平で透明性の高い報酬制度を構築することが求められます。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、2007年の創業以来、50社を超える顧問先で適正な役員報酬設定をサポートしてきました。「ミスを出さない仕組み」「連絡のしやすさ」「成長に合わせた支援内容」を重視し、あなたの会社に最適な報酬戦略をご提案します。
税理士との連携による税務最適化から、給与計算システムの効率化まで、包括的なサポートにより、法令遵守と経営効率を両立する報酬制度の構築をお手伝いいたします。
給与・役員報酬の設定でお悩みの経営者・総務担当者の皆様、今すぐ無料相談で現状の課題を整理し、最適な報酬戦略の構築を始めてみませんか?適正な報酬設計により、企業の成長と経営者の安心を同時に実現する仕組みを一緒に作り上げましょう。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人



