新着情報
残業代の計算方法、基本は?給与形態・業種・事業規模別の計算式と割増率、専門用語解説と、Excelテンプレート
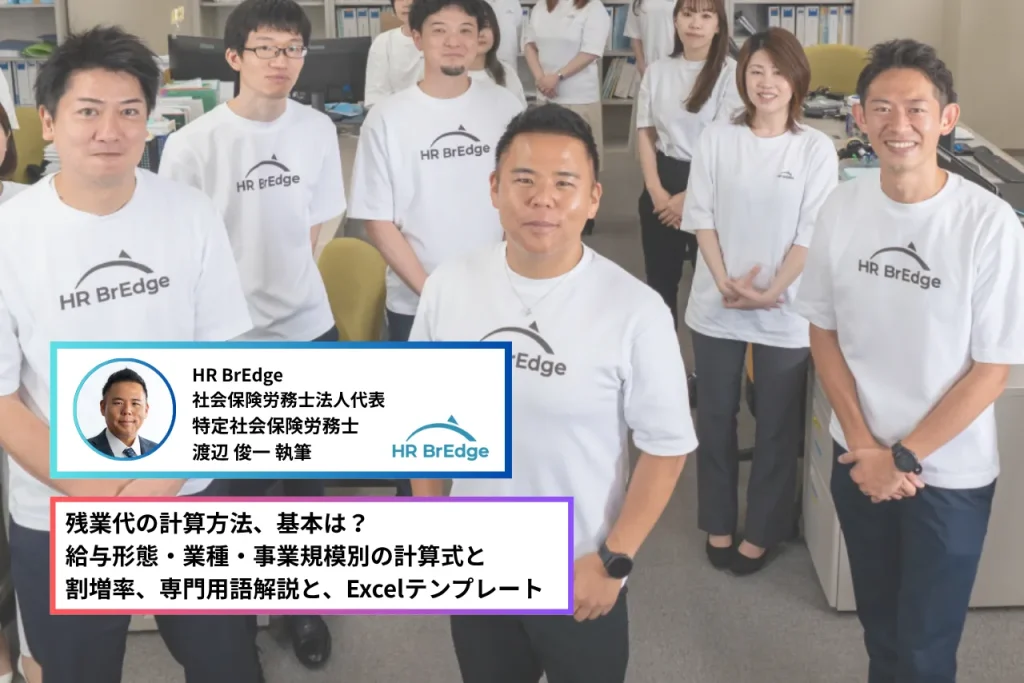
残業代の計算方法は「基礎時給×残業時間×割増率」という基本式で行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 残業代の計算方法基本式 | 残業代 = 基礎時給 × 残業時間 × 割増率 |
しかし、給与形態によって基礎時給の計算方法が異なり、月給制、時給制、日給制、年俸制などそれぞれに適した計算方法があります。
また、業界や業種、事業区分によっても、残業代の計算方法はさまざまです。
この記事では、社労士の視点から残業代の正確な計算方法を網羅的にお伝えします。
記事の中では、多くの事例をご紹介しますので、よろしければ、後述の目次もご活用頂きながら、貴社の業種にあっているトピックをご確認ください。
また、給与形態別、雇用形態別の具体的な計算例やシミュレーションも豊富に用意していますので、企業の経理担当者の方であれば、残業代の計算作業の理解につながります。
残業代計算のExcelダウンロードはHR-BrEdge法人_残業代計算のテンプレートからご利用ください。
もちろん、ご自身で自分の残業代が正しく計算されているか知りたい方も、ご自身の残業代について、しっかり理解することができます。
残業代の計算方法|基本の計算式と3つのステップ
残業代を正確に計算するためには、3つのステップを順番に進める必要があります。
まず基礎時給を算出し、次に残業時間を正確に把握し、最後に適切な割増率をかけて残業代を計算します。
このプロセスを理解すれば、どのような給与形態でも残業代を正しく計算できるようになります。
残業代の計算方法は、非常にシンプルですが、残業代計算にあたって、いくつか注意するポイントがあります。
それが、「この計算の基礎時給に、どのような給与・賞与・手当・時給が含まれるのか。」
「この計算の基礎時給に、どのような賃金、賞与が、含まれないのか。」の見分け方・振り分けです。
残業代の計算方法、基本式
まず、残業代の計算方法・計算式は下記のようになります。
|
・残業代の計算方法、基本式 = 「残業代=基礎時給×残業時間×割増率」 というのが基本の計算式になります。 |
| 区分 | 割増率・説明 |
|---|---|
| 法定時間外労働 | 25%(基礎時給の1.25倍)。 ※1か月60時間を超えた部分は50%(1.5倍)。 |
| 深夜労働(22:00〜5:00) | 25%(基礎時給の1.25倍)。時間外や休日と重なる場合は加算。 |
| 休日労働(法定休日) | 35%(基礎時給の1.35倍)。深夜と重なる場合はさらに加算。 |
この式における基礎時給とは、1時間あたりの賃金のことを指します。
残業時間は法定労働時間を超えて働いた時間、
割増率は労働基準法で定められた最低の割増率以上の率を適用します。
たとえば、
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条件 | 基礎時給1,500円 × 残業20時間 × 割増率1.25 |
| 残業代 | 37,500円 |
この計算式を基本として、給与形態や労働時間制度に応じて計算方法を調整していきます。
残業代の計算方法・ステップ① 基礎時給(1時間あたりの賃金)を計算する
残業代計算の最初のステップは、基礎時給を正確に算出することが大切です。
基礎時給は、月給や日給などの給与を時間単位に換算(月給や日給など、就業規則等で定められた金額を、時間で割ったもの)したものであり、この計算が正確でないと残業代全体が間違ってしまいます。
残業代の計算方法①-1.基礎時給を計算する。〜基礎時給の計算方法〜
残業代計算における、基礎時給の計算式は下記のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 式 | 基礎時給 = (基本給 + 諸手当) ÷ 月平均所定労働時間 |
ここで重要なのは、基本給だけでなく、一定の手当も含めて計算する必要があるという点です。
また、月平均所定労働時間は会社ごとに異なりますので、正確な数値を使用する必要があります。
残業代の計算方法①-2. 月平均所定労働時間を把握する。 〜月平均所定労働時間の計算方法〜
次に、残業代計算においては、月平均所定労働時間を把握しておく必要があります。
計算式は下記のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 式 | (365日 − 年間休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12 |
下記に、計算事例をご紹介します。
| 条件 | 結果 |
|---|---|
| 年間休日120日・1日8時間 | (365−120)×8 ÷ 12 = 163.3時間 |
ここで算出した、月平均所定労働時間を参考に、下記のように基礎時給を算出します。
| 条件 | 計算・結果 |
|---|---|
| 月給25万円・月平均163.3時間 | 250,000 ÷ 163.3 ≒ 1,531円 |
この基礎時給が残業代計算のベースになります。
残業代の計算方法①-3.基礎賃金に含まれる手当・除外できる手当を把握する
残業代の計算における基礎賃金には、
基本給だけでなく様々な手当も含まれますが、労働基準法によって除外できる手当も定められています。
これを正確に理解することが、適正な残業代計算の鍵となります。
基礎賃金に含まれる手当としては、
役職手当、資格手当、皆勤手当、職務手当、技術手当などがあります。
これらの手当は、
労働者の勤務成績や業務内容に密接に関連しているため、残業代の計算基礎に含める必要があります。
たとえば、
| 条件 | 内容・結果 |
|---|---|
| 基本給20万円+役職手当5万円 | 基礎賃金=25万円(この合計を基礎時給の分母に使用) |
一方、労働基準法第37条第5項および労働基準法施行規則第21条により、基礎賃金から除外できる手当も定められています。
まず、家族手当は扶養家族の人数に応じて支給される手当であり、労働の対価としての性質が薄いため除外できます。通勤手当も実費弁償的な性格を持つため除外可能です。
同様に、別居手当、子女教育手当、住宅手当も基礎賃金から除外できます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 基礎賃金から除外できる手当、実費弁償・家族関連 | 家族手当/通勤手当/別居手当/子女教育手当/住宅手当(実費性が明確な場合) |
| 基礎賃金から除外できる手当、臨時・長期周期 | 臨時に支払われた賃金/1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
ただし、これらの手当であっても、名称だけで判断するのではなく、実態に即して判断する必要があります。
例えば、住宅手当が基礎賃金から除外できるのは、賃貸住宅居住者に対して家賃の一定割合を補助するなど、実費弁償的な性格を持つ場合に限られます。
また、臨時に支払われた賃金や、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与やボーナスなど)も基礎賃金から除外できます。
ただし、賞与が年3回以下の支給であれば基礎賃金に含める必要はありませんが、年4回以上支給される場合は、賃金の一部とみなされ基礎賃金に算入する必要があります。
| 区分 | 内容・計算例 |
|---|---|
| 年3回以下 | 臨時的支給とみなし、基礎賃金に算入しない。 |
| 年4回以上(定期支給) | 実質的に定期賃金とみなし、基礎賃金に算入する場合あり。 例:基本給25万円+手当5万円、四半期賞与10万円×4回=年40万円 → 40万円÷12=約3.3万円を月額に加算。 基礎月額=25万+5万+3.3万=33.3万円 |
実務上は、給与明細を確認し、どの手当が基礎賃金に含まれるのかを正確に判断することが重要です。不明な点がある場合は、就業規則や賃金規程を確認するか、労務担当者や社労士に相談することをお勧めします。
残業代の計算方法・ステップ② 残業時間を正確に計算する
基礎時給が算出できたら、次は残業時間を正確に把握する必要があります。
残業時間の計算を誤ると、基礎時給が正確であっても、正しい残業代計算ができないケースも考えられます。
残業代の計算方法・ステップ②-1. 残業時間の計算方法|1分単位での計算が原則
労働時間は1分単位で正確に把握し、計算することが労働基準法上の原則です。
15分単位や30分単位で切り捨てて計算することは、労働基準法違反となります。
たとえば、8時間10分働いた場合、残業時間は10分(0.17時間)として計算しなければなりません。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 1分単位の把握・計算 | 労働時間は1分単位で正確に把握・計算するのが原則。 |
| 切り捨て計算の禁止 | 15分/30分単位の切り捨ては違法。端数処理は「月の合計」でのみ許容。 |
| 計算例 | 8時間10分勤務 → 残業10分(0.17時間)として計算。 |
| 客観的記録の活用 | タイムカード/ICカード/PCログ等で出退勤を正確把握。 |
| 実労働時間の算出 | (終業−始業)− 休憩 = 実労働時間。 |
| 所定外労働時間 | 実労働時間 − 所定労働時間 = 所定外労働時間。 |
| 時間外労働(割増対象) | 法定労働時間(1日8h/週40h)超過分が割増対象。 |
タイムカードやICカード、PCログなどの客観的な記録から、出勤時刻と退勤時刻を正確に把握します。
始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた時間が実労働時間となります。
この実労働時間から所定労働時間を引いた時間が、所定外労働時間です。
さらに、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える部分が、割増賃金の対象となる時間外労働となります。
1分単位で計算すると聞くと複雑に思えるかもしれませんが、最近の勤怠管理システムや給与計算ソフトでは自動的に1分単位で計算してくれます。
もちろん、私たち社労士法人にお任せすることも可能です。
手計算で行う場合は、分を60で割って時間に換算します。
たとえば、10分であれば10÷60≒0.17時間として計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間換算(手計算) | 分を60で割って時間に換算します(時間=分÷60)。例:10分 → 10÷60≒0.17時間。 |
| 換算の例 | 5分=0.08h/10分=0.17h/15分=0.25h/30分=0.50h/45分=0.75h(小数第3位以降は社内ルールに従い処理)。 |
| 端数処理の原則 | 労働基準法上、1か月の合計時間については端数処理が認められています。 |
| 月合計での端数処理 | 30分未満は切り捨て/30分以上は1時間に切り上げは違法ではありません(あくまで月合計に限る)。 |
| 禁止事項(重要) | 1日ごとの労働時間で端数を切り捨てることは違法。端数処理は月の合計時間にのみ適用可。 |
ただし、労働基準法では一定の端数処理が認められています。1ヶ月の労働時間の合計について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは違法ではありません。
重要なのは、1日ごとの労働時間で端数を切り捨てることは違法だという点です。あくまで1ヶ月の合計時間で端数処理を行う場合にのみ、この方法が認められています。
残業時間の種類と判定方法
残業時間にはいくつかの種類があり、それぞれ判定方法が異なります。正確に残業代を計算するには、どの時間がどの種類の残業に該当するかを判断する必要があります。
まず、1日8時間を超える労働は時間外労働となります。
| 区分 | 説明・適用条件 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間超) | 1日8時間を超える労働は時間外労働に該当します。 例:9時〜19時勤務・休憩1時間の場合、実労働9時間のうち1時間が時間外労働となり、25%以上の割増賃金が必要です。 |
| 所定外労働(法定内残業) | 会社の所定労働時間が7時間など短い場合、7〜8時間の労働は所定外労働となります。 この部分は法定内労働にあたり、割増賃金は不要(ただし就業規則で支給する場合あり)。 |
| 週40時間超の時間外労働 | 1日8時間以内でも、週の労働時間が40時間を超えた場合、その超過分は時間外労働です。 例:月〜金8時間勤務+土曜5時間勤務=週45時間 → 超過5時間に25%割増。 |
| 月60時間超の時間外労働 | 2023年4月から中小企業にも適用。 1か月の時間外労働が60時間を超える部分については、50%以上の割増が必要です。 例:月70時間の時間外労働 → 60時間までは25%、残り10時間は50%割増。 |
| 割増率の適用まとめ | ・所定外(法定内)労働:通常賃金または規程により支給 ・時間外(法定外)労働:25%以上割増 ・月60時間超過部分:50%以上割増 正確な残業代計算のためには、各時間の区分を正確に判定することが重要です。 |
たとえば、9時から19時まで働き、休憩が1時間であれば、実労働時間は9時間です。このうち8時間を超える1時間が時間外労働となり、25%以上の割増賃金が必要です。
ただし、所定労働時間が7時間の会社の場合、7時間から8時間までの1時間は所定外労働時間ですが法定内労働なので、割増賃金は不要です(就業規則で定めがあれば支給)。
8時間を超える部分から割増が必要になります。
次に、週40時間を超える労働も時間外労働です。
1日8時間以内でも、週の労働時間が40時間を超えた場合、その超過分には割増賃金が必要です。
たとえば、月曜から金曜まで毎日8時間働き、土曜日に5時間働いた場合、週の労働時間は45時間となり、40時間を超える5時間分には25%の割増が必要です。
月60時間以上の時間外労働については、2023年4月から中小企業にも50%以上の割増率が適用されるようになりました。
1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合、60時間までの部分は25%割増、60時間を超える部分は50%割増となります。
たとえば、月に70時間の時間外労働があった場合、60時間分は25%割増で計算し、残りの10時間分は50%割増で計算します。
このように、残業時間の種類を正確に判定し、それぞれに適切な割増率を適用することが、正確な残業代計算には不可欠です。
残業代の計算方法・ステップ③ 割増率をかけて残業代を算出する
基礎時給と残業時間が分かったら、最後に適切な割増率をかけて残業代を算出します。割増率は労働基準法で最低限の率が定められており、会社はこれ以上の率を設定することができます。
割増賃金の種類と割増率一覧
労働基準法では、時間外労働、深夜労働、休日労働に対して、それぞれ割増賃金の支払いが義務付けられています。それぞれの割増率について詳しく見ていきましょう。
時間外労働の割増率は25%以上です。
法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて働いた場合、その超過時間については通常の賃金に25%を上乗せした金額を支払う必要があります。
計算式で表すと、「基礎時給×1.25×時間外労働時間」となります。たとえば、基礎時給が1,500円で2時間の時間外労働があった場合、1,500円×1.25×2時間=3,750円が残業代となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 基礎時給 × 1.25 × 時間外労働時間 |
| 条件例 | 基礎時給:1,500円 / 時間外労働:2時間 / 割増率:25%(1.25倍) |
| 計算過程 | 1,500円 × 1.25 × 2時間 = 3,750円 |
| 結果 | 残業代:3,750円 |
月60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率が適用されます。
これは2023年4月から中小企業にも適用されるようになった制度です。
1ヶ月の時間外労働が60時間を超える部分については、通常の賃金に50%を上乗せした金額、つまり基礎時給の1.5倍の金額を支払う必要があります。
また、深夜労働の割増率は25%以上です。
深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯に働くことを指します。
この時間帯に働いた場合、通常の賃金に25%を上乗せした金額を支払います。
深夜労働の割増は、時間外労働の割増とは別に計算されます。
つまり、時間外労働かつ深夜労働の場合は、両方の割増が加算されます。
休日労働の割増率は35%以上です。法定休日に働いた場合、通常の賃金に35%を上乗せした金額、つまり基礎時給の1.35倍の金額を支払う必要があります。
法定休日とは、週1日または4週4日の休日のことを指します。多くの会社では日曜日を法定休日としています。
時間外労働と深夜労働が重なる場合、割増率は50%以上になります。
つまり、基礎時給×1.5となります。これは、時間外労働の25%と深夜労働の25%を合算したものです。
たとえば、午後11時まで残業した場合、午後10時までの残業は時間外労働として25%割増、午後10時から11時までの1時間は時間外労働と深夜労働の両方に該当するため50%割増となります。
休日労働と深夜労働が重なる場合、割増率は60%以上になります。
| 区分 | 内容・割増率 |
|---|---|
| 深夜労働 | 割増率:25%以上 対象時間帯:午後10時〜午前5時。 この時間帯の労働に対しては、通常の賃金に25%を上乗せした金額を支払う必要があります。 |
| 時間外労働+深夜労働 | 割増率:50%以上(基礎時給×1.5) 時間外労働(25%)+深夜労働(25%)が重なる場合は合算されます。 例:午後11時まで残業した場合、 午後10時まで=時間外労働25%、 午後10時〜11時=時間外+深夜で50%割増。 |
| 休日労働 | 割増率:35%以上(基礎時給×1.35) 法定休日に勤務した場合に適用。 法定休日=週1日または4週4日(多くは日曜)。 |
| 休日労働+深夜労働 | 割増率:60%以上(基礎時給×1.6) 休日労働(35%)+深夜労働(25%)を合算。 例:法定休日の午後10時〜午前5時勤務=60%割増。 |
| 会社独自の割増率設定 | これらの割増率は法定の最低基準。 就業規則や労働契約書で、より高い割増率が定められている場合はその率を適用します。 |
| 実務上の留意点 | 実際の残業代を計算する際は、自社の就業規則を確認し、適用される割増率を正確に把握することが重要です。 |
これは、休日労働の35%と深夜労働の25%を合算したものです。法定休日に午後10時から午前5時の時間帯に働いた場合、基礎時給×1.6で計算します。
これらの割増率は最低限の率であり、会社はこれ以上の率を就業規則を定めることで、設定することができます。
就業規則や労働契約書で、より高い割増率が定められている場合は、その率を適用します。
実際の残業代を計算する際は、自社の就業規則を確認し、適用される割増率を正確に把握することが重要です。
【給与形態別】残業代の具体的な計算方法とシミュレーション
残業代の計算方法は、給与形態によって基礎時給の算出方法が異なります。
月給制、時給制、日給制、年俸制、歩合給など、それぞれの給与形態に応じた正確な計算方法を理解することが重要です。
ここでは、各給与形態別に具体的な計算例とシミュレーションを示しながら、実務で使える知識を詳しく解説します。
時給制の残業代計算方法(パート・アルバイト・バイト)
時給制は、パートやアルバイト、バイトの方に多い給与形態です。
時給制の場合、時給そのものが基礎時給となりますので、計算は比較的シンプルです。
ただし、法定労働時間を超えた場合には、月給制の正社員と同様に割増賃金が必要になります。
パート・アルバイトの残業代計算方法
パートやアルバイトであっても、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えれば、25%以上の割増賃金が発生します。
時給制の場合、時給がそのまま基礎時給となりますので、「時給×割増率×残業時間」で計算します。
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 条件 | 時給:1,200円 / 勤務時間:10時間(8時間+残業2時間) |
| 通常勤務(8時間まで) | 1,200円 × 8時間 = 9,600円 |
| 時間外労働(2時間) | 1,200円 × 1.25 × 2時間 = 3,000円 |
| 合計賃金 | 9,600円 + 3,000円 = 12,600円 |
このように、時給制であっても法定労働時間を超えた部分には割増賃金が必要です。
パートやアルバイトだから残業代が出ないということはありません。
バイトの深夜労働を含む残業代計算方法
アルバイトやバイトの方が深夜時間帯(22時〜5時)に働く場合、深夜割増25%が加算されます。
さらに、時間外労働と深夜労働が重なる場合は、両方の割増が適用されます。
| 時間帯 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 時給:1,200円 / 勤務:17時〜23時(休憩1時間)= 実労働5時間 |
| 17時〜22時(5時間のうち通常労働) | 通常時給:1,200円 × 4時間 = 4,800円 |
| 22時〜23時(深夜1時間) | 深夜割増:1,200円 × 1.25 × 1時間 = 1,500円 |
| 合計賃金 | 4,800円 + 1,500円 = 6,300円 |
残業代の計算方法・時給制で1時間・30分・15分単位の計算
時給制の場合、1時間未満の残業についても1分単位で計算する必要があります。
| 残業時間 | 計算方法(時給1,200円の場合) |
|---|---|
| 1時間残業 | 1,200円 × 1.25 × 1時間 = 1,500円 |
| 30分残業 | 1,200円 × 1.25 × 0.5時間 = 750円 |
| 15分残業 | 1,200円 × 1.25 × 0.25時間 = 375円 |
| 10分残業 | 1,200円 × 1.25 × 0.17時間 ≒ 255円 |
| 計算のポイント | 分を時間に換算する場合:分 ÷ 60 = 時間 例:15分 ÷ 60 = 0.25時間 / 30分 ÷ 60 = 0.5時間 |
日給制・日給月給制の残業代計算方法
日給制は、建設業や運送業など、日単位で給与が決まる業種に多い給与形態です。
日給月給制は、月給制の一種ですが、欠勤があった場合に日割りで控除される制度です。
日給制の残業代計算方法と基礎時給の出し方
日給制の場合、まず日給を1日の所定労働時間で割って基礎時給を算出します。
計算式は「基礎時給=日給÷1日の所定労働時間」となります。
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 条件 | 日給:8,000円 / 1日の所定労働時間:8時間 |
| 基礎時給の計算 | 8,000円 ÷ 8時間 = 1,000円 |
| 1時間残業の場合 | 1,000円 × 1.25 × 1時間 = 1,250円 |
| 2時間残業の場合 | 1,000円 × 1.25 × 2時間 = 2,500円 |
| 1日の総賃金(2時間残業) | 日給8,000円 + 残業代2,500円 = 10,500円 |
日給制の深夜残業を含む残業代計算方法
日給制でも、深夜時間帯(22時〜5時)に働いた場合は深夜割増が適用されます。
| 時間帯 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 日給:8,000円(基礎時給1,000円) / 所定労働:8時間 / 残業:20時〜24時(4時間) |
| 通常の時間外労働(20時〜22時) | 1,000円 × 1.25 × 2時間 = 2,500円 |
| 深夜の時間外労働(22時〜24時) | 1,000円 × 1.5 × 2時間 = 3,000円 ※時間外25%+深夜25%=50%割増 |
| 残業代合計 | 2,500円 + 3,000円 = 5,500円 |
| 1日の総賃金 | 日給8,000円 + 残業代5,500円 = 13,500円 |
日給月給制の残業代計算方法
日給月給制とは、月給制の一種で、欠勤があった場合に日割りで控除される制度です。
残業代の計算方法は、基本的に月給制と同じです。
月給を月平均所定労働時間で割って基礎時給を算出し、残業時間と割増率をかけて計算します。
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 日給月給制の定義 | 月給で支給されるが、欠勤があると日割りで控除される給与形態 |
| 基礎時給の計算方法 | 月給 ÷ 月平均所定労働時間 = 基礎時給 |
| 計算例(条件) | 月給:24万円 / 月平均所定労働時間:173.3時間 / 残業:15時間 |
| 基礎時給 | 240,000円 ÷ 173.3時間 ≒ 1,385円 |
| 残業代 | 1,385円 × 1.25 × 15時間 = 25,969円 |
| 注意点 | 欠勤控除の有無は残業代計算には影響しません。 基礎時給の算出方法は通常の月給制と同じです。 |
日当制の残業代計算方法
日当制は、日給制と似ていますが、出張手当や営業手当として支給される場合があります。
日当に残業代が含まれているとされる場合でも、法定労働時間を超える部分については別途割増賃金の支払いが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日当制とは | 1日単位で支給される手当。出張日当、営業日当などがある。 |
| 基礎時給の算出 | 日当 ÷ 所定労働時間 = 基礎時給 この基礎時給をもとに残業代を計算します。 |
| 「日当に残業代が含まれる」という主張 | 日当に残業代が含まれるとしても、法定労働時間を超える部分は別途割増賃金が必要。 どの時間分の残業代が含まれているか明示されていない場合、無効となる可能性があります。 |
| 適法な固定残業代との違い | 固定残業代として認められるには、①通常賃金と残業代の明確な区別、②残業時間数の明示、③超過分の支払いが必要です。 単に「日当に残業代含む」では不十分です。 |
年俸制の残業代計算方法
年俸制は、1年間の給与額を事前に決定する給与形態です。
経営幹部や専門職に多い給与形態ですが、年俸制であっても原則として残業代の支払いが必要です。
年俸制でも残業代は発生する
「年俸制だから残業代は出ない」という誤解がありますが、これは間違いです。
年俸制であっても、労働基準法の適用を受けますので、法定労働時間を超えて働いた場合には割増賃金が必要です。
| 計算ステップ | 計算式・内容 |
|---|---|
| ①月額給与を算出 | 月額給与 = 年俸 ÷ 12ヶ月(または支給回数で割る) |
| ②基礎時給を算出 | 基礎時給 = 月額給与 ÷ 月平均所定労働時間 |
| ③残業代を計算 | 残業代 = 基礎時給 × 残業時間 × 割増率 |
【計算例】年俸600万円の場合の残業代計算方法
具体的な計算例を見ていきましょう。
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 年俸:600万円 / 月平均所定労働時間:173時間 / 月の残業時間:20時間 |
| 月額給与 | 6,000,000円 ÷ 12ヶ月 = 500,000円 |
| 基礎時給 | 500,000円 ÷ 173時間 ≒ 2,890円 |
| 月20時間残業の残業代 | 2,890円 × 1.25 × 20時間 = 72,250円 |
| 年間の残業代(毎月20時間残業の場合) | 72,250円 × 12ヶ月 = 867,000円 |
このように、年俸制であっても残業が発生すれば、別途残業代の支払いが必要です。
年俸制と年収の違い
年俸制と年収は異なる概念です。
| 用語 | 意味・内容 |
|---|---|
| 年俸制 | 給与形態の一種。1年間の給与額を事前に決定する制度。 年俸額が決まっていても、残業代は別途支給される(固定残業代が含まれる場合を除く)。 |
| 年収 | 1年間の総収入。基本給、手当、残業代、賞与など、全ての給与の合計額。 年俸制の場合:年収=年俸+残業代+その他手当 |
| 例 | 年俸600万円の社員が年間80万円の残業代を受け取った場合、 年俸:600万円 / 年収:680万円 |
歩合給・歩合制の残業代計算方法
歩合給・歩合制は、成果や売上に応じて給与が変動する給与形態です。
営業職やタクシー運転手、配送業などに多く見られます。
歩合給の場合の残業代計算は、通常の給与形態とは異なる特殊な計算方法が適用されます。
歩合給の基礎時給の算出方法と残業代計算
歩合給の場合、歩合給は既に労働時間に対する対価が含まれていると考えられます。
そのため、残業代としては割増部分(0.25)のみを追加で支払えば良いとされています。
| 項目 | 計算式・内容 |
|---|---|
| 基礎時給の算出 | 基礎時給 = 歩合給 ÷ 総労働時間 |
| 残業代の計算 | 残業代 = 基礎時給 × 0.25 × 残業時間 ※歩合給には既に労働の対価が含まれるため、割増部分(0.25)のみを追加 |
| 計算例(条件) | 当月の歩合給:30万円 / 総労働時間:180時間 / 残業時間:20時間 |
| 基礎時給 | 300,000円 ÷ 180時間 = 1,667円 |
| 残業代(割増部分のみ) | 1,667円 × 0.25 × 20時間 = 8,335円 |
この計算方法は、行政通達(昭和23年11月25日基発第1503号)に基づいています。
固定給+歩合給の場合の残業代計算方法
多くの場合、完全歩合制ではなく、固定給と歩合給を組み合わせた給与形態となっています。
この場合、固定給部分と歩合給部分で計算方法が異なります。
| 給与の種類 | 残業代の計算方法 |
|---|---|
| 固定給部分 | 通常の計算方法を適用。 (固定給 ÷ 月平均所定労働時間)× 1.25 × 残業時間 |
| 歩合給部分 | 割増部分のみを計算。 (歩合給 ÷ 総労働時間)× 0.25 × 残業時間 |
| 残業代の合計 | 固定給部分の残業代 + 歩合給部分の残業代 |
【計算例】固定給15万円+歩合給20万円の場合
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 固定給:15万円 / 歩合給:20万円 / 月平均所定労働時間:173時間 / 総労働時間:193時間 / 残業時間:20時間 |
| 固定給部分の基礎時給 | 150,000円 ÷ 173時間 ≒ 867円 |
| 固定給部分の残業代 | 867円 × 1.25 × 20時間 = 21,675円 |
| 歩合給部分の基礎時給 | 200,000円 ÷ 193時間 ≒ 1,036円 |
| 歩合給部分の残業代(割増部分のみ) | 1,036円 × 0.25 × 20時間 = 5,180円 |
| 残業代の合計 | 21,675円 + 5,180円 = 26,855円 |
このように、固定給と歩合給を組み合わせた給与形態では、それぞれ異なる計算方法で残業代を算出し、合算する必要があります。
【残業代の計算方法】分単位・端数処理の正しい方法
残業代の計算において、労働時間をどのように計算し、端数をどう処理するかは非常に重要です。
労働基準法では、労働時間は1分単位で計算することが原則とされていますが、一定の端数処理は認められています。
ここでは、分単位での計算方法と、適法な端数処理のルールについて詳しく解説します。
残業代の計算は1分単位が原則
労働基準法上、労働時間は1分単位で正確に把握し、計算することが原則です。
これは労働基準監督署や労働局の指導においても徹底されています。
労働基準法上の考え方と1分単位計算の原則
労働時間の把握と計算について、労働基準法では1分単位での計算が求められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 労働時間は1分単位で把握・計算することが労働基準法の原則です。 |
| 違法な切り捨て | 1日単位で15分未満、30分未満を切り捨てることは違法です。 労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反となります。 |
| 行政指導 | 労働基準監督署や労働局は、15分単位・30分単位の切り捨てを行っている企業に対して是正指導を行います。 |
| 罰則 | 労働基準法第24条違反:30万円以下の罰金(労働基準法第120条) |
15分単位・30分単位で計算している会社への対応
現在でも、15分単位や30分単位で残業時間を計算している会社がありますが、これは労働基準法違反です。
| 現状の問題 | 事例と解説 |
|---|---|
| 15分単位の切り捨て これは労働基準法違反 |
例:8時間13分勤務 → 8時間として計算(13分切り捨て) 是正しなければならない項目:13分(0.22時間)も残業時間として計算する必要があります。 |
| 30分単位の切り捨て これは労働基準法違反 |
例:8時間25分勤務 → 8時間として計算(25分切り捨て) 是正しなければならない項目:25分(0.42時間)も残業時間として計算する必要があります。 |
| 企業の対応(是正) | ①就業規則・賃金規程の変更 ②勤怠管理システムの設定変更 ③過去の未払い残業代の計算と支払い ④従業員への説明と周知 |
| 従業員の対応 | ①給与明細で残業時間の記載を確認 ②タイムカードと照合 ③労働基準監督署への相談 ④未払い残業代の請求(時効3年) |
残業代の計算の端数処理の正しいルール・方法(切り捨て・四捨五入・小数点)
労働時間や賃金の端数処理については、労働基準法と行政通達により、一定の処理方法が認められています。
ただし、これらのルールを正しく理解していないと、違法な切り捨てを行ってしまう可能性があります。
労働時間の端数処理方法
労働時間の端数処理について、労働基準法では原則1分単位での計算を求めていますが、1ヶ月の労働時間の合計については、一定の端数処理が認められています。
| 処理方法 | 適法性・内容 |
|---|---|
| 1か月の労働時間合計での端数処理 | 適法:1か月の労働時間の合計について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは認められます。 例:月の残業時間合計が20時間25分 → 20時間として計算可(25分切り捨て) 例:月の残業時間合計が20時間35分 → 21時間として計算(35分切り上げ) |
| 1日ごとの端数処理で切り捨て | 違法:1日ごとの労働時間について、端数を切り捨てることは違法です。 例:8時間25分勤務 → 8時間として計算(×違法) 正しくは8時間25分として記録し、月の合計で端数処理を行います。 |
| 15分単位・30分単位の切り捨て(1日ごと) | 違法:1日の労働時間を15分単位や30分単位で切り捨てることは違法です。 労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反します。 |
| 根拠 | 昭和63年3月14日基発第150号「労働時間の端数処理」 |
重要なポイントは、端数処理が認められるのは「1ヶ月の合計時間」に限られるという点です。
1日ごとに端数を切り捨てることは、たとえ30分未満であっても違法となります。
賃金(給与)の端数処理方法
賃金の端数処理についても、一定のルールが定められています。
| 処理方法 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ | 1か月の賃金総額について、1円未満の端数を処理する場合。 例:残業代が38,275.4円 → 38,275円(0.4円切り捨て) 例:残業代が38,275.6円 → 38,276円(0.6円切り上げ) |
| 100円未満四捨五入 | 1か月の賃金総額について、100円未満の端数を処理する場合。 例:残業代が38,275円 → 38,300円(75円を四捨五入で100円に) 例:残業代が38,240円 → 38,200円(40円を四捨五入で0円に) |
| 適用範囲 | これらの端数処理は、1か月の賃金支払額の合計に対してのみ認められます。 1日ごと、1回ごとの計算で端数を切り捨てることは違法です。 |
| 注意点 | 端数処理は常に労働者に不利となる切り捨てばかりではなく、切り上げも含めた処理である必要があります。 一方的な切り捨てのみは賃金全額払いの原則に反します。 |
| 根拠 | 昭和63年3月14日基発第150号「賃金の端数処理」 |
小数点以下・小数点の扱い方
残業代の計算では、基礎時給や残業時間を計算する過程で小数点が発生します。
この小数点をどう扱うかについても、実務上のルールがあります。
| 計算段階 | 小数点の扱い方 |
|---|---|
| 基礎時給の計算 | 基礎時給=月給÷月平均所定労働時間で計算すると、小数点以下の数値が出ます。 例:250,000円÷163.3時間=1,531.23…円 小数点第3位以降を切り捨て、または四捨五入するのが一般的です。 小数点第2位まで:1,531.23円 または 1,531円 |
| 残業時間の時間換算 | 分を時間に換算する場合、小数点が発生します。 例:25分÷60=0.4166…時間 小数点第3位以降を切り捨て、または四捨五入します。 小数点第2位まで:0.42時間 または 0.417時間 |
| 残業代の最終金額 | 基礎時給×残業時間×割増率を計算すると、1円未満の端数が出ることがあります。 例:1,531.23円×20時間×1.25=38,280.75円 50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げが認められます。 結果:38,281円 |
| 社内ルールの統一 | 小数点以下を何桁まで計算するか、どの段階で丸めるかは、社内で統一したルールを定めることが重要です。 就業規則や賃金規程に明記し、全従業員に同じ方法を適用します。 |
| 注意点 | 常に切り捨てだけを行うと、労働者に不利益となるため、切り上げも含めた処理方法を採用することが望ましいです。 |
【計算例】端数処理を含む残業代計算の実例
実際の計算で端数処理がどのように行われるか、具体例で見ていきましょう。
| 計算ステップ | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 月給:248,000円 / 月平均所定労働時間:168.5時間 / 残業時間:18時間47分 |
| ①基礎時給の計算 | 248,000円÷168.5時間=1,471.810…円 小数点第3位以降を四捨五入 → 1,471.81円 |
| ②残業時間の時間換算 | 18時間47分=18+(47÷60)時間=18.7833…時間 小数点第3位以降を四捨五入 → 18.78時間 |
| ③残業代の計算 | 1,471.81円×18.78時間×1.25=34,559.19…円 1円未満を四捨五入 → 34,559円 |
| 支払額 | 34,559円を残業代として支給 |
【時間帯・状況別】残業代の計算方法
残業代の計算では、どの時間帯に働いたか、どのような状況で働いたかによって、適用される割増率が変わります。
時間外労働、深夜労働、休日労働など、それぞれの状況に応じた正確な計算方法を理解することが重要です。
ここでは、時間帯や状況別の残業代計算方法について、具体例を交えながら詳しく解説します。
8時間以上・週40時間以上の残業代計算方法
労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間として定めています。
この法定労働時間を超えた労働に対しては、25%以上の割増賃金が必要です。
1日8時間を超える労働の残業代計算
1日8時間を超える労働は、時間外労働として25%以上の割増賃金が発生します。
| 項目 | 内容・計算例 |
|---|---|
| 原則 | 1日8時間を超えた部分は時間外労働となり、25%以上の割増が必要。 |
| 計算例(条件) | 基礎時給:1,500円 / 勤務時間:9時〜19時(休憩1時間)=実労働9時間 |
| 通常労働(8時間) | 1,500円×8時間=12,000円 |
| 時間外労働(1時間) | 1,500円×1.25×1時間=1,875円 |
| 1日の総賃金 | 12,000円+1,875円=13,875円 |
所定労働時間が8時間未満の場合の注意点
会社の所定労働時間が7時間など、8時間未満に設定されている場合、計算に注意が必要です。
| 労働時間の区分 | 割増率・計算 |
|---|---|
| 条件 | 所定労働時間:7時間 / 実労働時間:9時間 / 基礎時給:1,500円 |
| 所定労働時間内(7時間) | 通常賃金:1,500円×7時間=10,500円 |
| 所定外・法定内(7〜8時間の1時間) | 割増不要(ただし就業規則で定めがあれば支給):1,500円×1時間=1,500円 ※この部分は法定労働時間内のため、割増義務はありません。 |
| 法定外・時間外(8〜9時間の1時間) | 25%割増:1,500円×1.25×1時間=1,875円 |
| 1日の総賃金 | 10,500円+1,500円+1,875円=13,875円 |
| ポイント | 所定労働時間と法定労働時間の違いを理解し、8時間を超える部分から割増が必要と覚えておきましょう。 |
週40時間以上の残業代計算方法
1日8時間以内でも、週の労働時間が40時間を超えた場合、その超過分には25%以上の割増賃金が必要です。
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 条件 | 月〜金:各8時間勤務(合計40時間) / 土曜:5時間勤務 / 週の労働時間:45時間 / 基礎時給:1,500円 |
| 週40時間までの賃金 | 1,500円×40時間=60,000円 |
| 週40時間超の部分(5時間) | 1,500円×1.25×5時間=9,375円 |
| 週の総賃金 | 60,000円+9,375円=69,375円 |
| 注意点 | 1日8時間以内でも、週の合計が40時間を超えれば時間外労働として扱います。 週の起算日(通常は日曜日または月曜日)を確認し、正確に集計することが重要です。 |
深夜残業・夜勤の残業代計算方法
深夜時間帯(22時〜5時)に働いた場合、深夜労働として25%以上の割増賃金が必要です。
さらに、時間外労働と深夜労働が重なる場合は、両方の割増が加算されます。
深夜労働(22時〜5時)の割増率と計算方法
| 区分 | 割増率・内容 |
|---|---|
| 深夜労働のみ | 25%割増(基礎時給×1.25) 所定労働時間内であっても、22時〜5時の時間帯は25%割増が必要。 |
| 時間外労働+深夜労働 | 50%割増(基礎時給×1.5) 時間外25%+深夜25%=50% |
| 休日労働+深夜労働 | 60%割増(基礎時給×1.6) 休日35%+深夜25%=60% |
【計算例】深夜残業を含む1日の残業代計算
実際の深夜残業の計算例を見ていきましょう。
| 時間帯 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 勤務時間:9時〜23時(休憩1時間)=実労働13時間 / 基礎時給:1,500円 |
| 通常労働(9時〜17時:8時間) | 1,500円×8時間=12,000円 |
| 時間外労働(17時〜22時:5時間) | 1,500円×1.25×5時間=9,375円 |
| 時間外+深夜(22時〜23時:1時間) | 1,500円×1.5×1時間=2,250円 |
| 1日の総賃金 | 12,000円+9,375円+2,250円=23,625円 |
夜勤の残業代計算方法(夜間シフトの場合)
夜勤として、深夜時間帯を含むシフトで働く場合の計算例です。
| 時間帯 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 夜勤:22時〜翌7時(休憩1時間)=実労働8時間 / 基礎時給:1,200円 |
| 深夜時間帯(22時〜5時:7時間) | 1,200円×1.25×7時間=10,500円 ※所定労働時間内でも深夜は25%割増 |
| 通常時間帯(5時〜7時:1時間) | 1,200円×1時間=1,200円 |
| 夜勤1回の賃金 | 10,500円+1,200円=11,700円 |
| 夜勤で残業が発生した場合 | 例:翌7時〜9時まで2時間残業した場合 通常の時間外労働:1,200円×1.25×2時間=3,000円 合計:11,700円+3,000円=14,700円 |
休日出勤・祝日出勤の残業代計算方法
休日に出勤した場合の残業代計算は、法定休日か法定外休日かによって割増率が異なります。
残業代計算での、法定休日と法定外休日(所定休日)の違い
休日出勤の残業代を正確に計算するには、まず法定休日と法定外休日の違いを理解する必要があります。
| 区分 | 内容・割増率 |
|---|---|
| 法定休日 | 週1日または4週4日の休日(労働基準法第35条)。 多くの会社では日曜日を法定休日に設定。 割増率:35%以上(基礎時給×1.35) |
| 法定外休日(所定休日) | 法定休日以外の、会社が定めた休日。 例:週休2日制の場合の土曜日。 この日に出勤しても、週40時間以内なら割増不要。 週40時間を超える場合:25%割増(時間外労働として扱う) |
| 見分け方 | 就業規則の休日規定を確認。 「日曜日を法定休日とする」などの記載があります。 記載がない場合、週の最後の休日(通常は日曜)が法定休日となります。 |
【残業代計算方法の例】法定休日の出勤による残業代計算
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 日曜日(法定休日)に8時間勤務 / 基礎時給:1,500円 |
| 休日労働(8時間) | 1,500円×1.35×8時間=16,200円 |
| 深夜時間帯を含む場合 | 日曜22時〜翌5時(7時間)勤務した場合 休日+深夜:1,500円×1.6×7時間=16,800円 ※休日35%+深夜25%=60%割増 |
祝日出勤の扱いと残業代計算
祝日は法定休日ではありません。そのため、祝日出勤の扱いは通常の労働日と同じになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 祝日の位置づけ | 祝日は労働基準法上の法定休日ではありません。 会社が所定休日として定めているかどうかによって扱いが変わります。 |
| 祝日が所定休日の場合 | 会社が祝日を休日と定めている場合、祝日出勤は所定休日の出勤扱い。 週40時間を超えなければ割増不要、超えれば25%割増。 |
| 祝日が労働日の場合 | 会社が祝日を通常の労働日としている場合、通常の労働として扱います。 8時間を超えれば時間外労働として25%割増。 |
| 計算例 | 月〜金に各8時間(40時間)勤務し、祝日の月曜に8時間出勤した場合 週の労働時間:48時間 → 40時間超の8時間に25%割増が必要 1,500円×1.25×8時間=15,000円 |
| 注意点 | 就業規則で「祝日は休日とする」と定められている場合でも、法定休日ではないため35%割増ではなく、週40時間超の部分に25%割増となります。 |
振替休日と代休の違いと残業代への影響
休日出勤をした際、振替休日や代休を取得する場合がありますが、この2つは全く異なる制度です。
残業代の計算にも大きく影響しますので、正確に理解しておく必要があります。
| 区分 | 内容・残業代の扱い |
|---|---|
| 振替休日 | 事前に休日と労働日を入れ替えること。 例:日曜日に出勤する代わりに、事前に水曜日を休日とする。 割増賃金:原則不要(ただし、週をまたぐ場合で週40時間を超えると25%割増が必要) |
| 代休 | 事後に休日出勤の代わりに休日を付与すること。 例:日曜日に出勤した後、後日に代休を取得。 割増賃金:必要(35%の休日割増は支払う必要がある) |
| 振替休日の要件 | ①就業規則に規定があること ②振替日を事前に特定すること ③できる限り同一週内に振り替えること |
| 代休の扱い | 休日出勤の事実は変わらないため、35%の休日割増賃金を支払った上で、代休日は無給となるのが一般的。 または、休日割増を含めた賃金を支払い、代休日も通常通り有給とする場合もあります。 |
| 実務上の注意 | 「振替休日」と「代休」を混同している企業が多く、本来は休日割増が必要なケースで支払っていないことがあります。 事前に休日を特定して入れ替えたかが判断の分かれ目です。 |
【計算例】振替休日と代休の賃金比較
| ケース | 賃金計算 |
|---|---|
| 条件 | 基礎時給:1,500円 / 日曜日(法定休日)に8時間勤務 |
| 振替休日の場合 | 事前に水曜日と日曜日を入れ替え。 日曜日の賃金:1,500円×8時間=12,000円 水曜日:休日(無給) 割増賃金なし(通常の労働日として扱うため) |
| 代休の場合 | 日曜日に出勤後、後日に代休取得。 日曜日の賃金:1,500円×1.35×8時間=16,200円 代休日:無給 休日割増35%を含めた賃金を支払う必要がある |
| 賃金の差額 | 16,200円−12,000円=4,200円 代休の方が4,200円高くなります。 |
月60時間以上の残業の計算方法
2023年4月から、中小企業にも月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増率が適用されるようになり、長時間労働の抑制と、労働者の健康確保が図られています。
2023年4月から中小企業にも50%割増が適用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法改正の内容 | 2023年4月1日から、中小企業にも月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増率が適用されます。 ※大企業は2010年4月から既に適用されていました。 |
| 適用対象 | 1か月の時間外労働が60時間を超えた部分について適用。 60時間までは25%割増、60時間を超える部分は50%割増。 |
| 計算の基準 | 「1か月」の起算日は、賃金計算期間の初日(例:毎月1日〜末日、または16日〜翌15日など) |
| 深夜労働との関係 | 月60時間超の時間外労働が深夜時間帯の場合 50%(時間外)+25%(深夜)=75%割増 |
| 休日労働の扱い | 法定休日の労働時間は、月60時間の計算には含めません。 ただし、法定外休日の労働で時間外労働となった時間は含めます。 |
【計算例】月70時間残業した場合の残業代計算
具体的な計算例で、月60時間を超える残業代の計算方法を見ていきましょう。
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 基礎時給:1,500円 / 月の時間外労働:70時間 |
| 60時間までの部分 | 1,500円×1.25×60時間=112,500円 |
| 60時間を超える部分(10時間) | 1,500円×1.5×10時間=22,500円 |
| 残業代の合計 | 112,500円+22,500円=135,000円 |
| 参考(全て25%で計算した場合) | 1,500円×1.25×70時間=131,250円 差額:135,000円−131,250円=3,750円の増加 |
月60時間超の時間外労働が深夜時間帯の場合
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 基礎時給:1,500円 / 月の時間外労働:70時間(うち60時間超の10時間が深夜時間帯) |
| 60時間までの部分 | 1,500円×1.25×60時間=112,500円 |
| 60時間超+深夜の部分(10時間) | 1,500円×1.75×10時間=26,250円 ※時間外50%+深夜25%=75%割増 |
| 残業代の合計 | 112,500円+26,250円=138,750円 |
代替休暇の考え方と残業代への影響
月60時間を超える時間外労働について、労使協定を締結すれば、割増賃金の支払いに代えて代替休暇を付与することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代替休暇とは | 月60時間を超える時間外労働について、割増賃金の一部(25%分)の支払いに代えて有給の休暇を付与する制度。 |
| 要件 | 労使協定の締結が必要。 労働者の意向を確認し、本人が希望する場合のみ代替休暇を付与できます。 |
| 割増賃金の扱い | 60時間超の部分:本来50%割増 内訳:25%は必ず金銭で支払い、残りの25%を代替休暇に換算できる。 |
| 代替休暇の時間数 | (月60時間超の時間外労働時間)×25%=代替休暇の時間数 例:60時間超の部分が10時間の場合 10時間×0.25=2.5時間の代替休暇 |
| 計算例 | 月70時間の時間外労働の場合 60時間までの部分:1,500円×1.25×60時間=112,500円 60時間超の部分(10時間): ・金銭支払い(25%):1,500円×1.25×10時間=18,750円 ・代替休暇(25%相当):10時間×0.25=2.5時間 合計賃金:112,500円+18,750円=131,250円+代替休暇2.5時間 |
| 注意点 | 代替休暇は労働者が希望しない場合は付与できません。 希望しない場合は、50%割増の金銭を全額支払う必要があります。 |
【フレックス制度・変形労働時間制など】特殊な労働時間制度での残業代の計算方法
通常の労働時間制度(1日8時間、週40時間)以外に、業務の性質や実態に応じて、様々な特殊な労働時間制度が認められています。
これらの制度を採用している場合、残業代の計算方法も通常とは異なります。
ここでは、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、みなし残業制、時短勤務など、特殊な労働時間制度における残業代の計算方法を詳しく解説します。
変形労働時間制の残業代計算方法
変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に配分できる制度です。
一定期間を平均して、週40時間以内に収まれば、特定の日や週で法定労働時間を超えても時間外労働とはなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内に収める制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて労働が可能になる制度。 |
| 導入要件 | ①労使協定または就業規則で定める ②対象期間、労働日、各日の労働時間を事前に特定する |
| 時間外労働の判定(3段階) | 変形労働時間制では、以下の3つの基準で時間外労働を判定します。 |
| ①1日単位の判定 | 就業規則等で定めた各日の所定労働時間を超えた時間が時間外労働。 例:所定労働時間10時間の日に11時間働いた場合、1時間が時間外労働。 |
| ②1週単位の判定 | 就業規則等で定めた各週の所定労働時間を超え、かつ40時間を超えた時間が時間外労働。 ただし、①で時間外労働とされた時間は除く。 |
| ③1ヶ月単位の判定 | 1ヶ月の法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働。 ただし、①②で時間外労働とされた時間は除く。 |
| 法定労働時間の総枠 | 40時間×(対象期間の暦日数÷7) 例:31日の月の場合:40×(31÷7)≒177.1時間 |
【計算例】1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 条件 | 基礎時給:1,500円 / 対象期間:31日間 繁忙期(15日間):1日10時間勤務 閑散期(10日間):1日6時間勤務 休日:6日間 実際の労働:繁忙期の1日に11時間働いた |
| 所定労働時間の合計 | (10時間×15日)+(6時間×10日)=150+60=210時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 40時間×(31日÷7)≒177.1時間 |
| ①1日単位の時間外 | 所定10時間の日に11時間働いたので、1時間が時間外労働。 |
| 残業代 | 1,500円×1.25×1時間=1,875円 |
| ポイント | 変形労働時間制では、所定労働時間が10時間の日でも、その日の所定時間を超えなければ時間外労働にはなりません。 ただし、所定時間を1分でも超えれば時間外労働となります。 |
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1年間を平均して週40時間以内に収める制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 1年以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日・週・月に法定労働時間を超えて労働が実施が可能になる制度。 季節による業務の繁閑が大きい業種に適しています。 |
| 導入要件 | ①労使協定の締結・届出が必要 ②対象期間、労働日、各日の労働時間を事前に特定 ③対象期間は1ヶ月を超え1年以内 |
| 労働時間の上限 | ①1日の労働時間:10時間以内 ②1週の労働時間:52時間以内 ③連続労働日数:6日以内(特定期間は例外あり) ④対象期間が3ヶ月を超える場合、週48時間を超える週は連続3週以内、年間13週以内 |
| 時間外労働の判定 | 1ヶ月単位の変形労働時間制と同様に、①1日単位、②1週単位、③対象期間単位の3段階で判定します。 |
| 36協定の上限 | 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、36協定の上限は月42時間、年320時間となります(通常は月45時間、年360時間)。 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 1週間単位で労働時間を調整できる制度。 1週40時間以内であれば、特定の日に10時間まで働かせることができます。 |
| 対象事業 | 常時30人未満の労働者を使用する ①小売業 ②旅館 ③料理店 ④飲食店 |
| 導入要件 | ①労使協定の締結・届出 ②前週末までに各日の労働時間を書面で通知 |
| 時間外労働の判定 | ①1日10時間を超えた時間 ②週40時間を超えた時間 |
フレックスタイム制の残業代計算方法
フレックスタイム制は、労働者が始業・終業時刻を自由に決められる制度です。
一定期間(清算期間)の総労働時間を定め、その範囲内で日々の労働時間を労働者が決定します。
清算期間における総労働時間の考え方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 労働者が始業・終業時刻を自由に決定できる制度。 清算期間(最長3ヶ月)の総労働時間を定め、その範囲内で働きます。 |
| 導入要件 | ①就業規則で始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを規定 ②労使協定で清算期間、総労働時間等を定める ③清算期間が1ヶ月超の場合は労使協定を労働基準監督署に届出 |
| コアタイム | 必ず勤務しなければならない時間帯(設定は任意)。 例:10時〜15時(休憩1時間) |
| フレキシブルタイム | 労働者が自由に出退勤できる時間帯。 例:7時〜10時、15時〜22時 |
| 清算期間 | 労働時間を精算する期間。1ヶ月以内、または最長3ヶ月以内で設定。 |
【計算例】1ヶ月のフレックスタイム制の残業代
フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間で時間外労働を判定します。
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 清算期間:1ヶ月(31日間) / 基礎時給:1,500円 総労働時間:177時間と定めている 実労働時間:197時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 40時間×(31日÷7)≒177.1時間 |
| 時間外労働の判定 | 実労働時間197時間−法定労働時間177.1時間=19.9時間 この19.9時間が時間外労働となります。 |
| 残業代 | 1,500円×1.25×19.9時間≒37,312円 |
| ポイント | フレックスタイム制では、1日や1週の労働時間は関係なく、清算期間の総労働時間で判定します。 特定の日に10時間働いても、清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠内であれば時間外労働にはなりません。 |
清算期間が3ヶ月の場合の計算
清算期間が1ヶ月を超える場合、計算方法が少し複雑になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 清算期間1ヶ月超の場合の注意点 | 清算期間が1ヶ月を超える場合、各月の労働時間が週平均50時間を超えないようにする必要があります。 |
| 週平均50時間の計算 | 50時間×(その月の暦日数÷7) 例:31日の月:50×(31÷7)≒221時間 |
| 時間外労働の判定(2段階) | ①各月ごとに、週平均50時間を超えた時間を時間外労働として計算・支払い ②清算期間全体で、法定労働時間の総枠を超えた時間(①で支払った分を除く)を時間外労働として計算・支払い |
裁量労働制(みなし労働時間制)の残業代計算
裁量労働制は、業務の性質上、労働時間を労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
裁量労働制には、専門業務型と企画業務型の2種類があります。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を労働者の裁量に委ねる必要がある専門的な業務に適用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 対象業務について、実際の労働時間に関わらず、労使協定で定めた時間働いたものとみなす制度。 |
| 対象業務(19業務) | ①新商品・新技術の研究開発 ②情報処理システムの分析・設計 ③記事の取材・編集(新聞・出版・放送) ④デザイナー ⑤プロデューサー・ディレクター(放送番組・映画等) ⑥コピーライター ⑦システムコンサルタント ⑧インテリアコーディネーター ⑨ゲーム用ソフトウェアの創作 ⑩証券アナリスト ⑪金融商品の開発 ⑫大学の教授研究(主として研究に従事する者) ⑬公認会計士 ⑭弁護士 ⑮建築士 ⑯不動産鑑定士 ⑰弁理士 ⑱税理士 ⑲中小企業診断士 |
| 導入要件 | ①労使協定の締結・届出 ②対象業務、みなし労働時間、健康・福祉確保措置等を定める ③対象労働者の同意を得る |
| みなし労働時間 | 労使協定で定めた時間(例:8時間、9時間など)働いたものとみなされます。 |
専門業務型裁量労働制における残業代の計算方法
| 項目 | 内容・計算方法 |
|---|---|
| みなし時間が8時間以内の場合 | 時間外労働は発生しないため、残業代の支払いは不要。 実際に何時間働いても、8時間働いたものとみなされます。 |
| みなし時間が8時間を超える場合 | 8時間を超える部分について、25%以上の割増賃金が必要。 例:みなし時間が9時間の場合、1時間分の時間外労働に対する割増賃金を支払う。 |
| 計算例 | 基礎時給:1,500円 / みなし労働時間:9時間 時間外労働:9時間−8時間=1時間 残業代:1,500円×1.25×1時間=1,875円 この1,875円を毎日支払う必要があります(実際の労働時間に関わらず)。 |
| 深夜労働・休日労働 | 裁量労働制でも深夜労働(22時〜5時)と休日労働の割増賃金は別途必要。 実際に深夜時間帯に働いた時間、休日に働いた時間については割増賃金を支払います。 |
| 深夜労働の計算例 | 深夜時間帯に3時間働いた場合 1,500円×1.25×3時間=5,625円を追加で支払う |
| 休日労働の計算例 | 法定休日にみなし時間9時間働いた(とみなされる)場合 1,500円×1.35×9時間=18,225円 |
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、企業の本社等において、企画・立案・調査・分析を行う業務に適用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 事業運営の企画・立案・調査・分析業務について、実際の労働時間に関わらず、労使委員会の決議で定めた時間働いたものとみなす制度。 |
| 対象業務 | 企業の本社等において、事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務。 例:経営企画、人事企画、財務計画、営業企画など。 ※定型的な業務は対象外。 |
| 対象労働者 | 対象業務を適切に遂行するための知識・経験を有する労働者。 対象労働者の同意が必要。 |
| 導入要件 | ①労使委員会の設置(労働者の過半数代表も参加) ②労使委員会で5分の4以上の多数決議 ③決議を労働基準監督署に届出 ④対象労働者本人の同意 |
| 残業代の計算 | 専門業務型裁量労働制と同様の扱い。 みなし時間が8時間超なら、超過分に割増賃金が必要。 深夜・休日労働は別途割増賃金が必要。 |
事業場外みなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制は、外回り営業など、事業場外で業務に従事し、労働時間の算定が困難な場合に適用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 事業場外で業務に従事し、労働時間の算定が困難な場合、所定労働時間または労使協定で定めた時間働いたものとみなす制度。 |
| 適用条件 | ①労働者が事業場外で業務に従事 ②使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難 |
| 典型例 | 外回りの営業、出張、在宅勤務(労働時間の算定が困難な場合に限る) |
| 適用されないケース | ①携帯電話等で随時使用者の指示を受けている ②訪問先・帰社時刻等が具体的に指示されている ③PCログ等で労働時間を把握できる → これらの場合は「労働時間の算定が困難」とは言えません。 |
| みなし時間 | ①原則:所定労働時間働いたものとみなす ②業務遂行に通常所定労働時間を超える時間が必要な場合:労使協定で定めた時間働いたものとみなす |
| 残業代の計算 | みなし時間が8時間超の場合、超過分に25%以上の割増賃金が必要。 深夜・休日労働は別途割増賃金が必要。 |
みなし残業代・固定残業代制の計算方法
みなし残業代(固定残業代)は、一定時間分の残業代を毎月定額で支払う制度です。
「基本給に30時間分の残業代を含む」などの形で運用されますが、適法性の要件を満たさないと無効となる可能性があります。
固定残業代(みなし残業)の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 一定時間分の残業代を、実際の残業時間に関わらず毎月定額で支払う制度。 「みなし残業代」「定額残業代」とも呼ばれます。 |
| 固定残業代の形態 | ①基本給に含める方式:「基本給25万円(30時間分の残業代を含む)」 ②手当として支給する方式:「基本給20万円+固定残業手当5万円(30時間分)」 ②の手当方式の方が明確で望ましいとされています。 |
| 適法性の要件(3つ) | 固定残業代が有効と認められるには、以下の3要件を満たす必要があります。 |
| 要件①:明確な区別 | 通常の賃金部分と残業代部分を明確に区別できること。 給与明細や雇用契約書で、固定残業代の金額を明示する必要があります。 |
| 要件②:時間数の明示 | 何時間分の残業代が含まれているか明示すること。 「30時間分」など、具体的な時間数を示す必要があります。 |
| 要件③:超過分の支払い | 固定残業時間を超えた場合は、超過分を別途支払うこと。 これを就業規則や雇用契約書に明記し、実際に支払う必要があります。 |
| 無効となるケース | ①基本給と残業代の区別が不明確 ②時間数が明示されていない ③超過分を支払っていない → 固定残業代が無効となり、全額が通常の賃金とみなされ、別途残業代の支払いが必要になります。 |
固定残業代を超えた場合の残業代計算方法
固定残業時間を超えて働いた場合、超過分については別途残業代を計算して支払う必要があります。
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 基本給:20万円 / 固定残業手当:5万円(30時間分) 月平均所定労働時間:173時間 / 実残業時間:40時間 |
| 基礎時給の計算 | 基本給のみを使用して計算。 200,000円÷173時間≒1,156円 ※固定残業手当5万円は基礎賃金に含めません。 |
| 固定残業代の確認 | 固定残業手当5万円が30時間分として妥当か確認。 1,156円×1.25×30時間=43,350円 5万円>43,350円なので、固定残業手当は適正。 |
| 超過時間の計算 | 実残業時間40時間−固定残業時間30時間=10時間 |
| 超過分の残業代 | 1,156円×1.25×10時間=14,450円 |
| 支給額の合計 | 基本給20万円+固定残業手当5万円+超過分14,450円=264,450円 |
固定残業代が無効になるケースと対応
| 無効となるケース | 理由と対応 |
|---|---|
| ケース①:区別が不明確 | 「基本給25万円(残業代込み)」としか記載がない。 → 何時間分か、金額がいくらか不明なため無効。 対応:「基本給20万円+固定残業手当5万円(30時間分)」と明記。 |
| ケース②:時間数の未明示 | 「基本給25万円(残業代5万円を含む)」 → 何時間分か明示されていないため無効。 対応:時間数を明示「5万円(30時間分の残業代)」 |
| ケース③:超過分を支払わない | 30時間分の固定残業代を設定しているが、40時間残業しても追加支払いなし。 → 超過分を支払っていないため制度全体が無効の可能性。 対応:超過分10時間について必ず追加支払い。 |
| ケース④:金額が不当に低い | 固定残業手当2万円(50時間分)などと設定。 → 計算すると法定の割増率を満たしていないため無効。 対応:正しい計算式で適正な金額を設定。 |
| 無効となった場合の影響 | 固定残業代部分も含めて全額が基本給とみなされ、全ての残業時間について改めて残業代を計算する必要があります。 例:基本給20万円+固定残業手当5万円が全て基本給25万円とみなされ、40時間の残業全てに対して残業代を計算。 結果として二重払いに近い状況となり、企業の負担が大幅に増加します。 |
みなし労働時間制との違い
「みなし残業」と「みなし労働時間制」は名称が似ていますが、全く異なる制度です。
| 項目 | みなし残業(固定残業代) | みなし労働時間制 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 賃金の支払い方法 | 労働時間の算定方法 |
| 労働時間の把握 | 実際の労働時間を把握する必要がある | 実際の労働時間は把握不要(みなし時間で算定) |
| 残業代の計算 | 実際の残業時間で計算し、固定残業時間を超えたら追加支払い | みなし時間で計算(実際の時間は関係ない) |
| 適用業務 | 制限なし(全ての業務に適用可能) | 法律で定められた特定の業務のみ |
| 導入手続き | 就業規則・雇用契約書への記載 | 労使協定または労使委員会の決議・届出 |
時短勤務の残業代計算方法
育児や介護のために時短勤務をしている労働者についても、残業代の計算ルールは基本的に同じです。
ただし、所定労働時間が短いため、残業の判定には注意が必要です。
所定労働時間が短い場合の残業代計算
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時短勤務とは | 育児・介護短時間勤務制度により、所定労働時間を短縮して働くこと。 例:通常8時間勤務のところ、6時間勤務に短縮。 |
| 基礎時給の計算 | 時短勤務後の給与と月平均所定労働時間で計算。 例:時短後の月給18万円 / 月平均所定労働時間122.5時間 基礎時給:180,000円÷122.5時間≒1,469円 |
| 残業の判定(重要) | ①所定労働時間(6時間)〜法定労働時間(8時間):法定内残業(割増なし) ②法定労働時間(8時間)超:法定外残業(25%割増) |
【計算例】1日6時間の時短勤務者が8時間働いた場合
| 労働時間の区分 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 所定労働時間:6時間 / 実労働時間:8時間 / 基礎時給:1,469円 |
| 所定労働時間内(6時間) | 1,469円×6時間=8,814円 |
| 所定外・法定内(6〜8時間の2時間) | 法定労働時間(8時間)以内のため割増不要。 1,469円×2時間=2,938円 ※ただし、就業規則で割増を定めている場合は支給。 |
| 1日の総賃金 | 8,814円+2,938円=11,752円 |
【計算例】1日6時間の時短勤務者が9時間働いた場合
| 労働時間の区分 | 計算内容 |
|---|---|
| 条件 | 所定労働時間:6時間 / 実労働時間:9時間 / 基礎時給:1,469円 |
| 所定労働時間内(6時間) | 1,469円×6時間=8,814円 |
| 所定外・法定内(6〜8時間の2時間) | 1,469円×2時間=2,938円 |
| 法定外・時間外(8〜9時間の1時間) | 法定労働時間(8時間)を超えるため25%割増。 1,469円×1.25×1時間=1,836円 |
| 1日の総賃金 | 8,814円+2,938円+1,836円=13,588円 |
育児・介護による時短勤務のケース
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育児短時間勤務制度 | 3歳未満の子を養育する労働者が対象。 1日の所定労働時間を原則6時間に短縮。 育児・介護休業法により事業主に措置義務があります。 |
| 介護短時間勤務制度 | 要介護状態の家族を介護する労働者が対象。 所定労働時間の短縮等の措置を講じる義務。 |
| 給与の扱い | 時短勤務により労働時間が減少した分、給与も減額されるのが一般的。 例:8時間勤務→6時間勤務なら、給与も6/8=75%程度に。 |
| 残業の扱い | 時短勤務者にも残業を命じることは可能ですが、育児・介護の必要性を考慮する必要があります。 3歳未満の子を養育する労働者、要介護家族を介護する労働者は、所定外労働(残業)の免除を請求できます(育児・介護休業法)。 |
| 残業代計算 | 時短勤務者が残業した場合でも、残業代の計算方法は通常と同じ。 法定労働時間(8時間)を超える部分には25%割増が必要。 |
【雇用形態・職種別】残業代の計算方法
残業代の計算方法は、雇用形態や職種によっても異なる場合があります。
正社員、派遣社員、契約社員、管理職など、それぞれの雇用形態における残業代の考え方と計算方法について解説します。
特に管理職(管理監督者)については、「管理職だから残業代が出ない」という誤解が多いため、労働基準法上の正確な定義と判断基準を理解することが重要です。
正社員・社員の残業代計算
正社員や正規社員の残業代計算は、これまで解説してきた標準的な計算方法が適用されます。
月給制が一般的であり、基本給と各種手当から基礎時給を算出し、残業時間と割増率をかけて計算します。
正社員であっても、労働基準法の適用を受けますので、法定労働時間を超えて働いた場合には必ず25%以上の割増賃金が必要です。雇用形態が正社員であることを理由に、残業代を支払わないことは違法となります。
また、正社員の場合、賞与(ボーナス)が支給されることが多いですが、年3回以下の支給であれば基礎賃金に含める必要はありません。ただし、年4回以上支給される場合は、実質的に定期賃金とみなされ、基礎賃金に算入する必要がある場合があります。
派遣社員の残業代計算方法
派遣社員の残業代計算についても、基本的なルールは正社員と同じです。
ただし、派遣社員特有の雇用関係(派遣元と派遣先)があるため、その点を理解しておく必要があります。
派遣社員の雇用主は派遣元企業です。したがって、残業代を支払う義務があるのも派遣元企業となります。一方、実際の業務の指示は派遣先企業が行います。派遣先企業が法定労働時間を超えて労働を指示した場合、派遣元企業はその時間外労働に対して割増賃金を支払う必要があります。
派遣社員の給与形態は時給制が多いため、時給そのものが基礎時給となります。1日8時間、週40時間を超えて働いた場合、その超過分には25%以上の割増賃金が発生します。たとえば、時給1,500円の派遣社員が1日9時間働いた場合、8時間までは通常の時給1,500円、8時間を超える1時間については1,500円×1.25=1,875円を支払う必要があります。
派遣契約書には、所定労働時間や残業の可否について記載されています。契約上、残業が想定されていない場合でも、実際に法定労働時間を超えて働かせた場合には割増賃金の支払いが必要です。また、派遣先企業は、派遣社員に残業を指示する前に、派遣元企業と相談し、36協定の範囲内であることを確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用関係 | 派遣社員の雇用主は派遣元企業。残業代の支払い義務も派遣元にあります。 |
| 指揮命令 | 業務の指示は派遣先企業が行います。派遣先が残業を指示した場合、派遣元はその分の残業代を支払う必要があります。 |
| 給与形態 | 多くの場合時給制。時給×労働時間で賃金を計算。 |
| 残業代の計算 | 時給制のため、時給が基礎時給となります。 法定労働時間超過分:時給×1.25 深夜時間帯:時給×1.25(時間外と重なれば×1.5) |
| 36協定 | 派遣元企業が36協定を締結している必要があります。派遣先企業は、派遣元の36協定の範囲内で残業を指示する必要があります。 |
| 契約内容の確認 | 派遣契約書で所定労働時間、残業の可否、残業代の計算方法を確認することが重要です。 |
契約社員の残業代計算
契約社員(有期雇用労働者)についても、労働基準法は正社員と同様に適用されます。
雇用契約が有期であることを理由に、残業代を支払わないことは違法です。契約期間が定められているかどうかと、残業代の支払い義務は全く関係ありません。
契約社員の給与形態は、月給制、時給制、日給制など様々です。それぞれの給与形態に応じて、これまで解説してきた計算方法を適用します。月給制の契約社員であれば、月給を月平均所定労働時間で割って基礎時給を算出し、残業時間と割増率をかけて残業代を計算します。時給制の契約社員であれば、時給がそのまま基礎時給となり、法定労働時間を超えた部分に25%の割増をかけます。
契約社員の場合、雇用契約書に労働条件が明記されています。所定労働時間、所定労働日数、給与額、残業の有無などを契約書で確認し、その内容に基づいて残業代を計算します。ただし、契約書に「残業代は支払わない」などと記載されていても、そのような条項は労働基準法に違反するため無効です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働基準法の適用 | 契約社員も労働基準法の完全な適用対象。正社員と同じく残業代の支払い義務があります。 |
| 雇用形態と残業代 | 有期雇用であることを理由に残業代を支払わないことは違法です。 |
| 計算方法 | 給与形態(月給制、時給制、日給制等)に応じて、正社員と同じ方法で計算します。 |
| 雇用契約書の確認 | 所定労働時間、給与額、残業の有無を確認。ただし、「残業代不支給」などの条項は労働基準法違反で無効。 |
| 同一労働同一賃金 | パートタイム・有期雇用労働法により、正社員と同じ業務をしている場合は、不合理な待遇差は禁止されています。 |
管理職(管理監督者)の残業代計算について
管理職の残業代については、多くの誤解があります。「管理職だから残業代が出ない」という認識が広まっていますが、これは必ずしも正しくありません。
労働基準法では、「管理監督者」に該当する労働者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となります。つまり、真の管理監督者であれば、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、重要なのは、会社が「管理職」という肩書きを与えているだけでは管理監督者に該当しないという点です。労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかは、肩書きではなく、実態によって判断されます。課長、部長といった役職名があっても、実態が管理監督者の要件を満たしていなければ、残業代の支払いが必要です。これが「名ばかり管理職」の問題です。
労働基準法上の「管理監督者」の定義
労働基準法第41条第2号では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」を労働時間等の規定の適用除外としています。
この管理監督者に該当するかどうかは、以下の要素を総合的に判断します。単に一つの要素を満たしているだけでは不十分で、全ての要素を実質的に満たしている必要があります。
第一に、職務内容と権限です。管理監督者は、経営者と一体的な立場にある必要があります。具体的には、労務管理や経営上の重要事項について、経営者と同等の権限を持ち、決定に関与していることが求められます。単に部下に指示をする立場というだけでは不十分で、採用、解雇、人事考課、労働時間の管理など、重要な権限を実質的に行使している必要があります。
第二に、勤務態様です。管理監督者は、自己の出退勤について厳格な制限を受けず、労働時間に関する自由裁量を持っている必要があります。タイムカードでの出退勤管理や、遅刻・早退による減給などがある場合は、管理監督者とは認められにくくなります。
第三に、賃金等の待遇です。管理監督者は、その地位にふさわしい待遇を受けている必要があります。具体的には、時間外労働に対する割増賃金が支払われないことを考慮しても、十分な基本給や役職手当が支給されていることが必要です。一般の労働者と同程度、あるいはそれ以下の賃金では、管理監督者とは認められません。
| 判断要素 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ①職務内容・権限 | 経営者と一体的な立場にあること。 ・労務管理(採用、解雇、人事考課、労働時間管理等)について、実質的な権限を有する ・経営上の重要事項の決定に関与する ・部下への指示だけでは不十分 |
| ②勤務態様 | 労働時間に関する自由裁量があること。 ・出退勤時刻を自己の裁量で決定できる ・タイムカード等による厳格な時間管理を受けない ・遅刻、早退等による減給がない ・自己の労働時間について自由裁量がある |
| ③賃金等の待遇 | 地位にふさわしい待遇を受けていること。 ・時間外割増賃金が支払われなくても、それに見合う十分な基本給・手当がある ・一般労働者の賃金(残業代込み)と比較して、遜色ない、またはそれ以上の待遇 ・役職手当等が実質的に時間外労働の対価として十分な額である |
| 総合判断 | 上記の3要素を総合的に判断します。 肩書きだけでなく、実態が重要です。 |
管理監督者に該当するかのチェックリスト
自社の管理職が真の管理監督者に該当するかどうかを判断するために、以下のチェックリストを活用できます。
全ての項目に「はい」と答えられる場合にのみ、管理監督者として扱うことができます。一つでも「いいえ」がある場合は、管理監督者とは認められず、残業代の支払いが必要となる可能性が高いです。
| チェック項目 | 判断基準 |
|---|---|
| 経営会議等への参加 | □ 経営に関する重要な会議に参加し、意思決定に関与している |
| 人事権限 | □ 部下の採用、解雇、人事考課について、実質的な決定権または強い影響力を持っている |
| 労務管理権限 | □ 部下の労働時間管理、勤務シフトの決定について、実質的な権限を持っている |
| 出退勤の自由 | □ 出勤・退勤時刻を自己の裁量で決定でき、遅刻・早退による減給等のペナルティがない |
| 労働時間管理 | □ タイムカード等による厳格な労働時間管理を受けていない |
| 待遇の優位性 | □ 基本給、役職手当等の合計が、一般労働者の賃金(残業代込み)と比較して十分に高い |
| 時間外割増の補償 | □ 時間外割増賃金が支払われなくても、それに見合う十分な役職手当等が支給されている |
| 職務の重要性 | □ 会社の経営に直結する重要な職務を担当し、その責任を負っている |
名ばかり管理職の問題と判例
「名ばかり管理職」とは、管理職という肩書きや役職名は与えられているものの、実態として管理監督者の要件を満たしていない労働者のことを指します。
この問題が社会的に注目されるきっかけとなったのが、日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)です。この事件では、ファーストフード店の店長が管理監督者に該当するかどうかが争われました。
裁判所は、店長には①経営への関与が限定的で、店舗運営に関する裁量しかない、②アルバイトのシフト管理はするが、採用や解雇の権限は本部にあり、人事権限が乏しい、③出退勤時刻の自由裁量がなく、店舗の営業時間に拘束されている、④年収が店長以外の社員と比較して十分に優遇されているとは言えないなどの理由から、管理監督者には該当しないと判断しました。そして、未払いの時間外割増賃金の支払いを命じました。
この判決以降、「店長」「課長」などの肩書きがあるだけでは管理監督者とは認められず、実態を重視して判断する必要があることが明確になりました。企業は、管理職の処遇を見直し、真の管理監督者でない場合には残業代を支払うようになってきています。
| 判断要素 | 裁判所の判断内容 |
|---|---|
| 職務内容・権限 | 店長の権限は店舗運営に関する事項に限定されており、経営への関与は限定的。 アルバイトの採用面接はするが、最終決定権は本部。解雇の権限もない。 → 経営者と一体的な立場とは言えない |
| 勤務態様 | 店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由がない。 長時間労働を余儀なくされている。 → 労働時間の自由裁量がない |
| 賃金・待遇 | 年収は店長以外の正社員と比較して、格段に高いとは言えない。 残業代を含めた一般社員の収入と比較すると、優遇されているとは言えない。 → 管理監督者に見合う待遇ではない |
| 結論 | 店長は労働基準法上の管理監督者に該当しない。 したがって、時間外労働、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。 |
管理職でも深夜手当は必要
労働基準法第41条により、管理監督者は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されます。しかし、重要な点として、深夜労働に関する規定は適用除外されていません。
つまり、真の管理監督者であっても、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働した場合には、25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。これは労働基準法第37条第4項に明確に規定されています。
管理監督者について、時間外労働の割増(25%)は不要ですが、深夜労働の割増(25%)は必要です。したがって、管理監督者が深夜に働いた場合、その時間については基礎時給×1.25の深夜割増賃金を支払わなければなりません。
また、休日労働についても管理監督者には割増賃金は不要ですが、その休日労働が深夜時間帯に及ぶ場合には、やはり深夜割増賃金(25%)の支払いが必要です。
| 労働の種類 | 管理監督者の割増賃金 |
|---|---|
| 時間外労働(残業) | 割増賃金は不要 管理監督者は労働時間規制の適用除外のため、何時間働いても時間外割増は発生しません。 |
| 休日労働 | 割増賃金は不要 管理監督者は休日規制の適用除外のため、休日に働いても休日割増は発生しません。 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%の割増賃金が必要(労働基準法第37条第4項) 管理監督者であっても、深夜労働の規定は適用されます。 計算式:基礎時給×1.25×深夜労働時間 |
| 計算例 | 基礎時給3,000円の管理監督者が、午後10時から午前2時まで4時間働いた場合 深夜割増賃金:3,000円×1.25×4時間=15,000円 |
| 実務上の注意点 | 管理監督者の深夜労働時間を記録し、深夜割増賃金を正確に計算して支払う必要があります。 深夜労働の記録を怠ると、労働基準法違反となります。 |
公務員・地方公務員の残業代計算方法
公務員の残業代については、民間企業とは異なる法律や規則が適用されます。
国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法が適用され、労働基準法の一部規定が適用除外となっています。ただし、時間外労働に対する割増賃金の支払いという基本的な考え方は民間と同じです。
公務員の時間外勤務手当は、「超過勤務手当」「時間外勤務手当」などと呼ばれます。割増率は基本的に25%ですが、深夜勤務や休日勤務についてはさらに高い割増率が設定されている場合があります。また、公務員の場合、予算の制約から、実際の残業時間に対して十分な手当が支払われないケースもあり、いわゆる「サービス残業」の問題が指摘されています。
地方公務員の時間外勤務手当については、各自治体の条例や規則で定められています。基本的な考え方は国家公務員と同じですが、自治体によって細かい規定が異なる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用法令 | 国家公務員:国家公務員法、人事院規則 地方公務員:地方公務員法、各自治体の条例・規則 ※労働基準法の一部規定は適用除外 |
| 時間外勤務手当の名称 | 超過勤務手当、時間外勤務手当、時間外勤務割増賃金など |
| 割増率 | 基本的に25%(民間と同じ) 深夜勤務:25%〜50%(自治体により異なる) 休日勤務:35%(民間と同じ) |
| 計算方法 | (給料の月額+地域手当等の諸手当)÷月平均勤務時間数×割増率×時間外勤務時間 ※基本的な考え方は民間と同じ |
| 民間との違い | ①予算の制約があるため、実際の残業時間に対して十分な手当が支払われないことがある ②人事院規則や条例で細かく規定されている ③36協定は不要(公務のため労働基準法の適用除外) |
| 問題点 | 予算不足により、実際の残業時間の一部しか申請できない「サービス残業」の問題が指摘されています。 |
教員の残業代制度と計算方法
教員(公立学校の教員)の残業代については、非常に特殊な制度が適用されています。
公立学校の教員には、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(通称:給特法)が適用され、原則として時間外勤務手当が支給されません。その代わりに、給料月額の4%に相当する「教職調整額」が支給されます。
給特法では、教員の職務は自発性や創造性に基づくものであり、通常の労働とは異なるという考え方から、時間外勤務手当を支給しない代わりに、一律4%の調整額を支給する制度となっています。これは、昭和41年の教員の平均残業時間が月8時間程度だったことを根拠に設定されたものです。
しかし、現在の教員の実際の残業時間は月平均で数十時間に及ぶことも多く、4%の教職調整額では全く不十分だという指摘があります。長時間労働が常態化しているにもかかわらず、残業代が支払われないため、教員の働き方改革が喫緊の課題となっています。
なお、私立学校の教員については、給特法の適用はなく、労働基準法が適用されます。したがって、私立学校の教員には、民間企業と同様に時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用法律 | 給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法) |
| 時間外勤務手当 | 原則として支給されない 例外的に、①校外実習、②修学旅行、③職員会議、④非常災害時の業務のみ時間外勤務を命じることができ、手当が支給されます。 |
| 教職調整額 | 時間外勤務手当の代わりに、給料月額の4%に相当する「教職調整額」を支給。 例:給料月額30万円の場合、教職調整額は12,000円 |
| 4%の根拠 | 昭和41年当時の教員の平均残業時間(月約8時間)を根拠に設定。 しかし、現在の実態とは大きく乖離しています。 |
| 現在の問題点 | ①教員の実際の残業時間は月平均30〜50時間程度 ②4%の調整額では不十分 ③長時間労働が常態化 ④教員の働き方改革が喫緊の課題 |
| 私立学校の教員 | 給特法の適用はなく、労働基準法が適用されます。 したがって、私立学校の教員には、通常の時間外割増賃金が支払われます。 |
【業種別】残業代計算の特殊ケース
業種によっては、労働時間の管理方法や残業代の計算に特殊なルールが適用される場合があります。
特に、運送業、建設業などは、業務の性質上、通常のオフィスワークとは異なる労働時間管理が必要となり、残業代の計算にも注意が必要です。
ここでは、業種別の特殊な残業代計算方法について解説します。
運送業・トラックドライバーの残業代計算方法
運送業、特にトラックドライバーの労働時間管理は、一般的なオフィスワークとは大きく異なります。
拘束時間、運転時間、休憩時間、待機時間など、様々な時間の概念があり、これらを正確に理解した上で残業代を計算する必要があります。また、運送業には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)という特別な基準が適用されます。
拘束時間と労働時間の違い
運送業において重要な概念が「拘束時間」と「労働時間」の違いです。
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間であり、労働時間と休憩時間を合わせた時間です。一方、労働時間は、拘束時間から休憩時間を除いた、実際に労働に従事している時間を指します。残業代の計算に使用するのは、この労働時間です。
トラックドライバーの場合、運転時間はもちろん労働時間に含まれます。また、荷積み・荷卸しの時間、点呼の時間なども労働時間です。一方、完全に自由に利用できる休憩時間は労働時間に含まれません。
問題となるのが「待機時間」の扱いです。待機時間とは、荷主の都合で荷積み・荷卸しの順番を待っている時間などを指します。この待機時間が、労働時間に該当するかどうかは、その時間の自由度によって判断されます。使用者の指揮命令下にあり、いつでも業務に対応できる状態で待機している時間(手待ち時間)は労働時間に含まれます。一方、完全に自由に過ごせる時間であれば、労働時間には含まれません。実務上は、待機時間の多くは労働時間に該当すると考えられています。
| 時間の種類 | 内容・労働時間該当性 |
|---|---|
| 拘束時間 | 始業から終業までの全時間(労働時間+休憩時間) 改善基準告示で上限が定められています。 |
| 労働時間 | 実際に労働に従事している時間。残業代計算の基礎となる時間。 拘束時間から休憩時間を除いた時間。 |
| 運転時間 | 実際にトラックを運転している時間。労働時間に含まれる。 改善基準告示で上限が定められています。 |
| 荷積み・荷卸し時間 | 荷物の積み込み、積み降ろしの時間。労働時間に含まれる。 |
| 休憩時間 | 完全に自由に利用できる時間。労働時間に含まれない。 拘束時間から除外されます。 |
| 待機時間(手待ち時間) | 荷主の都合で待機している時間。 使用者の指揮命令下にあり、いつでも業務に対応できる状態なら労働時間に含まれる。 完全に自由に過ごせるなら労働時間に含まれない。 実務上は、多くの待機時間が労働時間に該当します。 |
改善基準告示との関係
運送業には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が適用されます。
これは、長時間労働になりがちな運送業において、運転者の健康を守るために設けられた基準です。拘束時間、運転時間、休息期間について、労働基準法とは別に上限が定められています。2024年4月からは、運送業にも時間外労働の上限規制が適用されるようになり、年960時間という特別な上限が設定されました。
改善基準告示で定められた拘束時間や運転時間の上限を守ることと、労働基準法に基づく残業代を正しく計算して支払うことは、別々の義務です。改善基準告示を守っていても、残業代の支払いが不要になるわけではありません。実際の労働時間に基づいて、適切に残業代を計算する必要があります。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 拘束時間(1日) | 原則として13時間以内(最大16時間まで延長可能) 15時間超は週2回まで |
| 拘束時間(1ヶ月) | 原則として293時間以内 労使協定により、1年のうち6ヶ月までは320時間まで延長可能 |
| 休息期間 | 勤務終了後、継続して8時間以上(9時間以上が望ましい) |
| 運転時間(2日平均) | 1日あたり平均9時間以内 |
| 運転時間(2週間) | 2週間で88時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩 |
| 時間外労働の上限(2024年4月〜) | 年960時間以内 ※一般労働者の年720時間より緩和された特別な上限 |
待機時間は労働時間か
運送業における待機時間の扱いは、残業代計算において非常に重要な論点です。
待機時間が労働時間に該当するかどうかは、その時間の実態によって判断されます。判断の基準は、「使用者の指揮命令下に置かれているか」という点です。
荷主の施設で荷積み・荷卸しの順番を待っている時間、すぐに運転を再開できる状態でトラック内で待機している時間などは、たとえ実際には何もしていなくても、使用者の指揮命令下にあり、いつでも業務に対応できる状態にあると言えます。このような「手待ち時間」は労働時間に含まれ、残業代の計算対象となります。
一方、完全に業務から解放され、自由に外出したり、自分の用事を済ませたりできる時間は、休憩時間として労働時間から除外されます。ただし、実務上、トラックドライバーが完全に自由な待機時間を持つことは少なく、多くの待機時間は労働時間に該当すると考えられます。
| 判断要素 | 内容 |
|---|---|
| 手待ち時間(労働時間) | 労働時間に含まれる待機時間 ①使用者の指揮命令下にある ②いつでも業務に対応できる状態で待機 ③自由に離れることができない ④荷主の施設での待機 ⑤トラック内での待機 |
| 休憩時間(労働時間外) | 労働時間に含まれない待機時間 ①完全に業務から解放されている ②自由に外出できる ③自分の用事を済ませられる ④使用者の指揮命令が及ばない |
| 実務上の判断 | 運送業の待機時間の多くは、「いつでも対応できる状態」を求められており、手待ち時間として労働時間に該当することが多い。 |
| 残業代計算への影響 | 待機時間を労働時間に含めるかどうかで、残業代の額が大きく変わります。 適切に労働時間を把握し、正確な残業代を計算する必要があります。 |
運送業の残業代計算例
実際の運送業における残業代計算の例を見てみましょう。
トラックドライバーの給与形態は、月給制、日給制、歩合制など様々ですが、ここでは月給制の例を紹介します。
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 条件 | 基本給:25万円 / 運転手当:3万円 / 通勤手当:1万円 月平均所定労働時間:173時間 / 月の実労働時間:230時間 |
| 基礎賃金 | 基本給25万円+運転手当3万円=28万円 ※通勤手当1万円は除外 |
| 基礎時給 | 280,000円÷173時間≒1,618円 |
| 時間外労働時間 | 実労働時間230時間−所定労働時間173時間=57時間 |
| 残業代 | 1,618円×1.25×57時間≒115,283円 |
| 月の総支給額 | 基本給25万円+運転手当3万円+通勤手当1万円+残業代115,283円=405,283円 |
| 注意点 | 待機時間を適切に労働時間として計上しているか、運転時間と非運転時間を正確に記録しているかが重要です。 |
建設業の残業代計算方法
建設業は、日給制が多く採用されている業種であり、また現場の状況によって労働時間が変動しやすいという特徴があります。
建設業においても、労働基準法が適用されますので、法定労働時間を超えて働いた場合には残業代の支払いが必要です。日給制の場合の残業代計算方法をしっかりと理解しておく必要があります。
日給制が多い建設業の残業代計算
建設業では、日給制で給与が支払われることが多くあります。日給制の場合、日給を1日の所定労働時間で割ることで基礎時給を算出します。
たとえば、日給12,000円で1日の所定労働時間が8時間の場合、基礎時給は12,000円÷8時間=1,500円となります。この基礎時給をもとに、法定労働時間(1日8時間)を超えた部分について、25%以上の割増賃金を計算します。
建設業の場合、天候に左右されやすく、雨天時には作業ができないことがあります。一方、工期の関係で長時間労働になることもあります。こうした状況下でも、実際の労働時間を正確に記録し、適切に残業代を計算することが重要です。
| 項目 | 内容・計算 |
|---|---|
| 条件 | 日給:12,000円 / 1日の所定労働時間:8時間 / 実労働時間:10時間 |
| 基礎時給 | 12,000円÷8時間=1,500円 |
| 通常労働(8時間) | 日給としてすでに支払われている:12,000円 |
| 時間外労働(2時間) | 1,500円×1.25×2時間=3,750円 |
| 1日の総賃金 | 12,000円+3,750円=15,750円 |
現場手当の取り扱い
建設業では、危険作業手当、現場手当、技能手当など、様々な手当が支給されることがあります。
これらの手当が残業代の計算における基礎賃金に含まれるかどうかは、その手当の性質によって判断されます。労働の対価として支払われる手当(技能手当、職務手当など)は基礎賃金に含める必要があります。一方、家族手当、通勤手当、住宅手当など、労働基準法施行規則第21条で除外が認められている手当は、基礎賃金から除外できます。
現場手当については、その性質を個別に判断する必要があります。特定の現場での作業に対する対価として支払われるものであれば、基礎賃金に含める必要があると考えられます。一方、通勤距離に応じて支払われる現場手当であれば、通勤手当と同様の性質を持つため、除外できる可能性があります。
| 手当の種類 | 基礎賃金への算入 |
|---|---|
| 技能手当 | 算入する 労働者の技能に対する対価であり、労働と密接な関係があります。 |
| 危険作業手当 | 算入する 特定の作業に対する対価であり、労働の内容に応じて支払われます。 |
| 現場手当 | 原則として算入する 特定の現場での作業に対する対価であれば算入。 ただし、通勤費の補填的性格が強い場合は除外できる可能性あり。 |
| 通勤手当 | 除外できる 労働基準法施行規則第21条により除外可能。 |
| 家族手当 | 除外できる 労働基準法施行規則第21条により除外可能。 |
| 住宅手当 | 除外できる(条件あり) 実費弁償的性格を持つ場合に限り除外可能。 |
悪天候による休業時の取り扱い
建設業では、雨天などの悪天候により作業ができず、休業となることがあります。
この場合の給与の取り扱いは、休業の原因が使用者の責めに帰すべき事由によるものか、天災事変など不可抗力によるものかによって異なります。
天候不良が不可抗力と認められる場合、使用者には休業手当の支払い義務はありません。ただし、事前に天候不良が予測できたにもかかわらず、適切な対応(作業の中止判断、別の作業の用意など)を取らなかった場合は、使用者の責めに帰すべき事由と判断される可能性があります。
実務上は、雨天時の取り扱いについて、就業規則や雇用契約書で明確に定めておくことが重要です。「雨天休業の場合は無給」などと規定している場合もありますが、その場合でも、使用者側に責任がある休業については、労働基準法第26条に基づき、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
| 休業の原因 | 賃金の取り扱い |
|---|---|
| 不可抗力による休業(天災等) | 休業手当の支払い義務なし 突発的な天候不良で、事前に予測不可能だった場合など。 ただし、就業規則で休業時の賃金を定めている場合はそれに従います。 |
| 使用者の責めに帰すべき事由による休業 | 平均賃金の60%以上の休業手当が必要(労働基準法第26条) 天候不良が事前に予測できたのに適切な対応をしなかった場合など。 |
| 実務上の対応 | ①就業規則で雨天時の取り扱いを明確に規定 ②天気予報等で事前に判断し、労働者に連絡 ③可能であれば、雨天時の別作業を用意 ④休業の原因を記録し、適切に賃金を支払う |
| 2024年4月からの上限規制 | 建設業にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。 災害時の復旧・復興事業を除き、年720時間、月45時間等の上限が適用されます。 |
会社員・一般企業の残業代計算
会社員や一般企業で働く労働者の残業代計算は、これまで解説してきた標準的な方法が適用されます。
業種による特殊性はなく、月給制であれば月給を月平均所定労働時間で割って基礎時給を算出し、残業時間と割増率をかけて計算します。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた部分には25%以上、深夜時間帯(22時〜5時)には25%以上、法定休日には35%以上の割増賃金が必要です。
一般企業の会社員の場合、勤怠管理システムやタイムカードで労働時間を正確に記録し、給与計算ソフトで残業代を自動計算することが一般的です。企業の労務担当者は、労働基準法を遵守し、適切に残業代を計算して支払う責任があります。
【実務・ツール】残業代計算を効率化する方法
残業代の計算は、給与形態や労働時間制度によって複雑になることがあります。
正確な計算を効率的に行うために、Excelなどの表計算ソフトや専用の計算ツール、勤怠管理システム、給与計算ソフトを活用することが有効です。ここでは、実務で使える残業代計算の効率化方法について解説します。
エクセル(Excel)での残業代計算方法
Excel(エクセル)は、多くの企業で導入されており、残業代の計算にも活用できます。
残業代計算Excelテンプレートを利用すると、データを入力するだけで自動的に残業代を計算できます。
ですが、これまでご説明したように、基礎時給や、残業代の割増率は複雑な計算が絡みますので、社労士の事前の相談がおすすめです。
【無料配布】残業代計算Excelテンプレート
実務で使える残業代計算のExcelテンプレートがあれば、データを入力するだけで簡単に残業代を計算できます。
基本的なテンプレートには、以下の項目を含めると便利です。従業員情報(氏名、社員番号など)、給与情報(基本給、各種手当)、労働時間情報(所定労働時間、月平均所定労働時間)、残業時間情報(通常の時間外労働、深夜労働、休日労働)、そして自動計算される項目(基礎時給、各種残業代、合計残業代、総支給額)です。
当事務所では、社労士として企業の給与計算をサポートしており、実務で使用しているExcelテンプレートをベースにした計算ツールを提供することも可能です。お問い合わせいただければ、貴社の給与体系に合わせたカスタマイズも承ります。
ExcelダウンロードはHR-BrEdge法人_残業代計算のテンプレートから
残業代計算ツール・アプリの活用
Excel以外にも、残業代を簡単に計算できる専用のツールやアプリが数多く提供されています。
Webブラウザ上で使える無料の計算ツールや、スマートフォンアプリなど、様々な選択肢があります。これらのツールを活用することで、外出先でも手軽に残業代を計算したり、自分の給与が正しいかを確認したりすることができます。
無料の残業代計算ツール
インターネット上には、無料で使える残業代計算ツールが多数公開されています。
これらのツールは、基本給、月平均所定労働時間、残業時間などを入力するだけで、自動的に残業代を計算してくれます。複雑な計算式を知らなくても、簡単に残業代を算出できるため、労働者が自分の残業代を確認する際に便利です。
ツールによっては、深夜労働や休日労働にも対応しており、それぞれの時間を入力すると、適切な割増率を適用して計算してくれます。また、月60時間を超える残業についても、自動的に50%割増で計算してくれるツールもあります。
ただし、無料ツールには限界もあります。複雑な給与体系(歩合給や固定残業代を含む場合など)には対応していないことが多く、あくまで簡易的な計算ツールとして利用することをお勧めします。正確な計算が必要な場合や、企業として給与計算を行う場合は、専門の給与計算ソフトや社労士への相談を検討してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ①無料で利用できる ②インストール不要(ブラウザで利用) ③簡単な入力で計算できる ④外出先でも利用可能 ⑤匿名で利用できる |
| 基本機能 | ①基本給からの基礎時給計算 ②時間外労働の残業代計算 ③深夜労働の残業代計算 ④休日労働の残業代計算 ⑤月60時間超の50%割増対応 |
| デメリット・限界 | ①複雑な給与体系に対応していない ②歩合給や固定残業代の計算は難しい ③変形労働時間制などには非対応 ④データの保存機能がない ⑤あくまで簡易計算ツール |
| 推奨する使い方 | ①自分の残業代の概算確認 ②給与明細との照合 ③未払い残業代の有無の簡易チェック ④正確な計算が必要な場合は専門家へ相談 |
| 注意点 | 無料ツールの計算結果は参考値として扱い、法的な主張の根拠とする場合は、専門家(社労士、弁護士)に正確な計算を依頼することをお勧めします。 |
残業代計算アプリ(スマホアプリ)
スマートフォンアプリとしても、残業代計算アプリが提供されています。
これらのアプリは、残業代の計算だけでなく、日々の労働時間を記録する機能や、給与明細を保存する機能、未払い残業代を自動算出する機能などを備えているものもあります。毎日の出退勤時刻を記録しておけば、月末に自動的に残業代を計算してくれるため、給与明細と照合して未払いがないかを確認できます。
アプリによっては、タイムカード機能、シフト管理機能、複数のアルバイトの給与管理機能など、便利な機能が搭載されています。特にパートやアルバイトで複数の職場で働いている方には、収入を一元管理できるアプリが便利です。
ただし、アプリに記録したデータが法的な証拠として十分かどうかは別問題です。未払い残業代を請求する際には、会社のタイムカードやPCログなど、客観的な記録が必要になります。アプリの記録は、あくまで自己管理のための補助的なツールとして活用し、公式な記録とは別に保管しておくことをお勧めします。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間記録機能 | ①出勤・退勤時刻の記録 ②休憩時間の記録 ③GPS機能で出勤場所を記録 ④写真でタイムカードを保存 |
| 残業代自動計算 | ①基本給・時給の設定 ②月末の自動集計 ③時間外・深夜・休日の自動判定 ④予想給与額の表示 |
| 給与管理機能 | ①給与明細の保存 ②複数職場の収入管理 ③年収の自動計算 ④グラフ表示 |
| その他の便利機能 | ①シフト管理 ②アラーム・通知機能 ③データのバックアップ ④CSV出力機能 |
| 法的証拠としての限界 | アプリの記録は自己申告であり、客観的な証拠としては弱い面があります。 未払い残業代を請求する際は、会社のタイムカード、PCログ、メールの送受信記録など、客観的な証拠を併せて用意する必要があります。 |
| 推奨する使い方 | ①日々の労働時間の自己管理 ②給与明細との照合 ③未払い残業代の概算把握 ④将来的な請求に備えた記録保存 |
残業単価計算ツールの使い方
残業単価(基礎時給)を計算する専用のツールもあります。
これは、月給や日給から基礎時給を算出するためのツールで、月平均所定労働時間の計算も同時に行ってくれます。年間休日数と1日の所定労働時間を入力すると、月平均所定労働時間が自動計算され、そこから基礎時給が算出されます。
基礎時給は残業代計算の基礎となる重要な数値ですが、計算方法が複雑なため、ツールを使うことで正確に算出できます。特に、どの手当を基礎賃金に含めるべきかの判断は難しいため、ツールに各手当の情報を入力すると、自動的に判定してくれる機能があるものもあります。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 月平均所定労働時間の計算 | 年間休日数と1日の所定労働時間を入力すると、自動計算されます。 計算式:(365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月 |
| 基礎賃金の自動判定 | 各手当の名称と金額を入力すると、基礎賃金に含めるべきかを自動判定。 ただし、完全に正確な判定は難しいため、最終的には人間の確認が必要です。 |
| 基礎時給の算出 | 基礎賃金÷月平均所定労働時間で基礎時給を算出。 この基礎時給を使って残業代を計算します。 |
| 複数の給与形態に対応 | 月給制、日給制、時給制など、それぞれの給与形態に応じた基礎時給の計算方法に対応しているツールもあります。 |
| 使い方のポイント | ①正確な年間休日数を確認 ②就業規則で所定労働時間を確認 ③各手当の性質を理解して入力 ④計算結果を給与明細と照合 |
勤怠管理システムでの残業時間・残業代の自動計算
企業が従業員の労働時間を管理し、残業代を正確に計算するためには、勤怠管理システムの導入が非常に有効です。
勤怠管理システムは、従業員の出退勤時刻を自動的に記録し、労働時間を集計し、残業時間を算出し、さらには残業代まで自動計算してくれる総合的なシステムです。近年は、クラウド型の勤怠管理システムが主流となっており、初期費用を抑えて導入でき、スマートフォンからも利用できるため、多くの企業で採用されています。
勤怠管理システムのメリット
勤怠管理システムを導入する最大のメリットは、労働時間の客観的な記録と正確な残業代計算が実現できることです。
従来の紙のタイムカードやExcelでの管理では、記録の改ざんや計算ミスのリスクがありました。また、集計作業に膨大な時間がかかり、労務担当者の負担が大きいという問題もありました。勤怠管理システムを導入すれば、これらの問題を一気に解決できます。
従業員は、ICカード、生体認証、スマートフォンなどで簡単に打刻できます。打刻データはリアルタイムでシステムに記録され、改ざんのリスクが大幅に減少します。また、労働時間は自動的に集計され、所定労働時間を超える部分、法定労働時間を超える部分などが自動的に区別されます。
さらに、給与計算ソフトと連携することで、集計された労働時間データが自動的に給与計算ソフトに渡され、残業代が自動計算されるため、計算ミスがなくなり、給与計算業務の効率が大幅に向上します。
労働基準法の遵守という観点からも、勤怠管理システムは有効です。システムには、労働時間の上限規制に近づいた従業員にアラートを出す機能、36協定の上限をチェックする機能、有給休暇の取得状況を管理する機能などが搭載されており、法令違反を未然に防ぐことができます。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 労働時間の客観的記録 | ①ICカード、生体認証、スマホで簡単打刻 ②リアルタイムで記録 ③改ざんのリスク低減 ④GPS機能で場所も記録(外勤者対応) |
| 残業時間の自動集計 | ①所定労働時間を超える時間を自動計算 ②法定労働時間を超える時間を自動判定 ③深夜時間帯、休日労働の自動区別 ④月60時間超の自動判定 |
| 残業代の自動計算 | ①給与計算ソフトとの連携 ②基礎時給の自動算出 ③割増率の自動適用 ④計算ミスの防止 |
| 法令遵守の支援 | ①上限規制の監視・アラート ②36協定の上限チェック ③有給休暇の管理 ④労働時間の見える化 |
| 業務効率化 | ①集計作業の自動化 ②労務担当者の負担軽減 ③ペーパーレス化 ④リモートワーク対応 |
| データ活用 | ①労働時間の分析 ②部署別・個人別の集計 ③残業削減の効果測定 ④経営判断のためのデータ提供 |
おすすめの勤怠管理システム
市場には多数の勤怠管理システムが提供されており、企業の規模や業種、ニーズに応じて選択できます。
クラウド型の勤怠管理システムは、初期費用が安く、インターネット環境があればどこからでも利用できるため、中小企業やリモートワークを導入している企業に人気です。代表的なシステムとしては、ジョブカン、キングオブタイム、AKASHI、マネーフォワードクラウド勤怠などがあります。
システムを選ぶ際のポイントは、自社の勤務形態に対応しているか、給与計算ソフトとの連携が可能か、操作が簡単か、サポート体制が充実しているかなどです。特に、変形労働時間制やフレックスタイム制など、特殊な労働時間制度を採用している場合は、それに対応したシステムを選ぶ必要があります。
導入にあたっては、無料トライアル期間を利用して、実際に使ってみることをお勧めします。従業員が使いやすいか、自社の業務フローに合っているかを確認した上で、正式に導入しましょう。また、導入後の従業員への説明や、システムの設定には専門知識が必要な場合があるため、社労士のサポートを受けることも検討してください。
| 選定ポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 自社の勤務形態への対応 | ①通常の勤務形態(固定時間制) ②変形労働時間制 ③フレックスタイム制 ④シフト制 ⑤リモートワーク・テレワーク |
| 打刻方法 | ①ICカード ②生体認証(指紋、顔認証等) ③スマートフォン ④PC ⑤GPS機能の有無 |
| 給与計算ソフトとの連携 | ①既存の給与計算ソフトとの連携可能性 ②データのCSV出力 ③API連携の有無 |
| 機能の充実度 | ①残業時間の自動集計 ②アラート機能 ③有給休暇管理 ④シフト作成機能 ⑤承認ワークフロー |
| 操作性 | ①従業員が使いやすいか ②管理者の操作は簡単か ③スマホ対応 ④無料トライアルで実際に試す |
| サポート体制 | ①導入時のサポート ②使い方の説明・研修 ③問い合わせ対応(電話、メール、チャット) ④マニュアルの充実度 |
| コスト | ①初期費用 ②月額料金(従業員数に応じて変動) ③追加オプションの料金 ④費用対効果 |
| 法令対応 | ①労働基準法の最新規定への対応 ②上限規制のチェック機能 ③法改正時のシステム更新 |
給与計算ソフトでの残業代計算
勤怠管理システムと連携する給与計算ソフトを導入すれば、残業代の計算から給与明細の作成まで、一連の給与計算業務を自動化できます。
給与計算ソフトには、従業員の基本給、各種手当、控除項目などの情報が登録されています。勤怠管理システムから労働時間のデータが送られてくると、給与計算ソフトは自動的に残業代を計算し、社会保険料、所得税などの控除額も計算し、最終的な支給額を算出します。
給与明細も自動で作成され、Web上で従業員に配信したり、メールで送信したりできます。ペーパーレス化により、印刷や封入の手間が省け、コスト削減にもつながります。
代表的な給与計算ソフトとしては、freee人事労務、マネーフォワードクラウド給与、ジョブカン給与計算、弥生給与などがあります。これらのソフトは、勤怠管理システムとの連携機能を持っており、データの二重入力の手間がなく、正確な給与計算が実現できます。
給与計算は専門知識が必要な業務であり、法改正にも対応する必要があります。給与計算ソフトを導入しても、設定や運用には専門知識が必要な場合があるため、社労士のサポートを受けながら導入することをお勧めします。当事務所では、給与計算ソフトの導入支援から、運用サポート、給与計算のアウトソーシングまで、幅広くサポートしております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データの自動連携 | 勤怠管理システムで集計された労働時間データが、自動的に給与計算ソフトに取り込まれます。 二重入力の手間がなく、入力ミスも防止できます。 |
| 残業代の自動計算 | 基礎時給、残業時間、割増率から、自動的に残業代が計算されます。 複雑な計算もソフトが自動で行うため、計算ミスがありません。 |
| 給与明細の自動作成 | 支給額、控除額を自動計算し、給与明細を作成。 Web給与明細システムで従業員に配信できます。 |
| 法改正への自動対応 | 税率、社会保険料率、労働法規の改正に自動対応。 常に最新の法令に基づいた計算が可能です。 |
| 業務効率化 | 給与計算にかかる時間を大幅に削減。 労務担当者は、より付加価値の高い業務に専念できます。 |
| 社労士のサポート | 給与計算ソフトの導入には専門知識が必要です。 当事務所では、システムの選定、初期設定、運用サポート、給与計算のアウトソーシングまで、トータルでサポートいたします。 |
【関連制度】残業代が影響する各種計算
残業代は、単に毎月の給与計算だけでなく、社会保険や雇用保険の各種給付金の計算にも影響を与えます。
雇用保険料、社会保険の標準報酬月額、育児休業給付の基礎となる休業開始時賃金日額、解雇予告手当の基礎となる平均賃金、傷病手当金など、様々な制度において残業代が計算の基礎に含まれます。これらの制度を正しく理解することで、労働者は適切な給付を受けることができ、企業も正確な社会保険手続きを行うことができます。
雇用保険料の計算方法と残業代が与える影響
雇用保険料は、毎月の給与から控除される社会保険料の一つです。
雇用保険料の計算において、残業代は非常に重要な要素となります。雇用保険料は、基本給だけでなく、残業代を含む総支給額をもとに計算されるためです。つまり、残業が多い月は、それだけ雇用保険料も高くなります。
雇用保険料の計算式は、「総支給額×雇用保険料率」となります。総支給額とは、基本給、諸手当、残業代、賞与などを全て含めた、控除前の給与の合計額です。ここから雇用保険料率をかけることで、雇用保険料が算出されます。
雇用保険料率は、一般の事業の場合、労働者負担が0.6%、事業主負担が0.95%です(2024年度)。建設業や農林水産業など、一部の業種では料率が異なります。この料率は毎年度見直される可能性があるため、最新の料率を確認する必要があります。
たとえば、ある月の総支給額が基本給25万円、残業代5万円、合計30万円だった場合、労働者が負担する雇用保険料は、300,000円×0.006=1,800円となります。残業代が含まれることで、残業代がない場合(25万円×0.006=1,500円)と比べて、300円雇用保険料が増えることになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 雇用保険料=総支給額×雇用保険料率 総支給額には、基本給、諸手当、残業代、賞与などが全て含まれます。 |
| 総支給額の範囲 | ①基本給 ②諸手当(役職手当、資格手当等) ③残業代(時間外・深夜・休日手当) ④通勤手当 ⑤住宅手当 ⑥家族手当 ⑦賞与(賞与月) |
| 雇用保険料率(2024年度) | 一般の事業 労働者負担:0.6% 事業主負担:0.95% 建設業 労働者負担:0.7% 事業主負担:1.15% 農林水産・清酒製造業 労働者負担:0.7% 事業主負担:1.05% |
| 計算例 | 条件:総支給額30万円(基本給25万円+残業代5万円) 労働者負担:300,000円×0.006=1,800円 事業主負担:300,000円×0.0095=2,850円 合計:4,650円 |
| 残業代の影響 | 残業代が増えると、その分雇用保険料も増加します。 ただし、労働者は将来的に失業給付や育児休業給付を受ける際、残業代を含めた高い賃金をもとに給付額が計算されるため、メリットもあります。 |
標準報酬月額に残業代が与える影響
標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料を計算するための基礎となる金額です。
標準報酬月額の決定においても、残業代は重要な要素となります。標準報酬月額は、毎年4月から6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額をもとに決定されます(定時決定)。この報酬には、基本給だけでなく、残業代も含まれます。
4月から6月に残業が多かった場合、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が高くなり、結果として健康保険料と厚生年金保険料が高くなります。逆に、4月から6月の残業が少なかった場合は、標準報酬月額が低くなり、保険料も安くなります。
標準報酬月額は、単に保険料の計算に使われるだけでなく、将来受け取る年金額の計算にも影響します。厚生年金保険料を多く払えば、将来受け取る年金額も増えます。また、健康保険の傷病手当金や出産手当金の計算にも、標準報酬月額が使用されます。したがって、残業代が標準報酬月額に含まれることは、長期的には労働者にとってメリットとなる場合もあります。
標準報酬月額は、定時決定(4月〜6月の平均)のほかに、随時改定(月額変更届)という仕組みもあります。昇給や降給などにより、固定的賃金が大きく変動し、3ヶ月間の平均報酬が2等級以上変動した場合には、随時改定により標準報酬月額が変更されます。ただし、残業代などの非固定的賃金の変動だけでは、随時改定の対象にはなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準報酬月額とは | 健康保険料・厚生年金保険料を計算するための基礎となる金額。 実際の報酬を一定の幅で区切った「等級」で管理されます。 |
| 定時決定(算定基礎届) | 毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。 この報酬には、残業代も含まれます。 |
| 報酬に含まれるもの | ①基本給 ②諸手当(役職手当、資格手当、家族手当、通勤手当等) ③残業代(時間外・深夜・休日手当) ④その他労働の対価として支払われるもの |
| 報酬に含まれないもの | ①年3回以下の賞与 ②臨時に支払われるもの ③見舞金等の恩恵的なもの |
| 計算例 | 条件:4月・5月・6月の報酬 4月:28万円(基本給25万円+残業代3万円) 5月:30万円(基本給25万円+残業代5万円) 6月:29万円(基本給25万円+残業代4万円) 平均:(28+30+29)÷3=29万円 この29万円をもとに標準報酬月額が決定されます(等級表に当てはめる)。 |
| 随時改定(月額変更) | 昇給・降給等により固定的賃金が変動し、継続した3ヶ月間の平均報酬が2等級以上変動した場合に標準報酬月額を改定。 注意:残業代などの非固定的賃金の変動のみでは、随時改定の対象になりません。 |
| 年金額への影響 | 標準報酬月額が高いほど、厚生年金保険料を多く払うことになりますが、将来受け取る年金額も増えます。 残業代が標準報酬月額に含まれることで、長期的には年金受給額が増えるメリットがあります。 |
ボーナス(賞与)の計算方法と残業代
ボーナス(賞与)は、通常、残業代の計算における基礎賃金には含まれません。
労働基準法施行規則第21条では、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は、残業代計算の基礎賃金から除外できると定められています。一般的な賞与は、年2回〜3回、3ヶ月以上の期間ごとに支払われるため、基礎賃金から除外できます。
ただし、年4回以上支給される賞与は、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは言えず、実質的に定期的な賃金の一部とみなされます。そのため、年4回以上支給される場合は、基礎賃金に算入する必要があります。
また、賞与の支給額を計算する際に、残業時間や残業代を考慮するかどうかは、会社の賞与規程によって決まります。一般的には、基本給をもとに賞与を計算する会社が多いですが、残業の多さを評価して賞与額に反映する会社もあります。これは会社の裁量によるものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賞与の基礎賃金への算入 | 年3回以下:基礎賃金に算入しない(除外できる) 年4回以上:基礎賃金に算入する(定期賃金とみなされる) |
| 年3回以下の場合 | 夏・冬の年2回、または夏・冬・決算賞与の年3回などの場合、残業代の計算には含めません。 これらは「臨時的」な賃金とみなされます。 |
| 年4回以上の場合 | 四半期ごと(年4回)の賞与などは、実質的に定期賃金の一部とみなされます。 この場合、賞与も含めて基礎時給を計算し、残業代を算出します。 |
| 年4回以上の賞与を含む基礎時給の計算 | 年間賞与総額÷12ヶ月=月額換算額 (基本給+諸手当+月額換算額)÷月平均所定労働時間=基礎時給 例:基本給25万円、賞与10万円×4回=年40万円 月額換算:40万円÷12=約3.3万円 基礎賃金:25万円+3.3万円=28.3万円 基礎時給:283,000円÷173時間≒1,636円 |
| 賞与額の計算に残業を考慮するか | これは会社の賞与規程によるもので、法律上の義務ではありません。 ①基本給のみを基準に計算する会社 ②残業時間や勤務態度を評価に含める会社 ③業績連動で計算する会社 など、様々な方法があります。 |
| 社会保険料との関係 | 賞与(年3回以下)には、健康保険料・厚生年金保険料がかかります(標準賞与額として計算)。 また、雇用保険料も賞与に対してかかります。 賞与の額が大きいと、それだけ社会保険料も高くなります。 |
【法的知識】残業代に関する労働基準法と厚生労働省の規定
残業代の支払いは、労働基準法によって明確に義務付けられています。
企業も労働者も、労働基準法の規定を正しく理解し、適切に残業代を計算・支払い・受け取ることが重要です。ここでは、残業代に関連する労働基準法の主要な条文と、厚生労働省の通達について解説します。
労働基準法第37条(時間外・休日・深夜労働の割増賃金)
残業代の支払いを義務付けている最も重要な条文が、労働基準法第37条です。
この条文では、使用者が労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金に対して、一定の割増率以上の割増賃金を支払わなければならないと定めています。
労働基準法第37条第1項では、時間外労働(法定労働時間を超える労働)については25%以上、休日労働(法定休日の労働)については35%以上の割増率で計算した割増賃金を支払うことが義務付けられています。また、同条第4項では、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については25%以上の割増率が必要とされています。
さらに、2010年4月からは、1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増率が適用されるようになりました(当初は大企業のみ、2023年4月からは中小企業にも適用)。これは、長時間労働を抑制し、労働者の健康を守るための措置です。
労働基準法第37条第5項および労働基準法施行規則第21条では、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当が定められています。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、基礎賃金から除外することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文の趣旨 | 使用者が労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、割増賃金を支払わなければならないと定めた条文。 |
| 時間外労働(第1項) | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働に対して、通常の賃金の25%以上の割増。 計算式:通常の賃金×1.25以上 |
| 月60時間超の時間外労働(第1項) | 1ヶ月の時間外労働が60時間を超える部分について、通常の賃金の50%以上の割増。 2023年4月から中小企業にも適用。 |
| 休日労働(第1項) | 法定休日の労働に対して、通常の賃金の35%以上の割増。 計算式:通常の賃金×1.35以上 |
| 深夜労働(第4項) | 午後10時〜午前5時の労働に対して、通常の賃金の25%以上の割増。 時間外労働や休日労働と重なる場合は、割増率を加算。 |
| 基礎賃金から除外できる手当(第5項、施行規則第21条) | ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
| 罰則 | 割増賃金を支払わない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条) |
厚生労働省の通達・解釈
労働基準法第37条の運用については、厚生労働省から様々な通達が出されており、実務上の判断基準となっています。
たとえば、昭和63年3月14日基発第150号では、労働時間と賃金の端数処理について、一定の端数処理が認められています。1ヶ月の労働時間の合計について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは違法ではないとされています。ただし、1日ごとの労働時間で端数を切り捨てることは違法です。
また、賃金の端数処理についても、1ヶ月の賃金総額に対して、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること、または100円未満を四捨五入することは認められています。
さらに、固定残業代(みなし残業代)に関する通達もあります。固定残業代が有効となるためには、通常の賃金部分と残業代部分が明確に区別されていること、何時間分の残業代が含まれているかが明示されていること、固定残業時間を超えた場合は超過分を別途支払うことが必要とされています。
| 通達 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間・賃金の端数処理 (昭和63年3月14日基発第150号) |
労働時間:1ヶ月の合計時間について、30分未満切り捨て・30分以上切り上げは可。 賃金:1ヶ月の賃金総額について、50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ、または100円未満四捨五入は可。 注意:1日ごとの端数切り捨ては違法。 |
| 労働時間の適正な把握 (平成29年1月20日基発0120第3号) |
使用者は、労働時間を適正に把握する責務があります。 ①客観的な記録(タイムカード、ICカード、PCログ等)による把握 ②自己申告制の場合は、実態調査と適正化措置が必要 ③労働時間の記録を3年間保存 |
| 固定残業代に関する指導 (各種通達・裁判例) |
固定残業代が有効となる要件: ①通常の賃金と残業代の明確な区別 ②残業時間数の明示 ③固定残業時間を超えた場合の超過分支払い これらを満たさない場合、固定残業代は無効となります。 |
| 割増賃金の基礎となる賃金 (労働基準法施行規則第21条) |
除外できる手当を具体的に列挙。 ただし、名称だけでなく実態に即して判断する必要があります。 |
残業の法的定義と基本知識もおさらい
残業代の計算方法を理解する上で、「そもそも残業とは何か」という基本的な定義を正確におさらいしておくことも重要です。
労働基準法における法定労働時間、法定休日の概念を理解し、法定内残業と法定外残業の違いを把握することで、より正確な残業代計算ができるようになります。
残業(時間外労働)の定義
残業とは、一般的に所定労働時間を超えて働くことを指しますが、労働基準法上の「時間外労働」は、より厳密に定義されています。
法定労働時間とは
労働基準法第32条では、使用者が労働者の従事可能な時間の上限を定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1日の法定労働時間 | 1日8時間が上限。 休憩時間を除き、1日に8時間を超えての従事は原則できません。 |
| 1週間の法定労働時間 | 1週40時間が上限。 休憩時間を除き、1週間に40時間を超えての従事は原則できません。 |
| 法定労働時間を超える場合 | 36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・届出が必要。 さらに、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。 |
| 特例措置対象事業場 | 常時10人未満の労働者を使用する特定の業種(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)では、週44時間まで認められます。 |
| 休憩時間の扱い | 労働時間には休憩時間は含まれません。 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります(労働基準法第34条)。 |
法定休日とは
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して休日を与えなければならないと定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法定休日の付与義務 | 使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 または、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。 |
| 法定休日の特定 | 就業規則で「日曜日を法定休日とする」などと特定することが望ましいです。 特定していない場合、週の最後の休日(通常は日曜日)が法定休日となります。 |
| 法定休日に労働が生じる場合 | 36協定の締結・届出が必要。 さらに、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。 |
| 週休2日制との関係 | 週休2日制の会社の場合、2日のうち1日が法定休日、もう1日は法定外休日(所定休日)です。 例:日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日。 |
残業代計算での、法定内残業と法定外残業の違い
残業には、「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。
この違いを理解することが、正確な残業代計算の基礎となります。
法定内残業(所定外労働)とは
法定内残業とは、会社の所定労働時間を超えるものの、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内の労働を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 所定労働時間を超えるが、法定労働時間(1日8時間、週40時間)以内の労働。 「所定外労働」とも呼ばれます。 |
| 具体例 | 所定労働時間が7時間の会社で、8時間働いた場合の1時間。 この1時間は所定労働時間を超えていますが、法定労働時間(8時間)以内です。 |
| 割増賃金の有無 | 労働基準法上の割増賃金の支払い義務はありません。 ただし、就業規則で定めがあれば支給する必要があります。 多くの会社では、通常の時給(割増なし)で支払っています。 |
| 計算方法 | 基礎時給×法定内残業時間(割増率1.0) 例:基礎時給1,500円×1時間×1.0=1,500円 |
法定外残業(法定時間外労働)とは
法定外残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を指します。
これが労働基準法第37条で規定される「時間外労働」であり、割増賃金の対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働。 労働基準法第37条で規定される「時間外労働」を指します。 |
| 具体例 | 1日9時間働いた場合の8時間を超える1時間。 週に45時間働いた場合の40時間を超える5時間。 |
| 割増賃金 | 25%以上の割増賃金の支払いが義務(労働基準法第37条)。 月60時間を超える部分は50%以上の割増。 |
| 36協定 | 法定外残業の実施にあたっては、36協定の締結・届出が必須。 36協定なしで法定外残業を行うことは違法です(労働基準法第32条違反)。 |
| 計算方法 | 基礎時給×時間外労働時間×1.25 例:基礎時給1,500円×1時間×1.25=1,875円 |
法定内残業と法定外残業の判定フローチャート
| 判定ステップ | 判定内容 |
|---|---|
| ステップ① | 所定労働時間を超えているか? YES → 所定外労働(さらにステップ②へ) NO → 通常労働(割増なし) |
| ステップ② | 1日8時間または週40時間を超えているか? YES → 法定外残業(25%以上割増) NO → 法定内残業(割増義務なし) |
| 具体例① | 所定労働時間7時間の会社で8時間働いた場合 7〜8時間の1時間:法定内残業(割増なし) |
| 具体例② | 所定労働時間7時間の会社で9時間働いた場合 7〜8時間の1時間:法定内残業(割増なし) 8〜9時間の1時間:法定外残業(25%割増) |
| 具体例③ | 所定労働時間8時間の会社で9時間働いた場合 8〜9時間の1時間:法定外残業(25%割増) |
残業代計算における、所定労働時間と所定労働日数とは
所定労働時間と所定労働日数は、会社が就業規則で定める労働条件であり、法定労働時間とは異なります。
所定労働時間の定義と確認方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所定労働時間とは | 会社が就業規則で定めた1日の労働時間。 法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、会社が自由に設定できます。 |
| 一般的な所定労働時間 | 多くの会社では1日8時間を所定労働時間としています。 例:9時〜18時(休憩1時間)=所定労働時間8時間 |
| 短時間の所定労働時間 | 所定労働時間を7時間や7.5時間としている会社もあります。 例:9時〜17時(休憩1時間)=所定労働時間7時間 |
| 確認方法 | ①就業規則の「労働時間」の項目を確認 ②雇用契約書の労働条件を確認 ③労務担当者に問い合わせ |
| 法定労働時間との関係 | 所定労働時間は、法定労働時間を超えて設定することはできません。 所定労働時間8時間はOK、9時間は違法。 |
所定労働日数の定義と年間労働日数
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所定労働日数とは | 会社が定めた年間の労働日数。 365日から年間休日数を引いた日数となります。 |
| 計算式 | 所定労働日数=365日−年間休日数 例:年間休日120日の場合 → 所定労働日数245日 |
| 一般的な所定労働日数 | 週休2日制で年間休日120日前後の場合:約240〜250日 週休1日制で年間休日80日前後の場合:約280〜290日 |
| 月平均所定労働時間の計算 | 所定労働日数を使って計算します。 (365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月 例:年間休日120日、1日8時間の場合 (365−120)×8÷12≒163.3時間 |
| 残業代計算への影響 | 月平均所定労働時間は基礎時給の計算に使用するため、所定労働日数は残業代に直接影響します。 所定労働日数が多い(休日が少ない)ほど、月平均所定労働時間が増え、基礎時給は下がります。 |
残業に関する法的要件|36協定と上限規制
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者に残業を行う場合、または法定休日に労働が発生する場合には、法律上の手続きが必要です。
具体的には、労使間で36協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、2019年の働き方改革関連法により、残業時間には上限規制が設けられ、違反した場合には罰則が科されるようになりました。
ここでは、残業に関するの法的要件と、企業が守るべき上限規制について詳しく解説します。
36協定(サブロク協定)とは
36協定は、労働基準法第36条に基づく労使協定で、時間外労働や休日労働を行う際に必須の手続きです。
この協定なしに、労働者に残業を行わせることは労働基準法違反となり、罰則の対象となります。
時間外労働・休日労働を実施するには36協定の締結が必要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 36協定とは | 労働基準法第36条に基づく、時間外労働・休日労働に関する労使協定。 正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。 |
| 締結の目的 | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や、法定休日の労働を適法に行うための手続き。 |
| 締結当事者 | 使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)との間で書面による協定を締結。 労働者の過半数代表者は、民主的な方法で選出される必要があります。 |
| 届出先 | 所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 届出をしないと、協定は効力を持ちません。 |
| 有効期間 | 一般的に1年間で設定することが多いです。 有効期間が満了する前に、新たに協定を締結・届出する必要があります。 |
| 違反した場合 | 36協定なしで時間外労働をさせた場合、労働基準法第32条違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)。 |
36協定の記載事項
36協定を締結する際には、法律で定められた事項を記載する必要があります。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 時間外労働を行う必要がある具体的事由 | なぜ残業が必要なのか、具体的な理由を記載。 例:「受注の集中」「納期対応」「月末・月初の業務集中」など |
| 対象労働者の範囲 | 時間外労働の対象となる労働者を明確にする。 例:「全従業員」「営業部門の従業員」「製造部門の従業員」など |
| 対象期間 | 協定の有効期間。1年間が一般的。 例:「2025年4月1日〜2026年3月31日」 |
| 1日の延長時間 | 1日あたり何時間まで残業が可能か。 法定労働時間(8時間)を超える時間を記載。 |
| 1ヶ月の延長時間 | 1ヶ月あたり何時間まで残業の実施が可能か。 原則として45時間以内(1年単位の変形労働時間制では42時間以内)。 |
| 1年の延長時間 | 1年あたり何時間まで残業の実施が可能か。 原則として360時間以内(1年単位の変形労働時間制では320時間以内)。 |
| 休日労働の日数・時間 | 休日労働を実施することができる日数と時間を記載。 |
36協定なしで残業させた場合の罰則
36協定を締結・届出せずに時間外労働や休日労働を実施することは、労働基準法違反となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 違反内容 | 36協定を締結・届出せずに、法定労働時間を超えて労働が発生すること。 または、法定休日に労働が発生すること。 |
| 該当する法律違反 | 労働基準法第32条違反(労働時間) 労働基準法第35条違反(休日) |
| 罰則 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条) ※使用者(会社および代表者)が処罰の対象となります。 |
| 労働基準監督署の対応 | ①是正勧告 ②指導・監督 ③悪質な場合は書類送検 |
| 実務上の影響 | ①企業イメージの低下 ②採用活動への悪影響 ③取引先からの信用失墜 ④労働者からの未払い残業代請求 |
残業時間の上限規制(2019年働き方改革関連法)
2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行された働き方改革関連法により、時間外労働には罰則付きの上限が設けられました。
36協定を締結していても、この上限を超えて残業を行うことはできません。
原則的な上限(月45時間、年360時間)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月の上限 | 月45時間まで ※1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間まで |
| 年の上限 | 年360時間まで ※1年単位の変形労働時間制の場合は年320時間まで |
| 適用時期 | 大企業:2019年4月1日から 中小企業:2020年4月1日から |
| 違反した場合 | 原則的な上限を超える36協定は無効。 ただし、特別条項付き36協定を締結すれば、一定の条件下で上限を超えることが可能(次項参照)。 |
特別条項付き36協定の上限
臨時的に特別の事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結することで、原則的な上限を超えて残業の実施が可能になります。
ただし、この場合でも守るべき上限があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用条件 | 臨時的に特別の事情がある場合に限り、年6回(6ヶ月)まで上限を超えることが可能。 「臨時的に特別の事情」とは:予算・決算業務、ボーナス商戦、納期のひっ迫、大規模クレームへの対応など。 |
| 年6回(6ヶ月)まで | 1年のうち、6ヶ月までは月45時間を超える残業が可能。 残りの6ヶ月は月45時間以内に抑える必要があります。 |
| 年間の上限 | 年720時間以内(休日労働は含まない) |
| 複数月平均の上限 | 休日労働を含めて、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均の全てで80時間以内。 いわゆる「過労死ライン」と言われる基準です。 |
| 単月の上限 | 休日労働を含めて、月100時間未満。 99時間59分までは適法ですが、100時間以上は違法です。 |
| 注意点 | 上記の上限は全てを同時に満たす必要があります。 1つでも超えると労働基準法違反となります。 |
上限規制違反の罰則
上限規制に違反した場合、罰則が科されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 罰則 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条) ※使用者(会社および代表者)が処罰の対象となります。 |
| 厚生労働省の対応 | ①指導・是正勧告 ②企業名の公表(悪質な場合) ③書類送検(重大・悪質な場合) |
| 企業が取るべき対策 | ①勤怠管理システムの導入 ②残業時間の月次モニタリング ③上限に近づいた従業員への警告 ④業務の見直しと効率化 ⑤人員の増強 |
| 違反を防ぐポイント | 特に「月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」の2つの基準に注意。 休日労働を含めた総労働時間を正確に把握することが重要です。 |
適用が猶予される業種
一部の業種については、上限規制の適用が猶予または除外されています。
| 業種 | 適用状況 |
|---|---|
| 建設業 | 2024年3月31日まで適用猶予。 2024年4月1日から上限規制が適用されました。 ただし、災害時の復旧・復興事業は引き続き除外。 |
| 自動車運転業務 | 2024年3月31日まで適用猶予。 2024年4月1日から上限規制が適用されました。 ただし、特別の上限(年960時間など)が設定されています。 |
| 医師 | 2024年3月31日まで適用猶予。 2024年4月1日から上限規制が適用されました。 ただし、医師特有の上限(年1,860時間など)が設定されています。 |
| 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業 | 2024年3月31日まで適用猶予。 2024年4月1日から上限規制が適用されました。 |
| 新技術・新商品等の研究開発業務 | 上限規制の適用除外。 ただし、健康確保措置(医師の面接指導など)の実施が必要。 |
【実務担当者向け】残業代計算と労働時間管理の注意点
企業の労務担当者や人事担当者にとって、残業代の正確な計算と適切な労働時間管理は重要な業務です。
労働基準法を遵守し、労働者に適切な残業代を支払うことは、企業の法的義務であるだけでなく、労働者の信頼を得て、良好な労使関係を築くためにも不可欠です。ここでは、実務担当者が特に注意すべきポイントについて解説します。
給与計算における残業代の取り扱い
給与計算において、残業代は毎月変動する項目であり、正確な計算が求められます。
給与計算の基本的な流れとしては、まず勤怠データ(出勤簿、タイムカード、勤怠管理システムのデータ等)から各従業員の労働時間を集計します。次に、所定労働時間を超える部分、法定労働時間を超える部分、深夜時間帯の労働、休日労働などを区分します。そして、それぞれの時間に対して適切な割増率を適用し、残業代を計算します。
計算した残業代は、基本給や諸手当と合算して総支給額を算出し、そこから社会保険料、雇用保険料、所得税などを控除して、最終的な手取り額を計算します。給与明細には、残業代の内訳(時間外労働、深夜労働、休日労働など)を明記することが望ましいです。
給与計算ソフトを使用している場合、勤怠管理システムとデータ連携することで、労働時間の集計から残業代の計算まで自動化でき、計算ミスを防ぎ、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①勤怠データの収集 | タイムカード、勤怠管理システムから労働時間のデータを収集します。 出勤日数、労働時間、残業時間、深夜労働時間、休日労働時間などを確認します。 |
| ②労働時間の区分 | 各従業員の労働時間を以下のように区分します: ①所定労働時間内 ②所定外・法定内労働時間 ③時間外労働時間(法定外) ④深夜労働時間 ⑤休日労働時間 |
| ③基礎時給の確認 | 各従業員の基本給、諸手当から基礎時給を算出します。 基礎賃金に含まれる手当、除外できる手当を正確に区別することが重要です。 |
| ④残業代の計算 | 区分した労働時間に対して、適切な割増率を適用して残業代を計算します: ①時間外労働:基礎時給×1.25×時間 ②深夜労働:基礎時給×1.25×時間(時間外と重なる場合は×1.5) ③休日労働:基礎時給×1.35×時間 ④月60時間超:基礎時給×1.5×時間 |
| ⑤総支給額の算出 | 基本給+諸手当+残業代+その他手当=総支給額 |
| ⑥控除額の計算 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などを控除します。 これらの保険料は、残業代を含む総支給額をもとに計算されます。 |
| ⑦手取り額の算出 | 総支給額−控除額=手取り額(差引支給額) |
| ⑧給与明細の作成 | 給与明細には、残業代の内訳を明記することが望ましいです: ・時間外手当:○○円(○○時間) ・深夜手当:○○円(○○時間) ・休日手当:○○円(○○時間) |
| 実務上の注意点 | ①計算ミスを防ぐため、給与計算ソフトの活用を推奨 ②複数人でダブルチェックを実施 ③給与明細は法定保存期間(3年間)保管 ④不明点があれば社労士に相談 |
残業時間の上限規制への対応
2019年4月から施行された働き方改革関連法により、時間外労働には罰則付きの上限規制が設けられました。
企業の労務担当者は、従業員の残業時間を常に監視し、上限規制に違反しないよう管理する必要があります。原則として、時間外労働は月45時間、年360時間以内に抑える必要があり、特別条項付き36協定を締結している場合でも、年720時間、月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)という上限を守らなければなりません。
実務上の対応としては、まず勤怠管理システムで残業時間をリアルタイムに把握します。月の途中でも、各従業員の残業時間を確認し、上限に近づいている従業員がいれば、早めに警告を出します。特に、月100時間に近づいている場合は、緊急対応が必要です。
また、複数月平均80時間以内という基準もあるため、過去数ヶ月の残業時間も併せて管理する必要があります。たとえば、ある月に80時間残業した従業員は、翌月以降の残業を抑える必要があります。
上限規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、企業名が公表されるリスクもあり、企業イメージに大きな影響を与えます。したがって、確実に上限規制を遵守することが重要です。
| 対応項目 | 具体的な対応方法 |
|---|---|
| リアルタイム監視 | 勤怠管理システムで、各従業員の残業時間をリアルタイムで把握します。 月の途中でも残業時間を確認し、上限に近づいている従業員を早期に発見します。 |
| アラート機能の活用 | 残業時間が一定時間(例:月40時間)を超えた時点で、自動的にアラートを出す機能を設定します。 管理者と本人の両方に通知することで、早期の対応が可能になります。 |
| 月100時間未満の厳守 | 休日労働を含めて月100時間に近づいている従業員には、緊急対応が必要です。 業務の分担見直し、他の従業員への振り分け、外部委託の検討などを行います。 |
| 複数月平均80時間の管理 | 過去2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均残業時間を常に計算します。 どの期間の平均も80時間以内に抑える必要があるため、Excelや勤怠システムで自動計算します。 |
| 年間残業時間の管理 | 各従業員の年間累計残業時間を管理し、720時間を超えないようにします。 年度途中でも進捗を確認し、年度末に上限を超えそうな従業員には早めに対応します。 |
| 36協定の遵守確認 | 36協定で定めた上限を超えていないか、毎月確認します。 特別条項を適用する月が年6ヶ月を超えないよう管理します。 |
| 業務の見直し | 恒常的に残業が多い部署や従業員については、業務の見直しが必要です: ①業務の効率化 ②不要な業務の削減 ③業務の平準化 ④人員の増強 ⑤外部委託の活用 |
| 管理職の教育 | 管理職に対して、上限規制の内容と重要性を教育します。 部下の残業時間を適切に管理し、上限を超えないよう指導する責任があることを認識させます。 |
| 違反時のリスク | ①罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ②企業名の公表:悪質な場合、厚生労働省が企業名を公表 ③企業イメージの低下:採用や取引に悪影響 ④労働者の健康被害:過労死・過労自殺のリスク |
最低賃金と残業代の計算方法
残業代を計算する際、最低賃金法との関係にも注意が必要です。
最低賃金法では、使用者は労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定めています。この最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められており、毎年10月頃に改定されます。特定最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金よりも高い金額が設定されている場合があります。
最低賃金の確認方法は、時給制の場合は時給と最低賃金を直接比較します。月給制の場合は、月給を月平均所定労働時間で割った基礎時給が、最低賃金以上である必要があります。
重要なのは、残業代込みの総支給額で最低賃金を判断するのではなく、基礎時給(残業代を除いた通常の時給)が最低賃金以上である必要があるという点です。たとえば、基礎時給が1,100円で、残業代を含めた時給換算が1,300円だったとしても、地域別最低賃金が1,226円であれば、最低賃金法違反となります。
最低賃金法に違反した場合、50万円以下の罰金が科されます。また、労働者から最低賃金との差額の支払いを請求される可能性もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低賃金の種類 | ①地域別最低賃金:都道府県ごとに設定(毎年10月頃改定) ②特定最低賃金:特定の産業について、地域別より高い金額が設定される場合あり |
| 最低賃金の確認方法(時給制) | 時給≧地域別最低賃金 例:時給1,300円、地域別最低賃金1,226円(東京都2025年10月3日改定)→OK |
| 最低賃金の確認方法(月給制) | 基礎時給≧地域別最低賃金 基礎時給=(基本給+諸手当−除外手当)÷月平均所定労働時間 例:月給21万円、月平均173時間 → 基礎時給1,214円 地域別最低賃金1,226円(東京都)→違反 |
| 残業代との関係 | 重要:残業代込みの総支給額ではなく、基礎時給が最低賃金以上である必要があります。 残業代を含めた時給換算で最低賃金を上回っていても、基礎時給が最低賃金未満であれば違反です。 |
| 計算例(違反ケース) | 条件:月給210,000円、月平均173時間、月40時間残業 基礎時給:210,000円÷173時間≒1,214円 残業代:1,214円×1.25×40時間≒60,700円 総支給額:210,000円+60,700円=270,700円 総支給額の時給換算:270,700円÷(173時間+40時間)≒1,271円 地域別最低賃金が1,226円(東京都2025年)の場合: 基礎時給1,214円<1,226円 → 最低賃金法違反 ※総支給額ベースでは1,271円だが、基礎時給が重要 |
| 除外できる手当 | 最低賃金の計算から除外できる手当: ①臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ③時間外・休日・深夜の割増賃金 ④精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
| 罰則 | 最低賃金法違反:50万円以下の罰金(最低賃金法第40条) |
| 実務上の対応 | ①毎年10月の最低賃金改定時に、全従業員の基礎時給を確認 ②最低賃金未満の従業員がいれば、速やかに賃金を引き上げ ③最低賃金ギリギリの設定は避け、余裕を持った賃金設定を推奨 ④2025年10月3日の改定により、東京都では1,226円以上が必須 |
残業代請求権の時効期間は3年
残業代を含む賃金の請求権には、時効があります。
2020年4月1日施行の改正労働基準法により、賃金請求権の消滅時効が2年から3年に延長、労働者は過去3年分の未払い残業代を請求できるようになりました。
この制度は、将来的には5年に延長される予定ですが、当面は3年とされています。
時効の起算日は、各月の賃金支払日の翌日です。たとえば、2023年4月分の給与が2023年5月25日に支払われた場合、その残業代の請求権は2026年5月25日まで存続します。つまり、毎月の給与ごとに、個別に時効が進行します。
企業にとって、過去3年分の未払い残業代を請求されるリスクがあるということは、非常に重要です。仮に毎月10万円の残業代未払いがあった場合、3年分で360万円にもなります。さらに、遅延損害金も加算されるため、金額はさらに膨らみます。
したがって、企業は日頃から適切に残業代を計算し、支払うことが重要です。もし過去に未払いがあることが発覚した場合は、速やかに労働者と協議し、適切に支払うことをお勧めします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時効期間 | 3年間(2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金) ※将来的には5年間となる予定ですが、当面は3年間 |
| 改正前の時効期間 | 2020年3月31日以前に支払期日が到来した賃金:2年間 |
| 起算日 | 各月の賃金支払日の翌日から起算します。 例:2023年4月分給与が2023年5月25日支払 → 時効は2026年5月25日まで |
| 毎月個別に時効進行 | 賃金請求権は毎月ごとに個別に時効が進行します。 3年前の分は時効消滅しますが、2年前、1年前の分は請求可能です。 |
| 企業のリスク | 未払い残業代が毎月10万円あった場合: 3年分:10万円×36ヶ月=360万円 さらに遅延損害金も加算されるため、金額はより大きくなります。 |
| 遅延損害金 | 未払い残業代には遅延損害金が加算されます: 在職中:年3%(商事法定利率) 退職後:年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律) |
| 時効の中断 | 労働者が請求(催告)した場合、時効が一時的に中断します。 その後6ヶ月以内に裁判上の請求等を行えば、時効は成立しません。 |
| 企業の対応 | ①日頃から適切に残業代を計算・支払う ②過去の未払いが発覚したら、速やかに労働者と協議 ③時効成立前に適切に支払うことで、リスクを最小化 ④不明点は社労士や弁護士に相談 |
| 労働者の対応 | 未払い残業代がある場合は、時効成立前に請求することが重要です。 証拠(タイムカード、メール、業務記録等)を保管し、必要に応じて専門家に相談してください。 |
当事務所のサポート内容
当社会保険労務士事務所では、企業様・労働者様の残業代に関する様々なご相談に対応しております。
残業代の計算や労働時間管理について悩んでいる場合、社会保険労務士(社労士)への相談が非常に有効です。
社労士は、労働・社会保険に関する法律の専門家であり、企業の労務管理から労働者の権利保護まで、幅広い知識と経験を持っています。残業代の問題は法律的に複雑なケースも多く、専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見出すことができます。
ここでは、なぜ社労士への相談がおすすめなのか、社労士ができること、相談のタイミングや費用について、詳しく解説します。
残業代計算が複雑で困っている方へ
残業代の計算は、一見シンプルに見えますが、実際には非常に複雑です。
基礎時給の算出方法、どの手当を基礎賃金に含めるべきか、変形労働時間制やフレックスタイム制での残業代計算、固定残業代制度の有効性判断、深夜・休日労働との重複時の割増率など、専門的な知識が必要な場面が数多くあります。
企業の労務担当者であれば、毎月の給与計算で正確な残業代を計算する必要がありますが、法改正や制度変更に追いつけず、計算ミスが発生するリスクがあります。また、労働者個人が自分の残業代を計算しようとしても、給与体系の複雑さや法律知識の不足から、正確な計算ができないことがあります。
こうした複雑な残業代計算の問題に対して、社労士は専門的な知識とノウハウを持っています。給与明細や勤怠記録を見ながら、正確に残業代を計算し、適切なアドバイスを提供できます。
特に、以下のようなケースでは、自己判断せず社労士に相談することを強くお勧めします。
| ケース | なぜ社労士への相談が必要か |
|---|---|
| 固定残業代制度を導入している | 固定残業代が法的に有効かを判断するには、専門知識が必要です。 無効と判断されれば、全額の残業代支払い義務が発生するため、事前に社労士のチェックを受けることが重要です。 |
| 変形労働時間制を採用している | 1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制では、残業時間の判定が複雑です。 法定要件を満たしているか、残業代計算が正確かを確認する必要があります。 |
| フレックスタイム制を導入している | 清算期間、総労働時間の設定、残業代の計算方法など、制度設計と運用が適切かを専門家に確認すべきです。 |
| 管理職に残業代を支払っていない | 「管理監督者」に該当するかの判断は非常に難しく、名ばかり管理職のリスクがあります。 実態を社労士に確認してもらい、適切に対応する必要があります。 |
| 複数の手当がある給与体系 | どの手当を基礎賃金に含めるべきか、専門的な判断が必要です。 計算ミスが発生しやすいため、社労士のチェックが有効です。 |
| 歩合給・出来高払いの従業員がいる | 歩合給の場合の基礎時給の算出方法は特殊で、保障給との関係も考慮する必要があります。 専門家のアドバイスが不可欠です。 |
| 未払い残業代を請求したい | 労働者側として未払い残業代を請求する場合、正確な計算と証拠の整理が必要です。 社労士が計算をサポートし、労働局のあっせん手続きで代理人を務めることもできます。 |
| 労働基準監督署から是正勧告を受けた | 是正勧告への対応は迅速かつ適切に行う必要があります。 社労士が是正報告書の作成や再発防止策の立案をサポートします。 |
社労士が解決できる5つの問題
社労士は、残業代に関する様々な問題を解決するための専門的なサポートを提供します。
社労士が特に力を発揮するのは、予防的な労務管理と、問題が発生した際の初期対応です。法的紛争に発展する前の段階で、適切なアドバイスを受け、制度を整備することで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
ここでは、社労士が解決できる主な5つの問題について解説します。
①残業代の正確な計算と検証
社労士の最も基本的な業務の一つが、残業代の正確な計算です。
企業の給与体系、労働時間制度、勤怠記録を分析し、現在の残業代計算が法令に適合しているかを検証します。計算ミスや法律解釈の誤りがあれば指摘し、正しい計算方法を提案します。
また、労働者からの依頼であれば、給与明細やタイムカードをもとに、本来支払われるべき残業代を計算し、未払いの有無を確認します。複雑なケースでも、専門的な知識に基づいて正確に計算できるのが社労士の強みです。
②就業規則・賃金規程の作成と見直し
残業代トラブルの多くは、就業規則や賃金規程が不明確であることから生じます。
社労士は、労働基準法に準拠した就業規則や賃金規程を作成し、労働時間制度、残業代の計算方法、固定残業代制度などを明確に規定します。既存の規程がある場合も、最新の法令に適合しているか見直し、必要に応じて改定を提案します。
特に、固定残業代制度を導入する場合は、法的要件を満たす慎重な規程作成が必要であり、社労士のサポートが不可欠です。
③勤怠管理システムの導入・運用支援
適切な労働時間管理は、正確な残業代計算の前提条件です。
社労士は、企業の規模や業態に合った勤怠管理システムの選定をサポートし、導入後の運用方法についてもアドバイスします。タイムカード、ICカード、クラウド型勤怠システムなど、様々な選択肢の中から最適なものを提案し、労働時間の客観的な記録を実現します。
また、勤怠管理システムと給与計算ソフトの連携により、残業代の自動計算を実現し、計算ミスを防止します。
④給与計算のアウトソーシング
複雑な残業代計算を含む給与計算業務全体を、社労士にアウトソーシングすることができます。
社労士は、毎月の勤怠データをもとに、残業代、社会保険料、所得税などを正確に計算し、給与明細を作成します。法改正にも自動的に対応し、常に最新の法令に基づいた給与計算が保証されます。
給与計算を外部委託することで、企業の労務担当者は本来の業務に専念でき、業務効率が大幅に向上します。また、専門家による正確な計算により、未払いや計算ミスのリスクを最小化できます。
⑤労務トラブルの予防と初期対応
社労士は、残業代に関する労務トラブルを未然に防ぐための予防的なサポートを提供します。
定期的な労務監査により、潜在的なリスクを発見し、改善策を提案します。上限規制への対応、管理監督者の適切な運用、固定残業代制度の見直しなど、トラブルの芽を早期に摘み取ります。
万が一、従業員から残業代の請求があった場合や、労働基準監督署から調査の通知があった場合も、社労士が初期対応をサポートします。証拠資料の整理、説明資料の作成、監督署との折衝など、適切な対応により、問題の早期解決を図ります。
| 問題 | 社労士のサポート内容 |
|---|---|
| ①残業代の正確な計算と検証 | 企業向け:現在の残業代計算が法令に適合しているか検証し、計算ミスや法律解釈の誤りを指摘 労働者向け:給与明細・タイムカードから本来支払われるべき残業代を計算し、未払いの有無を確認 メリット:専門的な知識に基づく正確な計算、複雑なケースにも対応可能 |
| ②就業規則・賃金規程の作成と見直し | サポート内容: ・労働基準法に準拠した就業規則・賃金規程の作成 ・労働時間制度、残業代計算方法の明確な規定 ・固定残業代制度の法的要件を満たす規程作成 ・既存規程の最新法令への適合性チェック 効果:トラブルの予防、労使双方の権利義務の明確化 |
| ③勤怠管理システムの導入・運用支援 | サポート内容: ・企業の規模・業態に合った勤怠システムの選定 ・導入時の設定サポート ・運用方法のアドバイス ・給与計算ソフトとの連携支援 効果:労働時間の客観的記録、残業代の自動計算、計算ミスの防止 |
| ④給与計算のアウトソーシング | サポート内容: ・毎月の給与計算業務の代行 ・残業代、社会保険料、所得税の正確な計算 ・給与明細の作成 ・法改正への自動対応 効果:労務担当者の負担軽減、計算の正確性保証、法令遵守 |
| ⑤労務トラブルの予防と初期対応 | 予防的サポート: ・定期的な労務監査によるリスク発見 ・上限規制への対応サポート ・管理監督者の適切な運用確認 初期対応サポート: ・従業員からの残業代請求への対応 ・労働基準監督署の調査対応 ・証拠資料の整理、説明資料の作成 効果:トラブルの未然防止、問題の早期解決 |
企業の労務リスクを未然に防ぐ
企業にとって、残業代の未払いや労働時間管理の不備は、重大な法的リスクとなります。
労働基準法違反による罰則、未払い残業代の遡及支払い、遅延損害金の発生、企業名の公表、従業員との信頼関係の破壊、採用活動への悪影響など、様々な悪影響が考えられます。特に、過去3年分の未払い残業代を一度に請求されると、企業の財務に深刻な打撃を与える可能性があります。
こうしたリスクを未然に防ぐために、社労士による定期的な労務診断が非常に有効です。
社労士による労務診断の内容
社労士による労務診断では、企業の労務管理全般を専門家の視点でチェックします。
就業規則や賃金規程が最新の法令に適合しているか、労働時間の記録が適切に行われているか、残業代の計算方法が正確か、36協定が適切に締結・届出されているか、上限規制が遵守されているか、管理監督者の運用が適切かなど、多角的に検証します。
診断の結果、問題点が発見されれば、具体的な改善策を提案し、実施をサポートします。法改正があった際にも、タイムリーに対応方法をアドバイスし、企業が常に法令を遵守できるようサポートします。
予防的労務管理のメリット
予防的な労務管理には、多くのメリットがあります。
まず、労務トラブルの発生を未然に防ぐことができます。問題が表面化する前に対処することで、従業員との関係悪化や法的紛争を回避できます。また、万が一トラブルが発生しても、日頃から適切な労務管理を行っていれば、早期に解決できる可能性が高まります。
さらに、適切な労務管理は、従業員の満足度向上にもつながります。残業代が適切に支払われ、労働時間が適正に管理されている職場では、従業員の信頼とモチベーションが高まります。これは、離職率の低下、生産性の向上、企業イメージの改善にもつながります。
談するタイミングと費用
社労士への相談を検討する際、「いつ相談すべきか」「どのくらい費用がかかるのか」が気になるところです。
結論から言えば、問題が小さいうちに、できるだけ早く相談することが重要です。問題が大きくなってからでは、解決に時間とコストがかかります。予防的な相談や、日常的な労務管理のサポートを受けることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
相談をおすすめするタイミング
社労士に相談すべきタイミングは、新しく会社を設立した時、従業員を初めて雇用する時、就業規則を作成または変更する時、新しい労働時間制度(変形労働時間制、フレックスタイム制、固定残業代制度など)を導入する時、労働基準監督署から調査の通知が来た時、従業員から残業代の請求があった時などが、相談におすすめのタイミングです。
費用の目安
社労士への費用は、依頼内容によって大きく異なりますが、一般的な相場をご紹介します。
スポット相談の場合、相談料は1時間あたり1万円〜2万円程度が相場です。初回相談を無料としている社労士も多いので、まずは無料相談を利用してみることをお勧めします。
就業規則の作成は、10万円〜30万円程度が相場です。企業の規模や内容の複雑さによって変動します。既存の就業規則の見直しは、5万円〜15万円程度です。
給与計算のアウトソーシングは、従業員1人あたり月額1,000円〜3,000円程度が相場です。従業員数が多いほど、1人あたりの単価は下がる傾向にあります。
顧問契約の場合、月額3万円〜5万円程度が一般的です。従業員数が多い企業や、相談内容が複雑な場合は、それ以上になることもあります。顧問契約により、日常的な相談が無料または定額で利用でき、緊急時にも迅速に対応してもらえます。
労働局のあっせん代理(特定社労士)は、10万円〜20万円程度が相場です。
費用は社労士によって異なるため、複数の社労士に見積もりを取って比較することをお勧めします。ただし、費用だけでなく、専門性、実績、相性なども考慮して選ぶことが重要です。
| サービス内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料〜1万円/1時間 多くの社労士が初回無料相談を実施しています。まずは無料相談を活用しましょう。 |
| スポット相談 | 1万円〜2万円/1時間 継続的な契約ではなく、単発の相談の場合。 |
| 残業代の計算 | 5万円〜10万円 過去の残業代を詳細に計算する場合。期間や複雑さにより変動。 |
| 就業規則の作成 | 10万円〜30万円 企業の規模、従業員数、内容の複雑さにより変動。 労働基準監督署への届出代行を含む。 |
| 就業規則の見直し | 5万円〜15万円 既存の就業規則を最新の法令に適合させる場合。 |
| 賃金規程の作成 | 5万円〜15万円 残業代の計算方法、固定残業代制度などを規定。 |
| 給与計算代行 | 1人あたり1,000円〜3,000円/月 従業員数により変動。人数が多いほど単価は下がる傾向。 例:従業員10人の場合、月額1万円〜3万円程度 |
| 勤怠管理システム導入支援 | 10万円〜30万円 システムの選定、設定、運用サポート。 ※システム本体の費用は別途 |
| 労務監査 | 10万円〜30万円 企業の労務管理全般を診断し、問題点と改善策を報告。 |
| 労働局あっせん代理 (特定社労士) |
10万円〜20万円 労働局のあっせん手続きでの代理業務。 |
| 顧問契約 | 月額3万円〜5万円 従業員数、相談頻度により変動。 顧問契約のメリット: ・日常的な相談が無料または定額 ・法改正への迅速な対応 ・緊急時の優先対応 ・労務リスクの継続的な管理 |
| 労働基準監督署の調査対応 | 10万円〜30万円 調査への立ち会い、資料作成、是正報告書の作成など。 |
初回無料相談を活用しよう
社労士への相談を躊躇している方も多いかもしれませんが、多くの社労士が初回無料相談を実施しています。
無料相談を活用することで、費用をかけずに専門家の意見を聞くことができ、問題の見通しや解決方法を知ることができます。また、社労士との相性を確認する良い機会にもなります。
無料相談でできること
初回無料相談では、通常30分〜1時間程度の時間で、以下のようなことができます。
残業代に関する悩みや疑問について相談し、専門家の見解を聞くことができます。給与明細やタイムカードを持参すれば、簡易的な残業代の計算や、未払いの有無を確認してもらえる場合もあります。
就業規則や労働時間制度について、法的に問題がないかを確認できます。固定残業代制度が有効かどうか、管理監督者の運用が適切かどうかなど、専門的な判断を得られます。
問題を解決するための具体的な方法や、今後の進め方についてアドバイスを受けられます。社労士に正式に依頼する場合の費用見積もりも提示してもらえます。
無料相談を受ける際の準備
無料相談を効果的に活用するために、事前に準備をしておくことをお勧めします。
まず、相談したい内容を整理し、質問事項をリストアップしておきます。時間が限られているため、優先順位をつけて、最も重要なことから相談しましょう。
関連する資料を持参します。給与明細、雇用契約書、就業規則、タイムカード、勤怠記録など、相談内容に関連する資料があれば、より具体的なアドバイスを受けられます。
会社の基本情報(従業員数、業種、労働時間制度など)も整理しておくと、スムーズに相談できます。
無料相談後の流れ
無料相談を受けた後、正式に依頼するかどうかを検討します。
無料相談だけで解決できる場合もあれば、継続的なサポートが必要な場合もあります。社労士から提案された解決策や費用を検討し、納得できれば正式に契約します。
複数の社労士に無料相談を受けることも可能です。専門性、実績、費用、相性などを比較して、最適な社労士を選びましょう。
無料相談を受けたからといって、必ず契約する必要はありません。まずは気軽に相談してみることが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 無料相談の時間 | 通常30分〜1時間程度 社労士によって異なるため、事前に確認しましょう。 |
| 無料相談でできること | ①残業代に関する悩み・疑問の相談 ②簡易的な残業代の計算・未払い確認 ③就業規則や労働時間制度の法的チェック ④問題解決のための具体的なアドバイス ⑤正式依頼する場合の費用見積もり ⑥社労士との相性確認 |
| 事前準備 | 相談内容の整理: ・質問事項をリストアップ ・優先順位をつける 資料の準備: ・給与明細(直近3ヶ月分以上) ・雇用契約書・労働条件通知書 ・就業規則・賃金規程 ・タイムカード・勤怠記録 会社情報の整理: ・従業員数 ・業種 ・労働時間制度(固定時間制、変形労働時間制等) ・給与体系 |
| 相談方法 | ①対面相談:事務所に出向いて面談 ②オンライン相談:ZoomやTeams等で面談 ③電話相談:電話で相談 ※資料を見せながら相談できる対面またはオンラインがおすすめ |
| 予約方法 | ①社労士のウェブサイトから予約フォームで申込 ②電話で予約 ③メールで予約 ※事前予約が必要な場合が多いです |
| 相談後の流れ | ①無料相談だけで解決できた場合 → 終了 ②継続的なサポートが必要な場合 → 正式契約を検討 ③提案された解決策・費用を検討 ④納得できれば正式に契約 ⑤複数の社労士に相談して比較することも可能 |
| 無料相談のメリット | ①費用をかけずに専門家の意見を聞ける ②問題の見通しが立つ ③解決方法が分かる ④社労士との相性を確認できる ⑤正式依頼の判断材料になる |
| 注意点 | ①無料相談を受けたからといって、必ず契約する必要はない ②時間が限られているため、質問を絞り込んで効率的に相談 ③詳細な計算や書類作成は、正式契約後の業務となる場合が多い ④複数の社労士に相談して比較検討することを推奨 |
| まずは気軽に相談を | 残業代の問題は、一人で悩まず、まず専門家に相談することが解決への第一歩です。 初回無料相談を活用して、問題解決の糸口を見つけましょう。 |
当事務所の無料相談のご案内
当社会保険労務士事務所では、残業代に関するご相談を初回無料で承っております。
【無料相談の内容】
- 残業代計算の方法と適正性の確認
- 就業規則・賃金規程の簡易チェック
- 固定残業代制度の有効性判断
- 労務管理上の問題点の指摘
- 解決策のご提案と費用見積もり
【相談方法】
対面相談・オンライン相談(Zoom)・電話相談から選択可能
【お問い合わせ】
電話:06-6214-6400 (全国対応、受付時間:平日9:00〜18:00)
メールでのお問い合わせはこちら (24時間)
まずはお気軽にお問い合わせください。企業様・労働者様どちらのご相談も歓迎いたします。
この記事の執筆者・著者情報 HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺 俊一

HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所) 代表 特定社会保険労務士 渡辺 俊一 ・保有資格 |
新ロゴ 旧ロゴ |
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人




