新着情報
【実務で困らない】役員手当とは?種類・税務・給与との違いをプロが徹底解説
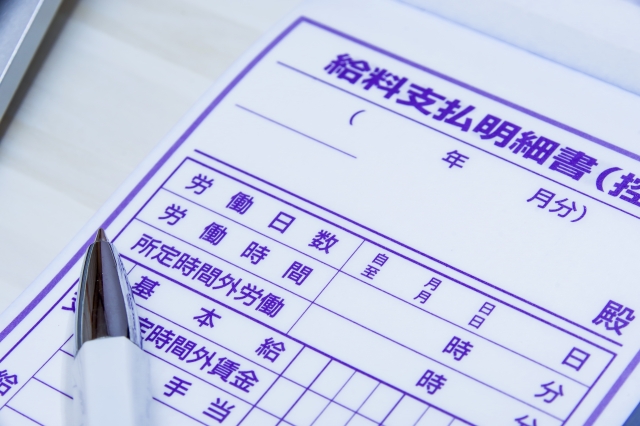
「役員手当って何?」「役員報酬とは違うの?」「税務や社会保険の処理がややこしくて困っている…」
このような疑問は、大阪・東京・名古屋・福岡といった都市圏の中小企業、特に従業員数100名以上の企業でよく聞かれます。役職者が増えると、給与計算・就業規則・税務処理の整合性が重要になりますが、“役員手当”という言葉の定義が曖昧なまま運用されていることも少なくありません。
この記事では、「役員手当とは何か?」「役員報酬との違い」「処理方法や注意点」について、顧問社労士の視点から徹底解説します。助成金や手続き対応、DX・アウトソースによるミス防止にも触れながら、実務に直結する知識をお届けします。
役員手当とは?役員報酬との違い
「役員手当」は正式な法律用語ではない
まず大前提として、“役員手当”という言葉は法律上の明確な定義があるわけではなく、実務上・会計処理上の用語として使われています。一般的には次のような意味で使われます:
- 役員報酬の一部としての「手当」:住宅手当・役職手当・職務手当などの名目で支給
- 給与と区別された役員への支給額:従業員に支給される給与・賞与とは異なる体系
役員報酬との位置づけ関係
| 項目 | 役員報酬 | 役員手当(通称) |
|---|---|---|
| 意味 | 役員に支払われるすべての報酬 | 報酬の中で特定名目の支給分 |
| 税務処理 | 原則として定期同額が必要 | 変動すると損金算入不可 |
| 社会保険 | 報酬総額で保険料を算定 | すべて保険料対象になる |
よくある勘違い
- 「役員にも残業代や手当がつく」→× 基本的に役員には労働基準法が適用されず、時間外手当の支給義務はありません。
- 「社員手当と同じ感覚で支給してよい」→× 変動性があると法人税で損金扱いできないリスクがあります。
ケーススタディ:東京のIT企業の失敗例
役員に“営業手当”“精勤手当”などを都度支給していた企業が、税務調査で「定期同額報酬の原則違反」と判断され、過去3年分の法人税が否認されました。
制度の裏話:助成金の対象にはならない
厚労省系の助成金(例:キャリアアップ助成金、業務改善助成金)は、あくまで「労働者(従業員)」に対する支援です。役員手当の増額は助成対象外です。
企業がとるべき8つの実務対応ポイント
-
1. 役員報酬の内訳は「明確化」する
方法:報酬明細に「基本報酬+役職手当」など記載するが、トータルが定期同額であることを確認
効果:税務調査でも整合が取れる -
2. 就業規則で役員の手当制度を除外明記
方法:従業員用の手当(通勤・残業等)は、役員対象外と記載
効果:制度の誤適用を防ぐ -
3. 年1回の定期決定ルールを守る
方法:年度開始後3ヶ月以内に報酬額を決定し、期中変更を避ける
効果:法人税の損金否認を防ぐ -
4. 議事録を残し、株主総会や取締役会で決議
方法:「役員手当含む報酬月額●万円」と明示
効果:会計監査や税務署への説明がスムーズ -
5. 雇用保険の対象外であることを確認
方法:使用人兼務役員を除き、雇用保険加入不可
効果:誤加入や保険料返納リスクを防止 -
6. 給与計算システムで役員区分を設定
方法:「役員報酬」コードを設け、従業員とは別処理
効果:誤支給・ミスを防止 -
7. 税理士・社労士との連携を密に
方法:報酬設計時に必ず顧問へ事前相談
効果:法令適合性・税務リスクの回避に直結 -
8. DX・アウトソースで管理精度を高める
方法:役員報酬管理をクラウドや給与計算委託で効率化
効果:属人化リスクを排除
Q&A:役員手当に関するよくある質問
Q. 役員にも住宅手当や通勤手当を支給してよい?
A. 原則可能ですが、定期同額報酬に含めて「毎月一定額」である必要があります。不定期・変動支給はNG。
Q. 従業員から役員に昇格した人の手当はどうすべき?
A. 労働者から使用人兼務役員になる場合、給与と報酬を分け、どちらも適正に設計・管理する必要があります。
Q. 役員に賞与を出すことはできる?
A. 「事前確定届出給与」として届け出れば可能。ただし、届出なしで支給すると税務上の損金にならず、会社負担が増えます。
Q. 従業員手当と役員手当を同じ扱いで処理していい?
A. NGです。社内規程・給与計算・社会保険・税務処理で異なる扱いになります。混同すると処理ミスが発生しやすくなります。
まとめ:役員手当は“名目”でなく“仕組み”が命|法令と整合性ある運用を
役員手当という言葉に明確な法的定義はありませんが、その扱いには税務・社会保険・就業規則・助成金制度すべてに波及する影響があります。
大阪・東京・福岡・名古屋などの都市圏において、拡大を続ける中小企業では、役員報酬と従業員給与の線引きが求められています。顧問社労士や税理士と連携し、正しい制度設計と給与計算運用を行うことが、組織運営の安定と法令順守につながります。
“役員手当”という言葉に惑わされず、正しい制度設計と運用を。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人



