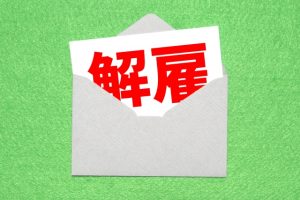新着情報
【2025年4月施行】育児介護休業法改正の概要
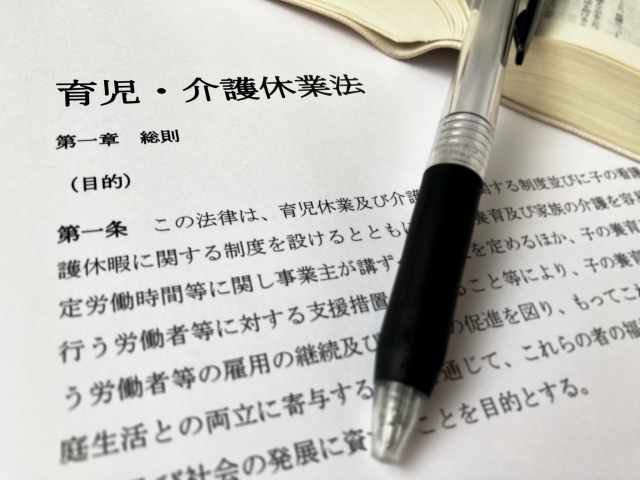
育児介護休業法の改正対応で不安を感じる総務担当者様へ
「2025年4月の育児介護休業法改正で、具体的にどんな対応が必要になるの?」「テレワーク導入が努力義務になるけれど、どこまで整備すれば良いのかわからない」「個別周知・意向確認が義務化されるが、具体的な手続きはどうすれば?」そんな不安を抱えていませんか?
100名規模の企業では、2025年4月施行の育児介護休業法改正により、新たな義務や努力義務への対応が求められます。特に、働き方の柔軟化、個別周知・意向確認の義務化、テレワーク導入の努力義務化など、制度整備と運用体制の構築が必要になります。適切な対応を怠ると、労働基準監督署の指導対象となるだけでなく、優秀な人材の流出や企業イメージの悪化を招くリスクもあります。
一方で、適切な改正対応により、従業員の満足度向上、人材確保・定着の実現、企業の競争力強化を図ることができます。特に人材不足が深刻な現在、育児・介護支援制度の充実は採用競争力の重要な要素となっています。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、100名規模企業の経営者・総務担当者が知るべき2025年育児介護休業法改正の内容と対応策を詳しく解説します。法改正を機会として活用し、魅力的な職場環境づくりを実現する実践的な情報をお届けします。
2025年育児介護休業法改正の全体像と100名規模企業への影響
2025年4月から施行される育児介護休業法の改正は、仕事と育児・介護を両立しやすい環境を整備することを目的としています。少子高齢化の進行を受け、働き方の柔軟性を高め、企業の支援体制を強化するための施策が盛り込まれています。
改正の3つの柱と企業への影響
今回の改正は、以下の3つの柱から構成されています:
| 改正の柱 | 主な内容 | 企業の義務・努力義務 | 100名企業への影響度 |
| 育児と仕事の両立支援 | 残業免除拡大・テレワーク推奨 | 努力義務(テレワーク) | 高 |
| 取得状況公表の強化 | 公表義務の対象拡大 | 公表義務(対象外) | 低 |
| 介護離職防止支援 | 情報提供・研修義務化 | 義務 | 中 |
100名規模の企業では、育児休業取得状況の公表義務は対象外(300人超が対象)ですが、その他の改正事項については対応が必要になります。
育児と仕事の両立支援強化の具体的内容
1. 残業免除の対象拡大
- 対象年齢:3歳未満 → 小学校就学前まで拡大
- 適用条件:労働者の請求により企業は残業させてはならない
- 例外:事業の正常な運営を妨げる場合の拒否は可能
- 手続き:1か月前までの書面申請
2. 子の看護休暇の拡充
- 取得理由の拡大:病気・けがの看護に加え、学校行事参加等も対象
- 対象年齢:小学校就学前まで(変更なし)
- 取得日数:子1人につき年5日、2人以上で年10日(変更なし)
- 取得単位:時間単位での取得も可能
3. テレワーク導入の努力義務化
- 対象:3歳未満の子を育てる労働者
- 位置づけ:企業の努力義務
- 条件:業務の性質上困難な場合は除外
- 代替措置:テレワークが困難な場合の代替支援策提供
4. 個別周知・意向確認の義務化
- 対象:妊娠・出産等を申し出た労働者
- 内容:両立支援制度の周知と利用意向の確認
- 時期:妊娠・出産の申出後、適切な時期
- 方法:面談・書面・FAX・電子メール等
介護離職防止支援の強化
介護を担う労働者への支援も大幅に強化されます:
- 制度周知の義務化:介護休業等の制度について定期的な情報提供
- 研修実施の義務化:管理職向けの介護両立支援研修
- 個別相談体制:介護に直面した労働者への相談対応
- テレワーク推奨:介護者向けのテレワーク導入努力義務
- 介護休暇の拡充:対象範囲の拡大と取得しやすさの向上
100名規模の企業では、高齢の親を持つ従業員が増加しており、介護離職防止は重要な経営課題となっています。
効果的な改正対応と実務上の成功事例
育児介護休業法改正への対応は、単なる法令遵守を超えて、従業員満足度向上と競争力強化の機会として活用できます。以下、実際の対応事例と効果的な取り組み方法をご紹介します。
包括的両立支援制度の構築事例
IT企業VV社(従業員112名)の先進的取り組み:
法改正を機に、育児・介護支援制度を包括的に見直し、「ライフステージ支援パッケージ」として体系化しました。顧問社労士と連携し、法的要件を満たしながら従業員のニーズに応える制度を構築しました。
構築した支援制度:
- 育児支援:在宅勤務制度・フレックス制度・短時間勤務制度
- 介護支援:介護休暇の有給化・介護相談窓口・介護セミナー
- 両立支援:復職支援プログラム・キャリア継続支援
- 職場環境:男性育休推進・上司向け研修・制度利用促進
結果、女性の離職率が半減し、男性の育休取得率も50%に向上しました。新卒採用でも「働きやすい会社」として高い評価を獲得し、応募者数が30%増加しています。
製造業WW社(従業員95名)の事例:
現場作業が中心のため、テレワーク導入が困難でしたが、現場に適した柔軟な働き方を検討し、独自の両立支援制度を構築しました。
導入した制度:
- シフト勤務の柔軟化(育児・介護対応)
- 短時間勤務制度の拡充
- 代替要員確保システム
- 育児・介護手当の新設
この取り組みにより、現場作業員の定着率が大幅に改善し、熟練技能の継承もスムーズに進むようになりました。
段階的な改正対応ロードマップ
第1段階:現状分析と制度設計(2024年12月まで)
- 現行制度と法改正要件の比較分析
- 従業員のニーズ・課題の把握
- 新制度の基本設計
- 必要な予算・リソースの算定
第2段階:制度構築と準備(2025年2月まで)
- 就業規則の改定
- 各種申請書類の整備
- システム・環境の整備(テレワーク等)
- 管理職向け研修プログラムの開発
第3段階:周知・教育と運用開始(2025年4月)
- 全従業員への制度説明会実施
- 管理職向け研修の実施
- 個別相談体制の構築
- 制度運用開始と初期フォロー
第4段階:運用定着と継続改善(2025年6月以降)
- 制度利用状況のモニタリング
- 従業員フィードバックの収集
- 制度の改善・調整
- 効果測定と評価
テレワーク導入の効果的なアプローチ
3歳未満の子を育てる労働者へのテレワーク導入(努力義務)については、以下のアプローチが効果的です:
導入可能業務の洗い出し
- 職種・業務内容別の在宅勤務適性評価
- 部分的テレワーク(週1-2日)の可能性検討
- 時差出勤・フレックスとの組み合わせ
- 短時間勤務制度との併用
代替措置の検討
- テレワークが困難な職種への配置転換
- 勤務時間の調整(早番・遅番)
- 育児支援手当の支給
- 託児所利用補助の提供
環境整備のポイント
- 情報セキュリティ対策の強化
- コミュニケーションツールの導入
- 労働時間管理システムの整備
- 在宅勤務手当・通信費補助
介護離職防止の実践的対策
100名規模の企業では、以下の対策が特に効果的です:
予防的アプローチ
- 40代以上の従業員向け介護セミナー開催
- 地域包括支援センターとの連携
- 介護保険制度の理解促進
- 早期相談の重要性啓発
制度面の整備
- 介護休暇の有給化(法定は無給)
- 介護休業の分割取得制度
- 介護のための短時間勤務制度
- 介護費用補助制度
職場環境の整備
- 介護に理解のある職場風土醸成
- 管理職の介護リテラシー向上
- チームでのカバー体制構築
- 業務の標準化・マニュアル化
助成金活用による制度整備コスト削減
育児介護支援制度の整備では、以下の助成金を活用できます:
| 助成金名 | 支給額目安 | 対象となる取り組み | 100名企業での活用効果 |
| 両立支援等助成金 | 年間100-300万円 | 育児・介護両立支援制度 | 制度整備費用の大幅削減 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 年間50-200万円 | テレワーク環境整備 | IT環境整備の支援 |
| 人材確保等支援助成金 | 年間100-200万円 | 雇用環境改善 | 人材定着促進 |
アウトソース先の社労士による助成金申請代行により、確実な受給と事務負担の軽減を同時に実現できます。
改正対応で頻出する実務上の疑問をQ&A形式で解決
Q1:テレワーク導入が困難な職種の従業員にはどのような代替措置を講じれば良い?
A: 業務の性質上テレワークが困難な場合は、他の両立支援措置を提供すれば努力義務を果たしたことになります。具体例として、勤務時間の調整(早番・遅番の選択)、短時間勤務制度の拡充、育児支援手当の支給、託児施設利用補助などがあります。経営者としては、従業員のニーズに応じた柔軟な制度設計により、テレワーク以外でも十分な両立支援が可能です。
Q2:個別周知・意向確認の義務化で、具体的にどのような手続きが必要?
A: 妊娠・出産・育児休業の申出があった労働者に対して、両立支援制度を個別に周知し、利用意向を確認する必要があります。面談、書面、電子メール等の方法で、育児休業制度、短時間勤務制度、テレワーク制度等について説明し、利用希望を聞き取ります。総務担当者は、申出のタイミングを逃さず、適切な時期に実施することが重要です。記録の保存も義務付けられているため、確実な記録管理が必要です。
Q3:100名規模の企業では育児休業取得状況の公表義務はないが、任意で公表するメリットは?
A: 任意での公表により企業イメージの向上と優秀な人材確保が期待できます。特に若年層の採用では、育児支援制度の充実度が重要な判断要素となっています。公表により透明性をアピールし、「働きやすい会社」としてのブランディング効果も期待できます。ただし、取得率が低い場合は逆効果になる可能性もあるため、制度改善と併せて検討することが重要です。
育児介護休業法改正を機会とした組織力強化
2025年4月の育児介護休業法改正は、単なる法令遵守の課題ではなく、組織の競争力強化と持続的成長を実現する絶好の機会です。適切な対応により、従業員の満足度向上、人材確保・定着の実現、企業イメージの向上を同時に達成できます。
100名規模の企業では、個人に寄り添ったきめ細かな支援と、組織全体での制度活用促進が可能です。法改正を機に、従業員のライフステージ全体を支援する包括的な制度を構築することで、変化の激しい時代に対応できる強靭な組織基盤を築くことができます。
法改正への対応でご不安を感じていらっしゃるなら、今すぐ専門家にご相談ください。全国対応のHR BrEdge社会保険労務士法人では、2007年創業・顧問先50社の豊富な実績をもとに、法改正対応から助成金活用まで包括的にサポートいたします。貴社の事業特性に応じた最適な制度設計により、法令遵守と競争力強化を同時に実現いたします。LINE・Slack・Chatworkでの迅速な相談対応も可能ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人