新着情報
就業規則の作成義務とは?
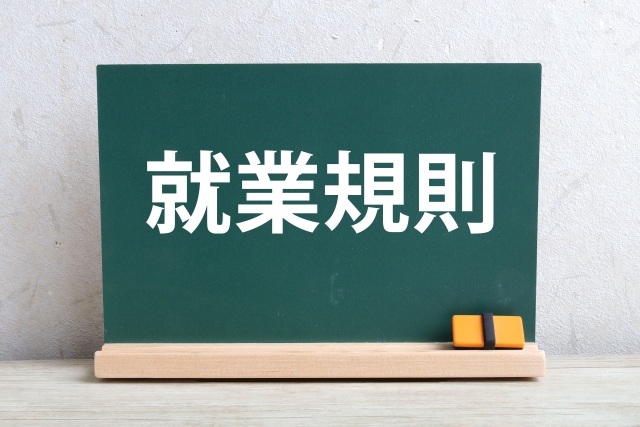
「また法改正?就業規則の見直しが追いつかない…」
「給与計算だけでも手いっぱいなのに、規則作成まで手が回らない」
100名を超える従業員を抱える企業の総務担当者や経営者の皆様、
このような悩みを抱えていませんか?
労働基準法に基づく就業規則の作成義務は、
企業規模に関わらず必須の対応事項です。
しかし、日々の業務に追われる中で、
適切な規則作成や更新作業は大きな負担となっているのが現実でしょう。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、
就業規則作成の法的義務から実践的な対策まで、
100名規模企業の実情に合わせて詳しく解説します。
規則作成に関する不安を解消し、
効率的な労務管理を実現するヒントをお届けいたします。
就業規則作成義務の基本知識と100名規模企業が陥りがちな落とし穴
労働基準法第89条では、
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています。
つまり、100名規模の企業であれば、
確実に就業規則の作成・届出義務が発生します。
多くの総務担当者が見落とす「周知義務」
作成・届出だけでなく、
従業員への周知も法的義務であることを
見落としている企業が少なくありません。
具体的には以下の方法による周知が必要です:
- 各作業場への掲示または備え付け
- 従業員への書面交付
- 電子メールやイントラネットでの送信
100名規模の企業では、
複数の部署や勤務地があることが多く、
「全従業員に確実に周知できているか?」という点で
課題を抱えるケースが頻発しています。
経営者視点:義務違反のリスクとコスト
就業規則の作成・届出義務を怠った場合、
30万円以下の罰金が科される可能性があります。
しかし、それ以上に深刻なのは以下のようなリスクです:
労働紛争の増加
明確なルールがないことで、
労働条件や手続きに関するトラブルが発生しやすくなります。
100名規模では、月に数件の労務相談が舞い込むことも珍しくありません。
助成金申請への影響
多くの助成金申請では、
適切な就業規則の整備が前提条件となっています。
人材育成や働き方改革関連の助成金を活用したくても、
規則不備で申請できないという事態が起こり得ます。
総務担当者視点:日常業務への影響
就業規則が不備だと、
日常の総務業務にも大きな支障が生じます。
手続きの標準化ができない
入退社手続き、休暇申請、懲戒処分など、
各種手続きの根拠が曖昧になり、
都度判断に迷うことになります。
給与計算との連動性
残業代の計算方法、各種手当の支給基準、
休暇取得時の給与控除など、
給与計算業務と就業規則は密接に関連しています。
規則が不明確だと、毎月の給与計算でも
判断に困る場面が増えてしまいます。
100名規模企業のための実践的な就業規則整備戦略
ここからは、実際に就業規則を整備・改善するための
具体的なアクションプランをご紹介します。
段階的アプローチで負担を軽減
第1段階:現状把握と優先度設定(1-2週間)
まず、現在の就業規則の状況を整理しましょう。
以下のチェックポイントを確認してください:
- 最新の法改正に対応しているか
- 実際の運用と規則内容に乖離がないか
- 従業員からの質問が多い項目はどこか
第2段階:重要項目から順次改定(1-3ヶ月)
すべてを一度に見直そうとせず、
影響度の高い項目から順次対応していくことが重要です。
成功事例:製造業A社(従業員120名)の取り組み
関西の製造業A社では、
就業規則の全面見直しを3ヶ月かけて実施しました。
課題
・10年間規則を更新せず、実態と大きく乖離
・パート・アルバイトの労働条件が不明確
・テレワーク制度導入に伴う規程整備が必要
対策
・社労士顧問契約により専門的なサポートを確保
・部署別ヒアリングで実態調査を実施
・段階的な規則改定でスムーズな移行を実現
結果
・労働トラブルが月3件から0件に減少
・従業員の労働条件に関する問い合わせが8割削減
・働き方改革推進交付金200万円の申請が可能に
失敗事例:サービス業B社(従業員80名)のケース
一方、関東のサービス業B社では、
内製化にこだわったことで課題が発生しました。
問題点
・インターネットのテンプレートを使用
・業界特有の事情を反映できていない
・法改正への対応が後手に回る
結果として生じた問題
・労働基準監督署の指導を受ける
・従業員からの不満が増加
・最終的に外部専門家への依頼が必要に
DXを活用した効率的な規則管理
100名規模の企業では、
デジタル化による業務効率改善も重要なポイントです。
クラウド型人事労務システムの活用
・就業規則と給与計算システムの連動
・法改正情報の自動アップデート
・従業員への周知状況の一元管理
アウトソース vs 内製化の判断基準
規模が大きくなるほど、
専門性の高い業務は外部委託が効率的です。
特に就業規則の作成・更新は、
法的知識と実務経験の両方が必要なため、
社労士への依頼を検討することをお勧めします。
よくある質問:100名規模企業の就業規則Q&A
Q1:既存の就業規則はいつまでに見直すべきでしょうか?
総務担当者の視点:
法改正があった場合は速やかに、
それ以外でも年1回の定期見直しを推奨します。
特に、働き方改革関連法や育児介護休業法の改正など、
頻繁に変更される分野については、
四半期ごとのチェックが安心です。
経営者の視点:
法的リスクを最小限に抑えるためには、
専門家による年次レビューの仕組み作りが重要です。
顧問社労士との契約により、
法改正情報の提供と規則更新を
セットで依頼するのが効率的でしょう。
Q2:パート・アルバイトにも同じ就業規則が適用されますか?
総務担当者の視点:
正社員とは異なる労働条件の場合、
別途「パートタイム労働者就業規則」の作成が必要です。
ただし、基本的なルール(服務規律、懲戒など)は
共通部分も多いため、
効率的な管理方法を検討しましょう。
経営者の視点:
同一労働同一賃金の観点から、
正社員とパート労働者の処遇差について
合理的な説明ができる規則作りが重要です。
不適切な格差は労働紛争の原因となります。
Q3:テレワーク制度導入時の就業規則はどう変更すべきですか?
総務担当者の視点:
労働時間の管理方法、通信費の負担区分、
セキュリティルールなど、
テレワーク特有の項目を明記する必要があります。
また、従来の「出社前提」の規定についても
見直しが必要です。
経営者の視点:
テレワーク導入は働き方改革の一環として、
助成金の対象になる場合があります。
適切な規則整備により、
コスト負担を軽減できる可能性があります。
まとめ
100名規模企業の就業規則作成は、
法的義務であると同時に、
組織運営を効率化する重要な経営ツールです。
総務担当者の皆様には、
日々の給与計算や各種手続きの負担軽減につながり、
経営者の皆様には、
法的リスクの回避と助成金活用のメリットをもたらします。
適切な就業規則の整備により、
従業員との信頼関係も深まり、
より良い職場環境の実現が可能になります。
しかし、法改正への対応や業界特有の事情を踏まえた
規則作成は、専門的な知識と豊富な経験が不可欠です。
「自社だけでは対応しきれない」
「専門家のサポートを受けたい」
そのようにお感じでしたら、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。
HR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、
100名規模企業の実情に合わせた
就業規則作成・改定をサポートしています。
LINE・Slack・Chatworkなど、
お客様のご利用ツールに合わせた
スムーズなやり取りで、
迅速かつ正確な対応をお約束いたします。
今すぐ無料相談で、
就業規則の不安を解消しませんか?
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人



