新着情報
中小企業が知っておきたい給与計算アウトソーシングの費用対効果
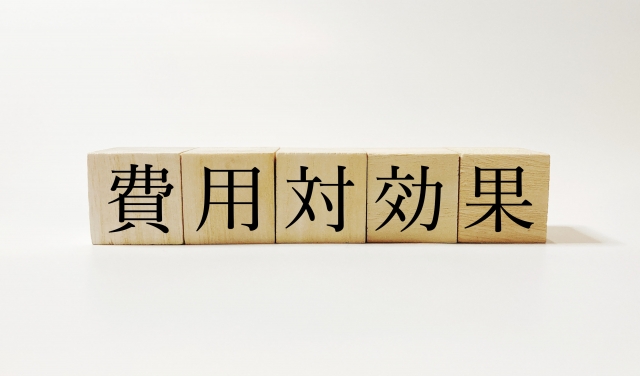
「給与計算をアウトソーシングしたいけれど、
本当にコストに見合う効果があるのだろうか?」
従業員100人規模の企業では、
毎月の給与計算業務が大きな負担となり、
外部委託を検討される経営者・総務担当者が増えています。
しかし、いざ検討を始めると
「費用が高そう」「情報漏洩が心配」「どの業者を選べばいいか分からない」
といった不安も生まれるのではないでしょうか。
実際に、適切な検討をせずに導入して
「期待したほどの効果が得られなかった」
「結局、内製化に戻した」という失敗例も存在します。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、
給与計算アウトソーシングのメリット・デメリットから
失敗しない業者選びまで、実践的なノウハウをお伝えします。
給与計算アウトソーシングの本当のメリット・デメリット
そもそも給与計算アウトソーシングとは?
給与計算アウトソーシングとは、毎月の給与計算業務を外部の専門業者に委託することです。
具体的には、以下の業務を外部に委託します:
- 基本給・各種手当の計算
- 社会保険料・税金の控除計算
- 給与明細書の作成・配布
- 年末調整業務
- 各種手続き(入退社、扶養変更など)
従業員100人規模では、これらの業務だけで
総務担当者の月間工数の30~40%を占めることも珍しくありません。
近年、業務のDX化と効率化を目指す企業が増え、
アウトソースを活用する中小企業が急増しています。
実際のメリット:時間とコストの削減効果
【経営者の視点】時間とコストの大幅削減
最大のメリットは、社内リソースの効率的な活用です。
給与計算には専門知識が必要で、
法改正のたびに学習コストも発生します。
外部委託により、これらの負担から解放され、
本来の事業活動に集中できるようになります。
実際の削減効果を見てみましょう:
・担当者の月間工数:40時間 → 5時間(▲35時間)
・法改正対応の学習時間:年20時間 → 0時間
・システム維持費:年50万円 → 0円
・ミス修正の工数:月5時間 → 0時間
【総務担当者の視点】業務品質の向上
外部の専門業者は最新の法規制に常に対応しており、
法令遵守の確実性が大幅に向上します。
2024年の雇用保険料率変更、
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額改定など、
頻繁な法改正への対応も自動的に実施されます。
「今月の法改正、対応できているかな?」
という不安から解放され、
精神的な負担も大幅に軽減されます。
隠れたデメリット:導入時の注意点
【経営者の視点】コスト構造の変化
アウトソーシングには月額固定費用が発生します。
従業員100人規模では、月額10~20万円程度が相場です。
一見高く感じますが、
人件費(担当者の給与・社会保険料)、
システム費用、研修費用などを総合すると、
多くの場合でコスト削減効果があります。
重要なのは「見えるコスト」だけでなく、
「見えないコスト」も含めた総合的な判断です。
【総務担当者の視点】情報セキュリティへの対応
給与データは最も機密性の高い情報の一つです。
外部委託により情報漏洩のリスクが気になる方も多いでしょう。
しかし、適切な業者を選べば、
むしろセキュリティレベルは向上します。
専門業者は以下の対策を標準装備しています:
・プライバシーマーク取得
・ISO27001認証
・暗号化通信
・アクセスログ管理
・定期的なセキュリティ監査
社内でのUSBメモリ使用、
印刷物の管理などの方が、
実はリスクが高い場合もあります。
失敗しない業者選びと導入の進め方
業者選定の5つのチェックポイント
1. 実績と専門性の確認
同規模企業での実績は必須条件です。
従業員100人規模特有の課題を理解し、
適切なソリューションを提供できるかを確認しましょう。
・同規模企業の顧客数
・社会保険労務士の資格保有者数
・業界特有の手当や制度への対応経験
・助成金申請サポートの有無
2. システム対応力とDX推進力
給与計算のDX化を推進するなら、
システム連携能力は重要な判断基準です。
・既存の勤怠管理システムとの連携
・クラウド対応とリアルタイム処理
・モバイル対応(スマホでの給与明細確認など)
・API連携による自動化の範囲
3. コミュニケーション体制
毎月の業務で重要なのは、
スムーズなコミュニケーションです。
・質問への回答スピード(24時間以内が理想)
・緊急時の対応体制
・担当者の固定化(コロコロ変わるのはNG)
・使い慣れたツール(LINE、Slack、Chatworkなど)での対応
成功事例:建設業D社(従業員105名)
D社は3社で相見積もりを実施。
最安値ではなく、現場作業員の複雑な勤務形態に
対応できる専門性を重視して選定。
結果、計算ミスゼロを2年間継続し、
労務トラブルも大幅に減少しました。
段階的導入で失敗リスクを最小化
Phase1:テスト導入(1~2ヶ月)
いきなり全面委託するのではなく、
まずは並行運用から始めましょう。
・社内計算と外部委託を並行実施
・結果の照合による精度確認
・コミュニケーション体制の検証
・問題点の早期発見と改善
Phase2:部分導入(3~6ヶ月)
テスト結果が良好であれば、
段階的に委託範囲を拡大します。
・給与計算のみ → 社会保険手続きも追加
・月次処理 → 年末調整も追加
・レポート体制の確立
・運用ルールの最適化
Phase3:本格運用(6ヶ月以降)
全面的な委託に移行し、
効果測定と継続改善を行います。
・労働保険年度更新も委託範囲に
・戦略的人事業務へのシフト
・ROI(投資対効果)の定期測定
・サービス品質の継続モニタリング
失敗事例:小売業E社(従業員88名)
E社は「早く楽になりたい」と考え、
検討期間わずか1週間で全面委託を決定。
結果、業者の対応力不足が判明し、
給与支払いが2日遅れる事態に。
従業員の信頼を失い、内製化に戻ることになりました。
費用対効果の正しい計算方法
アウトソーシングの導入判断で最も重要なのが、
正確な費用対効果の算出です。
【現状コストの洗い出し】
・担当者人件費:月給30万円×12ヶ月=360万円
・社会保険料:54万円(15%として)
・給与計算システム:年額60万円
・研修・書籍代:年額10万円
・ミス修正コスト:年額20万円
→ 年間総コスト:504万円
【アウトソーシングコスト】
・月額委託料:15万円×12ヶ月=180万円
・初期設定費:30万円
→ 年間総コスト:210万円
【削減効果】
504万円 – 210万円 = 年間294万円の削減
さらに、担当者が他の業務に専念できることで、
売上向上や業務改善などの間接効果も期待できます。
よくある疑問・不安にお答えします
Q1. 現在の顧問社労士がいるのに、追加で委託する必要がありますか?
A1. 顧問業務と実務処理は役割分担することで、双方の専門性を活かせます。
【経営者の視点】
顧問社労士は法的アドバイス、就業規則作成、
労務相談などのコンサルティング業務が専門です。
一方、給与計算は正確性とスピードが求められる
「実務処理」の色合いが強い業務です。
適材適所の役割分担により、
それぞれの専門性を最大限活用できます。
【総務担当者の視点】
月1回の顧問相談で解決する戦略的課題と、
毎月発生する定型的な計算業務は
求められるスキルが全く異なります。
「コンサルは顧問社労士、実務は専門業者」
というハイブリッド体制が最も効率的です。
Q2. 繁忙期だけ委託することは可能ですか?
A2. 可能ですが、年間契約の方が品質・コスト面でメリットがあります。
【経営者の視点】
年末調整や労働保険年度更新などの繁忙期のみの
スポット委託も技術的には可能です。
しかし、業者側も準備期間が必要で、
スポット料金は割高になるケースが多いです。
年間契約により、月平均化された
リーズナブルな料金設定が一般的です。
【総務担当者の視点】
スポット委託では、業者が社内のルールや
従業員の個別事情を把握しきれません。
継続的な関係により、
きめ細かい対応が可能になり、
結果的に業務品質が向上します。
Q3. システム導入が必要で、初期費用が心配です
A3. 多くの業者が既存システム連携に対応しており、大規模な導入は不要です。
【経営者の視点】
現在お使いの勤怠管理システムとの
データ連携が可能な業者を選べば、
追加のシステム導入は不要です。
CSVファイルでのデータ受け渡しなど、
柔軟な連携方法が用意されています。
【総務担当者の視点】
「新しいシステムを覚えるのが大変」
という不安もよく耳にしますが、
実際の操作は業者側で行うため、
学習コストはほとんど発生しません。
むしろ、複雑な給与計算ソフトの操作から
解放されるメリットの方が大きいです。
まとめ
給与計算アウトソーシングは、
従業員100人規模の企業にとって
業務効率化の強力な手段です。
適切に導入することで、
・年間200~300万円のコスト削減
・担当者の残業時間月35時間削減
・法改正対応の自動化
・計算ミスゼロの実現
が期待できます。
一方で、業者選定を誤ると
「期待した効果が得られない」
「情報漏洩などのトラブル発生」
「結局、内製化に戻すことになった」
といった失敗リスクもあります。
成功の鍵は、
・実績と専門性を重視した業者選定
・段階的導入によるリスク最小化
・正確な費用対効果の算出
・継続的なPDCAサイクルの実施
です。
「毎月の給与計算業務から解放されて、
もっと戦略的な業務に集中したい」
「法改正への対応不安を解消し、
安心して給与業務を任せたい」
「DXを推進して、
業務全体の効率化を実現したい」
そのような想いをお持ちの経営者・総務担当者の方は、
まずは現状の課題とコストを
正確に把握することから始めてみてください。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、
無料の現状分析コンサルティングを実施しています。
あなたの会社の状況に合わせて、
最適なソリューションをご提案いたします。
LINE、Slack、Chatworkなど
普段お使いのツールで
お気軽にご相談ください。
【今すぐ無料相談のお申し込みはこちら】
あなたの会社の給与計算業務を
劇的に改善する第一歩を踏み出しましょう。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人



