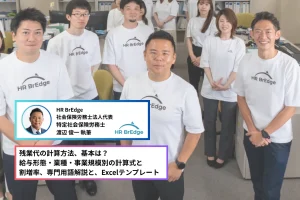新着情報
給与計算アウトソーシング・給与計算代行の完全ガイド!大手・中小ごとの相場・料金表や流れを比較!
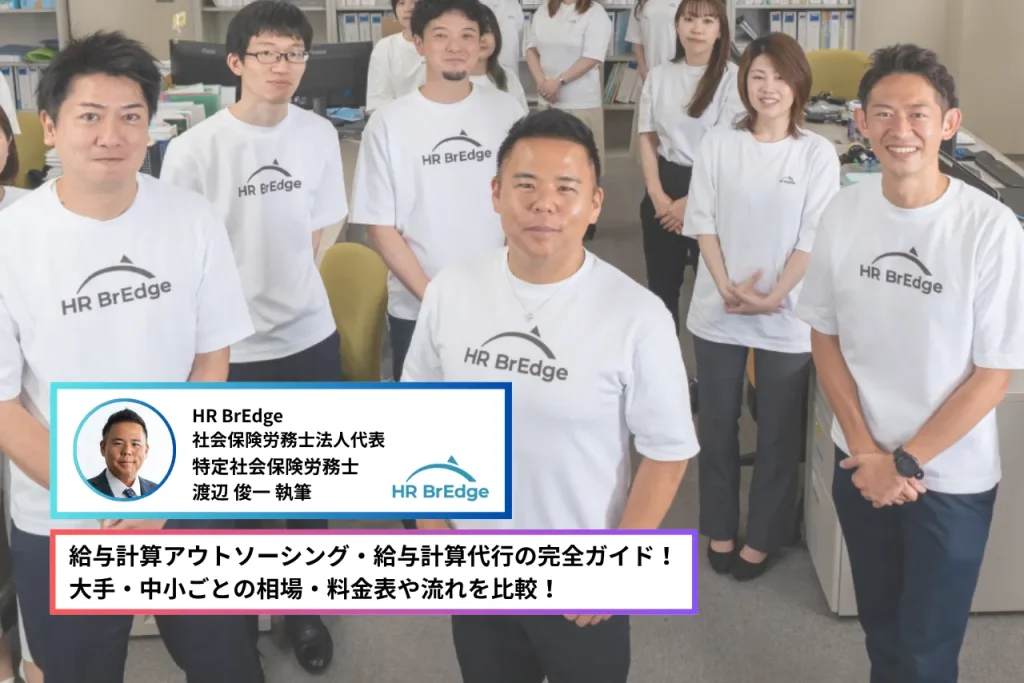
給与計算は企業にとって欠かせない業務ですが、法改正への対応や計算ミスのリスク、担当者の業務負担など、多くの課題を抱えている企業が少なくありません。
そこで注目されているのが「給与計算アウトソーシング」です。専門家に給与計算業務を委託することで、正確性の向上とコスト削減を同時に実現できます。
本記事では、創業18年・500社以上の導入実績を持つHR BrEdge社労士法人が、給与計算アウトソーシングの基礎知識から選び方、料金相場、導入事例まで徹底解説します。給与計算業務の効率化を検討されている経営者・人事担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
給与計算アウトソーシングとは?
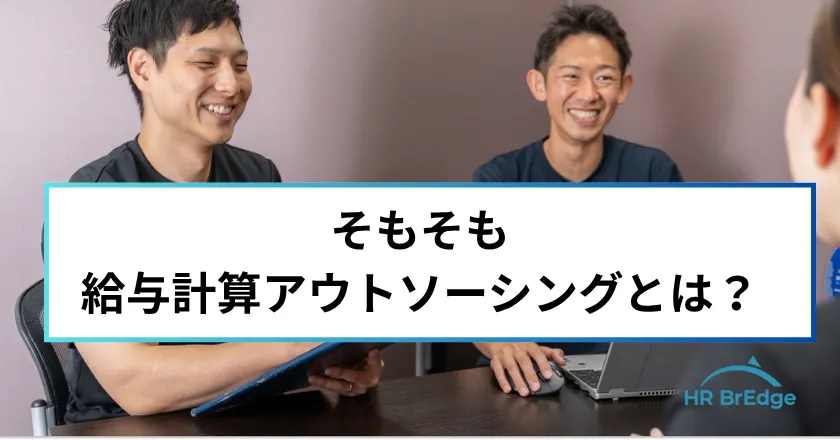
給与計算アウトソーシングとは、企業が自社の従業員に対する給与計算業務を外部の専門業者に委託するサービスのことです。給与計算だけでなく、関連する労務手続きや年末調整なども包括的に依頼できるのが特徴です。
給与計算アウトソーシングの定義と仕組み
給与計算アウトソーシングでは、企業が勤怠データなどの基礎情報を提供し、委託先の専門業者が以下のような業務を代行します。
- 月次給与計算・賞与計算
- 給与明細の作成・発行
- 社会保険料・所得税・住民税の計算
- 銀行振込データの作成
- 年末調整業務
- 各種労務手続き
委託先には、給与計算専門会社、社会保険労務士事務所、税理士事務所などがあり、それぞれ得意分野や対応範囲が異なります。特に社労士事務所の場合、労働保険や社会保険の手続きまで一括して依頼できるため、トータルでの業務効率化が期待できます。
基本的な流れとしては、企業が勤怠データを委託先に送付し、委託先が給与計算を実施した後、給与明細や振込データを納品するという形になります。クラウドシステムを活用することで、データのやり取りも効率化されています。
給与計算アウトソーシングが必要となる背景
給与計算アウトソーシングが注目される背景には、企業を取り巻く環境の変化があります。
①法改正への対応負担の増大
労働基準法や社会保険、税制は毎年のように改正されます。社会保険料率の変更や税制改正に対応するためには、常に最新情報をキャッチアップし、システムや計算方法を更新する必要があります。自社で対応する場合、担当者の学習コストや更新作業の負担が大きくなります。
②給与計算の複雑化
従業員数の増加や雇用形態の多様化(正社員、パート、アルバイト、契約社員など)により、給与計算は年々複雑になっています。時間外労働の計算、各種手当の処理、社会保険料の控除など、ミスが許されない業務であるにもかかわらず、作業量は増加し続けています。
③人手不足とコア業務への集中
多くの企業では人事・総務部門の人員が限られており、給与計算のような定型業務に多くの時間を割くことが難しくなっています。経営戦略に直結するコア業務に人的リソースを集中させるため、給与計算のような専門性の高いノンコア業務は外部に委託する企業が増えています。
④業務の属人化リスク
給与計算を特定の担当者だけが行っている場合、その担当者が退職や休職した際に業務が停滞するリスクがあります。また、担当者の世代交代時に知識やノウハウの引き継ぎがうまくいかないケースも少なくありません。
⑤テレワークへの対応
コロナ禍以降、テレワークが普及したことで、紙ベースでの給与計算業務が困難になった企業も多く存在します。クラウド化されたアウトソーシングサービスを活用することで、場所を問わず効率的に業務を進められるようになります。
給与計算アウトソーシングの普及状況(日本・海外の利用率)
給与計算アウトソーシングは、もともと専門性の高い業務を外部の専門家にアウトソーシングする考え方が普及していたアメリカで発展したサービスです。
日本では、1990年代のバブル崩壊後、企業がグローバル競争にさらされる中で業務のコストダウンが求められるようになり、給与計算アウトソーシングが急速に注目されるようになりました。2000年代に入ると、企業は本業に専念し、バックオフィス業務を外注するというビジネスモデルが一般化し、給与計算アウトソーシングの利用が拡大しました。
日本・海外の利用率比較
- 日本:約20%の企業が給与計算アウトソーシングを利用
- 北米:約20%の企業が利用
- 中南米:約60%の企業が利用
日本では現在、約20%の企業が給与計算アウトソーシングを利用していますが、海外と比較するとまだ普及の余地があると言えます。特に中南米では60%もの企業が利用しており、給与計算業務の外部委託が当たり前になっています。
日本国内でも、働き方改革やDX推進の流れを受けて、今後さらに給与計算アウトソーシングの利用が拡大していくことが予想されます。特に中小企業においては、限られた人的リソースを有効活用するための有力な選択肢として、給与計算アウトソーシングの導入が進んでいます。
給与計算アウトソーシングで委託できる業務範囲
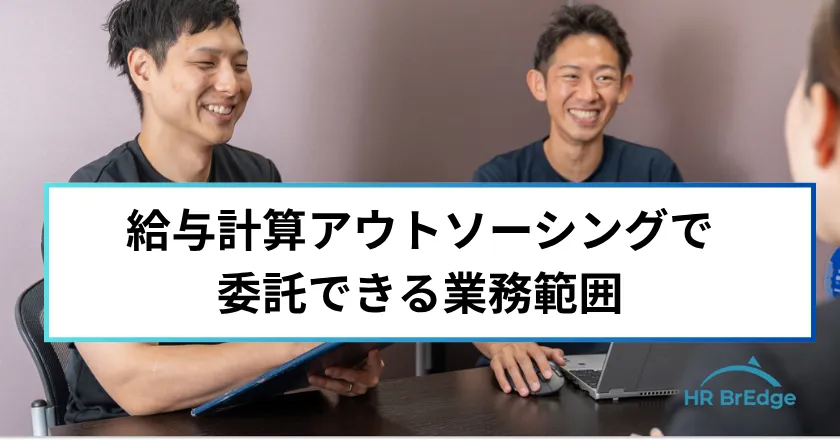
給与計算アウトソーシングで委託できる業務範囲は、サービス提供会社によって異なりますが、一般的には給与計算を中心とした幅広い労務業務に対応しています。ここでは、主要な委託可能業務について詳しく解説します。
給与計算のアウトソーシングでできること①給与・賞与計算代行
給与計算アウトソーシングの中核となるのが、月次の給与計算と賞与計算の代行業務です。
月次給与計算では、企業から提供された勤怠データを基に、基本給、残業代、各種手当(通勤手当、役職手当、家族手当など)の計算を行います。さらに、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)、所得税、住民税などの控除項目を正確に計算し、差し引き支給額を算出します。
賞与計算についても同様に、賞与支給額に基づいて社会保険料や所得税の計算を行い、正確な支給額を算出します。企業によっては計算が複雑になるケースもありますが、専門家に委託することで確実な処理が可能になります。
給与明細書や賞与明細書の作成・発行も含まれており、紙での発行だけでなく、Web明細への対応も可能なサービスが増えています。従業員がスマートフォンやパソコンから明細を確認できるため、ペーパーレス化にも貢献します。
給与計算のアウトソーシングでできること②振込・納税代行(銀行FBデータ作成含む)
給与計算が完了した後の振込業務も、アウトソーシングの対象となります。
具体的には、銀行への振込依頼データ(FBデータ:Firm Bankingデータ)の作成を行います。このデータを企業の取引銀行に送信することで、従業員の口座へ給与が自動的に振り込まれます。複数の銀行を利用している企業でも、各銀行のフォーマットに対応したデータ作成が可能です。
また、所得税の納付や社会保険料の納付に関するデータ作成も対応範囲に含まれます。納付期限の管理や納付額の計算を専門家が行うことで、納付漏れや計算ミスのリスクを軽減できます。
給与計算のアウトソーシングでできること④年末調整代行
年末調整は、毎年11月から12月にかけて実施される重要な業務ですが、膨大な作業量と専門知識が必要となるため、多くの企業がアウトソーシングを検討する業務のひとつです。
年末調整では、従業員から提出される扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などの書類を確認し、年間の所得税額を再計算します。過不足があれば12月または翌年1月の給与で精算を行います。
アウトソーシングサービスでは、従業員への案内文書の作成から始まり、提出書類の確認、年末調整計算、源泉徴収票の作成・発行まで、一連の業務を代行します。特に従業員数が多い企業では、年末調整だけで数週間かかることもあるため、外部委託による業務負担軽減の効果は大きいと言えます。
最近では、年末調整手続きの電子化も進んでおり、従業員がオンラインで必要事項を入力できるシステムを提供するサービスも増えています。
給与計算のアウトソーシングでできること⑤住民税更新代行(特別徴収額通知書の処理)
住民税の更新業務も、給与計算アウトソーシングで対応可能な業務です。
毎年5月から6月にかけて、各市区町村から企業宛に「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。この通知書には、各従業員の住民税額が記載されており、企業は6月から翌年5月までの1年間、給与から天引きして納付する義務があります。
住民税更新業務では、大量の紙媒体の通知書を処理する必要があり、従業員ごとに正確な税額をシステムに登録しなければなりません。デジタル化が遅れている市区町村も多く、紙での処理が中心となるため、非常に時間がかかる作業です。
アウトソーシングを活用すれば、この煩雑な住民税更新業務を専門スタッフが代行し、正確かつ迅速に給与システムへ反映させることができます。自社で行っている給与計算は継続しながら、住民税更新だけをスポットで外部委託する企業も少なくありません。
給与計算のアウトソーシングでできること⑥社会保険・労働保険手続き
給与計算と密接に関連する社会保険・労働保険の各種手続きも、アウトソーシングの対象となります。
具体的には、従業員の入社時における健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き、雇用保険の加入手続き、退職時の資格喪失手続きなどが含まれます。また、従業員の扶養家族の追加・削除、住所変更、氏名変更などの各種変更届の提出も代行します。
これらの手続きは、年金事務所やハローワークへの届出が必要であり、提出期限も定められています。手続きに不備があると従業員に不利益が生じる可能性もあるため、専門知識を持つ社会保険労務士に委託することで、確実かつスムーズな手続きが可能になります。
特に社労士事務所にアウトソーシングする場合、給与計算と社会保険手続きを一括して依頼できるため、情報の連携がスムーズで、手続き漏れを防ぐことができます。
給与計算のアウトソーシングでできること⑦勤怠管理・有給休暇管理
給与計算の基礎となる勤怠管理や有給休暇管理も、アウトソーシングサービスの対象範囲に含まれることがあります。
勤怠管理では、タイムカードやICカード、クラウド勤怠システムなどから取得した出退勤データを集計し、労働時間、残業時間、深夜労働時間、休日労働時間などを計算します。集計されたデータは給与計算に直接反映されるため、正確な勤怠管理が給与の正確性を担保します。
有給休暇管理では、従業員ごとの有給休暇の付与日数、取得日数、残日数をマスタ情報として管理します。労働基準法では年5日の有給休暇取得義務が定められているため、取得状況の把握と管理が重要になっています。アウトソーシングを活用すれば、担当者が個別に残日数を管理する手間が省け、法令遵守の徹底にもつながります。
サービスによっては、勤怠データの入力から集計、給与計算への連携まで一貫して対応してくれるため、企業側の業務負担を大幅に削減できます。
給与計算のアウトソーシングでできること⑧福利厚生代行
給与計算アウトソーシングサービスの中には、福利厚生に関する業務も代行してくれるものがあります。
福利厚生代行には、各種福利厚生サービスの加入手続き、従業員への案内、利用状況の管理などが含まれます。また、財形貯蓄や社内預金、従業員持株会などの給与天引きに関する処理も対応範囲となります。
健康診断の案内や受診状況の管理、ストレスチェックの実施サポートなども、サービスによっては対応可能です。これらの業務は給与計算と直接関係しませんが、人事労務業務全般をサポートする観点から、包括的に委託できる体制を整えているアウトソーシング会社も増えています。
給与計算のアウトソーシングでできること⑨従業員からの問い合わせ対応窓口
給与や手続きに関する従業員からの問い合わせ対応を、アウトソーシング先が代行してくれるサービスもあります。
従業員→人事部門→アウトソーシング先という経路で情報をやり取りすると、時間と手間がかかってしまいます。そこで、従業員が直接アウトソーシング先に問い合わせできる窓口を設けることで、迅速な対応が可能になります。
給与明細の見方、控除項目の内容、年末調整の書類の書き方、住所変更の手続き方法など、よくある質問に専門スタッフが対応します。Web上で情報を入力するだけで手続きが完了するシステムを提供しているサービスもあり、従業員がスマートフォンやタブレットから直接申請できるため、人事部門を介さずにスムーズな処理が可能です。
人事部門の負担軽減だけでなく、従業員の満足度向上にもつながるサービスと言えます。
給与計算アウトソーシングの種類と特徴
給与計算アウトソーシングには、いくつかのタイプがあり、企業の規模や課題、求めるサポート内容によって最適なサービスが異なります。ここでは、主要な4つのタイプについて詳しく解説します。
フルサポート型給与計算アウトソーシングの特徴
フルサポート型給与計算アウトソーシングは、給与計算業務に関するすべてのプロセスを包括的に委託できるタイプです。
このタイプでは、勤怠データの集計から給与計算、給与明細の発行、振込データの作成、さらには従業員からの問い合わせ対応まで、給与計算に関連する業務を一括して依頼できます。社会保険や労働保険の手続き、年末調整、住民税更新なども含めて対応してもらえるため、企業側の業務負担を最小限に抑えられます。
フルサポート型は、従業員数が数十名から数百名規模の中小企業に適しています。管理部門の人員に余裕がない企業や、給与計算業務を完全に外部に任せたいと考えている企業にとって、最も効果的な選択肢となります。
専任の担当者が付くケースが多く、企業の給与体系や特有のルールにも柔軟に対応してくれるため、きめ細かなサポートを受けられる点が大きなメリットです。ただし、他のタイプと比較すると費用は高めになる傾向があります。
クラウド系給与計算アウトソーシングの特徴
クラウド系給与計算アウトソーシングは、クラウドシステムを活用して給与計算業務を効率化するタイプです。
このタイプでは、企業がクラウド上の給与計算システムを利用し、勤怠データの入力や給与計算の一部を自社で行いながら、複雑な計算や専門的な処理をアウトソーシング先に委託します。システムとアウトソーシングサービスが一体化しているため、データの受け渡しがスムーズで、リアルタイムでの情報共有が可能です。
クラウドシステムを使用することで、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、テレワークにも対応できます。また、従業員自身が給与明細をオンラインで確認したり、年末調整の書類をWeb上で提出したりすることも可能になり、ペーパーレス化が進みます。
クラウド系給与計算アウトソーシングは、ITリテラシーが高い企業や、ある程度自社でも給与計算業務を行いたい企業に適しています。初期導入のハードルが低く、コストも比較的抑えられるため、小規模企業から中規模企業まで幅広く利用されています。
システム一体型給与計算アウトソーシングの特徴
システム一体型給与計算アウトソーシングは、給与計算システムの提供とアウトソーシングサービスがセットになったタイプです。
このタイプでは、アウトソーシング会社が提供する専用の給与計算システムを導入し、そのシステムを使用してアウトソーシング先が給与計算を行います。システムとサービスが完全に連携しているため、データの整合性が保たれ、スムーズな業務遂行が可能です。
システム一体型の大きなメリットは、給与計算システムの保守管理や法改正対応をアウトソーシング先が担当してくれる点です。企業側でシステムのバージョンアップや設定変更を行う必要がなく、常に最新の法令に対応した計算が自動的に行われます。
また、勤怠管理システムや会計システムとの連携機能を持つサービスも多く、人事労務業務全体のデジタル化を推進できます。企業の業務フローに合わせたカスタマイズも可能なケースが多いため、独自の給与体系や複雑な計算ロジックを持つ企業でも安心して利用できます。
システム一体型は、システム導入とアウトソーシングの両方を検討している企業や、既存システムの老朽化に悩んでいる企業に適しています。
スポット型給与計算アウトソーシングの特徴(年末調整のみなど)
スポット型給与計算アウトソーシングは、年末調整や住民税更新など、特定の業務だけを単発または期間限定で委託するタイプです。
通常の月次給与計算は自社で行いながら、繁忙期や専門性の高い業務だけを外部に依頼することで、必要な時に必要な分だけサポートを受けられます。年末調整は毎年11月から12月にかけて膨大な作業が発生するため、この期間だけアウトソーシングを活用する企業も多く存在します。
スポット型のメリットは、コストを抑えながら専門家のサポートを受けられる点です。年間を通じて委託契約を結ぶ必要がないため、初期費用や月額費用を抑えられます。給与計算担当者が急に休職・退職した場合の一時的な代行や、システム入れ替え時の移行期間だけの利用など、柔軟な活用が可能です。
ただし、スポット型は単発の利用となるため、通常の給与計算業務についてのサポートは受けられません。また、利用する期間や回数によっては、長期的に見ると包括的なサービスを利用した方がトータルコストを抑えられるケースもあります。
スポット型は、社内に給与計算担当者はいるが業務負荷を一時的に軽減したい企業や、特定業務の専門性を高めたい企業に適しています。
給与計算アウトソーシングの料金体系と相場【2025年版】

給与計算アウトソーシングを検討する際、最も気になるのが料金です。料金は企業の規模、従業員数、委託する業務範囲によって大きく異なります。ここでは、一般的な料金体系と相場について詳しく解説します。
給与計算アウトソーシングの料金体系3つのパターン
給与計算アウトソーシングの料金体系には、主に3つのパターンがあります。
従量課金制は、従業員1名につき月額いくらという形で料金が設定されるパターンです。例えば、従業員1名あたり月額500円から1,000円程度の単価が設定され、従業員数に応じて月額料金が変動します。このパターンは料金が明確で分かりやすく、従業員数の増減に柔軟に対応できる点がメリットです。ただし、基本料金が別途かかるケースが多いため、トータルコストを確認することが重要です。
月額料金制は、従業員数何名から何名まで月額いくらという形で、一定の範囲内であれば定額となるパターンです。例えば、従業員50名まで月額5万円、51名から100名まで月額8万円といった料金設定になります。従業員数が範囲内であれば料金が固定されるため、予算管理がしやすい点がメリットです。ただし、従業員数が範囲の境界線付近にある場合、数名の増減で料金が大きく変わる可能性があります。
稼働時間制は、代行スタッフの月の稼働時間の上限に応じて料金が設定されるパターンです。例えば、月20時間まで月額10万円、月40時間まで月額18万円といった形です。このパターンは、業務量が月によって変動する企業や、部分的な委託を希望する企業に適しています。ただし、稼働時間の管理や業務範囲の明確化が重要になります。
給与計算アウトソーシングの料金構成要素
給与計算アウトソーシングの料金は、いくつかの要素で構成されています。
導入費用(初期費用)は、サービス開始時に一度だけかかる費用です。システムのセットアップ、既存データの移行、業務フローの改善などが含まれます。導入費用は10万円から50万円程度が一般的ですが、企業の規模や複雑さによって変動します。サービスによっては初期費用が無料のケースもあります。
基本料金(サービス利用料金)は、毎月固定で発生する費用です。システムの利用料、基本的なサポート体制の維持費などが含まれます。基本料金は月額2万円から5万円程度が相場ですが、サービス内容や企業規模によって異なります。
月額費用(従業員1人当たり)は、従業員数に応じて変動する費用です。従業員1名あたり月額1,000円程度が一般的ですが、従業員数が多いほど単価は下がる傾向にあります。この費用には、月次給与計算や給与明細の発行などが含まれます。
オプション料金は、基本サービス以外の追加業務に対して発生する費用です。年末調整は従業員1名あたり1,000円から3,000円程度、住民税更新は従業員1名あたり500円から1,000円程度が相場です。また、勤怠管理代行、社会保険手続き代行、従業員対応窓口の設置などもオプション料金として設定されるケースが多くあります。
【外注先別】給与計算アウトソーシングの料金相場
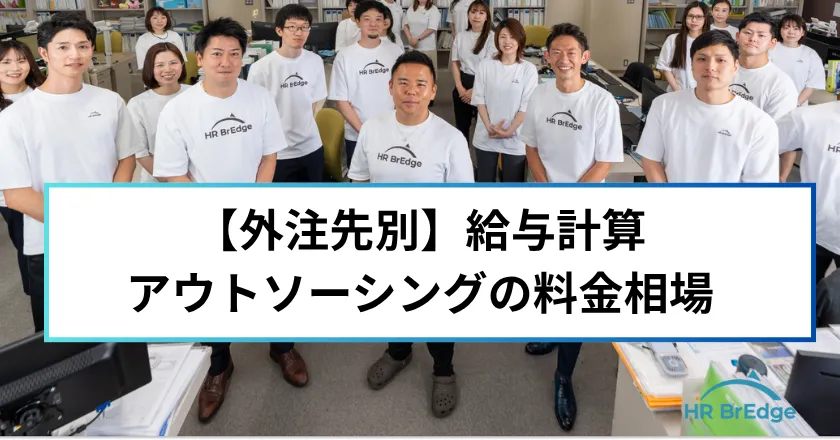
給与計算アウトソーシングの委託先には、給与計算代行会社、社会保険労務士事務所、税理士事務所があり、それぞれ料金体系や対応範囲が異なります。
給与計算代行会社に依頼する場合の料金相場
給与計算を専門に扱う代行会社は、給与計算業務に特化した体制を持っているため、効率的な処理が可能で、比較的リーズナブルな料金設定となっています。
給与計算代行会社の料金相場は、従業員50名程度の企業で月額4万円から6万円程度、従業員100名規模で月額8万円から12万円程度が目安です。基本料金は月額1万円から3万円程度、従業員1名あたりの単価は1000円程度が一般的です。
給与計算代行会社のメリットは、給与計算に関する豊富な実績とノウハウを持っている点です。大量の給与計算を効率的に処理できる体制が整っており、コストパフォーマンスに優れています。また、最新の給与計算システムを導入しているケースが多く、正確性とスピードが期待できます。
一方で、社会保険手続きや労務相談などは対応範囲外となるケースが多いため、これらの業務は別途社労士に依頼する必要があります。給与計算だけをシンプルに委託したい企業に適しています。
社労士事務所に依頼する給与計算アウトソーシングの料金相場
社会保険労務士事務所に給与計算を依頼する場合、給与計算だけでなく、社会保険手続きや労務相談まで包括的にサポートを受けられる点が大きな特徴です。
社労士事務所の料金相場は、従業員50名程度の企業で月額5万円から8万円程度、従業員100名規模で月額10万円から15万円程度が目安です。基本料金は月額3万円から5万円程度、従業員1名あたりの単価は500円から1,000円程度が一般的です。
社労士事務所に依頼する最大のメリットは、給与計算に関連する労務手続きを一括して任せられる点です。入退社時の社会保険手続き、雇用保険の加入・喪失手続き、労働保険の年度更新、算定基礎届の提出など、給与計算と密接に関連する業務をワンストップで対応してもらえます。
また、労働基準法や社会保険に関する専門知識を持つ社労士が対応するため、法令遵守の観点からも安心です。就業規則の作成・見直し、労務トラブルの相談、助成金の申請サポートなど、人事労務全般の相談ができる点も大きなメリットです。
料金は給与計算代行会社と比較するとやや高めになりますが、労務管理全体を考えるとトータルコストを抑えられるケースも多くあります。特に従業員数が50名以上の企業や、労務リスクを重視する企業に適しています。
税理士事務所に依頼する給与計算アウトソーシングの料金相場
税理士事務所に給与計算を依頼する場合、給与計算に加えて年末調整や税務に関するサポートを受けられる点が特徴です。
税理士事務所の料金相場は、従業員50名程度の企業で月額5万円から7万円程度、従業員100名規模で月額10万円から14万円程度が目安です。基本料金は月額2万円から4万円程度、従業員1名あたりの単価は500円から900円程度が一般的です。
税理士事務所に依頼するメリットは、給与計算から派生する税務処理を一貫して任せられる点です。特に年末調整は税務知識が必要となる業務であり、税理士の専門分野です。また、役員報酬の設定や退職金計算、ストックオプションの課税処理など、複雑な税務判断が必要なケースでも適切に対応してもらえます。
すでに税理士と顧問契約を結んでいる企業であれば、給与計算も同じ税理士事務所に依頼することで、会計処理との連携がスムーズになります。給与計算データを会計仕訳に自動連携できるため、経理業務の効率化にもつながります。
ただし、社会保険手続きは税理士の業務範囲外となるため、別途社労士に依頼する必要があります。税務と会計の観点から給与計算を管理したい企業に適しています。
【会社規模別】給与計算アウトソーシングの料金相場
給与計算アウトソーシングの料金は、企業の規模や従業員数によって大きく変動します。ここでは、従業員数別の具体的な料金相場を解説します。
従業員50名規模の給与計算アウトソーシング料金|月額7~12万円程度
従業員数が50名程度の企業における給与計算アウトソーシングの料金相場は、月額7万円から8万円程度です。
この規模の企業では、基本料金が月額2万円から3万円程度、従業員1名あたりの単価が900円から1,000円程度となるケースが一般的です。計算すると、基本料金3万円に従業員50名分の費用(50名×1,000円=5万円)を加えて、合計月額8万円程度となります。
従業員50名規模の企業は、給与計算を自社で行うには負担が大きく、かといって専任の給与計算担当者を雇用するほどではないという状況が多く見られます。この規模になると、社会保険手続きや年末調整の業務量も増加するため、アウトソーシングを検討する企業が増えてきます。
年末調整や住民税更新などの年次業務を含めると、年間のトータルコストは90万円から120万円程度となります。専任担当者を1名雇用するコストと比較すると、アウトソーシングの方がコストを抑えられるケースが多いと言えます。
従業員100名規模の給与計算アウトソーシング料金|月額16万円前後
従業員数が100名程度の企業における給与計算アウトソーシングの料金相場は、月額14万円から18万円程度、平均すると月額16万円前後となります。
この規模では、基本料金が月額5万円から9万円程度、従業員1名あたりの単価が800円〜1,000円程度が目安です。従業員数が増えることで、1名あたりの単価は下がる傾向にあります。
従業員100名規模の企業は、給与計算業務が複雑化し始める段階です。部署や職種が増え、給与体系も多様化するため、計算ミスのリスクも高まります。また、社会保険手続きの件数も月に数件から十数件発生するため、手続き漏れや遅延のリスクも考慮する必要があります。
この規模の企業では、給与計算と社会保険手続きを包括的に依頼できる社労士事務所への委託を検討する企業が多く見られます。年間のトータルコストは200万円から250万円程度となり、給与計算担当者を1名から2名雇用するコストと比較しても、費用対効果が高いと判断されるケースが多くあります。
従業員300名規模の給与計算アウトソーシング料金|月額30万円前後
従業員数が300名程度の企業における給与計算アウトソーシングの料金相場は、月額28万円から35万円程度、平均すると月額30万円前後となります。
この規模では、基本料金が月額7万円から10万円程度、従業員1名あたりの単価が700円から1,000円程度が目安です。スケールメリットにより、1名あたりの単価はさらに下がります。
従業員300名規模の企業は、給与計算業務が専門部署として独立している場合が多く、複数名の担当者が必要となります。事業所や支店が複数ある場合も多く、拠点ごとの給与体系の違いや地域による社会保険料率の違いなど、管理が複雑になります。
この規模になると、給与計算システムの導入と合わせてアウトソーシングを検討するケースが増えます。システム一体型の給与計算アウトソーシングを選択することで、業務の標準化と効率化を同時に実現できます。
年間のトータルコストは400万円から500万円程度となります。社内で給与計算部門を維持するコスト(人件費、システム費用、教育コストなど)と比較すると、アウトソーシングの方がコスト削減につながるケースが多く見られます。
従業員500名規模の給与計算アウトソーシング料金|月額50万円前後
従業員数が500名程度の企業における給与計算アウトソーシングの料金相場は、月額45万円から55万円程度、平均すると月額50万円前後となります。
この規模では、基本料金が月額10万円から15万円程度、従業員1名あたりの単価が600円から1,000円程度が目安です。大規模になるほど、スケールメリットによる単価の低減効果が大きくなります。
従業員500名規模の企業は、多くの場合、複数の事業所や支店を持ち、業種や職種も多岐にわたります。正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態も多様化しており、それぞれに異なる給与体系や社会保険の適用ルールがあります。
この規模の企業では、給与計算だけでなく、人事データの一元管理、勤怠管理との連携、会計システムへの自動仕訳など、包括的なシステム化が求められます。フルサポート型の給与計算アウトソーシングを選択し、人事労務業務全体を最適化するケースが一般的です。
年間のトータルコストは650万円から800万円程度となりますが、社内で給与計算部門を維持する場合の人件費(3名から5名程度の担当者)やシステム維持費を考慮すると、大幅なコスト削減が期待できます。
従業員1,000名規模の給与計算アウトソーシング料金|月額86万円前後
従業員数が1,000名程度の企業における給与計算アウトソーシングの料金相場は、月額80万円から95万円程度、平均すると月額86万円前後となります。
この規模では、基本料金が月額15万円から20万円程度、従業員1名あたりの単価が600円から1,000円程度が目安です。大規模企業向けの特別な料金体系が適用されるケースも多く見られます。
従業員1,000名規模の企業は、全国に複数の拠点を持ち、グループ会社を含めた統合管理が必要となることが多くあります。給与計算の処理量も膨大となり、月次処理だけでなく、賞与計算、年末調整、算定基礎届など、年間を通じて大量の業務が発生します。
この規模の企業では、給与計算アウトソーシングに高度な専門性とサービスレベルが求められます。専任チームによる対応、24時間365日のサポート体制、セキュリティの高度化、BCPBusiness Continuity Plan:事業継続計画)対応など、大企業向けの充実したサービスが必要です。
また、海外拠点を持つ企業の場合、グローバルペイロールサービスとの連携も重要になります。国内外の給与計算を統合管理できる体制づくりを行うことで、グループ全体の人件費管理や人事戦略の立案に役立ちます。
年間のトータルコストは1,200万円から1,500万円程度となりますが、社内で給与計算部門を維持する場合のコスト(専任担当者5名から10名程度の人件費、システム開発・保守費用、オフィススペース、教育研修費など)を総合的に考えると、大幅なコスト削減と業務品質の向上を実現できます。
給与計算アウトソーシングの料金を抑える3つのポイント
給与計算アウトソーシングを導入する際、できるだけコストを抑えながら効果的なサービスを受けたいと考えるのは当然です。ここでは、料金を抑えるための具体的なポイントを解説します。
アウトソーシング先の給与計算システムを導入する
給与計算アウトソーシングの料金を抑える最も効果的な方法のひとつが、アウトソーシング先が提供する給与計算システムを導入することです。
自社独自の給与計算システムを使い続ける場合、アウトソーシング先はそのシステムに合わせた作業フローを整備する必要があり、カスタマイズ費用や運用コストが高くなります。一方、アウトソーシング先が提供するシステムを利用すれば、標準化された効率的なプロセスで処理できるため、料金を抑えられます。
アウトソーシング先のシステムは、給与計算業務に最適化されており、法改正への対応も自動的に行われます。システムの保守管理や バージョンアップもアウトソーシング先が担当するため、企業側でシステム管理の負担やコストが発生しません。
ただし、システム移行には初期設定やデータ移行の作業が必要となります。移行期間中は既存システムと並行稼働させるケースもあるため、事前に移行計画をしっかり立てることが重要です。長期的に見れば、システム統一によるコスト削減効果は大きいと言えます。
自社の企業規模に適した給与計算アウトソーシング先を選ぶ
給与計算アウトソーシングの料金を適正化するためには、自社の企業規模に合ったサービスを選ぶことが重要です。
大企業向けのフルサポート型サービスは、充実した機能とサポート体制を持っていますが、その分料金も高額になります。従業員数が少ない小規模企業がこうしたサービスを選ぶと、必要以上の機能に対して費用を支払うことになり、コストパフォーマンスが悪くなります。
逆に、従業員数が多い企業が小規模企業向けのシンプルなサービスを選ぶと、対応できる業務範囲やサポート体制が不足し、結果的に複数のサービスを併用することになり、トータルコストが高くなる可能性があります。
従業員数が50名未満の小規模企業であれば、クラウド系やスポット型の給与計算アウトソーシングが適しています。従業員数が50名から300名程度の中小企業であれば、社労士事務所の包括的なサービスが費用対効果が高いでしょう。従業員数が300名以上の大企業であれば、フルサポート型やシステム一体型のサービスが適しています。
自社の規模と課題を正確に把握し、それに見合ったサービスを選択することが、適正な料金で最大の効果を得るポイントです。
必要最低限の業務のみ給与計算アウトソーシングする
給与計算アウトソーシングの料金を抑えるもうひとつの方法は、委託する業務範囲を必要最低限に絞ることです。
給与計算アウトソーシングでは、給与計算だけでなく、勤怠管理、社会保険手続き、年末調整、住民税更新、従業員対応窓口など、さまざまなオプションサービスが用意されています。これらをすべて委託すれば便利ですが、その分料金も高くなります。
まずは自社でどの業務に最も負担を感じているか、どの業務でミスが発生しやすいかを分析し、優先順位をつけることが重要です。例えば、月次の給与計算は自社で対応できるが、年末調整だけは専門性が高く負担が大きいという場合、年末調整のみをスポット委託する選択肢があります。
また、給与計算は委託するが、勤怠管理は自社のシステムで対応するという形も考えられます。勤怠データを整理した状態でアウトソーシング先に渡すことで、委託範囲を限定し、料金を抑えられます。
ただし、業務を細かく分割しすぎると、かえって管理コストが増加したり、責任の所在が不明確になったりするリスクもあります。最初は必要最低限の業務から始め、運用状況を見ながら徐々に委託範囲を広げていくというアプローチも有効です。
自社で対応可能な業務と、専門家に任せるべき業務を明確に区別し、バランスの取れた委託範囲を設定することが、コストを抑えながら効果を最大化するポイントです。
企業規模別|給与計算アウトソーシングのタイプと選び方
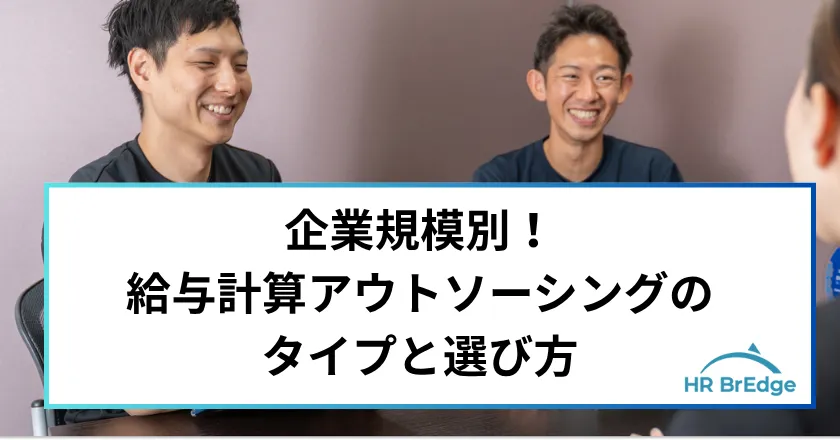
給与計算アウトソーシングを選ぶ際は、企業規模に応じて最適なサービスタイプが異なります。ここでは、企業規模別にどのようなサービスが適しているかを詳しく解説します。
大企業向けの給与計算アウトソーシング(300名以上)の特徴
従業員数が300名以上の大企業における給与計算アウトソーシングには、高度な専門性と充実したサポート体制が求められます。
大企業の場合、複数の事業所や支店を持つことが多く、拠点ごとに異なる給与体系や勤務形態があります。また、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など、多様な雇用形態が混在しており、それぞれに異なる給与計算ルールや社会保険の適用基準があります。
大企業向けの給与計算アウトソーシングでは、こうした複雑な要件に対応できる柔軟性が必要です。専任チームが配置され、企業専属の担当者が業務を統括するケースが一般的です。定期的なミーティングを通じて業務の進捗確認や改善提案を行い、企業の成長に合わせてサービス内容を最適化していきます。
また、大企業では給与計算の処理量が膨大になるため、処理能力とスピードも重要な要素です。月末の締め日から給与支給日までの期間が短い企業や、上場企業のように決算スケジュールがタイトな企業では、迅速かつ正確な処理が求められます。
セキュリティ面でも高度な対策が必要です。大企業は保有する従業員情報の量が多く、情報漏洩時の影響も甚大です。そのため、ISMS認証やプライバシーマーク、SRPⅡ認証などのセキュリティ認証を取得しているアウトソーシング先を選ぶことが重要です。
大企業向けサービスでは、BCP(事業継続計画)対応も重視されます。災害時やシステム障害時でも給与計算業務を継続できる体制が整備されており、バックアップセンターの設置や冗長化されたシステム構成によって、安定したサービス提供が保証されます。
中小企業向けの給与計算アウトソーシング(50~299名)の特徴
従業員数が50名から299名程度の中小企業における給与計算アウトソーシングは、コストパフォーマンスと柔軟性のバランスが重要です。
中小企業の多くは、管理部門の人員に余裕がなく、給与計算担当者が他の人事労務業務も兼務しているケースが一般的です。そのため、給与計算だけでなく、社会保険手続きや労務相談まで包括的にサポートしてくれるサービスが適しています。
特に社会保険労務士事務所が提供する給与計算アウトソーシングは、中小企業にとって最適な選択肢といえます。給与計算と社会保険手続きを一括して依頼できるため、手続きの連携がスムーズで、漏れやミスを防げます。また、就業規則の作成や見直し、労務トラブルの相談、助成金の申請サポートなど、人事労務全般の相談ができる点も大きなメリットです。
中小企業向けの給与計算アウトソーシングでは、企業の成長段階に合わせた柔軟な対応が求められます。従業員数が増加したり、新しい事業所を開設したり、給与体系を変更したりする際にも、スムーズに対応してくれるサービスが理想的です。
料金面では、従業員1名あたりの単価が明確で、従業員数の増減に応じて柔軟に調整できる従量課金制のサービスが使いやすいでしょう。初期費用や基本料金も大企業向けサービスと比較して抑えられており、導入のハードルが低い点も特徴です。
また、中小企業では給与計算システムを独自に導入していないケースも多いため、システム一体型の給与計算アウトソーシングも選択肢となります。システムとサービスがセットになっているため、システム選定の手間が省け、スムーズに導入できます。
小規模企業向けの給与計算アウトソーシング(1~49名)の特徴
従業員数が49名以下の小規模企業における給与計算アウトソーシングは、シンプルさとコストの低さが重視されます。
小規模企業では、経営者自身が給与計算を行っているケースや、総務担当者が他の業務と兼務しているケースが多く見られます。給与計算に多くの時間を割けないため、できるだけシンプルで分かりやすいサービスが求められます。
小規模企業向けの給与計算アウトソーシングでは、クラウド系サービスやスポット型サービスが適しています。クラウド系サービスは初期費用が安く、月額料金も抑えられているため、導入しやすい点が特徴です。また、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、テレワークにも対応できます。
スポット型サービスは、通常の給与計算は自社で対応しながら、年末調整や住民税更新など特定の業務だけを委託する形態です。必要な時に必要な分だけサービスを利用できるため、コストを最小限に抑えられます。
ただし、小規模企業でも給与計算の正確性は重要です。従業員数が少ないからといって計算ミスが許されるわけではなく、むしろ少人数だからこそ一人ひとりの給与に対する関心が高く、ミスがあると信頼を損ねる可能性があります。
また、小規模企業は成長段階にあることが多く、今後従業員数が増加する可能性も考慮する必要があります。将来的な拡張性を持ったサービスを選ぶことで、企業の成長に合わせてスムーズにサービスをスケールアップできます。
料金面では、従業員数が少ない場合、1名あたりの単価は高くなる傾向があります。そのため、基本料金が安く設定されているサービスや、小規模企業向けのパッケージプランを提供しているサービスを選ぶことで、コストを抑えられます。
システム一体型給与計算アウトソーシングが向いている企業とは?
システム一体型給与計算アウトソーシングは、給与計算システムとアウトソーシングサービスがセットになっているタイプで、特定の企業に適しています。
まず、現在使用している給与計算システムが古く、法改正への対応が遅れている企業には、システム一体型が適しています。システムの入れ替えとアウトソーシングの導入を同時に行うことで、業務フローを一から見直し、最新の体制を整備、醸成することができます。
次に、これまで給与計算をExcelなどの手作業で行っていた企業にも、システム一体型は有効です。システム化とアウトソーシングを同時に進めることで、業務の効率化と正確性の向上を一気に実現できます。システム選定の手間も省けるため、導入がスムーズに進みます。
また、勤怠管理システムや会計システムとの連携を重視する企業にも適しています。システム一体型サービスの多くは、主要な勤怠管理システムや会計システムとのデータ連携機能を標準で備えています。勤怠データを給与計算に自動連携し、給与計算データを会計仕訳に自動変換することで、手作業によるデータ入力を最小限に抑えられます。
さらに、ITリテラシーがあまり高くない企業でも、システム一体型は安心して利用できます。システムの保守管理や法改正対応はすべてアウトソーシング先が担当するため、企業側でシステムの専門知識を持つ必要がありません。操作方法についても充実したサポートが用意されています。
一方で、独自の給与体系や複雑な計算ロジックを持つ企業の場合、標準的なシステムでは対応できないケースもあります。そうした企業は、カスタマイズ性の高いシステム一体型サービスを選ぶか、既存システムをそのまま使用できるフルサポート型サービスを検討する必要があります。
失敗しない給与計算アウトソーシング会社の比較ポイント【8項目】
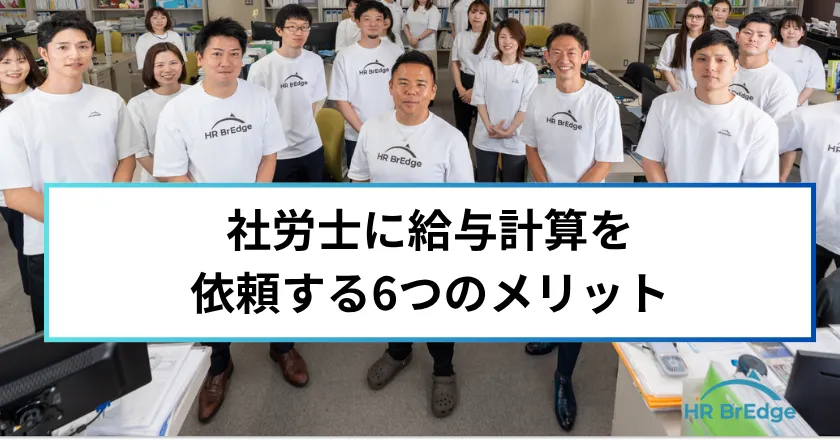
給与計算アウトソーシング会社を選ぶ際には、料金だけでなく、さまざまな観点から比較検討することが重要です。ここでは、失敗しないための8つの比較ポイントを解説します。
①対応実績と給与計算アウトソーシング導入企業数の確認
給与計算アウトソーシング会社を選ぶ際、最初に確認すべきは対応実績と導入企業数です。
豊富な実績を持つアウトソーシング会社は、さまざまな業種や企業規模の給与計算に対応してきたノウハウを蓄積しています。製造業、小売業、飲食業、IT業など、業種によって給与体系や勤務形態が異なるため、自社の業種での実績があるかを確認することが重要です。
導入企業数も重要な指標です。多くの企業に選ばれているということは、サービス品質や信頼性が高い証拠といえます。例えば、500社以上の導入実績を持つアウトソーシング会社であれば、安定したサービス提供体制が整っていると判断できます。
また、創業年数や事業継続期間も確認しましょう。長年にわたって事業を継続しているということは、顧客満足度が高く、安定した経営基盤を持っている証拠です。給与計算は毎月継続的に発生する業務であるため、長期的に安心して任せられるパートナーを選ぶことが重要です。
可能であれば、自社と同じ規模や業種の導入事例を確認し、具体的にどのような課題を解決できたのか、どのような効果が得られたのかを把握することをお勧めします。
②対応業務の範囲と柔軟性の確認
給与計算アウトソーシング会社によって、対応できる業務範囲は大きく異なります。
基本的な月次給与計算だけを対応する会社もあれば、賞与計算、年末調整、住民税更新、社会保険手続き、勤怠管理、従業員対応窓口まで包括的に対応する会社もあります。自社がどの業務を委託したいのか、将来的にどの業務まで拡大する可能性があるのかを明確にし、それに対応できるサービスを選ぶことが重要です。
また、オプションサービスの充実度も確認しましょう。当初は給与計算のみを委託するつもりでも、運用を始めてから追加で依頼したい業務が出てくることがあります。その際に柔軟に対応してもらえるかどうかは、長期的なパートナーシップにおいて重要なポイントです。
部分的な委託が可能かどうかも確認が必要です。例えば、給与計算は自社で行うが年末調整だけを委託したい、通常の給与計算は委託するが賞与計算は自社で行いたい、といったニーズに対応できるかを確認しましょう。
③自社特有の要件への対応可否の確認
企業によって給与体系や計算ルールは異なるため、自社特有の要件に対応できるかを確認することが重要です。
多くの給与計算アウトソーシング会社は、標準的な給与体系には対応できますが、特殊な手当の計算、複雑な勤務シフト制、変形労働時間制、裁量労働制など、独自の計算ロジックが必要なケースでは対応できない場合があります。
自社の給与計算に特殊な要件がある場合は、契約前に必ず詳細をアウトソーシング会社に伝え、対応可能かどうかを確認しましょう。具体的には、現在使用している給与計算のロジックや計算式、特殊な手当の内容、拠点ごとの違いなどを説明し、そのまま引き継げるか、あるいは調整が必要かを明確にします。
また、業界特有のルールにも注意が必要です。建設業の日給月給制、飲食業の深夜手当計算、医療業の宿日直手当、運送業の歩合給計算など、業種によって給与計算の考え方が異なります。自社の業種での実績があるアウトソーシング会社を選ぶことで、スムーズな対応が期待できます。
計算ロジックの変更が必要な場合でも、現行の方法を維持したまま移行できるか、それとも標準的な方法に変更する必要があるかを確認しましょう。変更が必要な場合は、従業員への説明や就業規則の改定も必要になる可能性があります。
④情報セキュリティ対策の確認(Pマーク・ISO認証・SRPⅡ認証)
給与計算では従業員の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、銀行口座、家族構成など、極めて機密性の高い個人情報を取り扱います。そのため、アウトソーシング会社のセキュリティ対策は最重要の確認ポイントです。
まず確認すべきは、第三者認証の取得状況です。プライバシーマーク(Pマーク)は、個人情報の適切な取り扱いを行っている事業者に付与される認証です。ISO27001(ISMS認証)は、情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格の認証です。これらの認証を取得している企業は、一定レベル以上のセキュリティレベルに達していると判断できます。
特に社会保険労務士事務所に給与計算を依頼する場合は、SRPⅡ認証の取得状況を確認しましょう。SRPⅡ認証は、全国社会保険労務士会連合会が運営する、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度です。マイナンバー制度に対応した厳格な安全管理措置が求められており、Pマークと同等以上の高度なセキュリティ基準をクリアした社労士事務所のみが取得できます。
認証の取得状況だけでなく、具体的なセキュリティ対策の内容も確認しましょう。データの暗号化、アクセス権限の管理、入退室管理、監視カメラの設置、セキュリティ研修の実施など、多層的な対策が講じられているかを確認します。
また、データの保管場所や保管期間、廃棄方法についても確認が必要です。クラウドサービスを利用している場合は、データセンターの所在地やセキュリティレベルも重要なポイントです。
⑤申請方法のWeb対応の有無の確認
給与計算アウトソーシングを効率的に活用するためには、申請方法のWeb対応状況を確認することが重要です。
従来型のアウトソーシングでは、従業員からの住所変更や扶養家族の変更などの申請を、紙の書類で人事部門に提出し、人事部門がそれをアウトソーシング会社に送付するという流れでした。この方法では、書類の授受に時間がかかり、紛失のリスクもあります。
Web対応しているサービスでは、従業員がスマートフォンやパソコンから直接情報を入力でき、人事部門を介さずにアウトソーシング会社に情報が届きます。これにより、申請から処理完了までの時間が大幅に短縮され、書類の管理コストも削減できます。
特に申請量が多い企業や、複数の拠点を持つ企業では、Web対応の有無が業務効率に大きく影響します。本社と支店の間で書類をやり取りする手間が省け、リアルタイムでの情報更新が可能になります。
また、給与明細のWeb配信機能も確認しましょう。紙の給与明細を廃止してWeb明細に移行することで、印刷コスト、封入作業、配布作業などが不要になり、ペーパーレス化を推進できます。従業員も過去の給与明細をいつでも確認できるため、利便性が向上します。
年末調整のWeb対応も重要です。従業員がオンラインで保険料控除などの情報を入力できるシステムがあれば、紙の書類の回収や確認作業が大幅に削減され、年末調整業務の効率化につながります。
⑥従業員対応窓口の有無の確認
給与や手続きに関する従業員からの問い合わせに、アウトソーシング会社が直接対応してくれるかどうかも重要なポイントです。
従業員対応窓口がない場合、給与明細の見方、控除項目の内容、年末調整の書類の書き方などの質問は、すべて人事部門が対応しなければなりません。従業員数が多い企業では、こうした問い合わせだけで相当な時間を取られることになります。
従業員対応窓口を設けているアウトソーシング会社では、従業員が直接問い合わせできる専用の電話番号やメールアドレス、チャット機能などが用意されています。給与計算の専門スタッフが対応するため、正確で迅速な回答が得られ、従業員の満足度も向上します。
人事部門にとっても、定型的な質問対応から解放されることで、より戦略的な業務に時間を割けるようになります。特に、年末調整の時期や住民税更新の時期など、問い合わせが集中する時期には、この窓口の有無が業務負荷に大きく影響します。
従業員対応窓口の対応時間や対応方法(電話、メール、チャットなど)、対応言語(外国人従業員が多い場合)なども確認しておくと安心です。
⑦対応スピードと納品スケジュールの柔軟性の確認
給与計算アウトソーシングでは、データの提出から給与明細の納品までの期間、つまり対応スピードが業務に大きく影響します。
一般的なアウトソーシング会社では、勤怠データを締め日の翌営業日に提出し、3営業日から5営業日後に給与明細や振込データが納品されるスケジュールが標準的です。しかし、企業によっては、月末締め翌月3日払いなど、タイトなスケジュールで給与を支給しているケースもあります。
こうした企業では、データ受領から2営業日での納品が可能など、柔軟な対応ができるアウトソーシング会社を選ぶ必要があります。特に上場企業では、決算スケジュールの関係で給与支給日を前倒しできないケースもあり、対応スピードが重要な選定基準となります。
また、納品スケジュールの柔軟性も確認しましょう。通常は標準スケジュールで問題なくても、年度末や決算期などで特別に早めの納品が必要になる場合があります。そうした臨時の要望にも対応してもらえるかを確認しておくと安心です。
さらに、急な追加・変更依頼への対応力も重要です。給与計算の締め後に遡及修正が必要になったり、急遽退職者が発生したりするケースもあります。こうした突発的な事態にも迅速に対応してくれる体制があるかを確認しましょう。
問い合わせへの回答スピードも業務効率に影響します。メールや電話での問い合わせに対して、当日または翌営業日に回答してもらえるか、緊急時の連絡体制はどうなっているかなども確認ポイントです。
⑧料金とコストパフォーマンスの確認
給与計算アウトソーシングを選ぶ際、料金は重要な判断基準ですが、単純に安いサービスを選べば良いというわけではありません。料金とサービス内容のバランス、つまりコストパフォーマンスを総合的に評価することが重要です。
まず、料金体系の透明性を確認しましょう。基本料金、従業員1名あたりの単価、オプション料金、初期費用などが明確に提示されているか、追加料金が発生する条件は何かを確認します。見積もり時には、年間のトータルコスト(月額料金×12ヶ月+年末調整費用+住民税更新費用など)を計算し、予算内に収まるかを確認しましょう。
料金だけでなく、その料金で受けられるサービスの内容と品質を評価することが重要です。専任担当者が付くか、対応業務の範囲はどこまでか、サポート体制は充実しているか、セキュリティ対策は万全かなど、総合的に判断します。
安価なサービスを選んだ結果、対応範囲が狭く追加費用が頻繁に発生したり、サポートが不十分で社内の負担が減らなかったりするケースもあります。逆に、高額なサービスでも、自社には不要な機能が多く含まれていて、コストに見合った効果が得られないケースもあります。
自社で給与計算を行う場合のコスト(担当者の人件費、システム費用、教育コスト、ミスによるリスクコストなど)と比較し、アウトソーシングによってどれだけコスト削減や業務効率化が実現できるかを具体的に試算することをお勧めします。
また、複数の給与計算アウトソーシング会社から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討することも重要です。ただし、最も安い会社を選ぶのではなく、自社のニーズに最も合致し、長期的に安心して任せられるパートナーを選ぶという視点を持ちましょう。
給与計算アウトソーシングを検討する目安
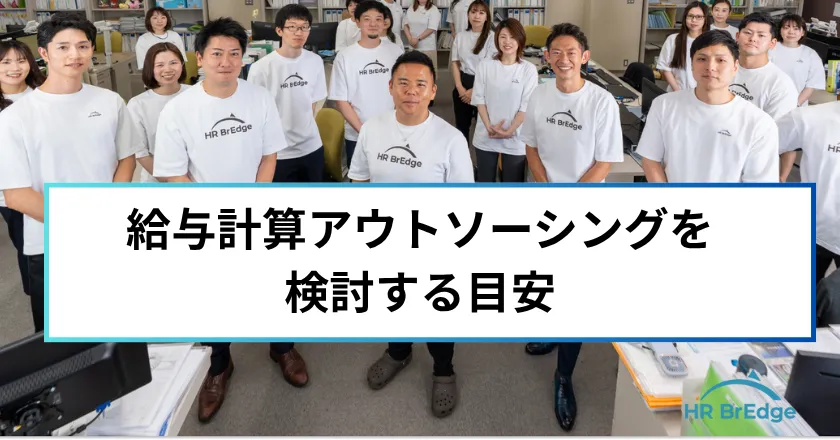
給与計算アウトソーシングは多くのメリットがありますが、すべての企業に適しているわけではありません。ここでは、アウトソーシングを検討すべき企業の目安を解説します。
従業員数が10名以上~数百名の企業における給与計算アウトソーシング
給与計算アウトソーシングが最も効果を発揮するのは、従業員数が10名以上から数百名程度の企業です。
従業員数が10名未満の小規模企業の場合、給与計算をExcelで管理したり、会計ソフトの給与機能を使ったりすることで、比較的簡単に自社で対応できます。アウトソーシングの費用対効果が見込めないケースも多いため、まずは自社での対応を検討することをお勧めします。
一方、従業員数が10名を超えてくると、給与計算の複雑さが増し、担当者の負担も大きくなります。社会保険の加入・脱退手続きも頻繁に発生し始め、年末調整の作業量も無視できないレベルになります。この段階でアウトソーシングを検討することで、業務効率化とコスト削減の両方を実現できます。
従業員数が50名を超えると、給与計算は専門的な業務となり、担当者の専門知識や経験が重要になります。計算ミスや手続き漏れのリスクも高まるため、専門家にアウトソーシングすることで、業務品質の向上とリスク軽減が期待できます。
従業員数が100名以上になると、給与計算部門として独立した体制が必要になりますが、複数名の担当者を配置するコストと比較すると、アウトソーシングの方が費用対効果が高いケースが多くなります。
従業員数が数百名を超える大企業でも、アウトソーシングは有効です。社内で給与計算部門を維持するコストや、システム開発・保守のコスト、法改正対応のコストなどを総合的に考えると、アウトソーシングによってトータルコストを削減できる可能性があります。
正確に給与計算を行いたい企業における給与計算アウトソーシング
給与計算の正確性を重視する企業にとって、アウトソーシングは有効な選択肢です。
給与計算は、従業員の生活に直結する重要な業務であり、ミスは許されません。計算ミスがあると、従業員からの信頼を失うだけでなく、修正作業にも多大な時間とコストがかかります。また、社会保険料や税金の計算ミスは、行政への届出内容にも影響し、後々大きな問題に発展する可能性があります。
給与計算アウトソーシングでは、専門知識を持ったスタッフが給与計算を行い、複数名でのダブルチェック体制を取っているケースが一般的です。また、最新の給与計算システムを使用しているため、計算ミスのリスクを大幅に軽減できます。
特に法改正への対応は、専門家でなければ正確に把握することが難しい場合があります。社会保険料率の変更、雇用保険料率の改定、所得税の税率変更、最低賃金の改定など、毎年のように法改正が行われます。こうした変更を見逃すと、計算ミスにつながります。
アウトソーシング会社は、法改正の情報を常にキャッチアップし、システムにも自動的に反映されるため、企業側で法改正を追いかける必要がありません。正確な給与計算を維持しながら、担当者の負担を軽減できます。
また、社内の担当者が退職や休職した場合でも、アウトソーシングを利用していれば業務が滞ることはありません。属人化のリスクを回避し、安定的に給与計算を行える体制を、整えることができます。
人事担当者の業務負担を軽減したい企業における給与計算アウトソーシング
人事担当者の業務負担が過大になっている企業にとって、給与計算アウトソーシングは効果的な解決策となります。
多くの中小企業では、人事担当者が給与計算だけでなく、採用活動、研修企画、労務管理、社会保険手続き、勤怠管理など、多岐にわたる業務を兼務しています。特に給与計算は毎月必ず発生する業務であり、締め日から支給日までの限られた期間に集中して作業を行う必要があるため、他の業務を圧迫する要因となります。
給与計算業務は正確性が求められる一方で、基本的には定型的な作業の繰り返しです。こうしたルーチンワークに多くの時間を割くことで、本来注力すべき戦略的な人事業務に時間を使えないという課題を抱える企業は少なくありません。
給与計算をアウトソーシングすることで、人事担当者は採用戦略の立案、人材育成プログラムの開発、人事評価制度の改善、従業員エンゲージメントの向上など、企業の成長に直結するコア業務に集中できるようになります。給与計算にかけていた時間を、より付加価値の高い業務にシフトすることで、人事部門全体の生産性が向上します。
また、給与計算の時期は月末から月初にかけての繁忙期となり、残業が発生しやすい時期でもあります。アウトソーシングによってこの繁忙期の業務負担を軽減できれば、担当者のワークライフバランスの改善にもつながります。
さらに、給与計算担当者が1名しかいない企業では、その担当者が休暇を取りづらい、退職時の引き継ぎが困難といった問題も発生します。アウトソーシングを活用することで、こうした属人化のリスクを解消し、安定した業務体制を構築できます。
法改正対応に不安がある企業における給与計算アウトソーシング
労働法規や税制の改正に対応することに不安を感じている企業にとって、給与計算アウトソーシングは心強い味方となります。
給与計算に関連する法律は複雑で、しかも頻繁に改正されます。労働基準法、最低賃金法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、所得税法、住民税など、複数の法律が給与計算に関係しており、それぞれが独立して改正されます。
例えば、社会保険料率は毎年3月に変更され、雇用保険料率も数年ごとに改定されます。最低賃金は都道府県ごとに毎年10月頃に改定され、所得税の扶養控除の要件や税率も変更されることがあります。こうした変更を漏れなく把握し、給与計算に正確に反映させることは、専門知識がないと非常に困難です。
自社で給与計算を行っている場合、法改正の情報を収集し、内容を理解し、給与計算システムの設定を変更し、計算ロジックを修正するという一連の作業をすべて担当者が行わなければなりません。法改正の内容を誤って理解したり、システムの設定ミスがあったりすると、給与計算ミスにつながり、従業員への不利益や行政からの指摘を受けるリスクがあります。
給与計算アウトソーシングを利用すれば、こうした法改正への対応はすべて専門家が担当します。アウトソーシング会社は法改正の情報を常に監視しており、改正内容を正確に把握しています。また、使用している給与計算システムも法改正に合わせて自動的にアップデートされるため、企業側で特別な対応を行う必要がありません。
特に社会保険労務士事務所にアウトソーシングする場合、労働法規や社会保険制度の専門家である社労士が対応するため、法改正への対応はもちろん、改正内容が自社にどのような影響を与えるか、どのような準備が必要かといったアドバイスも受けられます。
法改正対応の不安から解放され、常に最新の法令に準拠した正確な給与計算を維持できることは、給与計算アウトソーシングの大きなメリットのひとつです。
給与計算アウトソーシングのメリット7選
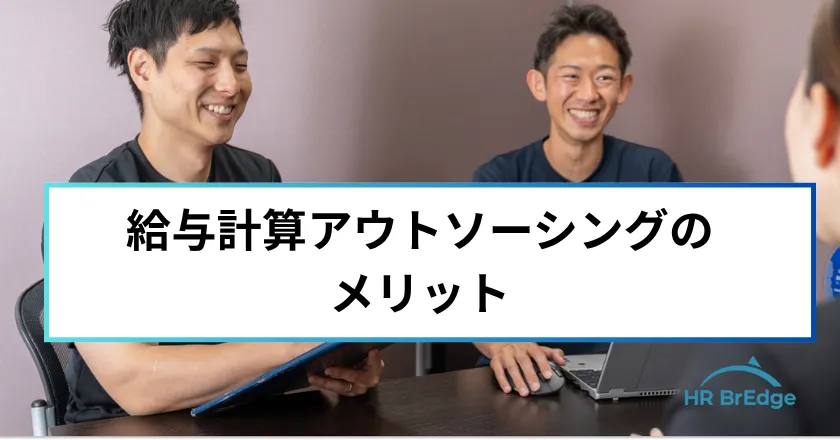
給与計算アウトソーシングを導入することで、企業はさまざまなメリットを享受できます。ここでは、主要な7つのメリットについて詳しく解説します。
トータルコストの削減(人件費・システム費用)
給与計算アウトソーシングの最も大きなメリットのひとつが、トータルコストの削減です。
給与計算を自社で行う場合、専任担当者の人件費が必要です。従業員数が50名程度の企業でも、給与計算担当者として1名分の人件費(年間400万円から600万円程度)が発生します。従業員数が100名を超えると、複数名の担当者が必要となり、人件費はさらに増加します。
さらに、給与計算システムの導入費用やライセンス費用、保守費用も必要です。システムの初期導入には数十万円から数百万円のコストがかかり、年間の保守費用も発生します。法改正への対応でシステムのバージョンアップが必要になる場合、追加費用が発生することもあります。
担当者の教育コストも見逃せません。給与計算には専門知識が必要であり、新しい担当者を育成するには時間とコストがかかります。また、法改正や制度変更があるたびに、担当者は最新情報を学習する必要があり、継続的な教育コストが発生します。
給与計算アウトソーシングを利用すれば、これらのコストを大幅に削減できます。従業員100名規模の企業で月額16万円程度、年間200万円程度のコストで、給与計算業務のすべてを委託できます。専任担当者を雇用するコストと比較すると、半分以下に抑えられるケースも少なくありません。
また、システム費用もアウトソーシング料金に含まれているため、別途システムを購入・保守する必要がありません。法改正への対応もアウトソーシング会社が担当するため、システムのバージョンアップ費用や担当者の学習コストも不要です。
さらに、給与計算ミスによる修正作業のコストや、手続き遅延による罰則金のリスクも軽減されます。長期的に見れば、トータルコストの削減効果は非常に大きいと言えます。
担当者が給与計算以外のコア業務に専念できる
給与計算アウトソーシングを導入することで、人事担当者は本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになります。
給与計算は重要な業務ですが、企業の利益に直接貢献するものではありません。毎月決まった時期に必ず発生するルーチンワークであり、正確に処理することが求められますが、創造性や戦略性を発揮する余地は少ない業務です。
一方、人事部門には、企業の成長に直結する重要な役割があります。優秀な人材の採用、従業員の能力開発、人事評価制度の構築と運用、組織風土の改善、従業員エンゲージメントの向上、労務リスクの予防など、戦略的かつ創造的な業務が多数あります。
給与計算に多くの時間を取られることで、こうしたコア業務に十分な時間を割けないという課題を抱える企業は少なくありません。特に月末から月初にかけての給与計算の時期は、他の業務が後回しになりがちです。
給与計算をアウトソーシングすることで、人事担当者は給与計算から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。採用活動に時間をかけて優秀な人材を獲得したり、従業員の育成プログラムを充実させたり、働きやすい職場環境を整備したりすることで、企業の競争力強化に貢献できます。
また、経営層から人事戦略の立案を求められた際にも、給与計算に追われることなく、しっかりと時間をかけて戦略を練ることができます。人事部門が本来の役割を果たせるようになることで、企業全体の生産性向上につながります。
法令改正への迅速な対応
給与計算アウトソーシングのメリットとして、法令改正への迅速かつ正確な対応が挙げられます。
給与計算に関連する法律は複雑で、しかも頻繁に改正されます。2020年には新型コロナウイルス対応として雇用調整助成金の特例措置が設けられ、わずか2ヶ月間で法規制に関する通達が380%増加し、900件もの新たな法規制が作られました。このような急激な変化に自社だけで対応することは非常に困難です。
給与計算アウトソーシング会社は、法令改正の情報を専門的に収集・分析する体制を持っています。労働法規や税制の改正があれば、いち早く情報をキャッチし、内容を正確に理解し、給与計算への影響を分析します。そして、使用している給与計算システムに改正内容を反映させ、正確な計算ができる体制を整えます。
企業側では、法令改正の詳細を追いかける必要がなく、アウトソーシング会社から必要な情報の提供や対応の案内を受けるだけで済みます。法改正への対応が自動的に行われるため、改正内容を誤解したり、対応が遅れたりするリスクがありません。
特に社会保険労務士事務所にアウトソーシングする場合、労働法規の専門家である社労士が法令改正の内容を分析し、自社にどのような影響があるか、どのような準備や対応が必要かを具体的にアドバイスしてくれます。就業規則の変更が必要な場合や、従業員への説明が必要な場合も、適切なサポートを受けられます。
法令改正への対応を専門家に任せることで、コンプライアンスリスクを大幅に軽減でき、安心して事業運営に集中できます。
給与計算ミスのリスク軽減と専門家の品質
給与計算アウトソーシングを利用することで、給与計算ミスのリスクを大幅に軽減できます。
給与計算は複雑な計算が多く、人為的なミスが発生しやすい業務です。基本給の計算、残業代の計算、各種手当の加算、社会保険料の控除、所得税の計算、住民税の控除など、多くの計算項目があり、それぞれに異なる計算ルールがあります。
自社で給与計算を行う場合、担当者の疲労や集中力の低下、知識不足、確認不足などにより、計算ミスが発生する可能性があります。給与計算ミスは従業員の生活に直接影響するため、信頼を損ねる要因となります。また、修正作業にも多大な時間とコストがかかります。
給与計算アウトソーシング会社では、給与計算の専門スタッフが業務を担当します。豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、最新の給与計算システムを使用して正確に計算を行います。多くのアウトソーシング会社では、計算結果を複数名でダブルチェックする体制を構築しており、ミスを防ぐ仕組みが整っています。
また、アウトソーシング会社は年間を通じて大量の給与計算を処理しているため、さまざまなケースに対応するノウハウを蓄積しています。特殊な計算や複雑な事例にも適切に対応できる経験値があります。
万が一ミスが発生した場合でも、アウトソーシング会社が責任を持って修正対応を行います。契約内容によっては、ミスによって生じた損害を補償する保険に加入しているケースもあり、企業側のリスクを最小限に抑えられます。
専門家の高品質なサービスを利用することで、給与計算の正確性を維持しながら、ミスによるリスクを大幅に軽減できます。
業務の属人化防止
給与計算アウトソーシングを導入することで、給与計算業務の属人化を防ぐことができます。
多くの企業では、給与計算を特定の担当者だけが行っており、その担当者だけが業務の詳細を把握しているという状況が見られます。こうした属人化は、担当者が休暇を取る際や、退職・異動する際に大きな問題となります。
給与計算担当者が長期休暇を取る場合、代わりに給与計算を行える人がいないため、担当者は休暇を取りづらくなります。また、病気や家庭の事情で急に休まなければならない場合、給与計算が滞ってしまい、従業員への給与支払いに影響が出るリスクがあります。
担当者が退職する場合は、さらに深刻な問題となります。給与計算の知識やノウハウは一朝一夕で身につくものではなく、後任者への引き継ぎには相当な時間がかかります。引き継ぎが不十分な状態で担当者が退職してしまうと、給与計算の方法や特殊なルールが分からなくなり、業務が混乱する可能性があります。
給与計算をアウトソーシングすることで、こうした属人化のリスクを完全に解消できます。アウトソーシング会社では、組織として給与計算業務を担当するため、特定の個人に依存することがありません。担当者が変わっても、業務の継続性は確保されます。
また、給与計算のルールや手順は、アウトソーシング会社のシステムやマニュアルに明文化されているため、ノウハウが失われる心配もありません。自社の給与体系や計算ロジックは、アウトソーシング会社がしっかりと記録・管理してくれます。
さらに、企業側の人事担当者が交代する場合でも、アウトソーシング会社が業務の引き継ぎをサポートしてくれるため、スムーズな引き継ぎが可能です。新しい担当者が着任した際には、業務の流れや連絡方法を丁寧に説明してもらえます。
属人化を防ぐことで、安定的かつ継続的に給与計算業務を運営できる体制を構築できます。
繁閑期の業務量変動への対応と社内リソースの最適化
給与計算アウトソーシングを活用することで、繁閑期の業務量変動に柔軟に対応でき、社内リソースを最適化できます。
給与計算業務は、月次の通常業務に加えて、年末調整(11月~1月)、算定基礎届(7月)、労働保険の年度更新(6月~7月)、住民税更新(5月~6月)など、特定の時期に集中する業務があります。これらの時期は、人事担当者の業務負荷が一気に高まり、残業や休日出勤が発生することも少なくありません。
特に年末調整は、従業員全員から書類を回収し、内容を確認し、計算を行い、源泉徴収票を発行するという膨大な作業が必要です。従業員数が多い企業では、この時期だけで通常業務の数倍の作業量となり、他の業務が完全に停滞してしまうケースもあります。
自社で給与計算を行う場合、こうした繁忙期に対応するために、通常は不要な人員を配置しておく必要があったり、他部署からの応援を要請したりする必要があります。しかし、年間を通じて見れば、繁忙期は限られた期間であり、その期間のために人員を確保しておくことは非効率です。
給与計算アウトソーシングを利用すれば、繁閑期の業務量変動を吸収してもらえます。アウトソーシング会社は、年末調整や住民税更新などの季節業務も含めて対応する体制を持っており、繁忙期でも安定したサービスを提供します。企業側では、繁忙期のために特別な人員配置を行う必要がありません。
また、従業員数の増減にも柔軟に対応できます。事業拡大により従業員が増加した場合でも、アウトソーシング会社は追加の従業員分の給与計算を問題なく処理します。逆に、事業縮小により従業員が減少した場合は、料金も従業員数に応じて減額されるため、無駄なコストが発生しません。
社内リソースを繁閑期の変動に左右されずに最適化できることで、人事部門の生産性が向上し、より効率的な組織運営が可能になります。
勤務時間管理の徹底
給与計算アウトソーシングを導入することで、勤務時間管理の徹底にもつながります。
給与計算を正確に行うためには、勤怠データが正確である必要があります。出勤時刻、退勤時刻、休憩時間、残業時間、休日出勤などを正確に記録し、集計しなければなりません。
自社で給与計算を行っている場合、勤怠管理が曖昧でも、担当者が経験と勘で給与計算を行ってしまうケースがあります。タイムカードの打刻漏れがあっても、本人に確認せずに前日と同じ時間で計算したり、残業時間の計算が正確でなくても慣例的な方法で処理したりすることがあります。
しかし、給与計算アウトソーシングを利用する場合、勤怠データを正確に整備して提出する必要があります。アウトソーシング会社は、提供されたデータに基づいて給与計算を行うため、データに不備があれば確認の連絡が入ります。
この仕組みにより、企業は勤怠管理を正確に行う必要性を認識し、勤怠管理システムの導入や運用ルールの整備を進めるようになります。結果として、労働時間の管理が徹底され、労働基準法の遵守にもつながります。
また、アウトソーシング会社から勤怠管理に関するアドバイスを受けることもできます。労働時間の集計方法、残業時間の計算ルール、有給休暇の管理方法など、適切な勤怠管理の方法を提案してもらえます。
特に、働き方改革関連法により、労働時間の上限規制や有給休暇の取得義務化が強化されています。これらの法令を遵守するためには、正確な勤怠管理が不可欠です。給与計算アウトソーシングを通じて勤怠管理を徹底することで、コンプライアンスリスクを軽減できます。
勤務時間管理が徹底されることで、従業員の健康管理や労働環境の改善にもつながり、企業全体の労務管理レベルが向上します。
給与計算アウトソーシングのデメリットと対策
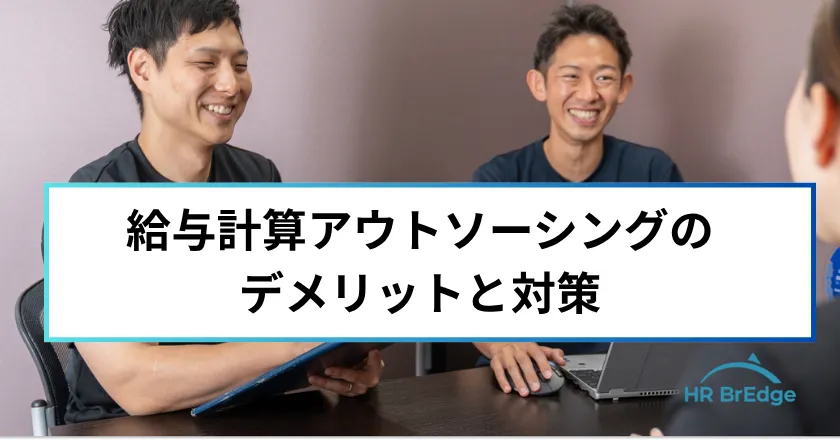
給与計算アウトソーシングには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。ここでは、主要なデメリットとその対策について解説します。
社内ノウハウが蓄積されにくい
給与計算アウトソーシングの最も大きなデメリットのひとつが、社内にノウハウが蓄積されにくくなることです。
給与計算業務を完全に外部に委託すると、社内に給与計算の専門知識を持つ人材がいなくなります。給与の仕組み、社会保険料の計算方法、税金の控除ルール、法改正の内容など、給与計算に関する知識が社内に残らなくなります。
将来的にアウトソーシングを終了して内製化する場合や、アウトソーシング会社を変更する場合に、社内にノウハウがないと移行が困難になる可能性があります。また、従業員から給与に関する質問を受けた際に、人事担当者が即座に回答できないという問題も発生します。
【対策】給与計算業務をすべて丸投げするのではなく、定期的にアウトソーシング会社から報告を受け、給与計算の流れや変更点を把握しておくことが重要です。月次の給与計算結果のレビューや、年末調整の進捗確認などを通じて、最低限の知識は維持するようにしましょう。
また、アウトソーシング会社との定期ミーティングを設定し、法改正の内容や給与計算のポイントについて説明を受けることも有効です。多くのアウトソーシング会社では、顧客企業の担当者向けに勉強会やセミナーを開催しているため、こうした機会を活用して知識を維持できます。
さらに、業務マニュアルやフローチャートを整備してもらい、自社でも保管しておくことで、いざという時に参照できる体制を作っておくことが推奨されます。
一部業務負担が残存する
給与計算アウトソーシングを導入しても、すべての業務がなくなるわけではなく、一部の業務負担は残ります。
アウトソーシング会社が給与計算を行うためには、企業側から勤怠データや人事異動情報、手当の変更情報などを提供する必要があります。これらのデータを整理し、決められた期日までにアウトソーシング会社に提出する作業は、企業側で行わなければなりません。
また、アウトソーシング会社から納品された給与明細や振込データを確認し、従業員へ配布したり、銀行へ振込依頼を行ったりする作業も必要です。給与に関する従業員からの問い合わせに対応する業務も、完全になくなるわけではありません。
特に、従業員からの個別の相談や、急な変更依頼などは、企業側で一次対応を行う必要があります。アウトソーシング会社はデータに基づいて計算を行うため、データ以外の情報や背景事情は企業側でしか把握できません。
【対策】業務負担を最小限に抑えるためには、勤怠管理システムとアウトソーシング会社のシステムを連携させ、データの受け渡しを自動化することが有効です。手作業でのデータ作成や入力を減らすことで、業務負担を大幅に削減できます。
また、従業員対応窓口を設けているアウトソーシングサービスを選ぶことで、従業員からの問い合わせ対応の負担も軽減できます。従業員が直接アウトソーシング会社に問い合わせできる体制があれば、人事部門の負担は最小限に抑えられます。
さらに、業務フローを明確にし、企業側とアウトソーシング会社の役割分担を文書化しておくことで、混乱を防ぎ、効率的な運用が可能になります。
データ漏洩のリスク
給与計算アウトソーシングでは、従業員の個人情報や給与情報を外部に提供することになるため、データ漏洩のリスクが懸念されます。
給与計算には、従業員の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、銀行口座、家族構成、給与額など、極めて機密性の高い情報が含まれます。これらの情報が外部に漏洩した場合、従業員に多大な迷惑をかけるだけでなく、企業の信頼も大きく損なわれます。
また、個人情報保護法やマイナンバー法に違反した場合、企業は法的責任を問われ、罰則を受ける可能性もあります。情報漏洩による損害賠償請求や、社会的信用の失墜など、企業にとって重大なリスクとなります。
【対策】データ漏洩のリスクを最小限に抑えるためには、セキュリティ対策が万全なアウトソーシング会社を選ぶことが最も重要です。プライバシーマーク(Pマーク)、ISO27001(ISMS認証)、SRPⅡ認証などのセキュリティ認証を取得している会社を選びましょう。
特に社会保険労務士事務所にアウトソーシングする場合、SRPⅡ認証の取得状況を確認することが推奨されます。SRPⅡ認証は、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度であり、マイナンバー制度に対応した厳格な安全管理措置が求められています。この認証を取得している社労士事務所は、業界最高水準のセキュリティ対策を講じていると判断できます。
契約時には、機密保持契約(NDA)をしっかりと締結し、データの取り扱い方法、保管場所、保管期間、廃棄方法などを明確に定めておくことも重要です。また、定期的にセキュリティ監査を実施し、適切に管理されているかを確認する体制を作ることも推奨されます。
万が一情報漏洩が発生した場合の対応手順や責任の所在についても、契約書に明記しておくことで、リスクを最小限に抑えられます。
コミュニケーションコストの発生
給与計算アウトソーシングを利用する場合、アウトソーシング会社とのコミュニケーションに一定のコストが発生します。
社内で給与計算を行っている場合は、担当者に直接口頭で伝えればすぐに対応できますが、アウトソーシングを利用する場合は、メールや電話で情報を伝え、確認のやり取りを行う必要があります。情報の伝達に時間がかかったり、意図が正確に伝わらなかったりするケースもあります。
また、急な変更や追加依頼が発生した場合、すでに締め切りを過ぎていて対応できないケースや、追加料金が発生するケースもあります。社内であれば柔軟に対応できることでも、外部委託の場合は契約内容や業務フローに沿った対応となるため、制約が生じることがあります。
【対策】コミュニケーションコストを最小限に抑えるためには、定期的なミーティングを設定し、スケジュールや業務フローを明確にしておくことが重要です。月次の給与計算のスケジュール、データ提出の期限、納品日などを事前に合意し、共有しておくことで、スムーズな連携が可能になります。
また、専任の担当者を配置しているアウトソーシング会社を選ぶことで、コミュニケーションの効率が向上します。同じ担当者と継続的にやり取りすることで、企業の状況や特性を理解してもらいやすくなり、意思疎通もスムーズになります。
さらに、よくある質問や変更パターンをマニュアル化し、標準的な対応方法を確立しておくことで、都度確認する手間を省けます。クラウドシステムを活用して情報共有を効率化することも有効です。
小規模企業では割高になる可能性
従業員数が少ない小規模企業の場合、給与計算アウトソーシングを利用すると、かえってコストが高くなる可能性があります。
給与計算アウトソーシングの料金体系では、基本料金に加えて従業員1名あたりの単価が設定されるケースが一般的です。従業員数が多い企業では、スケールメリットにより1名あたりの単価が下がりますが、従業員数が少ない企業では単価が高めに設定されることが多く、費用対効果が見込めない場合があります。
例えば、従業員5名の企業で給与計算アウトソーシングを利用する場合、基本料金が月額3万円、従業員1名あたり1,000円とすると、月額3万5,000円、年間42万円のコストとなります。この規模の企業であれば、クラウド型の給与計算ソフトを利用して自社で給与計算を行う方が、コストを抑えられる可能性があります。
また、小規模企業では給与体系がシンプルなケースが多く、給与計算の複雑さもそれほど高くありません。経営者や総務担当者が給与計算ソフトを使用すれば、比較的簡単に給与計算を行えるため、わざわざアウトソーシングを利用する必要性が低いとも言えます。
【対策】小規模企業がアウトソーシングを検討する場合は、まず自社で給与計算を行うコストとアウトソーシングのコストを詳細に比較することが重要です。単純な料金比較だけでなく、担当者の時間コスト、ミスのリスク、法改正対応の負担なども考慮に入れて、総合的に判断しましょう。
また、月次の給与計算は自社で対応し、年末調整や住民税更新などの特定業務だけをスポット委託するという方法も検討できます。これにより、コストを抑えながら、負担の大きい業務だけを専門家に任せることができます。
さらに、小規模企業向けの料金プランを提供しているアウトソーシング会社を探すことも有効です。従業員数が少ない企業に特化したサービスでは、基本料金を低く設定していることがあります。
将来的な事業拡大を見据えている場合は、早い段階でアウトソーシングを導入し、企業の成長に合わせてスムーズにスケールアップできる体制を整えておくという考え方もあります。
各デメリットへの具体的な対処法まとめ
給与計算アウトソーシングのデメリットは、適切な対策を講じることで最小限に抑えることができます。
社内ノウハウの蓄積については、完全に業務を委託するのではなく、定期的な報告やミーティングを通じて最低限の知識を維持することが重要です。アウトソーシング会社を教育パートナーとして活用し、担当者のスキルアップにもつなげられます。
一部業務負担の残存については、システム連携やWeb対応を活用して、データの受け渡しや申請手続きを自動化・効率化することで対応できます。従業員対応窓口を設けているサービスを選ぶことも有効です。
データ漏洩リスクについては、セキュリティ認証を取得している信頼できるアウトソーシング会社を選び、機密保持契約をしっかり締結することで対策できます。特にSRPⅡ認証を取得している社労士事務所は、マイナンバーを含む個人情報の管理に関して最高水準の対策を講じています。
コミュニケーションコストについては、定期ミーティングの設定や専任担当者の配置により、効率的な連携体制を構築できます。業務フローやスケジュールを明確にし、標準化することで、都度確認する手間を省けます。
小規模企業のコスト問題については、費用対効果を総合的に評価し、必要に応じてスポット委託を活用するなど、柔軟な利用方法を検討することが解決策となります。
これらの対策を適切に実施することで、デメリットを最小限に抑えながら、給与計算アウトソーシングのメリットを最大限に享受できます。
給与計算アウトソーシングに関するよくあるトラブルとその対処法
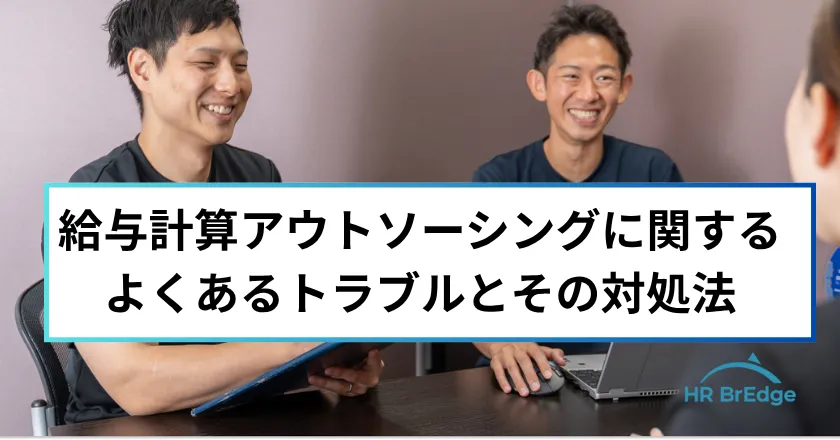
給与計算アウトソーシングを導入する際、いくつかのトラブルが発生することがあります。ここでは、よくあるトラブルとその対処法について解説します。
想定外の追加費用が発生した
給与計算アウトソーシングでよくあるトラブルのひとつが、契約時に想定していなかった追加費用が発生するケースです。
基本料金と従業員1名あたりの単価だけを確認して契約したところ、年末調整や住民税更新、賞与計算などが別料金だったというケースがあります。また、従業員の入退社が多い企業では、その都度手続き費用が発生し、予想以上のコストになることもあります。
さらに、給与計算の修正や遡及計算、特殊な手当の追加、カスタマイズ対応などが追加料金の対象となり、毎月のように追加費用が発生してしまうケースもあります。
【対処法】契約前に、料金体系を詳細に確認することが最も重要です。月額の基本料金だけでなく、年末調整、住民税更新、賞与計算、社会保険手続き、従業員の入退社対応など、年間を通じて発生する可能性のある業務について、それぞれ料金がかかるのか、基本料金に含まれているのかを明確にしましょう。
見積もりを依頼する際は、自社の従業員数、給与体系、年間の入退社数、支店の有無、特殊な手当の有無などを正確に伝え、年間のトータルコストを算出してもらうことが重要です。月額料金だけでなく、年間コストで比較することで、より正確な判断ができます。
また、契約書や重要事項説明書を入念にチェックし、どのような場合に追加料金が発生するのかを把握しておきましょう。不明な点があれば、契約前に必ず質問して明確にしておくことが重要です。
対応スピードが遅い・柔軟性に欠ける
給与計算アウトソーシングを利用し始めてから、対応スピードが遅かったり、急な変更に対応してもらえなかったりするトラブルもあります。
データを提出してから給与明細の納品までに予想以上の日数がかかり、給与支給日に間に合わないケースや、問い合わせへの回答が遅く、必要な情報がタイムリーに得られないケースがあります。また、急な人事異動や給与変更に対して、柔軟に対応してもらえず、業務に支障が出ることもあります。
標準的なサービスメニュー以外の対応を依頼すると、「対応できない」「追加料金が発生する」「時間がかかる」と言われてしまい、期待していたサポートが受けられないというケースもあります。
【対処法】契約前に、標準的な処理スケジュール(データ提出から納品までの日数)を確認し、自社の給与支給スケジュールに合うかを検証することが重要です。タイトなスケジュールが必要な場合は、短納期対応が可能なアウトソーシング会社を選びましょう。
問い合わせへの回答時間についても事前に確認しておくことが推奨されます。当日または翌営業日に回答してもらえるか、緊急時の連絡体制はどうなっているかを確認しましょう。
また、自社の業務の特性(急な変更が多い、特殊な計算が必要など)を契約前にアウトソーシング会社に伝え、対応可能かどうかを確認することも重要です。柔軟な対応を重視する場合は、カスタマイズ対応に強いアウトソーシング会社や、専任担当者が付くサービスを選ぶことが推奨されます。
定期的なミーティングを設定し、対応状況や課題を共有することで、サービス品質の改善を図ることも有効です。
自社の計算ロジックに対応してもらえない
給与計算アウトソーシングを導入する際、自社独自の給与計算ロジックや特殊な手当に対応してもらえず、給与体系の変更を余儀なくされるトラブルがあります。
長年にわたって自社で構築してきた給与体系や計算方法を、アウトソーシング会社の標準的なシステムでは再現できないと言われ、給与体系を変更しなければならないケースがあります。しかし、給与体系の変更は従業員への説明や就業規則の改定が必要となり、大きな労力がかかります。
また、業種特有の計算方法(建設業の日給月給制、飲食業の深夜手当計算、医療業の宿日直手当など)に対応できず、結局自社で一部の計算を行わなければならないケースもあります。
【対処法】契約前に、自社の給与計算の詳細をアウトソーシング会社に伝え、対応可能かどうかを必ず確認することが重要です。現在使用している給与規程、計算式、特殊な手当の内容などを提示し、そのまま引き継げるかを検証してもらいましょう。
多くのアウトソーシング会社では、契約前にトライアル期間を設けたり、サンプルデータで試算を行ったりするサービスを提供しています。実際に自社のデータで給与計算を試してもらい、正確に計算できるかを確認してから本契約を結ぶことが推奨されます。
どうしても標準システムで対応できない場合は、カスタマイズが可能なアウトソーシング会社を選ぶか、既存システムをそのまま使用できるフルサポート型のサービスを検討しましょう。
また、給与体系の変更が必要な場合でも、それによって従業員に不利益が生じないように配慮することが重要です。変更の必要性や内容を従業員に丁寧に説明し、理解を得ることが円滑な移行につながります。
システムの連携がうまくいかない
給与計算アウトソーシングを導入する際、既存の勤怠管理システムや会計システムとの連携がうまくいかず、二重入力が必要になったり、データの整合性が取れなかったりするトラブルがあります。
勤怠管理システムから出力したデータが、アウトソーシング会社のシステムに取り込めるフォーマットになっていないため、手作業でデータを加工しなければならないケースがあります。また、給与計算の結果を会計システムに連携する際に、仕訳データの形式が合わず、手作業で入力し直す必要が生じることもあります。
こうしたシステム連携の問題により、期待していた業務効率化が実現できず、かえって作業負担が増えてしまうケースもあります。
【対処法】契約前に、自社で使用している勤怠管理システムや会計システムの名称をアウトソーシング会社に伝え、連携可能かどうかを確認することが重要です。多くのアウトソーシング会社では、主要な勤怠管理システム(ジョブカン、KING OF TIME、freee勤怠管理など)や会計システム(freee会計、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計など)との連携実績があります。
連携機能がない場合でも、データの入出力フォーマットを調整することで対応できるケースがあります。契約前に、データのサンプルをやり取りして、実際に連携できるかをテストすることが推奨されます。
どうしても連携が難しい場合は、システム一体型の給与計算アウトソーシングを選び、勤怠管理から給与計算、会計連携まで一貫して対応できる環境を構築することも選択肢となります。
また、アウトソーシング会社からITツールの導入提案を受けることも有効です。給与計算業務を効率化するために最適なシステム構成をアドバイスしてもらえるアウトソーシング会社もあります。
給与計算アウトソーシング導入の流れ【6ステップ】

給与計算アウトソーシングをスムーズに導入するためには、適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、一般的な導入の流れを6つのステップで解説します。
ステップ1: お申し込みと初回相談
給与計算アウトソーシング導入の最初のステップは、アウトソーシング会社への問い合わせとお申し込みです。
まず、自社のニーズや課題を整理しましょう。従業員数、給与体系、委託したい業務範囲、予算、導入希望時期などを明確にしておくことで、アウトソーシング会社との相談がスムーズに進みます。
複数のアウトソーシング会社に問い合わせを行い、サービス内容や料金、対応範囲などを比較検討することが推奨されます。各社のWebサイトから資料請求や問い合わせフォームを利用して、初回相談の予約を取りましょう。
初回相談では、自社の状況を詳しく説明し、アウトソーシング会社からサービス内容や料金体系の説明を受けます。疑問点や不安な点があれば、この段階で遠慮なく質問しましょう。また、担当者の対応や相性も確認し、長期的なパートナーとして信頼できるかを判断することが重要です。
初回相談は無料で対応している会社がほとんどです。この段階では契約の義務はありませんので、複数社と相談して比較検討することをお勧めします。
ステップ2: ヒアリング(現状の業務整理とニーズの明確化)
導入を検討することを決めたら、次のステップはアウトソーシング会社による詳細なヒアリングです。
ヒアリングでは、現在の給与計算業務の流れ、使用しているシステム、給与体系、特殊な手当や計算ルール、従業員数の内訳(正社員、パート、アルバイトなど)、事業所の数、年間の入退社数など、詳細な情報を提供します。
アウトソーシング会社は、これらの情報を基に、自社のサービスで対応可能かどうかを判断し、最適なサービス内容を提案します。現在の給与規程や過去の給与明細のサンプルを提示することで、より正確な提案を受けられます。
この段階で、課題や改善したい点を具体的に伝えることが重要です。給与計算のスケジュールがタイトで困っている、法改正への対応が不安、従業員からの問い合わせ対応に時間がかかるなど、具体的な悩みを共有することで、それに対応したサービス内容を提案してもらえます。
ヒアリングを通じて、アウトソーシング会社は自社の業務に合わせた導入プランを作成します。この段階で、業務の分担、データの受け渡し方法、スケジュールなどの大枠が決まります。
ステップ3: ミーティング(見積もり提示と契約)
ヒアリングの内容を基に、アウトソーシング会社から正式な見積もりが提示されます。
見積もりには、初期費用、月額基本料金、従業員1名あたりの単価、オプション料金(年末調整、住民税更新、賞与計算など)が明記されます。料金だけでなく、対応業務の範囲、納品物の内容、納品スケジュール、サポート体制なども詳細に説明されます。
この段階で、見積もり内容を精査し、不明な点や追加で確認したい点があれば質問しましょう。年間のトータルコストを計算し、予算内に収まるか、費用対効果が見込めるかを慎重に判断します。
複数のアウトソーシング会社から見積もりを取っている場合は、料金だけでなく、サービス内容、対応の柔軟性、セキュリティ対策、実績などを総合的に比較検討しましょう。最も安い会社ではなく、自社のニーズに最も合致し、長期的に信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。
委託先を決定したら、契約書の内容を入念に確認します。契約期間、解約条件、料金の支払い条件、業務範囲、責任の所在、機密保持義務、損害賠償の規定などを細かくチェックし、疑問点があれば契約前に明確にしておきましょう。
契約書に加えて、機密保持契約(NDA)や個人情報取扱いに関する覚書なども締結します。特に個人情報の取り扱いについては、マイナンバーの管理方法、データの保管場所、廃棄方法などを明確に定めておくことが重要です。
契約が完了したら、次のステップであるセットアップに進みます。
ステップ4: 本番環境でのテストラン(セットアップ)
契約締結後、給与計算アウトソーシングの本格運用に向けて、システムのセットアップとテストランを行います。
セットアップでは、まず従業員のマスタ情報をアウトソーシング会社のシステムに登録します。従業員の氏名、生年月日、入社日、雇用形態、給与体系、扶養家族情報、社会保険の加入状況、銀行口座など、給与計算に必要なすべての情報を提供します。
次に、給与計算のルールやロジックを設定します。基本給の計算方法、各種手当の計算ルール、残業代の計算方法、控除項目の設定など、自社の給与規程に基づいた計算ロジックをシステムに反映させます。特殊な計算が必要な場合は、この段階で詳細に説明し、正確に設定されるように確認します。
勤怠管理システムや会計システムとの連携が必要な場合は、データの入出力フォーマットを調整し、連携テストを行います。実際のデータを使用して、スムーズにデータが受け渡しできるかを検証します。
セットアップが完了したら、本番環境でのテストランを実施します。直近の給与計算データを使用して、アウトソーシング会社に給与計算を依頼し、結果を確認します。計算結果が正確か、給与明細の様式は適切か、振込データは正しく作成されているかなどを細かくチェックします。
テストランで問題が見つかった場合は、設定を修正し、再度テストを行います。完全に正確な計算ができることが確認できるまで、テストを繰り返します。この段階で徹底的に検証しておくことで、本番運用開始後のトラブルを防げます。
ステップ5: 最終調整ミーティング
テストランが完了し、給与計算が正確に行えることが確認できたら、本番運用開始前の最終調整ミーティングを行います。
最終調整ミーティングでは、業務フローとスケジュールを最終確認します。毎月の給与計算のスケジュール(締め日、データ提出期限、納品日、振込日)、データの提出方法、納品物の受け取り方法、連絡手段などを明確にします。
また、担当者の役割分担も確認します。企業側とアウトソーシング会社のそれぞれが、どの業務を担当するのか、問い合わせはどこに連絡すればよいのか、緊急時の連絡体制はどうなっているのかなどを明確にしておきます。
テストラン中に発見された課題や改善点についても、この段階で対策を協議します。計算ロジックの微調整が必要な場合や、データフォーマットの変更が必要な場合は、本番運用開始までに対応します。
従業員への案内方法についても協議します。給与計算がアウトソーシングに切り替わることを従業員にどのように説明するか、給与明細の配布方法が変わる場合はどのように周知するか、問い合わせ先が変わる場合はどのように案内するかなどを決定します。
最終調整ミーティングを通じて、運用開始に向けた準備を万全に整えます。すべての確認が完了したら、いよいよ本番運用の開始です。
ステップ6: 給与計算のアウトソーシング化(運用開始)
準備が整ったら、給与計算アウトソーシングの本番運用を開始します。
運用開始初月は、特に注意深く進める必要があります。スケジュール通りにデータを提出し、納品物を確認し、従業員への給与明細配布や振込手続きを行います。初月は慣れない作業もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが推奨されます。
初回の給与計算が完了したら、アウトソーシング会社と振り返りミーティングを行い、スムーズに処理できたか、改善すべき点はないかを確認します。問題があれば早期に対策を講じ、次回以降の業務改善につなげます。
運用が安定してきたら、定期的なミーティングの頻度を調整します。月次のミーティングや、四半期ごとの定例会議などを設定し、業務の状況を共有し、課題を協議します。法改正や制度変更があった場合の対応についても、定期的に情報共有を行います。
運用開始後も、継続的な改善を心がけることが重要です。業務フローの見直し、システム連携の強化、新しいサービスの追加など、より効率的で効果的な運用を目指して、アウトソーシング会社とともに改善を進めていきます。
また、従業員からのフィードバックも重要です。給与明細の見やすさ、問い合わせ対応の品質、手続きのしやすさなどについて、従業員の意見を聞き、サービス改善に活かしていきましょう。
給与計算アウトソーシングは、導入して終わりではなく、継続的な改善を通じて、より大きな効果を生み出すことができます。アウトソーシング会社と良好なパートナーシップを築き、長期的な視点で活用していくことが成功の鍵となります。
社労士に給与計算を依頼する6つのメリット
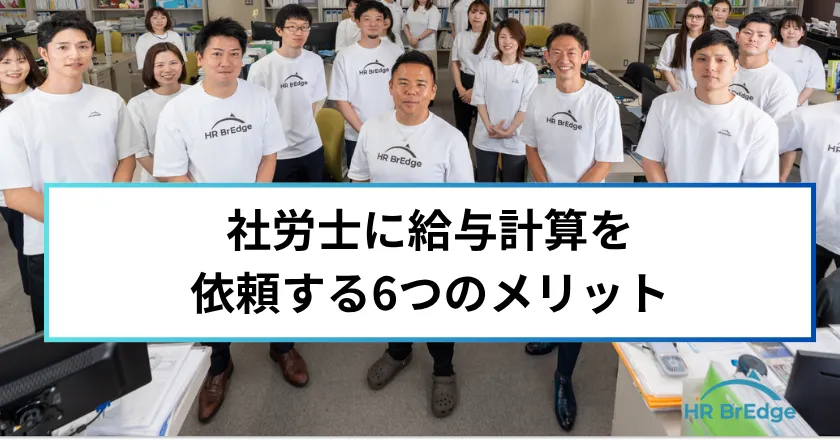
給与計算アウトソーシングの委託先には、給与計算代行会社、税理士事務所、社会保険労務士事務所などがありますが、ここでは特に社労士に給与計算を依頼するメリットについて詳しく解説します。
労働保険・社会保険手続きまで一括対応
社会保険労務士に給与計算を依頼する最大のメリットのひとつが、労働保険・社会保険手続きまで一括して対応してもらえることです。
給与計算と社会保険手続きは密接に関連しています。従業員の入社時には健康保険・厚生年金保険の資格取得届や雇用保険の加入手続きが必要であり、これらの手続きは給与計算にも影響します。退職時には資格喪失届の提出が必要で、最終給与の計算にも関係します。
給与計算を給与計算代行会社に依頼し、社会保険手続きを別の社労士に依頼している場合、情報の連携に手間がかかります。入社や退職の情報を両方に伝える必要があり、手続きの漏れや遅延が発生するリスクもあります。
社労士に給与計算と社会保険手続きを一括して依頼すれば、こうした二重管理の手間がなくなります。入退社の情報を社労士に伝えるだけで、給与計算への反映と社会保険手続きの両方が自動的に進められます。情報の一元管理により、手続き漏れのリスクも大幅に軽減されます。
また、算定基礎届(毎年7月)、労働保険の年度更新(毎年6月~7月)、賞与支払届など、給与に関連する定期的な手続きもすべて社労士が担当します。企業側では、これらの複雑な手続きを意識する必要がなくなります。
扶養家族の追加・削除、住所変更、氏名変更などの各種変更届についても、社労士が迅速に対応します。給与計算への反映と行政への届出が同時に行われるため、情報の齟齬が発生しません。
社労士に給与計算と社会保険手続きを一括して依頼することで、トータルでの業務効率化とコスト削減を実現できます。
労務トラブルの未然防止と法的リスク回避
社労士に給与計算を依頼することで、労務トラブルの未然防止と法的リスクの回避にもつながります。
社会保険労務士は、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、労働・社会保険に関する法律の専門家です。給与計算を通じて、企業の労務管理全般をチェックし、法令違反や労務リスクを早期に発見できます。
例えば、残業代の計算方法が労働基準法に違反していないか、最低賃金を下回っていないか、36協定の上限時間を超えていないか、有給休暇の取得義務を満たしているかなど、給与計算のデータから労務リスクを把握できます。問題が発見されれば、早期に改善策を提案し、労働基準監督署からの是正勧告や労働者とのトラブルを未然に防げます。
また、社労士は労使トラブルの解決にも精通しています。未払い残業代の請求、不当解雇の訴え、パワハラ・セクハラの相談など、労働問題が発生した際にも、法的な観点からアドバイスを受けられます。給与計算を依頼している社労士であれば、企業の給与体系や勤務実態を把握しているため、より具体的で実践的なアドバイスが可能です。
法改正への対応も、社労士の重要な役割です。働き方改革関連法、パートタイム・有期雇用労働法、改正育児・介護休業法など、労働法規は頻繁に改正されます。社労士は法改正の内容をいち早く把握し、企業に必要な対応を具体的にアドバイスします。就業規則の変更が必要な場合も、適切にサポートしてくれます。
社労士に給与計算を依頼することは、単なる事務作業の委託ではなく、労務管理全般のパートナーを得ることを意味します。法的リスクを軽減し、安心して事業運営に集中できる環境を構築できます。
助成金申請のサポート
社労士に給与計算を依頼することで、雇用関係の助成金申請についても専門的なサポートを受けられます。
厚生労働省は、雇用の安定や従業員の能力開発を支援するため、さまざまな助成金制度を設けています。キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金、65歳超雇用推進助成金など、多数の助成金があり、要件を満たせば企業は支給を受けられます。
しかし、助成金の制度は複雑で、申請要件や手続き方法を正確に理解することは容易ではありません。また、申請には給与台帳、出勤簿、就業規則など、多くの書類が必要となります。自社だけで申請を行うことは、時間と労力がかかります。
社労士は助成金申請の専門家でもあります。企業の状況を把握した上で、活用できる助成金を提案し、申請要件を満たすための準備をサポートします。給与計算を依頼している社労士であれば、給与台帳などの必要書類をすでに把握しているため、申請手続きがよりスムーズに進みます。
助成金の申請には、事前の計画届の提出が必要なケースが多くあります。制度を利用する前に届出を行わなければならないため、タイミングを逃すと助成金を受給できません。社労士に給与計算を依頼していれば、企業の採用計画や人材育成計画を共有することで、適切なタイミングで助成金の活用を提案してもらえます。
助成金の受給により、採用コストや研修コストの負担を軽減でき、企業の成長を支援できます。社労士のサポートを受けることで、活用できる助成金を見逃すことなく、確実に受給できる体制を構築できます。
就業規則・給与規程の整備支援
社労士に給与計算を依頼することで、就業規則や給与規程の整備についても専門的な支援を受けられます。
就業規則は、従業員数が常時10名以上の企業に作成と届出が義務付けられている重要な規程です。労働時間、休日、休暇、賃金、退職などの労働条件を定めたものであり、企業と従業員の間のルールを明確にする役割を果たします。
給与規程は、就業規則の一部または別規程として、給与の計算方法や支給条件を詳細に定めたものです。基本給の決定方法、各種手当の支給条件、賞与の算定方法、昇給のルールなどが記載されます。
これらの規程は、法律に適合している必要があり、また実際の運用と一致していなければなりません。規程と実態が乖離していると、労働トラブルの原因となったり、労働基準監督署から是正を求められたりする可能性があります。
社労士に給与計算を依頼している場合、実際の給与計算の内容と給与規程の内容を照らし合わせることができます。規程と実態に齟齬がある場合は、早期に発見し、規程の改定または運用の見直しを提案してもらえます。
また、法改正があった場合には、就業規則や給与規程の変更が必要になることがあります。社労士は法改正の内容を踏まえて、必要な規程変更を提案し、改定案の作成から労働基準監督署への届出まで、一連の手続きをサポートします。
新しい人事制度や給与体系を導入する際にも、社労士のサポートは有効です。制度設計の段階から関与してもらうことで、法的に問題のない制度を構築でき、給与計算への反映もスムーズに行えます。
就業規則や給与規程の整備は、労務管理の基盤となる重要な作業です。社労士の専門知識を活用することで、法令に適合し、実態に即した規程を整備できます。
労働基準監督署の調査対応
社労士に給与計算を依頼することで、労働基準監督署の調査が入った際にも、適切なサポートを受けられます。
労働基準監督署は、企業が労働基準法を遵守しているかを確認するため、定期的または申告に基づいて調査を実施します。調査では、労働時間の管理状況、残業代の支払い状況、有給休暇の取得状況、就業規則の整備状況などがチェックされ、給与台帳や出勤簿、タイムカードなどの提出を求められます。
調査の結果、法令違反が発見されると、是正勧告が出され、改善が求められます。悪質な違反の場合は、刑事罰の対象となることもあります。また、未払い残業代があれば、過去に遡って支払いを命じられ、多額の追加支払いが発生する可能性もあります。
社労士に給与計算を依頼していれば、労働基準監督署の調査が入った際に、専門家としてのサポートを受けられます。調査の対応方法についてアドバイスを受けたり、必要書類の準備を手伝ってもらったり、場合によっては調査の立ち会いを依頼したりすることができます。
また、日頃から社労士に給与計算を依頼していることで、労働基準法に適合した給与計算が行われているため、調査で指摘を受けるリスクが大幅に軽減されます。残業代の計算方法、割増賃金の算定、最低賃金の確認など、法令遵守の観点から給与計算が行われているため、安心して調査に対応できます。
万が一、調査で是正勧告を受けた場合でも、社労士が改善計画の策定や是正報告書の作成をサポートします。法令に適合した運用方法を具体的に提案し、再発防止策の実施を支援します。
労働基準監督署の調査は、企業にとって大きなストレスとなりますが、社労士のサポートがあれば、冷静かつ適切に対応できます。日頃から労務管理を専門家に任せることで、調査のリスクを最小限に抑えられます。
社労士業界唯一のSRPⅡ認証による高度な情報セキュリティ
社労士に給与計算を依頼する大きなメリットのひとつが、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度であるSRPⅡ認証による高度な情報セキュリティ対策です。
給与計算では、従業員の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、銀行口座、家族構成、給与額など、極めて機密性の高い個人情報を取り扱います。これらの情報が漏洩した場合、企業と従業員の双方に深刻な損害が発生します。
プライバシーマーク(Pマーク)やISO27001などの一般的なセキュリティ認証もありますが、社労士事務所に特化したSRPⅡ認証は、社労士が取り扱う個人情報の特性を踏まえた、より専門的な認証制度です。
SRPⅡ認証を取得している社労士事務所は、マイナンバー制度に対応した厳格な安全管理措置を講じています。個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に準拠し、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置、人的安全管理措置、組織的安全管理措置の4つの観点から、包括的なセキュリティ対策を実施しています。
具体的には、入退室管理の徹底、データの暗号化、アクセス権限の厳格な管理、従業員への定期的なセキュリティ研修、情報漏洩防止のための内部監査など、多層的な対策が講じられています。
SRPⅡ認証は、全国社会保険労務士会連合会が運営する認証制度であり、第三者機関による厳格な審査を経て取得されます。認証取得後も定期的な更新審査があり、継続的に高いセキュリティレベルが維持されていることが確認されます。
給与計算を委託する際、情報セキュリティは最も重要な選定基準のひとつです。SRPⅡ認証を取得している社労士事務所であれば、業界最高水準のセキュリティ対策が講じられており、安心して個人情報を委託できます。
SRPⅡ認証とは?社労士業界唯一の個人情報保護認証制度
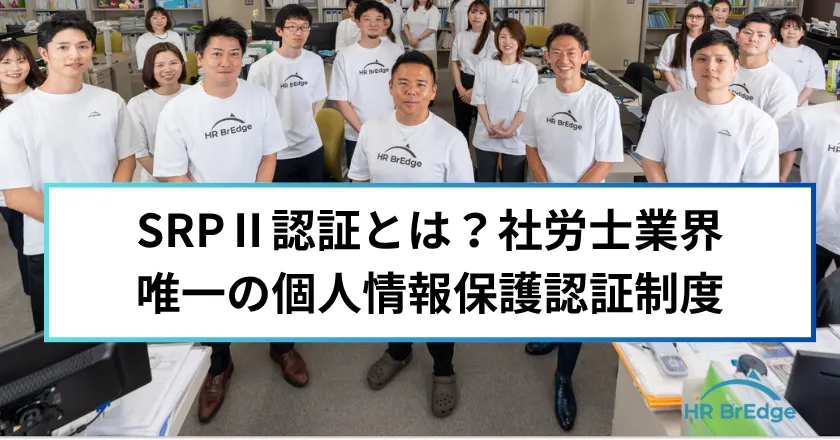
給与計算アウトソーシングを検討する際、情報セキュリティは最重要の確認ポイントです。ここでは、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度であるSRPⅡ認証について詳しく解説します。
SRPⅡ認証制度の概要と重要性
SRPⅡ認証制度(社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度)は、全国社会保険労務士会連合会が平成20年度に創設した、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度です。
社会保険労務士は、顧問先企業の従業員情報を含む、常に多くの個人情報を取り扱う士業です。給与計算業務では、氏名、住所、生年月日、マイナンバー、銀行口座、家族構成、給与額など、極めて機密性の高い情報を扱います。社会保険手続きでは、健康保険や厚生年金の加入情報、病歴に関わる情報なども扱います。
平成17年に個人情報保護法が全面施行されて以降、日本においても個人情報とその保護に対する意識が一層高まりました。企業においても個人情報の取扱基準の策定が急速に進み、他社との差別化を図るため、プライバシーマーク(Pマーク)の取得やISMS適合性評価制度の認証取得などが進められてきました。
このような状況を踏まえ、全国社会保険労務士会連合会は、社労士が個人情報を適正に取り扱っていることを「見える化」し、顧問先等からの信用・信頼をより確固たるものにするため、士業で唯一の個人情報保護の認証制度としてSRP認証制度を創設しました。
平成28年より運用が開始されたマイナンバー制度では、個人情報保護法より更に厳しい罰則が設けられており、厳格な安全管理措置を講ずることが求められています。社労士は、委託先として適切な安全管理措置が講じられているか顧問先等から監督される立場となります。
こうした状況に対応するため、連合会はマイナンバー制度に係る対応として、個人情報保護委員会が作成した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき「社労士版マイナンバー対応ハンドブック」を作成し、さらにSRP認証制度を当該ハンドブックの安全管理措置に準拠した「SRPⅡ認証制度」に刷新しました。
SRPⅡ認証は、マイナンバーを含む個人情報について、適切な安全管理措置を講じている事務所であることを証明する認証制度であり、社労士に給与計算や労務管理を委託する企業にとって、重要な選定基準となります。
Pマーク・ISMSとの違い
SRPⅡ認証は、プライバシーマーク(Pマーク)やISO27001(ISMS認証)などの一般的なセキュリティ認証と比較して、どのような違いがあるのでしょうか。
プライバシーマーク(Pマーク)は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営する、個人情報保護に関する第三者認証制度です。日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合している事業者に付与されます。業種を問わず、幅広い企業・団体が取得できる汎用的な認証制度です。
ISO27001(ISMS認証)は、情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格です。個人情報だけでなく、企業が保有するすべての情報資産を対象とした、包括的なセキュリティマネジメントの認証制度です。こちらも業種を問わず取得できるグローバルな認証制度です。
一方、SRPⅡ認証は、社会保険労務士事務所に特化した認証制度です。社労士が取り扱う個人情報の特性(マイナンバー、健康情報、給与情報など)を踏まえた、より専門的で厳格な基準が設けられています。
SRPⅡ認証の大きな特徴は、マイナンバー制度に完全対応している点です。個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に準拠しており、マイナンバーの取得から保管、利用、廃棄まで、すべてのプロセスにおいて厳格な安全管理措置が求められます。
また、SRPⅡ認証は、社労士会連合会という業界団体が運営する認証制度であるため、社労士業務の実態を深く理解した上での審査が行われます。給与計算業務や社会保険手続き業務における個人情報の取り扱いについて、実務に即した具体的な基準が設けられています。
PマークやISMS認証も優れた認証制度ですが、SRPⅡ認証は社労士事務所に特化した、より専門性の高い認証制度であり、給与計算や労務管理を委託する企業にとって、信頼性の高い指標となります。
マイナンバー制度への対応と安全管理措置
SRPⅡ認証の最も重要な特徴が、マイナンバー制度への完全対応です。ここでは、SRPⅡ認証で求められる安全管理措置について解説します。
マイナンバー制度では、個人情報保護法よりも厳しい罰則が設けられており、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取り扱いには、通常の個人情報以上に厳格な安全管理措置が求められています。
SRPⅡ認証では、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、以下の4つの安全管理措置が求められます。
組織的安全管理措置では、個人情報保護に関する規程の整備、責任者の明確化、従業員への教育・研修の実施、取扱状況の記録・保存、情報漏洩等の事案への対応体制の整備などが求められます。SRPⅡ認証を取得している事務所では、個人情報保護方針を明文化し、全従業員がこれを遵守する体制が構築されています。
人的安全管理措置では、従業員との機密保持契約の締結、定期的なセキュリティ研修の実施、退職後の秘密保持義務の明確化などが求められます。社労士事務所では、すべての従業員が個人情報の重要性を理解し、適切に取り扱う能力を有していることが確認されます。
物理的安全管理措置では、入退室管理の徹底、個人情報を取り扱う区域の明確化、機器・書類の盗難防止、個人情報が記載された書類やデータの適切な保管・廃棄などが求められます。SRPⅡ認証取得事務所では、監視カメラの設置、施錠管理、シュレッダーによる書類廃棄など、物理的なセキュリティ対策が徹底されています。
技術的安全管理措置では、アクセス制御の実施、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス防止、情報システムの監視、データの暗号化などが求められます。パスワード管理、ファイアウォールの設置、ウイルス対策ソフトの導入、データの暗号化通信など、技術的な対策が多層的に講じられています。
これらの安全管理措置を総合的に実施することで、マイナンバーを含む個人情報の漏洩、滅失、毀損のリスクを最小限に抑えることができます。SRPⅡ認証を取得している社労士事務所は、これらの措置を確実に実施していることが、第三者機関によって審査・認証されています。
HR BrEdge社労士法人のSRPⅡ認証(認証番号:1600640)
HR BrEdge社労士法人(旧渡辺事務所)は、SRPⅡ認証を取得しており、認証番号は1600640です。
HR BrEdge社労士法人は、創業18年、500社以上の企業に給与計算や労務管理のサービスを提供してきた実績を持つ社労士法人です。長年にわたる豊富な経験と専門知識を活かし、顧客企業の大切な個人情報を守るため、業界最高水準のセキュリティ対策を講じています。
SRPⅡ認証の取得により、HR BrEdge社労士法人は、マイナンバーを含む個人情報について、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を総合的に実施していることが、第三者機関によって認証されています。
具体的には、個人情報保護方針の明文化と全従業員への周知徹底、定期的なセキュリティ研修の実施、入退室管理システムによる物理的セキュリティの確保、データの暗号化通信、アクセス権限の厳格な管理など、多層的な対策を講じています。
また、情報漏洩等の事案が発生した場合の対応手順も明確に定められており、迅速かつ適切な対応ができる体制が整備されています。万が一の事態にも、被害を最小限に抑え、顧客企業と従業員の皆様を守る体制が構築されています。
給与計算や労務管理を委託する際、個人情報の保護は最も重要な選定基準のひとつです。HR BrEdge社労士法人は、SRPⅡ認証を取得することで、顧客企業の皆様に安心してサービスをご利用いただける環境を整えています。
個人情報保護への取り組みは、一度実施すれば終わりというものではありません。HR BrEdge社労士法人は、SRPⅡ認証の定期的な更新審査を受けながら、継続的にセキュリティレベルの向上に努めています。最新の技術動向や法令改正を踏まえ、常に最高水準のセキュリティ対策を維持しています。
給与計算アウトソーシングを検討されている企業の皆様には、ぜひSRPⅡ認証の取得状況を確認し、安心して個人情報を委託できるパートナーを選んでいただきたいと思います。
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングの利点
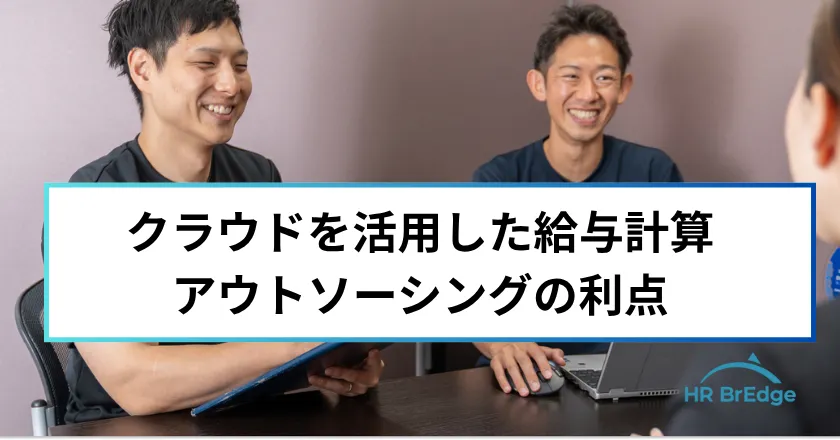
近年、クラウド技術を活用した給与計算アウトソーシングサービスが増えています。ここでは、クラウドを活用することで得られる具体的な利点について解説します。
多くのデータと容易に連携できる
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングの大きな利点のひとつが、多くのシステムやデータと容易に連携できることです。
従来の給与計算では、勤怠管理システム、人事管理システム、会計システムなど、複数のシステムが独立して存在し、それぞれのシステム間でデータを手作業で受け渡しする必要がありました。データの入力や転記作業に多くの時間がかかり、入力ミスのリスクも高い状態でした。
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングでは、API連携やデータ連携機能により、各システム間で自動的にデータを受け渡しできます。勤怠管理システムで記録された労働時間データが、自動的に給与計算システムに取り込まれ、給与計算が行われます。計算結果は、会計システムに自動的に仕訳データとして連携され、経理処理もスムーズに進みます。
主要な勤怠管理システム(ジョブカン、KING OF TIME、freee勤怠管理、マネーフォワード クラウド勤怠など)との連携実績があるサービスが多く、既存のシステムを継続して利用しながら、給与計算だけをアウトソーシングすることも可能です。
また、クラウドシステムでは、銀行の振込システムとも連携できます。給与計算が完了すると、自動的に銀行振込用のFBデータが生成され、インターネットバンキングを通じて振込処理を行えます。振込作業の手間が大幅に削減され、振込ミスのリスクも軽減されます。
さらに、年末調整のデータを税務署の電子申告システム(e-Tax)と連携させることも可能です。源泉徴収票や法定調書合計表などを電子データで作成し、そのまま電子申告できるため、紙の書類を作成・提出する手間が省けます。
クラウドを活用することで、給与計算業務を中心とした人事労務業務全体のデジタル化を推進でき、業務効率を大幅に向上させることができます。
データの安全性と管理の容易さ
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングでは、データの安全性と管理の容易さも大きな利点となります。
従来のオンプレミス型のシステムでは、企業内のサーバーにデータが保管されていました。そのため、サーバーの保守管理、バックアップの実施、セキュリティ対策の更新など、企業側で多くの管理業務を行う必要がありました。また、サーバーの故障や災害によるデータ消失のリスクもありました。
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングでは、データは高度なセキュリティ対策が施されたデータセンターに保管されます。データセンターは、24時間365日の監視体制、入退室管理、耐震・耐火構造、停電対策などが整備されており、物理的な安全性が確保されています。
また、データは自動的に複数の拠点にバックアップされるため、万が一ひとつのデータセンターに障害が発生しても、他の拠点からデータを復旧できます。企業側でバックアップ作業を行う必要がなく、データ消失のリスクも最小限に抑えられます。
セキュリティ面では、データの暗号化通信、アクセス権限の厳格な管理、多要素認証の導入など、最新の技術が活用されています。システムのセキュリティアップデートも自動的に行われるため、常に最新のセキュリティ対策が適用された状態が維持されます。
データの管理も容易です。クラウドシステムでは、過去の給与データや年末調整データを長期間保管でき、必要な時にいつでも検索・参照できます。紙の書類をファイリングして保管する必要がなく、オフィスのスペースも節約できます。
また、法定保存期間が定められている労働関係書類(給与台帳、出勤簿、労働者名簿など)についても、クラウド上で適切に管理され、保存期間を過ぎたデータは自動的に削除する設定も可能です。法令遵守の観点からも安心して利用できます。
クラウドを活用することで、データの安全性を確保しながら、管理の手間を大幅に削減できます。
リモートワークへの対応
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングは、リモートワークやテレワークへの対応にも優れています。
新型コロナウイルスの感染拡大以降、多くの企業でリモートワークが導入されましたが、給与計算業務は紙ベースの作業が多く、リモートワークへの移行が困難な業務のひとつでした。タイムカードの回収、紙の給与明細の配布、押印が必要な書類の処理など、出社しなければできない作業が多数ありました。
クラウドを活用した給与計算アウトソーシングでは、すべての業務をオンラインで完結できます。勤怠データはクラウド勤怠管理システムで記録され、自動的に給与計算システムに連携されます。給与明細はWeb明細として従業員がオンラインで確認でき、紙の明細を配布する必要がありません。
人事担当者も、インターネット環境があればどこからでもクラウドシステムにアクセスし、給与計算の進捗を確認したり、データを確認したりできます。アウトソーシング会社とのやり取りも、メールやチャット、Web会議などで行えるため、出社する必要がありません。
従業員からの申請手続きも、Web上で完結できます。住所変更、扶養家族の追加・削除、年末調整の書類提出など、従来は紙の書類で行っていた手続きを、スマートフォンやパソコンから直接オンラインで申請できます。人事部門を経由せずに、従業員が直接アウトソーシング会社のシステムに情報を入力できるため、リモートワーク環境でもスムーズに手続きが進みます。
また、クラウドシステムでは、複数の担当者が同時にアクセスして作業することも可能です。本社と支店、または複数の担当者が分担して給与計算業務を進める場合でも、リアルタイムで情報を共有しながら作業できます。
リモートワークの普及により、働き方が多様化している現代において、クラウドを活用した給与計算アウトソーシングは、柔軟な働き方を実現するための重要なツールとなっています。
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービス

ここからは、HR BrEdge社労士法人が提供する給与計算アウトソーシングサービスの具体的な内容について詳しくご紹介します。
労務相談・手続き・給与計算 包括顧問プラン
HR BrEdge社労士法人では、労務相談、労働社会保険手続き、給与計算業務を包括的にサポートする「労務相談・手続き・給与計算 包括顧問プラン」を提供しています。
このプランは、給与計算だけでなく、労務に関するあらゆる相談に対応し、労働社会保険の各種手続き、給与計算業務まで一括してサポートする包括的なサービスです。従業員管理にかかる業務負担を大幅に軽減し、企業が安心して事業運営に集中していただけるよう設計されています。
労務相談では、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法などの労働関係法令に関する質問に対応します。就業規則の作成や見直し、人事制度の構築、労働トラブルの予防と対応、法改正への対応など、人事労務に関する幅広い相談をお受けします。日々の業務で発生する疑問や課題について、専門家の立場から具体的なアドバイスを提供します。
労働社会保険手続きでは、従業員の入退社時の各種手続き、扶養家族の追加・削除、住所変更などの変更届、算定基礎届、労働保険の年度更新、賞与支払届など、すべての手続きを代行します。手続きの期限管理も行うため、手続き漏れや遅延のリスクがありません。
給与計算業務では、月次給与計算、賞与計算、年末調整、住民税更新など、給与に関するすべての業務に対応します。勤怠データを提供いただければ、給与計算、給与明細の作成、振込データの作成まで、一括して処理します。
包括顧問プランの最大の特徴は、これらのサービスをすべてワンストップで提供できることです。給与計算と社会保険手続きを別々の業者に依頼する必要がなく、情報の一元管理により、手続きの連携がスムーズで、漏れやミスを防げます。
また、専任の担当者が企業の状況を継続的に把握しているため、企業の特性に合わせたきめ細かなサポートが可能です。長期的なパートナーとして、企業の成長を支援します。
料金体系|基本契約30,000円+従業員数に応じた従量課金
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスの料金体系は、シンプルで分かりやすい設定となっています。
基本契約料金は、月額30,000円です。この基本契約には、労務相談、労働社会保険手続き、給与計算業務の基本的なサービスがすべて含まれています。追加料金なしで、包括的なサポートを受けられます。
従業員数に応じた従量課金は、従業員の人数によって単価が変動する仕組みです。従業員数が多いほど、1名あたりの単価が下がるスケールメリットがあります。
具体的な料金設定は以下の通りです。従業員5名までは、手続き・給与計算ともに基本契約料金に含まれています。従業員6名から20名までは、1名あたり手続き1,000円、給与計算1,000円です。従業員21名から50名までは、1名あたり手続き950円、給与計算950円です。従業員51名から100名までは、1名あたり手続き900円、給与計算900円です。従業員101名から150名までは、1名あたり手続き850円、給与計算850円です。従業員151名から200名までは、1名あたり手続き800円、給与計算800円です。従業員201名から300名までは、1名あたり手続き750円、給与計算750円です。従業員301名以上は、1名あたり手続き700円、給与計算700円です。
この料金体系により、企業規模に応じた適正な料金でサービスをご利用いただけます。従業員数が増加しても、1名あたりの単価が下がるため、企業の成長に合わせて費用対効果が向上します。
料金には、月次給与計算、賞与計算、年末調整、社会保険手続き、労務相談など、基本的なサービスがすべて含まれています。追加料金が発生するケースは限定的であり、料金の透明性が高い点も特徴です。
また、従業員数の変動にも柔軟に対応します。従業員が増減した場合は、翌月から料金を調整するため、無駄なコストが発生しません。
従業員数別の料金シミュレーション(6名~300名超)
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスの料金を、従業員数別に具体的にシミュレーションしてみましょう。
従業員10名の企業の場合、基本契約30,000円に、従業員6名から10名の5名分の費用(手続き1,000円×5名+給与計算1,000円×5名=10,000円)を加えて、月額40,000円となります。年間では480,000円です。
従業員30名の企業の場合、基本契約30,000円に、6名から20名の15名分(2,000円×15名=30,000円)と、21名から30名の10名分(1,900円×10名=19,000円)を加えて、月額79,000円となります。年間では948,000円です。
従業員50名の企業の場合、基本契約30,000円に、6名から20名の15名分(30,000円)、21名から50名の30名分(1,900円×30名=57,000円)を加えて、月額117,000円となります。年間では1,404,000円です。
従業員100名の企業の場合、基本契約30,000円に、6名から20名の15名分(30,000円)、21名から50名の30名分(57,000円)、51名から100名の50名分(1,800円×50名=90,000円)を加えて、月額207,000円となります。年間では2,484,000円です。
従業員150名の企業の場合、基本契約30,000円に、各階層の費用を積み上げて、月額297,000円となります。年間では3,564,000円です。
従業員200名の企業の場合、月額382,000円、年間では4,584,000円となります。
従業員300名の企業の場合、月額557,000円、年間では6,684,000円となります。
これらの料金には、給与計算だけでなく、社会保険手続きや労務相談もすべて含まれています。専任担当者を雇用するコストや、給与計算システムの維持費用と比較すると、大幅なコスト削減が期待できます。
また、年末調整や住民税更新などの年次業務も基本料金に含まれているため、追加費用の心配がありません。料金体系がシンプルで分かりやすく、予算管理がしやすい点も特徴です。
具体的な料金や、自社の規模に合わせたお見積もりについては、お気軽にお問い合わせください。無料で詳細なお見積もりを提示いたします。
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングの強み

HR BrEdge社労士法人(旧渡辺事務所)は、創業18年、500社以上の企業に給与計算や労務管理のサービスを提供してきた実績を持つ社労士法人です。ここでは、当法人の給与計算アウトソーシングサービスの具体的な強みについて詳しくご紹介します。
創業18年・500社以上の豊富な実績
HR BrEdge社労士法人は、2007年の設立以来18年にわたり、給与計算や労務管理のサービスを提供してきました。2025年で創業18周年を迎え、これまでに500社以上の企業に導入いただいた豊富な実績があります。
長年にわたって多くの企業をサポートしてきた経験から、さまざまな業種や企業規模に対応できるノウハウを蓄積しています。製造業、飲食業、小売業、IT業、医療・福祉業、建設業など、幅広い業種での給与計算実績があり、それぞれの業種特有の給与体系や勤務形態にも精通しています。
企業規模も、従業員数十名の中小企業から、数百名規模の企業まで幅広く対応しています。企業の成長段階に合わせたサービス提供が可能であり、創業間もない企業が成長して従業員数が増加しても、継続してサポートできる体制を整えています。
豊富な実績により培われた経験とノウハウは、顧客企業の課題解決に活かされています。他社での成功事例や改善事例を参考にしながら、最適なソリューションを提案できます。また、さまざまな給与計算のケースに対応してきた経験から、特殊な計算や複雑な事例にも適切に対応できる能力があります。
創業以来、多くの企業から信頼をいただき、長期的なパートナーシップを築いてきました。顧客企業の中には、10年以上継続してサービスをご利用いただいている企業も多数あります。長期的な信頼関係により、企業の状況を深く理解し、より効果的なサポートが可能になっています。
SRPⅡ認証取得による業界最高水準のセキュリティ対策
HR BrEdge社労士法人は、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度であるSRPⅡ認証を取得しており、認証番号は1600640です。
給与計算では、従業員の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、銀行口座、家族構成、給与額など、極めて機密性の高い個人情報を取り扱います。これらの情報を安全に管理することは、給与計算アウトソーシングにおいて最も重要な要素です。
SRPⅡ認証は、マイナンバー制度に対応した厳格な安全管理措置を講じていることを証明する認証制度です。組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置の4つの観点から、包括的なセキュリティ対策を実施しています。
具体的には、個人情報保護方針の明文化と全従業員への周知徹底、機密保持契約の締結、定期的なセキュリティ研修の実施、入退室管理システムによる物理的セキュリティの確保、監視カメラの設置、データの暗号化通信、アクセス権限の厳格な管理、ファイアウォールの設置、ウイルス対策ソフトの導入など、多層的な対策を講じています。
また、情報漏洩等の事案が発生した場合の対応手順も明確に定められており、迅速かつ適切な対応ができる体制が整備されています。万が一の事態にも、被害を最小限に抑える仕組みが構築されています。
SRPⅡ認証は、第三者機関による厳格な審査を経て取得され、定期的な更新審査によって継続的に高いセキュリティレベルが維持されていることが確認されます。HR BrEdge社労士法人は、業界最高水準のセキュリティ対策により、顧客企業の大切な個人情報を守り、安心してサービスをご利用いただける環境を提供しています。
専属担当者による充実したサポート体制
HR BrEdge社労士法人では、顧客企業ごとに専属の担当者を配置し、きめ細かなサポートを提供しています。
専属担当者制の最大のメリットは、企業の状況を深く理解した担当者が継続的にサポートできることです。企業の給与体系、勤務形態、特殊なルール、組織構成などを把握した担当者が対応するため、毎回ゼロから説明する必要がなく、スムーズなコミュニケーションが可能です。
また、企業の課題や悩みを理解している担当者だからこそ、適切なタイミングで最適な提案ができます。法改正があった際には、自社にどのような影響があるのか、どのような対応が必要なのかを、具体的にアドバイスします。他社の事例を参考にしながら、企業に合った改善策を提案することも可能です。
専属担当者は、給与計算や労務管理の専門知識を持つプロフェッショナルです。社会保険労務士の資格を持つスタッフや、豊富な実務経験を持つスタッフが担当するため、専門的な相談にも的確に対応できます。
連絡や相談がしやすい関係性を築けることも、専属担当者制の大きなメリットです。顧客企業からは、「担当者がついてもらえることで、連絡や相談がスムーズに行える」「不在で連絡がつながらないということがなく、いつでも相談できる安心感がある」といった評価をいただいています。
また、担当者が変更になる場合でも、引き継ぎを徹底して行うため、サービス品質が低下することはありません。前任者から後任者へ、企業の情報や特性、これまでの経緯などを詳細に引き継ぎ、継続して高品質なサービスを提供します。
専属担当者による充実したサポート体制により、長期的なパートナーシップを築き、企業の成長を支援しています。
自由なフォーマットで既存フローを変更不要
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスでは、データの提出フォーマットは自由であり、現在のフローを変更する必要がありません。
多くの給与計算アウトソーシング会社では、指定されたフォーマットでデータを提出する必要があります。そのため、企業側で現在使用しているデータを、アウトソーシング会社のフォーマットに合わせて加工しなければならず、余計な手間がかかります。
HR BrEdge社労士法人では、企業が現在使用しているフォーマットのまま、データを提出していただけます。Excelのシート形式、CSVファイル、勤怠管理システムから出力されるデータなど、どのような形式でも問題ありません。アウトソーシング会社側で、受け取ったデータを適切に処理します。
これにより、企業側でデータの加工作業を行う必要がなく、現在の業務フローをそのまま継続できます。アウトソーシング導入のために新しいシステムを導入したり、業務フローを大きく変更したりする必要がないため、導入のハードルが低く、スムーズに移行できます。
また、勤怠管理システムや人事管理システムを使用している企業では、そのシステムから出力されるデータをそのまま提出していただければ、給与計算に反映します。既存のシステムを継続して使用しながら、給与計算だけをアウトソーシングすることが可能です。
企業ごとに最適なデータ提出方法を協議し、最も効率的な方法を採用します。柔軟な対応により、企業の負担を最小限に抑えながら、給与計算アウトソーシングのメリットを享受していただけます。
現行の計算ロジックを維持したまま移行可能
HR BrEdge社労士法人では、企業が現在使用している給与計算のロジックを、そのまま維持したまま移行することが可能です。
多くの企業では、長年にわたって構築してきた独自の給与計算ロジックや計算方法があります。基本給の計算方法、残業代の計算ルール、各種手当の支給条件、賞与の算定方法など、企業ごとに異なるルールが設定されています。
給与計算アウトソーシングを導入する際、これらの計算ロジックをアウトソーシング会社の標準的なシステムに合わせて変更しなければならないケースがあります。しかし、給与体系の変更は従業員への説明や就業規則の改定が必要となり、大きな労力がかかります。
HR BrEdge社労士法人では、企業の現行の計算ロジックを詳細にヒアリングし、そのロジックをそのまま再現できるようにシステムを設定します。特殊な計算が必要な場合でも、柔軟に対応し、現在の給与体系を維持したまま、アウトソーシングに移行できます。
また、セットアップの過程で計算ロジックに誤りが発見された場合は、改善のための提案も行います。法令に適合していない計算方法や、従業員に不利益を与える可能性のある計算方法については、より適切な方法を提案し、企業の労務リスクを軽減します。
現行の計算ロジックを維持できることで、従業員への影響を最小限に抑えながら、スムーズにアウトソーシングへ移行できます。給与額が大きく変わることもないため、従業員の理解も得やすく、円滑な導入が可能です。
柔軟な納品スケジュール(最短2営業日対応も可能)
HR BrEdge社労士法人では、企業のスケジュールに合わせた柔軟な納品対応が可能です。お客様のご要望に応じて、資料受領から最短2営業日での納品対応も行っています。
企業によって、給与の締め日から支給日までの期間はさまざまです。月末締め翌月25日払いのように余裕のあるスケジュールの企業もあれば、月末締め翌月3日払いのようにタイトなスケジュールの企業もあります。
標準的な給与計算アウトソーシングでは、データ受領から納品まで3営業日から5営業日程度かかるケースが一般的です。しかし、タイトなスケジュールの企業では、この期間では間に合わないことがあります。
HR BrEdge社労士法人では、企業のスケジュールに合わせて、最短2営業日での納品が可能です。例えば、月末の営業日にデータを提出いただければ、翌々営業日には給与明細や振込データを納品できます。上場企業のようにタイトなスケジュールで給与を支給している企業でも、安心してご利用いただけます。
また、通常は標準スケジュールで問題なくても、年度末や決算期などで特別に早めの納品が必要になる場合にも、柔軟に対応します。事前にご相談いただければ、可能な限り対応いたします。
納品スケジュールだけでなく、急な追加や変更依頼にも迅速に対応します。締め後に遡及修正が必要になった場合や、急遽退職者が発生した場合なども、できる限り柔軟に対応し、企業の業務をサポートします。
柔軟な納品スケジュールにより、企業の多様なニーズに対応し、給与支給業務をスムーズに進めていただけます。
自由な納品物形式(お客様のご要望に対応)
HR BrEdge社労士法人では、納品物の種類や形式もお客様のご要望に応じて柔軟に対応します。
給与計算の納品物としては、給与明細、支給控除一覧表、銀行振込一覧、住民税一覧、勤怠管理一覧などがあります。これらの納品物について、企業が現在使用しているフォーマットに合わせて作成することが可能です。
例えば、給与明細のレイアウトや記載項目、支給控除一覧表の並び順や集計方法など、企業ごとに異なる要望に対応します。会計システムへの取り込みが必要な場合は、会計仕訳データを企業のフォーマットに合わせて加工して納品することも可能です。
納品形式についても、PDFファイル、Excelファイル、CSVファイルなど、企業が使いやすい形式を選択していただけます。紙での納品が必要な場合は、印刷して郵送することも可能です。
また、納品物の内容についても、企業のニーズに合わせてカスタマイズできます。部門別の集計が必要な場合、事業所別の集計が必要な場合、特定の手当だけを抽出した一覧が必要な場合など、さまざまな要望に対応します。
顧客企業からは、「納品物を当社の形式に合わせていただいているので、そのまま使える」「会計システムへの取り込みがスムーズで、経理業務の効率化にもつながっている」といった評価をいただいています。
企業ごとに最適な納品形式を協議し、業務効率が最大化される方法を採用します。柔軟な対応により、企業の既存の業務フローを変更することなく、給与計算アウトソーシングを活用していただけます。
ITツールの導入提案と業務効率化支援
HR BrEdge社労士法人では、給与計算業務だけでなく、労務管理全般の業務効率化を支援するため、ITツールの導入提案も行っています。
労務管理を進めていく上で、適切なITツールの活用は欠かせません。しかし、どのようなツールを選べばよいのか、どのように導入すればよいのか分からないという企業も多くあります。
HR BrEdge社労士法人では、企業の課題やニーズをヒアリングした上で、最適なITツールを提案します。勤怠管理システム、人事管理システム、労務管理クラウド、電子契約システムなど、さまざまなツールの中から、企業の規模や業種、課題に合ったものを推奨します。
また、ツールの導入にあたっては、設定方法や運用方法についてもアドバイスします。導入後のサポートも行うため、安心してツールを活用していただけます。
顧客企業からは、「想定していなかったメリットとして、ITツールの導入があった」「労務管理に必要なツールの提案をもらえたのは想定外だった」「このツールにより、日常の業務が効率化され、時間とコストの節約につながった」といった評価をいただいています。
ITツールの導入により、業務の効率化だけでなく、データの一元管理やペーパーレス化も進みます。給与計算アウトソーシングとITツールを組み合わせることで、人事労務業務全体の最適化が実現できます。
HR BrEdge社労士法人は、給与計算の専門家としてだけでなく、労務管理全般のパートナーとして、企業の業務効率化を総合的に支援します。
他社事例の共有による多角的なソリューション提案
HR BrEdge社労士法人は、500社以上の豊富な顧問先を持つ社労士法人です。この強みを活かし、他社の成功事例や改善事例を参考にしながら、多角的なソリューションを提案できます。
企業が抱える課題は、多くの場合、他の企業も同様に経験している課題です。人材不足への対応、働き方改革への対応、労務トラブルの予防、人事制度の構築など、共通する課題が数多くあります。
HR BrEdge社労士法人では、さまざまな業種や規模の企業をサポートしてきた経験から、豊富な事例を蓄積しています。ある企業で成功した取り組みや、課題を解決した方法を、他の企業にも応用して提案することができます。もちろん、企業の固有情報は厳重に管理し、機密保持を徹底した上で、一般化された知見として共有します。
顧客企業からは、「顧問先が多いので、他社の色々な事例を聞けることがメリットが大きい」「異なる視点からのヒントを得ることができる」といった評価をいただいています。業種は異なっても、課題の本質は共通していることが多く、他業種の事例が自社の問題解決に役立つこともあります。
例えば、飲食業の企業が人材確保に苦労している場合、同じく人材不足に悩んでいた製造業の企業がどのような採用戦略を取ったのか、どのような福利厚生制度を導入したのかといった事例を参考にすることができます。また、IT業の企業がリモートワーク制度を導入する際に、すでに導入している他社の運用方法や課題を聞くことで、スムーズな導入が可能になります。
さらに、業界の最新トレンドや法改正の動向についても、多くの企業をサポートしている経験から、より実践的な情報を提供できます。法改正があった際に、他社がどのように対応しているのか、どのような課題が発生しているのかといった生の情報を共有することで、自社の対応策を検討する際の参考にしていただけます。
他社事例の共有により、企業は自社だけでは気づかなかった課題や、思いつかなかった解決策を知ることができます。多角的な視点からのソリューション提案により、より効果的な課題解決が可能になります。
給与計算だけでなく人事戦略まで包括的にサポート
HR BrEdge社労士法人は、単なる給与計算の代行業者ではなく、人事戦略を含めた包括的なサポートを提供する、企業の人事労務のパートナーです。
給与計算業務を通じて、企業の人件費の状況、従業員の勤務実態、残業時間の推移、有給休暇の取得状況など、さまざまな情報を把握しています。これらのデータを分析することで、企業の人事労務における課題を発見し、改善策を提案できます。
顧客企業からは、「制度作りから人事戦略的な視点を持って、給与計算に反映させることが重要だと感じている」「人事戦略や制度作り、給与計算などを相談している」といった評価をいただいています。給与計算は単なる事務作業ではなく、人事戦略を実現するための重要なツールです。
例えば、賃金の昇給シミュレーションや賞与原資の配分について相談を受けることがあります。企業の業績、従業員のモチベーション、市場水準などを考慮しながら、最適な賃金体系を提案します。また、社内規程の整備についても、就業規則や給与規程だけでなく、退職金規程、育児・介護休業規程など、人事労務に関わる規程全般の作成・見直しをサポートします。
人事評価制度の構築についても支援します。公平で納得感のある評価制度を設計し、評価結果を給与や賞与にどのように反映させるかをアドバイスします。制度設計から運用、給与計算への反映まで、一貫してサポートできます。
また、企業の成長段階に応じた人事労務管理のあり方についてもアドバイスします。創業期、成長期、成熟期など、企業のステージによって必要な人事施策は異なります。将来を見据えた人事戦略の立案をサポートし、10年後の事業戦略や人員配置に関する計画策定にも関与します。
顧客企業からは、「コロナ禍により事業や経営に関わる問題が顕在化した際、銀行や事業企画の面でサポートを受け、事業計画の策定やコロナによる影響への対応が可能となった」「10年後の事業戦略や人員配置に関する計画を重要視している」といった評価もいただいています。
経営や事業に関する計画を立てていると、問題解決がスムーズに進められます。人事労務の専門家として、経営視点からのアドバイスも提供し、企業の持続的な成長を支援します。
HR BrEdge社労士法人は、給与計算アウトソーシングを入口として、企業の人事戦略全般をサポートする、真のパートナーを目指しています。
給与計算アウトソーシングの納品物一例
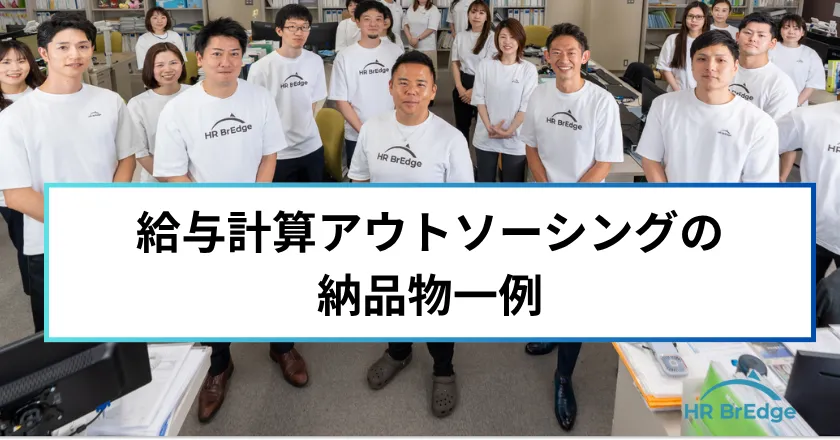
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスでは、さまざまな納品物を提供しています。ここでは、主要な納品物について詳しく解説します。
月次給与計算(給与明細・支給控除一覧・銀行振込一覧)
月次給与計算の基本的な納品物として、給与明細、支給控除一覧、銀行振込一覧を提供します。
給与明細は、従業員一人ひとりの給与の内訳を示す書類です。基本給、各種手当(残業手当、通勤手当、役職手当、家族手当など)の支給額、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除額、そして差し引き支給額が記載されます。給与明細は、紙での納品だけでなく、Web明細としての配信にも対応しています。Web明細を利用することで、ペーパーレス化が進み、従業員はスマートフォンやパソコンからいつでも給与明細を確認できます。
支給控除一覧は、全従業員の給与を一覧表にまとめた資料です。個人別の一覧と部門別の一覧の両方を作成します。個人別一覧では、従業員ごとの支給額、控除額、差し引き支給額が一覧で確認でき、全体の人件費を把握できます。部門別一覧では、部門ごとに集計された人件費が確認でき、部門別の予算管理に活用できます。これらの資料は、経営層への報告資料としても利用されます。
銀行振込一覧は、従業員への給与振込に必要な情報をまとめた資料です。従業員の氏名、銀行名、支店名、口座番号、振込金額が記載されており、この資料を基に銀行での振込手続きを行います。また、銀行の振込システムに直接取り込める形式(FBデータ)でも提供可能です。
これらの納品物は、企業のご要望に応じてフォーマットや内容をカスタマイズできます。既存の様式に合わせることも、新しい様式を提案することも可能です。
賞与計算
賞与計算についても、月次給与計算と同様に、賞与明細、賞与支給控除一覧、銀行振込一覧を提供します。
賞与計算では、賞与支給額に基づき、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税を計算します。賞与の社会保険料は、月次給与とは異なる計算方法が適用されるため、正確な計算が必要です。また、所得税についても、賞与特有の計算方法(前月の給与額を基準とした税率の適用)により算出します。
賞与明細には、支給額、控除額、差し引き支給額が明記され、従業員に配布されます。賞与支給控除一覧では、全従業員の賞与額が一覧で確認でき、賞与の総額や部門別の配分状況を把握できます。
また、賞与支払届の作成もサポートします。賞与を支給した際には、年金事務所や健康保険組合に賞与支払届を提出する必要があります。この書類の作成と提出も、社会保険手続きの一環として代行します。
賞与計算は、企業によって支給時期や計算方法が異なりますが、柔軟に対応します。年2回の定期賞与だけでなく、決算賞与や臨時賞与の計算にも対応可能です。
年末調整
年末調整は、毎年11月から1月にかけて実施される重要な業務です。HR BrEdge社労士法人では、年末調整の一連の業務を包括的にサポートします。
年末調整では、まず従業員への案内文書を作成し、必要な書類(扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書など)の回収を行います。回収した書類の内容を確認し、不備があれば従業員に確認を取りながら、正確な情報を把握します。
年末調整の計算では、1年間の給与と賞与の合計額を基に、所得税額を再計算します。生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除、扶養控除などを適用し、正確な年税額を算出します。すでに徴収している所得税との差額を計算し、過不足があれば12月または1月の給与で精算します。
年末調整が完了したら、源泉徴収票を作成し、従業員に配布します。源泉徴収票は、確定申告や住宅ローンの審査などで必要となる重要な書類です。また、退職者についても、退職時または年末調整時に源泉徴収票を発行します。
さらに、税務署への提出書類(源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表など)も作成します。これらの書類は、電子申告(e-Tax)にも対応しており、スムーズな提出が可能です。
年末調整は作業量が膨大で複雑な業務ですが、HR BrEdge社労士法人にお任せいただければ、正確かつ迅速に処理します。企業の担当者の負担を大幅に軽減できます。
銀行FBデータ作成
銀行FBデータ(Firm Bankingデータ)は、銀行の振込システムに直接取り込むことができるデータファイルです。HR BrEdge社労士法人では、給与振込や賞与振込に必要な銀行FBデータの作成を行います。
FBデータを利用することで、銀行での振込手続きが大幅に効率化されます。従来は、振込依頼書に従業員の氏名、口座番号、振込金額などを手書きで記入したり、インターネットバンキングの画面で一件ずつ入力したりする必要がありましたが、FBデータを取り込むことで、一括して振込処理を行えます。
HR BrEdge社労士法人では、企業が取引している銀行のフォーマットに合わせてFBデータを作成します。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行など、主要な銀行のフォーマットに対応しています。複数の銀行を利用している企業でも、それぞれの銀行に対応したFBデータを作成できます。
FBデータには、振込先の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義、振込金額などの情報が含まれています。このデータをインターネットバンキングや銀行の専用システムに取り込むことで、瞬時に振込処理が完了します。
FBデータの利用により、振込作業の時間が大幅に短縮されるだけでなく、入力ミスのリスクも軽減されます。振込先や金額の誤りによるトラブルを防ぎ、確実に給与を支払うことができます。
住民税FBデータ作成
住民税FBデータは、住民税の納付に使用するデータファイルです。HR BrEdge社労士法人では、住民税の納付手続きを効率化するため、住民税FBデータの作成にも対応しています。
住民税の特別徴収では、企業が従業員の給与から住民税を天引きし、各市区町村に納付する必要があります。従業員が多い企業や、従業員の居住地が複数の市区町村にまたがる企業では、納付先が多数になり、納付手続きが煩雑になります。
住民税FBデータを利用することで、複数の市区町村への納付を一括して処理できます。地方税共通納税システム(eLTAX)を利用することで、電子納税が可能になり、銀行への振込や納付書の作成が不要になります。
HR BrEdge社労士法人では、給与計算時に計算された住民税額を基に、市区町村別に集計し、住民税FBデータを作成します。このデータをeLTAXに取り込むことで、スムーズに電子納税を行えます。
住民税の納付期限は翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)と定められており、納付漏れや遅延があると延滞金が発生します。FBデータを利用することで、確実かつ効率的に納付手続きを行い、期限内の納付を実現できます。
勤怠管理・有給休暇管理
HR BrEdge社労士法人では、給与計算に加えて、勤怠管理や有給休暇管理についてもサポートを提供しています。
勤怠管理では、企業から提供された勤怠データ(タイムカード、ICカード、勤怠管理システムの出力データなど)を取りまとめ、勤怠資料として整理します。出勤日数、欠勤日数、遅刻・早退の回数、残業時間、休日出勤時間、深夜労働時間などを集計し、一覧表にまとめます。
勤怠資料は、給与計算の基礎資料となるだけでなく、労働時間の管理や労働基準法の遵守状況を確認するための重要な資料です。36協定の上限時間を超えていないか、有給休暇の取得義務を満たしているかなど、法令遵守の観点からもチェックを行います。
有給休暇管理では、従業員ごとの有給休暇の付与日数、取得日数、残日数をマスタ情報として管理します。有給休暇は、入社日を基準に付与され、繰越や時効消滅のルールもあるため、正確な管理が必要です。
HR BrEdge社労士法人では、有給休暇の付与日や日数を自動計算し、取得状況を一覧で管理します。年5日の有給休暇取得義務が定められているため、取得日数が不足している従業員を把握し、企業に情報提供します。これにより、企業は計画的に有給休暇の取得を促すことができ、法令遵守を徹底できます。
勤怠管理や有給休暇管理をアウトソーシングすることで、担当者が個別に管理する手間が省け、正確で効率的な管理が実現します。
HR BrEdge社労士法人の導入事例

HR BrEdge社労士法人(旧渡辺事務所)の給与計算アウトソーシングサービスを導入いただいた企業の具体的な事例をご紹介します。実際にサービスをご利用いただいている企業の声をお聞きください。
【製造業・従業員126名】給与計算の正確性向上と人事制度のアップデートを実現
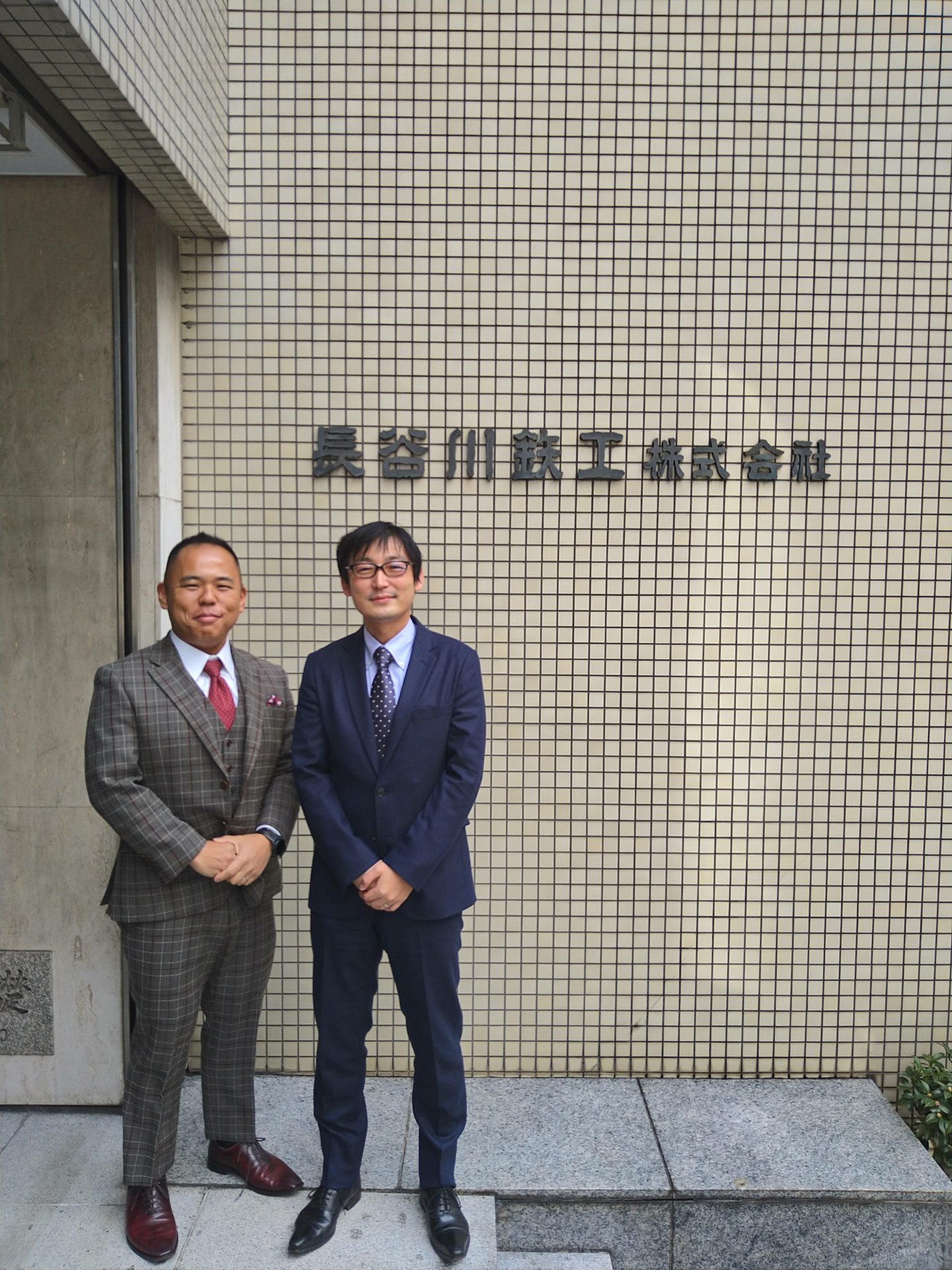
産業用冷凍設備の導入コンサルから開発・設計、製造、メンテナンスまで手掛ける長谷川鉄工株式会社様は、従業員126名の製造業企業です。コンビニエンスストアのアイスコーヒーに使用される氷を製造する製氷工場の設備を納めるなど、日本各地で事業を展開されています。
導入前の課題
長谷川鉄工様では、当初社労士と契約しておらず、昔からの習慣で社内でさまざまなことを進めていました。しかし、時代の変化が激しくなる中で、これまでのやり方ではうまくいかない部分が出てきました。労務管理や人事制度が時代に合わせて進化していく中で、専門的な知識が必要となり、自分たちで考えることに限界を感じるようになりました。
特に給与計算については、社内で行っていた時には担当者の教育やオペレーションの安定性といった点で不安がありました。また、より専門的な知識とサポートを提供してくれる社労士事務所を探し始めたのがきっかけでした。
HR BrEdge社労士法人を選んだ理由
長谷川鉄工様がHR BrEdge社労士法人(当時の渡辺事務所)を選んだ決め手は、給与計算をアウトソースできることと、商売の話が分かること(事業内容に対する理解度があること)の2つの要件を満たしていたことでした。過去の繋がりから紹介を受け、この要件に合致したことが契約を決断したキーポイントとなりました。
導入後の効果
導入後、長谷川鉄工様は大きく2つのメリットを実感されています。
ひとつ目は給与計算についてです。社内でやっていた時には担当者の教育やオペレーションの安定性といった点で不安がありましたが、契約後は給与計算の正確性と効率が向上し、人事労務関連のリスク管理が強化されました。専門家に任せることで、計算ミスのリスクが大幅に軽減され、安心して給与計算業務を任せられるようになりました。
もうひとつは、人事制度の面では、社内規定が常にアップデートされていることです。法令変更に対する迅速な情報提供と対応策を提案いただけるので、それに向けて余裕を持って準備ができるようになっています。法改正への対応が遅れることなく、常に最新の状態を維持できることが大きなメリットとなっています。
想定外のメリット
契約前には想定していなかったメリットとして、ITツールの導入支援がありました。労務管理を進めていくにあたって必要なITツールの提案をもらえたのは想定していませんでした。このツールにより、日常の業務が効率化され、時間とコストの節約につながりました。また、社労士側も話が早いので、双方にとってメリットがあったと感じています。
さらに、HR BrEdge社労士法人は顧問先が多いため、他社の色々な事例を聞けることもメリットが大きいです。異なる視点からのヒントを得ることができ、自社の課題解決に活かせています。
活用のポイント
長谷川鉄工様からは、「とにかく聞く。気になったら聞く」ことが上手に活用するポイントだとアドバイスをいただきました。質問しなくても先に情報提供してもらえますが、いただいた情報が自社にどう関わり、どう影響があるのかを具体的にイメージしづらい時などは、なんでも聞くと色々な自社に沿った具体的な提案をしてくれるとのことです。
【飲食業・11店舗展開】個人事務所からの切り替えでシステム化と専属担当制を実現
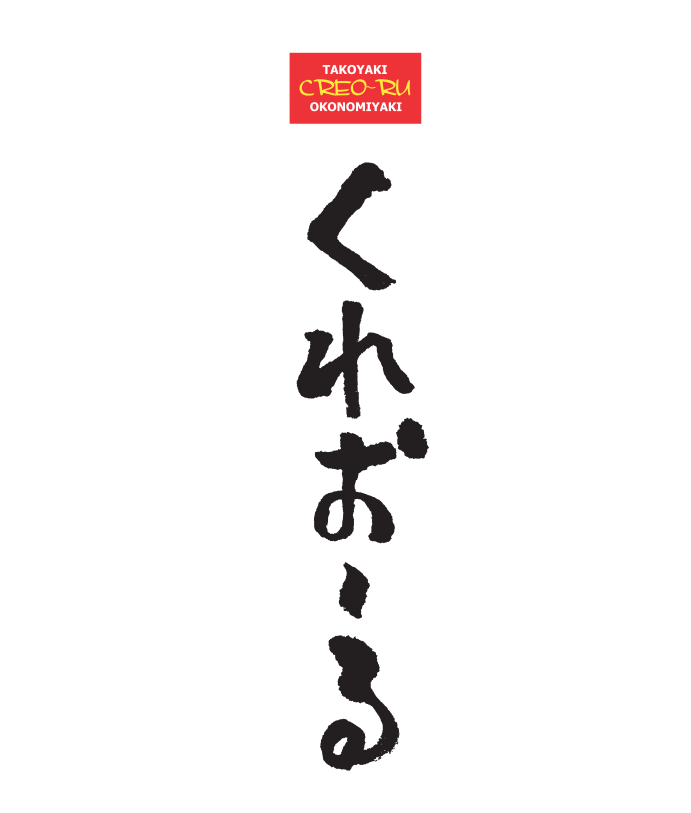
大阪を中心に11店舗の直営店を展開し、従業員数126名を擁する株式会社くれおーる様は、道頓堀を中心に「たこ焼き」「焼きそば」「お好み焼き」「串焼き」など大阪名物が全部食べられる総合レストランを展開する飲食業の企業です。
導入前の課題
くれおーる様では、以前は個人の社労士事務所と契約していましたが、その事務所には限界を感じていました。具体的には、タイムカードでの勤務管理をしており、それに関連する不備が見られました。タイムカードの計算や提出に手間がかかる状況であり、システム化されていないことが大きな課題でした。
また、以前の個人事務所では不在で連絡がなかなか繋がらなかったり、機能が不足していた部分もありました。人事や労務関連の問題を包括的に考える必要があり、より大きな組織であることが求められていました。
HR BrEdge社労士法人を選んだ理由
くれおーる様がHR BrEdge社労士法人(当時の渡辺事務所)を選んだ決め手は、総合的に組織立ってやっているところでした。当社社長が渡辺事務所の代表と知り合いだったことに加え、より大きな組織であることが重要なポイントでした。
他の社労士事務所との比較では、主にシステム化の観点から検討されました。HR BrEdge社労士法人はシステム化されており、人事や労務関連の仕組みを構築してくれることが期待できました。また、規模の大きさや人員の豊富さも魅力的でした。個人で対応してもらっていた以前の事務所と比較して、一定の規模や組織力が必要だと感じていたためです。
導入後の効果
専属の担当者がついてもらえることが大きなメリットでした。これにより、連絡や相談がスムーズに行えるようになりました。以前は個人事務所だったため、不在で連絡がなかなか繋がらなかったり、機能が不足していた部分もありましたが、現在は担当者を通じて円滑なコミュニケーションができていると感じています。
相談内容としては、主に人事戦略や制度作り、給与計算などが挙げられます。給与計算は一つのアウトプットであり、それに繋がる人事戦略的な要素を構築したいと考えています。制度作りから人事戦略的な視点を持って、給与計算に反映させることが重要だと実感されています。
想定外のメリット
想定していなかったメリットは、問題の指摘や解決方法について相談できる点です。クライアントには言いにくいことでも、法律的な問題やNGな点について、明確に指摘していただけ、一緒に解決策を探れるところが一番のメリットです。これらの要素が経営の改善につながっています。
また、コロナ禍により事業や経営に関わる問題が顕在化した際、銀行や事業企画の面でサポートを受け、事業計画の策定やコロナによる影響への対応が可能となりました。特に、10年後の事業戦略や人員配置に関する計画を重要視されており、利益を生むためには、やはり「人」が大事だと再確認されました。
人員配置に関する計画は、事業の展開や法令順守において重要な要素であり、HR BrEdge社労士法人に相談することで、適切な計画が立てられました。経営や事業に関する計画を立てていると問題解決がスムーズに進められます。
活用のポイント
くれおーる様からは、目の前の課題に集中する傾向がありましたが、コロナ禍を契機に長期的な視点での計画の重要性を再認識されたとのことです。経営や事業に関する計画を立てることで、問題解決がスムーズに進められます。
お客様の声|長谷川鉄工株式会社様
長谷川鉄工株式会社様からは、顧問契約を検討されている経営者の方へのメッセージとして、以下のようなお言葉をいただきました。
「こればかりは使わないと分からないと思います。やっぱり実績を見て判断されるのがいいかと思います。使ってダメなら替える訳ですし。何故そんなに多くの顧問先を抱えているのかという実績を契約されてみたら、その価値が分かるのではないかと思います。契約を検討されている経営者の方は、一度、専門家の力を借りてみることをお勧めします。時には想定していなかったメリットまで得られることもありますので、積極的に相談し、自社に合ったサービスを見極めてください。先ずは踏み込んでみられてはどうでしょうか。」
お客様の声|株式会社くれおーる様
株式会社くれおーる様からは、顧問契約を検討されている経営者の方へのメッセージとして、以下のようなお言葉をいただきました。
「HR BrEdge社労士法人では、何でも相談できるという雰囲気があります。社労士事務所を活用することで経営や労働に関するさまざまな問題について、長期的な視点で相談し、計画を立てることができます。人事に関する専門的なサポートがあり、残業や労働時間の管理などの課題にも対応してもらえます。これにより、労働時間の適切な管理や労働条件の改善など、経営に関する重要な課題に取り組むことが可能です。より効果的な経営が実現できると思いますので、ぜひ一度相談してみてください。」
給与計算アウトソーシングのよくある質問(FAQ)
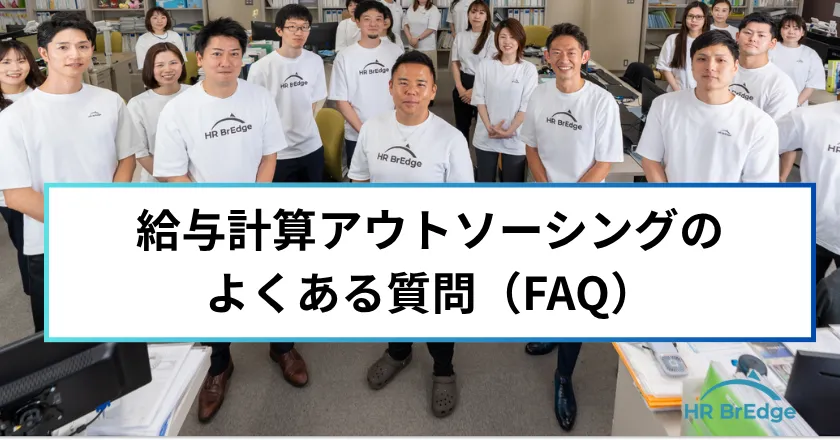
給与計算アウトソーシングに関して、よくいただく質問とその回答をまとめました。
給与計算でアウトソーシング・代行できる業務は?
給与計算アウトソーシングでは、月次給与計算、賞与計算、年末調整、住民税更新など、給与に関するほぼすべての業務を委託できます。
具体的には、勤怠データを基にした給与計算、給与明細の作成・発行、振込データの作成、社会保険料や税金の計算、年末調整の計算と源泉徴収票の発行、住民税の更新作業などが含まれます。また、社会保険労務士事務所に依頼する場合は、社会保険や労働保険の各種手続き、労務相談なども一括して委託できます。
サービスによっては、勤怠管理、有給休暇管理、従業員からの問い合わせ対応、福利厚生に関する手続きなども対応可能です。委託したい業務範囲については、契約前にアウトソーシング会社と詳しく相談することをお勧めします。
給与計算のアウトソーシング・代行にかかる費用は?
給与計算アウトソーシングの費用は、企業の規模や従業員数、委託する業務範囲によって異なります。
一般的な料金体系としては、基本料金に従業員数に応じた従量課金が加わる形式が多く見られます。従業員50名程度の企業で月額4万5,000円から8万円程度、従業員100名規模で月額16万円前後が相場です。従業員数が多いほど、1名あたりの単価は下がる傾向にあります。
HR BrEdge社労士法人の場合、基本契約30,000円に従業員数に応じた従量課金(従業員6名から20名までは1名あたり手続き1,000円、給与計算1,000円など)を加えた料金体系となっています。年末調整や住民税更新なども基本料金に含まれており、料金体系がシンプルで分かりやすい点が特徴です。
詳しい料金については、企業の状況に応じて個別にお見積もりを提示しますので、お気軽にお問い合わせください。
ペイロールの意味は何ですか?
ペイロール(Payroll)とは、英語で「給与」「給与台帳」「給与計算」を意味する言葉です。企業が従業員に支払う給与の管理や計算業務全般を指します。
ペイロールアウトソーシングとは、この給与計算業務を外部の専門業者に委託することを意味します。欧米では一般的な用語であり、日本でも給与計算アウトソーシングと同じ意味で使用されることがあります。
給与計算の事務作業すべてが含まれていますか?
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスでは、給与計算に関する主要な事務作業はすべて含まれています。
具体的には、月次給与計算、賞与計算、給与明細の作成、振込データの作成、年末調整、源泉徴収票の発行、住民税の更新などが基本サービスに含まれます。また、社会保険労務士事務所ですので、社会保険や労働保険の各種手続きも一括して対応します。
ただし、勤怠データの集計や人事異動情報の整理など、一部の業務については企業側で対応いただく必要があります。どこまでを委託するかについては、企業のニーズに応じて柔軟に対応しますので、契約前にご相談ください。
新しいソフトやシステムを導入する必要はありますか?
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスでは、企業側で新しいソフトやシステムを導入する必要は基本的にありません。
現在使用している勤怠管理システムや人事管理システムをそのまま継続してご利用いただけます。データの提出フォーマットも自由ですので、現在の業務フローを変更する必要がありません。
ただし、業務効率化のために新しいITツールの導入を検討されている場合は、最適なツールの提案も行っています。勤怠管理システムやクラウド労務管理システムなど、企業の課題に合ったツールをご紹介し、導入支援も行います。
本社以外の事業所や支店にも対応できますか?
はい、本社以外の事業所や支店がある企業にも対応可能です。
全国に複数の拠点を持つ企業でも、一括して給与計算を行うことができます。拠点ごとに異なる給与体系や勤務形態がある場合でも、柔軟に対応します。また、拠点別の集計資料を作成することも可能です。
社会保険や労働保険の手続きについても、各拠点の所轄の年金事務所やハローワークへの届出を代行します。拠点が増えた場合でも、スムーズに対応できる体制を整えています。
税制改正や制度改正には対応してもらえますか?
はい、税制改正や制度改正には確実に対応します。
HR BrEdge社労士法人では、労働法規や税制の改正情報を常に監視しており、改正があれば速やかにシステムに反映します。社会保険料率の変更、雇用保険料率の改定、所得税の税率変更、最低賃金の改定など、すべての法改正に対応します。
企業側では、法改正の詳細を追いかける必要がなく、常に最新の法令に準拠した給与計算が行われます。また、法改正が自社にどのような影響を与えるか、どのような準備が必要かについても、適切にアドバイスします。
就業規則や給与規定の策定も相談できますか?
はい、就業規則や給与規定の策定についてもご相談いただけます。
HR BrEdge社労士法人は社会保険労務士事務所ですので、就業規則や給与規定の作成・見直しも専門業務のひとつです。現在の規定が法令に適合しているか、実際の運用と一致しているかをチェックし、必要に応じて改定案を提案します。
また、新しい人事制度や給与体系を導入する際の規定作成もサポートします。法的に問題のない規定を作成し、労働基準監督署への届出まで一括して対応します。給与計算と規定整備を同じ事務所に依頼することで、規定と実態の整合性を保ちやすくなります。
従業員によって給与体系が異なりますが対応できますか?
はい、従業員によって給与体系が異なる場合でも対応可能です。
正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態による給与体系の違いはもちろん、職種や等級による給与体系の違い、拠点や部門による違いなど、さまざまなパターンに対応できます。
また、月給制、日給月給制、時給制、年俸制など、異なる給与形態が混在している場合でも問題ありません。複雑な給与体系でも正確に計算できるシステムとノウハウを持っています。
契約前のヒアリング段階で、企業の給与体系を詳しくお聞きし、対応可能かどうかを確認します。特殊な計算が必要な場合でも、柔軟に対応しますので、まずはご相談ください。
担当者が業務知識に乏しいのですが大丈夫ですか?
はい、担当者の業務知識が乏しい場合でも問題ありません。
HR BrEdge社労士法人では、専属担当者が丁寧にサポートします。給与計算の仕組みや必要な手続きについて、わかりやすく説明しながら進めていきますので、初めて給与計算業務を担当する方でも安心してご利用いただけます。
実際の導入事例でも、「経験の浅い担当者にも親身に寄り添っていただいている」という評価をいただいています。わからないことがあれば、いつでも質問していただける体制を整えています。
また、業務の流れやスケジュール、必要な資料などをマニュアル化して提供しますので、担当者が交代する場合でもスムーズに引き継ぎができます。
給与振込みデータはどのような形式でもらえますか?
給与振込みデータは、企業が取引している銀行のフォーマットに合わせて作成します。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行など、主要な銀行のFBデータフォーマットに対応しています。複数の銀行を利用している企業でも、それぞれの銀行に対応したFBデータを作成できます。
また、インターネットバンキングに直接取り込める形式や、銀行の専用システムに対応した形式での納品も可能です。企業のご要望に応じて、最適な形式で納品します。
いつから導入できる?導入にかかる期間は?
給与計算アウトソーシングの導入にかかる期間は、企業の規模や給与体系の複雑さによって異なりますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月程度です。
導入の流れとしては、まずお問い合わせいただき、初回相談でサービス内容をご説明します。その後、詳細なヒアリングを行い、見積もりを提示します。契約締結後、システムのセットアップとテストランを実施し、問題がなければ本番運用を開始します。
急いで導入したい場合は、スケジュールを調整して対応することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
既存の給与システムはどうなる?
既存の給与システムは、そのまま継続して使用することも、使用を停止することも可能です。
勤怠管理システムや人事管理システムを使用している場合は、それらのシステムから出力されるデータを活用して給与計算を行いますので、システムを継続してご利用いただけます。
給与計算ソフトを使用している場合は、アウトソーシング導入後は使用する必要がなくなりますので、ライセンス費用などのコストを削減できます。ただし、データの参照用として残しておくことも可能です。
機密情報の取り扱いは大丈夫?
HR BrEdge社労士法人は、SRPⅡ認証(認証番号:1600640)を取得しており、業界最高水準のセキュリティ対策を講じています。
マイナンバーを含む個人情報について、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を総合的に実施しています。データの暗号化、アクセス権限の厳格な管理、入退室管理、監視カメラの設置など、多層的なセキュリティ対策により、情報漏洩のリスクを最小限に抑えています。
また、機密保持契約を締結し、従業員全員が守秘義務を負っています。第三者機関による定期的な審査を受けながら、継続的にセキュリティレベルの向上に努めていますので、安心してお任せください。
途中で解約できる?
はい、契約期間中でも解約は可能です。ただし、契約内容によって解約予告期間が定められている場合があります。
一般的には、1ヶ月前から3ヶ月前までに解約の意思表示をしていただく必要があります。具体的な解約条件については、契約書に明記されていますので、契約時に確認してください。
解約を検討される場合は、まずは担当者にご相談ください。サービス内容や料金について改善できる点があれば、継続してご利用いただけるよう調整させていただきます。
御社の導入実績はどのくらいですか?
HR BrEdge社労士法人は、2007年の設立以来18年にわたり、給与計算や労務管理のサービスを提供してきました。これまでに500社以上の企業に導入いただいた豊富な実績があります。
製造業、飲食業、小売業、IT業、医療・福祉業、建設業など、幅広い業種での実績があり、従業員数十名の中小企業から数百名規模の企業まで、さまざまな規模の企業をサポートしています。
長年にわたって多くの企業をサポートしてきた経験から、豊富なノウハウを蓄積しており、企業の多様なニーズに対応できる体制を整えています。
どのような業種の企業が利用していますか?
HR BrEdge社労士法人の給与計算アウトソーシングサービスは、幅広い業種の企業にご利用いただいています。
製造業(産業用機械製造、食品製造など)、飲食業(レストランチェーン、居酒屋など)、小売業(専門店、スーパーマーケットなど)、IT業(システム開発、Webサービスなど)、医療・福祉業(クリニック、介護施設など)、建設業、不動産業、サービス業など、多岐にわたります。
業種によって給与体系や勤務形態が異なりますが、それぞれの業種特有のルールや計算方法に精通しており、柔軟に対応できます。
SRPⅡ認証とは何ですか?Pマークとの違いは?
SRPⅡ認証は、全国社会保険労務士会連合会が運営する、社労士業界唯一の個人情報保護認証制度です。マイナンバー制度に対応した厳格な安全管理措置を講じていることを証明する認証です。
プライバシーマーク(Pマーク)は、業種を問わず幅広い企業・団体が取得できる汎用的な個人情報保護の認証制度です。一方、SRPⅡ認証は、社労士事務所に特化した認証制度であり、社労士が取り扱う個人情報(マイナンバー、健康情報、給与情報など)の特性を踏まえた、より専門的で厳格な基準が設けられています。
SRPⅡ認証は、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に準拠しており、Pマークと同等以上の高度なセキュリティ基準をクリアした社労士事務所のみが取得できます。
専属担当者はつきますか?
はい、HR BrEdge社労士法人では、顧客企業ごとに専属の担当者を配置しています。
専属担当者が企業の状況を継続的に把握し、きめ細かなサポートを提供します。給与計算や労務管理の専門知識を持つプロフェッショナルが担当しますので、専門的な相談にも的確に対応できます。
同じ担当者が継続してサポートすることで、企業の特性や課題を深く理解し、より効果的な提案ができます。連絡や相談もスムーズに行え、長期的なパートナーシップを築くことができます。
まとめ:給与計算アウトソーシングで業務効率化を実現しませんか?
給与計算アウトソーシングは、企業の業務効率化とコスト削減を同時に実現できる、効果的なソリューションです。
本記事では、給与計算アウトソーシングの基礎知識から、料金相場、選び方、メリット・デメリット、導入の流れまで、詳しく解説してきました。
給与計算アウトソーシングの主なメリットは、トータルコストの削減、担当者がコア業務に専念できること、法令改正への迅速な対応、給与計算ミスのリスク軽減、業務の属人化防止、繁閑期の業務量変動への対応、勤務時間管理の徹底などが挙げられます。
特に社労士に給与計算を依頼するメリットとしては、労働保険・社会保険手続きまで一括対応できること、労務トラブルの未然防止、助成金申請のサポート、就業規則・給与規程の整備支援、労働基準監督署の調査対応、SRPⅡ認証による高度なセキュリティ対策などがあります。
HR BrEdge社労士法人は、創業18年、500社以上の豊富な実績を持つ社労士法人です。SRPⅡ認証(認証番号:1600640)を取得し、業界最高水準のセキュリティ対策を講じています。専属担当者による充実したサポート体制、自由なフォーマットでの対応、現行の計算ロジックの維持、柔軟な納品スケジュール、ITツールの導入提案など、多くの強みを持っています。
料金体系は、基本契約30,000円に従業員数に応じた従量課金を加えたシンプルな構成です。年末調整や住民税更新も基本料金に含まれており、追加費用の心配がありません。
給与計算業務に課題を感じている企業、人事担当者の負担を軽減したい企業、法改正対応に不安がある企業、労務リスクを軽減したい企業は、ぜひ給与計算アウトソーシングの導入を検討してみてください。
HR BrEdge社労士法人では、無料相談を随時受け付けています。企業の状況をお聞きした上で、最適なサービス内容をご提案し、詳細なお見積もりを提示いたします。給与計算アウトソーシングをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
給与計算業務を専門家に任せることで、企業は本来注力すべきコア業務に集中でき、持続的な成長を実現できます。HR BrEdge社労士法人は、企業の人事労務のパートナーとして、長期的な視点で企業の成長を支援いたします。
この記事の執筆者・著者情報 HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺 俊一

HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所) 代表 特定社会保険労務士 渡辺 俊一 ・保有資格 |
新ロゴ 旧ロゴ |
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人