新着情報
中小企業経営者必見!社会保険適用拡大で知っておくべきポイント
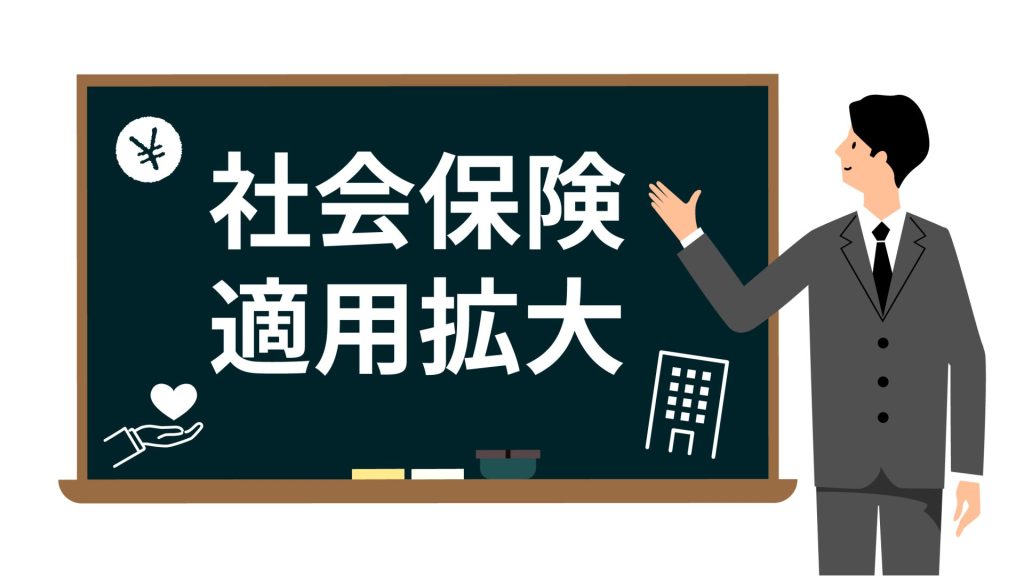
「来年の社会保険適用拡大で、うちの会社はどうなってしまうのか…」
最近、こんな不安を抱える中小企業の経営者の方が急増しています。
2024年10月からの社会保険適用拡大により、
従業員50人以下の企業でも新たに多くの従業員が加入対象となる可能性があるからです。
特に100人規模の企業では、これまで社会保険に加入していなかった
パートタイム従業員やアルバイトスタッフが一気に加入対象となり、
「社会保険料負担が年間数百万円増加する」
「給与計算が複雑化して対応しきれない」
といった深刻な問題に直面しています。
しかし、適切な対策を講じれば、
この変化をむしろ企業の競争力強化につなげることも可能です。
従業員の福利厚生充実により人材確保が容易になり、
離職率の大幅改善を実現した企業も少なくありません。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、
社会保険適用拡大の具体的な影響から、
100人規模企業が取るべき実践的な対策まで、
給与計算の効率化やDX推進も含めて詳しく解説いたします。
社会保険適用拡大が100人規模企業に与える衝撃の実態
社会保険適用拡大の影響は、多くの経営者が想像している以上に深刻です。
実際に対象となった企業の事例を通じて、その実態を詳しく見ていきましょう。
コスト負担の急激な増加
従業員100人規模の小売業A社では、
パートタイム従業員40名が新たに社会保険の加入対象となりました。
その結果、年間の社会保険料負担が約480万円増加。
これは同社の年間利益の約15%に相当する金額でした。
同社経営者は振り返ります:
「事前に試算はしていましたが、実際に請求が来ると想像以上の衝撃でした。
毎月40万円の固定費増加は、正直かなりの経営圧迫です。
価格転嫁も簡単ではない中、利益確保に苦慮しています」
さらに深刻なのは、総務担当者への業務負荷です。
「40名分の加入手続きだけで2週間を要し、
その間他の業務が完全にストップしてしまいました。
毎月の給与計算も従来の倍以上の時間がかかるようになり、
総務スタッフの残業が常態化しています」(同社総務部長談)
手続き業務の複雑化による混乱
製造業B社(従業員85名)では、
適用条件の判定自体で大きな混乱が発生しました。
「週20時間以上の勤務実態があるかどうかの判定で、
個々の従業員の労働時間を詳細に分析する必要が生じました。
しかし、従来の勤怠管理では正確な把握ができておらず、
過去3か月分の勤務記録を手作業で集計することに…」
結果として、加入手続きに2か月を要し、
その間に労働基準監督署から指導を受ける事態となりました。
「適用条件を満たしているのに加入手続きが遅れている」
という指摘を受け、遡及加入と付加金の支払いが必要となったのです。
就業規則改定の必要性と法的リスク
サービス業C社(従業員110名)では、
就業規則の改定が急務となりました。
「社会保険の適用基準が変わることで、
雇用契約書や就業規則の見直しが必要になりました。
特に、パートタイム従業員の労働時間管理や、
社会保険料の労使負担について明確に記載する必要があります」
しかし、適切な就業規則改定を怠ったため、
従業員とのトラブルが発生してしまいました。
「社会保険料の自己負担について十分な説明がなかった」
として、複数の従業員から苦情が寄せられ、
労働局への相談にまで発展する事態となったのです。
DX化の遅れが招く業務破綻
建設業D社(従業員95名)では、
従来の手作業による給与計算システムが完全に破綻しました。
「これまでExcelで管理していた給与計算では、
新たに加入する30名分の社会保険料計算に対応できませんでした。
計算ミスが頻発し、従業員への説明と訂正作業で
毎月1週間以上を費やす状況に…」
経営者の視点では、さらに深刻な問題が浮上:
「給与計算に追われて、本来注力すべき営業活動や
現場管理に支障をきたすようになりました。
結果として、受注機会を逃すケースも発生し、
売上面でも大きな影響を受けています」
成功企業に学ぶ:社会保険適用拡大を機会に変える戦略的アプローチ
一方で、適用拡大を機会として捉え、
大きな競争力向上を実現した企業も存在します。
その成功の秘訣を詳しく分析してみましょう。
戦略1:アウトソーシングとDXの同時推進
運輸業E社(従業員120名)では、
適用拡大を機に給与計算の完全アウトソーシングを決断しました。
「新たに35名の従業員が社会保険加入対象となることが判明した時点で、
内製での対応は不可能と判断。
クラウド勤怠システムと給与計算アウトソーシングを
パッケージで導入することにしました」
結果は期待を大きく上回るものでした:
・給与計算関連業務の85%削減
・社会保険手続きの完全自動化
・総務スタッフの残業時間ゼロ達成
・空いたリソースで助成金申請に注力し、年間600万円を獲得
「社会保険料の増加分は年間約300万円でしたが、
業務効率化と助成金獲得により、
実質的には300万円のプラス効果となりました」(同社経営者談)
戦略2:福利厚生充実による人材確保戦略
小売業F社(従業員90名)では、
適用拡大を「福利厚生充実のチャンス」として積極活用しました。
「これまで社会保険に加入できなかった
パートタイム従業員25名が新たに加入対象となったことを、
採用活動の大きなセールスポイントとして打ち出しました」
採用活動での効果は劇的でした:
・求人応募数が前年比で300%増加
・面接辞退率が50%から15%に改善
・入社後1年以内の離職率が25%から8%に大幅改善
・結果として、採用コストを年間200万円削減
「社会保険料の負担増は年間約250万円でしたが、
採用コスト削減と離職率改善により、
トータルでは大幅なコスト削減を実現できました」
戦略3:顧問社労士との戦略的パートナーシップ
製造業G社(従業員105名)では、
顧問社労士との連携を大幅に強化しました。
「適用拡大に伴う複雑な手続きを一人で判断するのは無理だと感じ、
顧問契約の内容を見直して、より包括的なサポートを受けることにしました」
パートナーシップ強化の具体的な効果:
・適用条件の正確な判定により、対象者を適切に特定
・就業規則の改定により、労使トラブルを事前に回避
・助成金の活用により、社会保険料負担の一部を相殺
・将来の法改正に対する事前準備体制の構築
「月々の顧問料は増加しましたが、
法的リスクの回避と助成金獲得により、
投資効果は十分に得られています」(同社経営者談)
戦略4:段階的な労働時間管理の最適化
サービス業H社(従業員115名)では、
適用拡大を機に労働時間管理を根本から見直しました。
「単純に社会保険料負担を受け入れるのではなく、
従業員の働き方自体を最適化することで、
生産性向上と負担軽減の両立を図りました」
最適化の具体的なアプローチ:
・週20時間未満の短時間勤務者の業務効率向上
・週20時間以上の従業員のスキルアップ支援
・シフト管理の最適化による人件費効率化
・DXツール導入による業務自動化
結果として、従業員一人当たりの生産性が20%向上し、
社会保険料の負担増を売上増加で相殺することに成功しました。
よくある疑問・不安にお答えします
Q1: 社会保険料の負担増加で経営が厳しくなりそうです。どう対処すべきでしょうか?
A: 負担増加は避けられませんが、戦略的な対応により影響を最小限に抑えられます。
具体的な対策:
・助成金の積極活用(キャリアアップ助成金など)
・業務効率化による人件費最適化
・福利厚生充実による採用コスト削減
・給与計算アウトソーシングによる間接費削減
「当初は年間400万円の負担増を覚悟していましたが、
助成金獲得と業務効率化により、
実質的な負担は100万円程度に抑えることができました。
むしろ従業員満足度が向上し、長期的にはプラス効果の方が大きいです」
(製造業・経営者談)
Q2: 給与計算が複雑になりすぎて、社内では対応しきれません
A: 多くの企業で同様の課題が発生しており、
アウトソーシングやDX化による解決が効果的です。
推奨される解決策:
・給与計算の専門業者への委託
・クラウド型給与システムの導入
・勤怠管理システムとの連携自動化
・顧問社労士との連携強化
「社会保険適用拡大を機に、思い切って給与計算を外部委託しました。
複雑な計算や手続きから解放され、
総務スタッフは戦略的な業務に集中できるようになりました。
結果として、DX推進や人事制度改革が大きく進歩しています」
(小売業・総務部長談)
Q3: 就業規則の改定や従業員への説明に不安があります
A: 適切な準備と専門家のサポートにより、
スムーズな移行が可能です。
成功のポイント:
・従業員への事前説明会の開催
・就業規則改定時の労働基準監督署への届出
・個別相談窓口の設置
・社会保険のメリットを丁寧に説明
「最初は従業員からの反発を心配していましたが、
社会保険加入のメリット(医療費負担軽減、将来の年金など)を
具体的な数字で説明したところ、むしろ感謝されました。
適切な説明により、労使の信頼関係がより深まったと感じています」
(サービス業・経営者談)
まとめ
社会保険適用拡大は確かに中小企業にとって大きな変化ですが、
適切な対策を講じることで企業の競争力強化につなげることができます。
重要なのは、単純にコスト負担として捉えるのではなく、
業務効率化、DX推進、人材確保戦略の一環として
戦略的にアプローチすることです。
成功企業に共通するのは以下の特徴です:
・早期の現状分析と対策立案
・アウトソーシングとDXの積極活用
・助成金や補助金の戦略的活用
・顧問社労士との密接な連携
・従業員への丁寧な説明とコミュニケーション
特に給与計算の複雑化に対しては、
内製化での対応には限界があります。
クラウドシステムの導入や専門業者への委託により、
正確性と効率性の両立を図ることが重要です。
また、適用拡大による福利厚生の充実を
人材採用や従業員定着の武器として活用することで、
長期的な競争力向上も期待できます。
もし社会保険適用拡大への対応でお困りでしたら、
一人で悩まずに専門家にご相談ください。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、
社会保険適用拡大への対応から給与計算の効率化まで、
100人規模企業様の課題を総合的にサポートしております。
LINE・Slack・Chatworkなど、お使いのツールで
お気軽にご相談いただけます。
今すぐ無料相談で、あなたの会社に最適な対策をご提案いたします。
適用拡大を機会に変える戦略的アプローチから、
具体的な手続き方法まで、経験豊富な専門家が
丁寧にサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人



