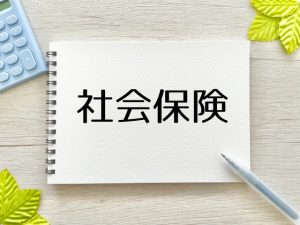新着情報
社会保険適用拡大で何が変わる?中小企業が直面する課題と対策

「2024年10月から、うちの会社も社会保険適用拡大の対象になる…
一体何から手をつければいいのか分からない」
従業員51人以上の企業経営者や総務担当者の方から、
このような不安の声が続々と寄せられています。
2024年10月から施行される社会保険適用拡大により、
従業員51人以上の企業では、これまで加入していなかった
パートタイム従業員やアルバイトスタッフの多くが
新たに社会保険加入の対象となります。
「社会保険料の負担が年間いくら増えるのか?」
「複雑化する給与計算にどう対応すればいいのか?」
「手続きを間違えて法的トラブルになったらどうしよう?」
多くの企業が、こうした不安を抱えているのが現実です。
しかし、適切な準備と対策を講じることで、
この変化を企業の成長機会に変えることも可能です。
従業員の福利厚生充実により採用力が向上し、
優秀な人材の確保と定着を実現した企業も少なくありません。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、
2024年10月の社会保険適用拡大の具体的な内容から、
実際の対応手順、そして給与計算の効率化まで、
51人以上の企業が知っておくべき全てを詳しく解説いたします。
2024年10月適用拡大で何が変わる?具体的な影響を徹底解説
2024年10月からの社会保険適用拡大は、
多くの企業が考えている以上に大きな変化をもたらします。
まずは、具体的に何が変わるのかを正確に理解しましょう。
適用対象となる企業と従業員の条件
【対象企業】
従業員数51人以上の企業(これまでは101人以上が対象)
【加入対象となる従業員の条件】
以下の4つの条件をすべて満たす従業員:
・週の労働時間が20時間以上
・雇用期間が2か月を超える見込み
・年間賃金が88万円以上
・学生ではない(夜間・通信・定時制の学生は除く)
これまで対象外だった多くのパートタイム従業員が、
新たに社会保険加入の対象となることになります。
実際の企業への影響を数字で見る
【影響試算例:従業員80名の小売業の場合】
・正社員:50名(既に社会保険加入済み)
・パートタイム従業員:30名
・このうち新たに加入対象となる従業員:18名
年間の社会保険料負担増加額:約432万円
(1名当たり月額2万円×18名×12か月)
製造業A社(従業員75名)の経営者は語ります:
「試算してみて、その負担の大きさに正直驚きました。
年間400万円以上の固定費増加は、経営に大きな影響を与えます。
ただ、単純にコスト増と捉えるのではなく、
人材確保の武器として活用する方法を模索しています」
給与計算業務の複雑化という見落としがちな問題
多くの企業が見落としているのが、
給与計算業務の大幅な複雑化です。
サービス業B社(従業員90名)の総務担当者は振り返ります:
「新たに25名の従業員が社会保険に加入することになり、
毎月の給与計算時間が従来の2倍以上になってしまいました。
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の計算に加え、
標準報酬月額の管理も必要になり、もう手作業では限界です」
特に深刻なのは、以下の業務負荷増加:
・社会保険資格取得届の作成・提出
・標準報酬月額決定通知書の管理
・算定基礎届の対象者拡大
・年度更新時の労働保険料計算対象者増加
・従業員への個別説明と質問対応
手続きミスが招く法的リスクの実態
適用拡大に伴う手続きでは、
法的リスクも大幅に増大します。
建設業C社(従業員65名)で実際に起こった事例:
「週20時間以上の勤務実態があるにも関わらず、
適用条件の判定を誤って加入手続きを怠ってしまいました。
労働基準監督署の調査で発覚し、
遡及加入と付加金の支払いで総額150万円の追加負担が発生。
さらに、従業員からの信頼失墜も深刻でした」
経営者の視点では、さらに深刻な問題が:
「手続きミスの対応に総務スタッフが1か月間専念することになり、
他の重要業務が完全にストップしてしまいました。
特に年度末の繁忙期と重なったため、
売上機会の損失も含めると、被害は計り知れません」
成功企業の実践的対応策:準備から運用まで完全ガイド
適用拡大を成功に導くには、
段階的で計画的なアプローチが不可欠です。
実際に成功を収めた企業の事例から、実践的な対応策を学びましょう。
ステップ1:現状分析と対象者の正確な把握
まずは、自社の従業員の中で
誰が新たに加入対象となるかを正確に把握することから始めます。
運輸業D社(従業員120名)の成功事例:
「過去6か月分の勤務記録を詳細に分析し、
各従業員の労働時間、雇用期間、年間賃金を
スプレッドシートで一覧化しました。
その結果、28名が新たに加入対象となることが判明」
【分析すべき項目】
・過去6か月の平均労働時間(週単位)
・雇用契約期間と更新予定
・年間賃金の見込み額
・学生かどうかの確認
・現在の社会保険加入状況
「詳細な分析により、グレーゾーンの従業員も事前に特定でき、
適用開始前に労働時間の調整や契約内容の見直しを
計画的に進めることができました」(同社総務部長談)
ステップ2:給与計算システムの見直しとDX化
手作業での給与計算では、
増加する社会保険料計算に対応しきれません。
システム化・DX化は必須の対策です。
小売業E社(従業員85名)のDX化成功事例:
「適用拡大を機に、クラウド型の給与計算システムを導入。
勤怠管理システムとの連携により、
労働時間から社会保険の適用判定まで自動化しました」
導入後の劇的な効果:
・給与計算時間を70%削減
・計算ミスをゼロに
・社会保険手続きの自動化
・総務スタッフの残業時間を月20時間削減
「初期投資は120万円程度かかりましたが、
人件費削減効果を考えると、1年で投資回収できる計算です。
何より、スタッフのストレス軽減効果は計り知れません」
(同社経営者談)
ステップ3:アウトソーシングの戦略的活用
社会保険手続きの複雑化に対応するため、
専門業者への委託を検討する企業が急増しています。
製造業F社(従業員95名)のアウトソーシング活用事例:
「社会保険の加入手続きから毎月の給与計算まで、
一括して社労士法人に委託することを決断しました。
特に適用拡大の初期対応では、専門知識が不可欠だと判断」
アウトソーシングによる効果:
・法的リスクの完全回避
・手続きミスによるトラブルゼロ
・総務業務の大幅効率化
・助成金活用による負担軽減
「月額の委託費用は25万円程度ですが、
総務スタッフの人件費削減と法的リスク回避を考えると、
十分にペイする投資だと思います。
何より、本業に集中できる環境が整いました」
ステップ4:従業員コミュニケーションと就業規則改定
適用拡大を成功させるには、
従業員への丁寧な説明と理解促進が不可欠です。
サービス業G社(従業員70名)のコミュニケーション成功事例:
「適用開始の3か月前から、対象従業員向けの説明会を開催。
社会保険加入のメリットを具体的な数字で説明しました」
【説明会で伝えた内容】
・医療費負担の軽減効果(3割→1割負担の場合も)
・将来受け取れる厚生年金の増加額
・傷病手当金などの手厚い保障
・社会保険料の労使折半による企業負担
「最初は保険料負担への不満もありましたが、
将来のメリットを具体的に説明したところ、
多くの従業員から『安心して働ける』という声をいただきました。
結果として、離職率も大幅に改善しています」
よくある疑問・不安にお答えします
Q1: 社会保険料の負担増で経営が厳しくなりそうです。何か軽減策はありますか?
A: 複数の軽減策を組み合わせることで、実質的な負担を大幅に抑えることができます。
主な軽減策:
・キャリアアップ助成金の活用(正社員化促進)
・人材確保等支援助成金の活用
・業務効率化による人件費最適化
・福利厚生充実による採用コスト削減
・給与計算アウトソーシングによる間接費削減
「当初は年間500万円の負担増を覚悟していましたが、
助成金活用と業務効率化により、実質負担は200万円程度に。
むしろ従業員満足度向上による生産性アップで、
売上も前年比110%を達成できました」(製造業・経営者談)
Q2: 適用条件の判定が複雑で、間違えそうで不安です
A: 専門家のサポートを受けることで、
正確な判定と適切な手続きが可能になります。
判定で注意すべきポイント:
・労働時間の計算方法(所定労働時間 vs 実労働時間)
・雇用期間の判定(契約更新の可能性を含む)
・年間賃金の算定方法(賞与・諸手当の扱い)
・学生の定義と除外条件
「顧問社労士に詳細な判定をお願いしたところ、
自社で判定していた結果と5名の相違がありました。
専門家の知見により、適切な対応ができて安心です」
(小売業・総務担当者談)
Q3: 給与計算が複雑になり、現在のシステムでは対応できません
A: システム更新やアウトソーシングにより、
効率的で正確な給与計算が実現できます。
推奨される解決策:
・クラウド型給与計算システムの導入
・勤怠管理システムとの連携自動化
・給与計算の専門業者への委託
・社労士との顧問契約強化
「手作業から脱却し、給与計算を外部委託したことで、
正確性と効率性が大幅に向上しました。
空いた時間で戦略的な人事施策に取り組めるようになり、
会社全体の競争力強化につながっています」
(サービス業・経営者談)
まとめ
2024年10月からの社会保険適用拡大は、
51人以上の企業にとって大きな変化をもたらしますが、
適切な準備と対策により、むしろ競争力強化の機会とすることができます。
成功のカギとなるのは以下の要素です:
・対象従業員の正確な把握と早期準備
・給与計算システムのDX化・効率化
・専門家との連携による法的リスク回避
・助成金活用による負担軽減
・従業員への丁寧な説明とコミュニケーション
特に重要なのは、給与計算業務の抜本的見直しです。
手作業では増大する業務量に対応しきれないため、
システム化やアウトソーシングの検討が不可欠となります。
また、適用拡大による福利厚生の充実を
人材採用や従業員定着の武器として活用することで、
長期的な企業価値向上も期待できます。
準備は早ければ早いほど有利です。
適用開始まで時間が限られている今、
迅速かつ適切な対応が求められています。
もし2024年10月の適用拡大への対応でお困りでしたら、
一人で悩まずに専門家にご相談ください。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、
社会保険適用拡大への対応から給与計算の効率化まで、
51人以上企業様の課題を総合的にサポートしております。
LINE・Slack・Chatworkなど、お使いのツールで
お気軽にご相談いただけます。
今すぐ無料相談で、あなたの会社に最適な対策をご提案いたします。
対象従業員の正確な判定から具体的な手続き方法、
給与計算の効率化まで、経験豊富な専門家が
親身になってサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人