新着情報
給与計算代行とは?中小企業が導入すべき理由と選び方
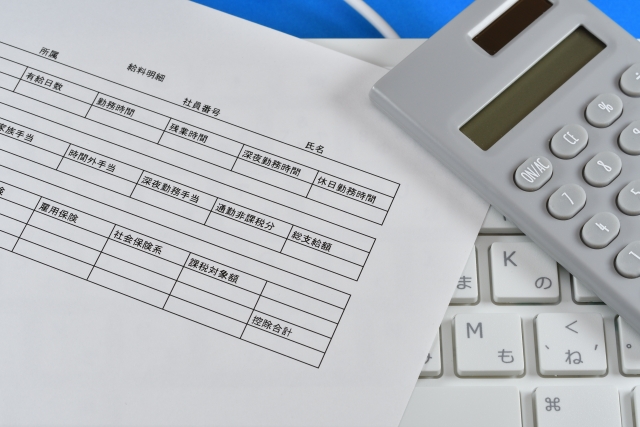
「また今月も給与計算の時期がやってきた…」
毎月末になると、総務担当者の方はため息をついていませんか?
100人規模の企業では、給与計算だけでなく就業規則の管理や手続き業務、助成金申請など、やるべき業務が山積みです。
経営者の皆さまも「人事労務にかかる時間とコストを削減したい」「法改正への対応が追いつかない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
そんな課題を解決する選択肢として、給与計算代行サービスが注目されています。
しかし、「料金が安いから」という理由だけで選んでしまい、
給与支払い遅延や計算ミスで大きなトラブルを招いた企業も少なくありません。
適切な代行業者を選ばなければ、かえって業務負担が増大してしまうリスクがあるのです。
本記事では、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、
100人規模企業における給与計算代行の選び方から成功のポイントまで、
実際の失敗事例と成功事例を交えながら実践的な情報をお伝えします。
アウトソースと内製化のメリット・デメリットを比較しながら、
あなたの会社に最適な選択肢を見つけていきましょう。
100人規模企業が陥りがちな給与計算代行の選定ミス
給与計算代行の選定で失敗する企業には、共通するパターンがあります。
まずは実際に起こった失敗事例から、避けるべき落とし穴を理解していきましょう。
失敗パターン1:価格だけで判断した結果の悲劇
【失敗例:IT企業B社(従業員95名)】
「月額12万円という安さに魅力を感じて、実績の少ない代行業者と契約しました。
しかし、3か月目にシステム障害が発生し、給与支払いが5日間遅延。
従業員からの苦情が殺到し、労働基準監督署への相談まで検討される事態に…」
同社の総務部長は振り返ります:
「遅延の説明と謝罪で1週間を費やし、従業員の信頼回復に3か月かかりました。
結局、別の業者に変更することになり、
移行費用だけで150万円の追加コストが発生してしまったんです」
この失敗から学ぶべきポイント:
・料金の安さだけでなく、システムの安定性を重視する
・障害時の対応体制とバックアップ体制を事前に確認する
・同規模企業での実績があるかを必ず確認する
失敗パターン2:既存システムとの連携を軽視した結果
【失敗例:製造業C社(従業員110名)】
「勤怠管理システムとの連携ができる」という説明を信じて契約したものの、
実際には手作業でのデータ変換が必要で、むしろ業務負担が増加してしまいました。
「毎月、勤怠データをCSVでエクスポートし、
代行業者の指定フォーマットに手作業で変換する作業が発生。
結果的に、内製化していた頃よりも時間がかかるようになってしまいました」
(同社総務担当者談)
経営者の視点では、さらに深刻な問題が発覚:
「代行業者への委託費用に加えて、
データ変換作業のための残業代が月10万円程度発生。
コスト削減どころか、総額では以前より高くついている状況です」
失敗パターン3:サポート体制の甘い見積もり
【失敗例:小売業D社(従業員85名)】
「契約時は『電話サポート対応』と聞いていたのに、
実際には平日の限られた時間しか対応してもらえず、
緊急時に連絡が取れない状況が頻発しました」
特に問題となったのは、法改正対応の遅れでした:
「最低賃金の改定時期に、計算方法の確認で連絡したところ、
『担当者が不在のため、3日後に回答します』と言われ、
給与支払い直前まで正確な金額が分からない状態に。
結局、急遽内製で計算し直すことになりました」
成功企業が実践している正しい選定基準
一方で、給与計算代行で大きな成果を上げている企業は、
以下の5つの基準で総合的に判断しています。
【成功例:建設業E社(従業員120名)】
「最初は3社で比較検討し、料金は中程度でしたが、
・同業界での10年以上の実績
・24時間365日の緊急対応体制
・既存の勤怠システムとの完全連携
・月次報告での詳細な説明とアドバイス
・セキュリティ認証の取得状況
これらを総合的に評価して決定しました」
導入後の効果は劇的でした:
「月末の残業時間が80%削減され、空いた時間で助成金申請に注力。
初年度だけで年間400万円の助成金を獲得できました。
代行費用を差し引いても、200万円以上のプラス効果です」
確実に成功する給与計算代行の導入手順と活用法
給与計算代行を成功させるには、導入前の準備が何より重要です。
多くの成功企業が実践している、段階的なアプローチをご紹介します。
ステップ1:現状分析と要件定義の徹底
まずは自社の給与計算プロセスを詳細に分析することから始めます。
単純に「外部に委託する」のではなく、
どの部分を委託し、どの部分は社内に残すかを明確にする必要があります。
【分析すべき項目】
・現在の給与計算にかかる時間と人件費
・使用している勤怠管理システムの仕様
・特殊な手当や控除項目の有無
・年末調整や労働保険手続きとの連携
・将来的な人員増加の予定
サービス業F社(従業員105名)の事例:
「詳細な分析により、勤怠データの収集に最も時間がかかっていることが判明。
代行業者選定時に、この部分の自動化を重点的に検討した結果、
業務時間を従来の70%削減することができました」
ステップ2:段階的導入による リスク最小化
いきなり全面的な委託は危険です。
成功企業の多くは、3段階のプロセスで安全に移行しています。
【推奨導入スケジュール】
・1か月目:テスト計算と精度検証
・2か月目:並行稼働による比較確認
・3か月目:完全移行と運用最適化
運輸業G社(従業員90名)の段階的導入事例:
「1か月目のテスト計算で、社内計算との差異が3件発見されました。
詳しく調べると、すべて社内計算のミスだったことが判明。
代行業者の精度の高さを実感し、安心して移行できました」
経営者の視点では、さらなるメリットも:
「段階的に進めることで、従業員の不安も最小限に抑えられました。
『給与が正確に支払われるか心配』という声もありましたが、
並行稼働期間中に透明性を保てたことで、スムーズに移行できたんです」
ステップ3:DXとの連携による業務変革
単純な代行委託で終わらせるのではなく、
DX推進と組み合わせることで真の業務変革が実現できます。
製造業H社(従業員115名)の変革事例:
「クラウド勤怠システムと給与計算代行を同時に導入。
従業員はスマートフォンで出退勤を記録し、
そのデータが自動的に代行業者に送信されます。
私たちは月末に最終確認するだけで済むようになりました」
結果として得られた効果:
・給与計算関連業務の90%自動化
・総務担当者の月末残業ゼロ達成
・空いたリソースで人材採用強化
・年間離職率を20%から8%に改善
成功企業が重視する「パートナーシップ」の構築
単なる作業代行ではなく、戦略的パートナーとしての関係構築が重要です。
成功企業では、以下のような連携を行っています。
卸売業I社(従業員100名)の連携事例:
「月次の報告会では、給与計算の結果だけでなく、
・労働時間の傾向分析
・法改正の影響予測
・人件費最適化の提案
・助成金活用の可能性
といった戦略的なアドバイスも受けられます」
「これにより、単純なコスト削減を超えて、
人事戦略全体の最適化が図れるようになりました。
顧問料以上の価値を感じています」(同社経営者談)
よくある疑問・不安にお答えします
Q1: 給与計算代行にかかる費用は、内製化と比べてどうでしょうか?
A: 100人規模の企業では、トータルコストで代行の方が有利になるケースが多いです。
内製化の場合の年間コスト:
・専任担当者の人件費:360万円
・給与計算ソフト・サーバー費用:120万円
・法改正対応・研修費用:50万円
・合計:530万円
代行サービスの場合:
・月額代行費用:18~25万円(年間216~300万円)
・初期設定費用:50万円
・合計:266~350万円
「数字で見ても代行の方が有利ですが、
それ以上に、総務担当者が戦略的業務に専念できる価値は
金額では計り知れません」(製造業・経営者談)
Q2: セキュリティ面での不安があります。どのような対策が必要でしょうか?
A: 信頼できる代行業者では、以下の対策が標準装備されています。
必須のセキュリティ対策:
・プライバシーマークまたはISMS認証の取得
・データ暗号化通信(SSL/TLS)
・多重バックアップシステム
・アクセスログの詳細管理
・従業員の秘密保持契約
「当初はセキュリティが心配でしたが、
社内管理よりもむしろ厳格なセキュリティ体制で、
安心してお任せできています。
定期的な監査報告も受けられるので、透明性も確保されています」
(IT企業・総務部長談)
Q3: 現在の就業規則や勤怠システムはそのまま使えますか?
A: 多くの代行業者では、既存システムとの連携が可能ですが、
事前の詳細確認が重要です。
確認すべきポイント:
・現在の勤怠システムとのAPI連携の可否
・データエクスポート形式の互換性
・特殊な手当・控除項目への対応
・就業規則の複雑な規定への対応
・将来的なシステム変更への柔軟性
「既存の勤怠システムとの完全連携により、
データ入力作業が一切不要になりました。
これも事前に詳しく確認していたからこそ実現できた効率化です」
(サービス業・総務担当者談)
まとめ
100人規模企業における給与計算代行は、
単なるコスト削減の手段ではありません。
戦略的な業務変革を実現し、企業の競争力強化につながる重要な投資なのです。
成功のカギは、価格だけでなく以下の要素を総合的に評価することです:
・実績と信頼性
・セキュリティ対策
・システム連携の柔軟性
・サポート体制の充実
・戦略的パートナーシップの構築
適切な代行業者を選択することで、以下の効果が期待できます:
・月20時間以上の業務時間削減
・給与計算ミスの大幅な減少
・法改正への迅速な対応
・助成金申請などの付加価値業務への注力
・DX推進による競争力向上
重要なのは、段階的な導入アプローチにより、
リスクを最小限に抑えながら確実に効果を実現することです。
テスト計算から並行稼働、完全移行まで、
慎重なプロセスを踏むことで安心して移行できます。
「給与計算に追われる日々から解放されたい」
「もっと戦略的な業務に時間を使いたい」
そのような想いをお持ちでしたら、まずは専門家にご相談ください。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、2007年の創業以来、
50社を超える企業様の給与計算を月1万人規模でサポートしてまいりました。
LINE・Slack・Chatworkなど、お客様の環境に合わせた柔軟な対応と、
「ミスを出さない仕組み」で安心してお任せいただけます。
今すぐ無料相談で、あなたの会社に最適な給与計算代行プランをご提案いたします。
失敗しない業者選びのポイントから、具体的な導入手順まで、
経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人



