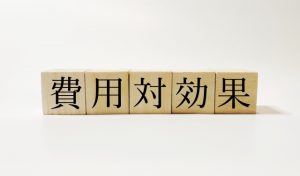新着情報
給与計算のアウトソーシングで中小企業が得られる3つの大きなメリット

毎月20日を過ぎると、「また給与計算の時期がきた…」と憂うつになる総務担当者の方は多いのではないでしょうか。
従業員100人を超える企業では、給与計算だけでなく
社会保険手続きや法改正への対応など、
人事労務業務が複雑化し続けています。
「今月も残業続きで給与計算が終わらない」
「法改正についていけず、ミスが心配」
「DXを進めたいが、何から手をつければいいか分からない」
このような悩みを抱える経営者・総務担当者に向けて、
本記事では給与計算業務のアウトソーシングについて、
メリットから実際の導入ステップまで詳しく解説します。
全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人の
豊富な実績をもとに、あなたの会社に最適な選択肢を見つけていきましょう。
なぜ100人規模の企業で給与計算の負担が急増するのか
従業員が100人を超えると、給与計算業務は劇的に複雑化します。
50人規模の頃は「なんとか回せていた」業務も、
100人を境に質的な変化が起こるのです。
複雑化する要因1:多様な雇用形態と勤務パターン
100人規模になると、正社員だけでなく
契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など
多様な雇用形態が混在するようになります。
さらに、時短勤務、フレックスタイム、
テレワーク手当、営業手当など
個別の手当や控除も増加し、
一人ひとりの計算パターンが異なってきます。
「今月はAさんが育休から復帰で時短勤務、
Bさんは営業成績により歩合給が変動、
Cさんは残業時間の計算にミスがあって修正…」
このような状況が毎月繰り返されると、
担当者の負担は想像以上に重くなります。
複雑化する要因2:法改正への継続的な対応
労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法など
給与計算に関わる法律は頻繁に改正されます。
2023年だけでも、以下のような変更がありました:
- 雇用保険料率の変更
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額上限の改定
- 最低賃金の引き上げ
- 助成金制度の新設・変更
内製化では、これらの情報収集から
システム設定の変更、就業規則の見直しまで
すべて自社で対応する必要があります。
「法改正の情報をキャッチしたものの、
実際の手続きまで手が回らない」
「ミスが発覚して、後から修正に追われる」
こうした状況は、経営者にとっても
総務担当者にとっても大きなストレスとなります。
複雑化する要因3:システム運用とセキュリティの課題
給与計算システムの導入・運用には
専門的な知識が必要です。
システムのアップデート、
データバックアップ、セキュリティ対策など
IT面での管理業務も増加します。
特に個人情報を扱う給与データは
厳重な管理が求められ、
情報漏洩のリスクも常に意識する必要があります。
「DXを進めたいが、セキュリティが心配」
「システムトラブルで給与支払いが遅れてしまった」
このような技術的な課題も、
100人規模の企業が直面する現実なのです。
成功する給与計算アウトソーシングの進め方
ステップ1:現状分析と課題の明確化
アウトソーシングを成功させる第一歩は、
自社の現状を正確に把握することです。
【経営者の視点】
・給与計算にかかる人件費(担当者の工数×時給)
・システム導入・維持費用
・ミスによる追加コスト
・法改正対応の遅れによるリスク
【総務担当者の視点】
・月間の給与計算作業時間
・繁忙期の残業時間
・ミスの発生頻度と修正工数
・ストレスレベルと他業務への影響
成功事例:製造業A社(従業員120名)
A社では総務担当者が月末に40時間の残業を続けていました。
時給換算すると月10万円のコスト。
さらに年2回のミスで追加修正作業が発生し、
年間で約200万円の隠れコストが判明しました。
ステップ2:適切なアウトソーシング先の選定
給与計算のアウトソース先選定では、
以下のポイントを重視しましょう。
1. 実績と専門性
・同規模企業での実績
・社会保険労務士の資格保有
・法改正への迅速な対応体制
2. システムと連携体制
・既存システムとの連携可能性
・クラウド対応とセキュリティ
・レポート機能の充実度
3. コミュニケーション体制
・質問への回答スピード
・緊急時の対応体制
・担当者の変更リスク
失敗事例:サービス業B社(従業員95名)
B社は価格の安さだけで委託先を選定。
しかし、質問への回答が遅く、
法改正対応も後手に回り、
結果的に内製化に戻すことになりました。
「安かろう悪かろう」の典型例です。
ステップ3:段階的な移行とPDCAサイクル
いきなり全面的にアウトソーシングするのではなく、
段階的な移行をおすすめします。
第1段階(1~2ヶ月)
・給与計算のみ委託
・内製化と並行実施でチェック
・問題点の洗い出し
第2段階(3~6ヶ月)
・社会保険手続きも委託範囲に追加
・月次のレポート体制確立
・運用ルールの最適化
第3段階(6ヶ月以降)
・年末調整、労働保険年度更新も委託
・戦略的人事業務へのシフト
・成果測定と継続改善
成功事例:IT企業C社(従業員110名)
C社は段階的移行により、
総務担当者の残業時間を月40時間から5時間に削減。
浮いた時間で採用活動と社員研修に注力し、
離職率を15%から8%に改善しました。
よくある疑問・不安にお答えします
Q1. アウトソーシングにするとコストが高くなりませんか?
A1. 総合的に見ると、多くの場合でコスト削減効果があります。
【経営者の視点】
人件費(担当者の給与・社会保険料)、
システム費用、研修費用などを総合すると、
月額15~25万円程度かかるケースが多いです。
一方、アウトソーシングは月額8~15万円程度で、
年間で100万円以上の削減も珍しくありません。
【総務担当者の視点】
何より、毎月の残業ストレスから解放され、
より戦略的な業務に集中できるようになります。
「コストは投資、時間は資産」という考え方が重要です。
Q2. 情報漏洩などのセキュリティリスクが心配です
A2. 適切な委託先選定により、むしろセキュリティは向上します。
【経営者の視点】
専門業者は個人情報保護に関する
厳格な管理体制を整備しています。
プライバシーマーク取得、ISO27001認証など
第三者認証を確認しましょう。
【総務担当者の視点】
社内での情報管理(USBメモリ、印刷物など)の方が
実はリスクが高い場合もあります。
クラウドシステムでの暗号化通信、
アクセスログ管理など、
プロレベルのセキュリティが実現できます。
Q3. 顧問社労士がいるので、追加で委託する必要はないのでは?
A3. 顧問業務と給与計算は、求められるスキルが異なります。
【経営者の視点】
顧問社労士は法的アドバイスや
就業規則作成が専門分野です。
一方、給与計算は正確性とスピードが重要で、
専門チームでの対応が効率的です。
役割分担により、それぞれの専門性を活かせます。
【総務担当者の視点】
助成金申請、労務相談は顧問社労士、
毎月の給与計算は専門業者という
ハイブリッド体制が最も効果的。
「餅は餅屋」の発想で、
業務品質の向上が期待できます。
まとめ
従業員100人規模の企業にとって、
給与計算の内製化には限界があります。
法改正への対応、多様な雇用形態への対応、
セキュリティリスクの管理など、
専門的な知識と継続的な学習が必要な分野だからです。
アウトソーシングを活用することで、
・コスト削減(年間100万円以上の削減も可能)
・業務品質の向上(ミスの削減、法改正への迅速対応)
・人的資源の最適配分(戦略業務への集中)
が実現できます。
特に、DXを推進したい企業にとって、
給与計算のアウトソーシングは
デジタル化の第一歩としても有効です。
「毎月の給与計算に追われる日々から解放されたい」
「法改正対応のストレスを軽減したい」
「より戦略的な人事業務に集中したい」
そのような想いをお持ちの経営者・総務担当者の方は、
まずは現状の課題分析から始めてみてください。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、
無料相談で貴社の現状分析をお手伝いしています。
LINE、Slack、Chatworkなど
お使いのツールでお気軽にご連絡ください。
今すぐ行動を起こして、
給与計算業務の効率化を実現しましょう。
【今すぐ無料相談のお申し込みはこちら】
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人