障害年金受給額を徹底解説平均額や計算方法を知って受給額を把握しよう
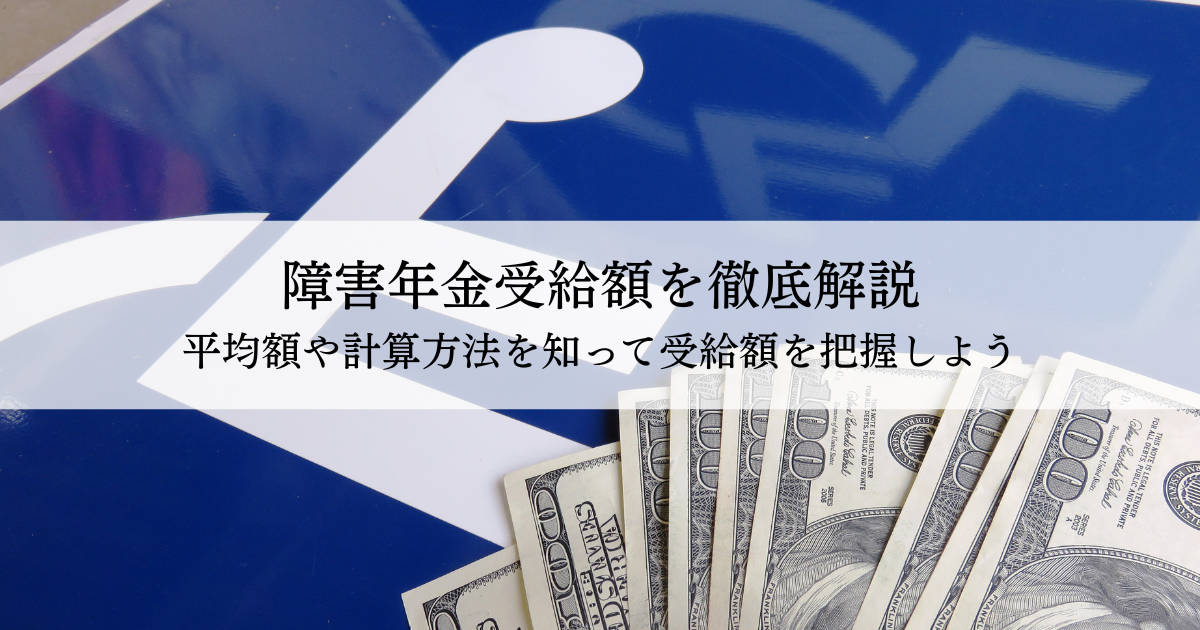
障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に支障がある方を対象とした公的年金制度です。
受給額は障害の程度や年金の種類、加入期間など様々な要素によって決まります。
そのため、自分がどれくらい受給できるのかを把握することは重要です。
そこで今回は、障害年金の平均受給額や受給額の決定方法、そして自身の受給額が妥当か確認する方法について詳しく解説します。
障害年金の平均受給額
障害等級別の平均受給額
障害年金の受給額は、障害等級によって大きく異なります。
1級から6級まで等級が分かれており、1級が最も重い障害で、受給額も最も高くなります。
厚生労働省の統計データによると、平成30年度における障害年金の平均受給額は、1級で約200万円、2級で約150万円、3級で約100万円、4級で約70万円程度となっています。
また、これはあくまで平均値です。
個々の受給額は、障害の状態や年齢、勤続年数などの要因によって変動します。
例えば、同じ3級でも、障害の状態が重い場合や長年勤続していた場合は、平均よりも高い金額を受給できる可能性があります。
一方で、障害の状態が比較的軽い場合や勤続年数が短い場合は、平均よりも低い金額になる可能性もあるのです。
障害年金の種類別の平均受給額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金は、国民年金の加入期間がある方を対象とした年金です。
一方で、障害厚生年金は、厚生年金保険に加入していた方を対象とした年金です。
それぞれの平均受給額は、障害等級や加入期間、保険料の納付状況などによって異なりますが、一般的に障害厚生年金のほうが受給額は高くなります。
これは、障害基礎年金は国民年金に加入していた期間に基づいて計算されるのに対し、障害厚生年金は加入期間と保険料の納付状況、そして給与水準などを考慮して計算されるためです。
そのため、同じ障害等級であっても、受給額に差が生じるのは当然と言えるでしょう。
さらに、それぞれの年金制度の目的や給付水準の違いも影響しているといえます。
加算される金額の平均
障害年金には、障害の状態によって加算される金額があります。
例えば、介護が必要な場合や日常生活に支障がある場合は、加算金が支給されます。
この加算金の平均額は、障害等級や介護の程度によって異なりますが、平均で月額数万円程度となるケースが多いです。
具体的な金額は、個々の状況によって異なるため、詳細な情報は、年金事務所に問い合わせることをお勧めします。
また、加算の対象となる要件や金額は法改正によって変更される場合もあるため、最新の情報を確認することが重要です。
さらに、専門家への相談も有効な手段となるでしょう。
障害年金の受給額の決定方法
障害等級の影響
障害年金の受給額は、まず障害等級によって決定されます。
医師の診断に基づいて、障害の程度が評価され、1級から6級のいずれかの等級に分類されます。
等級が高いほど、より重い障害と判断され、受給額も高くなります。
この等級判定は非常に複雑で、医師の専門的な知識と経験が求められる作業です。
そのため、診断書の作成にあたっては、信頼できる医師に依頼することが非常に重要となります。
また、セカンドオピニオンを受けることも検討すると良いでしょう。
所得と資産の制限
障害年金の受給額は、受給者の所得や資産によって制限される場合があります。
一定以上の所得や資産がある場合は、年金の支給額が減額される、または支給されない場合があります。
具体的にどの程度の所得や資産までが支給対象となるかは、年金制度の規定により定められています。
そのため、自身の所得や資産状況を正確に把握し、年金事務所に確認することが大切です。
また、所得や資産の状況は定期的に見直されるため、最新の情報を確認しておく必要があります。
年金加入期間と子の有無による加算
年金加入期間が長いほど、受給額は高くなります。
これは、障害基礎年金と障害厚生年金の両方において共通の要素です。
加入期間が短い場合は、受給額が低くなる可能性があるため、自身の加入期間を確認しておくことが重要です。
また、障害年金受給者が未成年の子を扶養している場合は、児童扶養手当と同様に、扶養手当として加算金が支給されます。
この加算金は、子の数によって金額が異なります。
さらに、子の年齢によっても加算額が変わるため、注意が必要です。
自分の障害年金受給額は妥当?
受給額シミュレーションの方法
自身の障害年金受給額が妥当かどうかを確認するには、年金事務所のホームページなどで提供されているシミュレーションツールを利用する方法があります。
これらのツールでは、障害等級や加入期間、所得などの情報を基に、概算の受給額を計算することができます。
ただし、シミュレーション結果はあくまで概算であり、実際の受給額とは異なる可能性があることを理解しておく必要があります。
また、入力する情報によって結果が大きく変わるため、正確な情報を入力することが重要です。
専門家への相談窓口
年金制度は複雑なため、自身で受給額を判断することに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
彼らは年金制度に精通しており、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供してくれます。
また、各地域の年金事務所でも相談窓口が設置されているため、気軽に相談することができます。
さらに、相談前に自身の状況を整理しておくと、スムーズな相談につながります。
まとめ
障害年金の受給額は、障害等級、年金の種類、所得・資産状況、年金加入期間、扶養家族の有無など、様々な要素によって決定されます。
平均受給額を参考にしながらも、自身の状況を正確に把握し、必要に応じて専門家への相談を検討することで、より適切な受給額を得られるよう努めることが重要です。
また、年金制度は法改正によって変更される場合があるため、常に最新の情報を確認しておくことが大切です。





